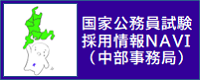国家公務員トーク
~当日いただいたご質問への回答~
Q1.(→名古屋市)名古屋市のような地方公務員で英語力はアピールになりますか?Q2.併願先はどのように決めていきましたか
Q3.(→人事院中部事務局)1人で模擬面接を行っていたとおっしゃっていましたが、問題は自分で抜粋して行っていたのでしょうか?
Q4.入庁後に最も印象に残った仕事は何でしょうか?
Q5.業務について、どのようなことがデジタル化されていますでしょうか。
Q6.組織に入る前と入った後のギャップはありましたか。
Q7.勉強時間はどれくらいですか
Q8.作文の内容を教えていただきたいです。
Q9.地方公務員から国家公務員になる人は、周りにいらっしゃいましたか。また、それは転職の扱いになるのでしょうか。
Q10.どのように勉強のモチベーションを保っていたのか知りたいです。
Q11.若い時から規模の大きい仕事に取り組むことができるとおっしゃっていましたが、先輩職員のサポートはありましたか?
Q12.残業はありますか?
Q13.実際の面接で受けた質問で、印象に残ったものはありますか?
Q14.面接ではニコニコしているのと真面目なのとどちらが好ましいですか?
Q15.公務員は、旧型の体系が問題視されがちですが、実態はどのようになっているのでしょうか。また、今後改善の兆しは見えていますか?
Q16.面接練習はトータル何回くらい練習しましたか?
Q17.(→名古屋市)名古屋市職員採用試験に新設された社会人枠について詳しく教えていただきたいです。
Q18.週休三日制について、現場を知る立場からどう考えていらっしゃいますか。
Q19.面接で質問が難しくて、言葉が詰まってしまった場合の対応の仕方を教えていただきたいです。
Q20二点お伺いしたいことがございます。地方公務員、国家公務員において、実際にどのような方がご活躍されているのか、活躍されている方々の共通してあげられる特徴などあれば教えていただきたいです。また、これまでご自身が1番きつかった、苦しかったと感じる仕事を教えていただきたいです。
Q21.実際に働いていらっしゃるお二方から見た、職場の雰囲気を教えていただきたいです。
Q22.公務員で働かれている方の中には中途採用の方で活躍されてる方はどのくらいいますか?
Q23.今の時期は何時間くらい勉強されていましたか?また、参考書は何冊ぐらい使用していましたか?
Q24.適性検査はどんな対策しましたか?
Q25.(→人事院中部事務局)参考書はなにを使って勉強されていましたか?
Q26.子どもがいても採用して頂けますか?子どもがいる受験者を採用する時に、心配事などはありますでしょうか?
Q27.(→名古屋市)名古屋市役所では、面接の時どんなところをみて評価されますか?
Q28.(→名古屋市)名古屋市の論文対策はどのように行いましたか?
Q29.(→名古屋市)地方公務員の志望動機で「○○ならでは」という点を考えるのが難しいと感じています。どのように志望動機を構成されましたか?
Q30.民間企業と比べて、デメリットだなと感じるところはありますか?
Q31.特別な挑戦や経験のエピソードがなくても面接対策は可能だと思われますか?
Q32.公務員という身分を獲得したことによって困ったことなどがあればお聞きしたいです。
Q33.民間から公務員に転職した人の場合、仕事内容は民間の業界に近くなるのでしょうか? それとも全く別の仕事を経験できるのでしょうか?
Q34.ゼミやサークルに入っていないことはやはり面接において不利になりますか?
Q35.業務の中で課題に感じていることを教えていただきたいです。(個人的なことでも、市・国家としてでも構いません)
Q36.必ず、毎年各職種に募集がされるとは限らないと聞きました。そこで、早期選考において志望職種が募集されていない場合、秋の募集もない可能性が高いと思った方が良いのでしょうか。
Q37.実際の試験時間で問題を解く練習や、論文試験対策はどのような教材を使用して練習されていましたか?
Q38.最近だと時代に合わせて行政の手続きなどもAI利用などスマート化しているかと思います。国家一般、地方公務員関わらず、DXに対応してけるような取り組みが内部、外部であると思うのですが、そういった情報関係における知識やスキルは事前にあった方が良いですか?
Q39.面接で答えるのが難しいと感じた質問があれば教えていただきたいです。
Q40.自分が採用の面接官だったら、どんな質問をしますか? なぜその質問をしたいのか背景も交えて教えてもらえたら嬉しいです。
Q41.来年度3年生になるのですが、民間のインターンにいきながら公務員の勉強をするのは可能ですか? どちらかに絞った方がいいですか?
Q42.社会人の試験では、社会人経験が直接どのように活かせるか重視されますか? 長く子育てや主婦をメインでしていた場合は、志望できない、または対象外ですか?
Q43.社会人試験の受験者に対して求めることはどういったことでしょうか? 大卒程度の一般枠との違いはどのようなことになりますか?
Q44.受けられるものは受けられるだけ受けたとおっしゃっていましたが、市役所試験に関して、自治体研究は志望先の自治体全て同程度で深掘りを進めていましたか?
Q45.今後の説明会の予定がありましたら教えて頂きたいです
Q46.インターンや説明会に参加していなくても意欲は伝わりますか?
Q47.教養試験は社会人経験がある方の方が採用率が高いのでしょうか
Q48.(→人事院中部事務局)国家公務員の建築職には、どのようなお仕事がありますか。また、どのような職場の環境ですか。(インターンで地方公務員について学んだことと比較したいため) 高専卒より大学卒の方が有利でしょうか。また、技術職の場合、採用においてより多くの専門知識を持っている方が有利でしょうか。
Q1. 名古屋市のような地方公務員で英語力はアピールになりますか?
(名古屋市)
本市の外国人住民の数は増加傾向にあり窓口等での接遇の機会も想定されます。そのほか、国際交流関連事業など、英語を活用する機会はあります。また「職員通訳者登録制度」といった制度もあります。
本市の外国人住民の数は増加傾向にあり窓口等での接遇の機会も想定されます。そのほか、国際交流関連事業など、英語を活用する機会はあります。また「職員通訳者登録制度」といった制度もあります。
Q2. 併願先はどのように決めていきましたか
(名古屋市)
地方公務員を志望していましたが、公務員専願だったので、国家公務員も含めて日程的に受験可能なものは極力受験しました。公務員以外では国立大学法人等の職員も受けました。
(人事院中部事務局)
民間企業は併願しませんでしたが、公務員については、試験日程が重ならなければ可能な限り受験しました。併願先を手広くするか、ある程度絞るかはご自身との相談になってしまいますが、多くの試験を受験することで、試験慣れもしてくると思います。私は、国家公務員採用総合職試験、国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)、専門職試験、裁判所事務官、衆議院事務局、県庁、特別区、地方公務員上級を受験しました。
地方公務員を志望していましたが、公務員専願だったので、国家公務員も含めて日程的に受験可能なものは極力受験しました。公務員以外では国立大学法人等の職員も受けました。
(人事院中部事務局)
民間企業は併願しませんでしたが、公務員については、試験日程が重ならなければ可能な限り受験しました。併願先を手広くするか、ある程度絞るかはご自身との相談になってしまいますが、多くの試験を受験することで、試験慣れもしてくると思います。私は、国家公務員採用総合職試験、国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)、専門職試験、裁判所事務官、衆議院事務局、県庁、特別区、地方公務員上級を受験しました。
Q3. 1人で模擬面接を行っていたとおっしゃっていましたが、問題は自分で抜粋して行っていたのでしょうか?
(人事院中部事務局)
1人で行っていたのは、筆記試験の勉強でした。筆記試験対策については、試験日程が近づいてきたら、時間配分の練習のために、科目ごとの問題演習ではなく、実際の試験問題を実際の試験時間で解く練習をしました。問題については公務員予備校から提供されたものを利用していました。
ちなみに、面接対策については、公務員予備校の面接対策が充実していたので、面接カードの作成から模擬面接まで、面接の苦手意識が薄くなるまでたくさん利用しました。
1人で行っていたのは、筆記試験の勉強でした。筆記試験対策については、試験日程が近づいてきたら、時間配分の練習のために、科目ごとの問題演習ではなく、実際の試験問題を実際の試験時間で解く練習をしました。問題については公務員予備校から提供されたものを利用していました。
ちなみに、面接対策については、公務員予備校の面接対策が充実していたので、面接カードの作成から模擬面接まで、面接の苦手意識が薄くなるまでたくさん利用しました。
Q4. 入庁後に最も印象に残った仕事は何でしょうか?
(名古屋市)
上下水道局在籍時の令和6年能登半島地震での被災地派遣が印象に残っています。市民生活を支えるインフラとしての上下水道の重要性について、現地での活動を通じて、改めて実感しました。
(人事院中部事務局)
採用3年目で担当した研修係において、オンライン形式での研修実施を確立したことが最も印象に残っています。今ではオンライン会議やオンライン授業は当たり前の世の中になっていますが、当時はコロナ禍でノウハウがない中、対面形式の時と比較して、研修効果が下がらないよう、どのような講義内容にすればよいか、事前の接続テストを含め、運営はどのようにしたらよいか、等を課内の職員や外部講師と一から考え直し、オンライン研修を作り上げました。 オンライン研修を確立したということで功績表彰されましたし、今でも私が作成したWeb会議システムのマニュアルが使用され続けていることを嬉しく感じています。
上下水道局在籍時の令和6年能登半島地震での被災地派遣が印象に残っています。市民生活を支えるインフラとしての上下水道の重要性について、現地での活動を通じて、改めて実感しました。
(人事院中部事務局)
採用3年目で担当した研修係において、オンライン形式での研修実施を確立したことが最も印象に残っています。今ではオンライン会議やオンライン授業は当たり前の世の中になっていますが、当時はコロナ禍でノウハウがない中、対面形式の時と比較して、研修効果が下がらないよう、どのような講義内容にすればよいか、事前の接続テストを含め、運営はどのようにしたらよいか、等を課内の職員や外部講師と一から考え直し、オンライン研修を作り上げました。 オンライン研修を確立したということで功績表彰されましたし、今でも私が作成したWeb会議システムのマニュアルが使用され続けていることを嬉しく感じています。
Q5. 業務について、どのようなことがデジタル化されていますでしょうか。
(名古屋市)
電子申請サービスなど、市民サービスにおける行政手続のオンライン化を進めています。また、会議や内部事務においても、ペーパーレス化の取組みを進めています。チャットツールのほか、テレワーク環境も整備しています。
(人事院中部事務局)
コロナを機にではありますが、テレワーク等が盛んになり、働き方がより柔軟化しましたし、会議等もオンライン会議が多くなった印象です。人事院は全国9つの各管区に地方事務局があるのですが、人事院本院を含めた全国的な会議も気軽に行われるようになりました。
また、多くの業務において押印が見直され、押印で管理していた出勤簿もデジタル化しました。その他、各種資料も電子媒体での作業が多くなりました。
電子申請サービスなど、市民サービスにおける行政手続のオンライン化を進めています。また、会議や内部事務においても、ペーパーレス化の取組みを進めています。チャットツールのほか、テレワーク環境も整備しています。
(人事院中部事務局)
コロナを機にではありますが、テレワーク等が盛んになり、働き方がより柔軟化しましたし、会議等もオンライン会議が多くなった印象です。人事院は全国9つの各管区に地方事務局があるのですが、人事院本院を含めた全国的な会議も気軽に行われるようになりました。
また、多くの業務において押印が見直され、押印で管理していた出勤簿もデジタル化しました。その他、各種資料も電子媒体での作業が多くなりました。
Q6. 組織に入る前と入った後のギャップはありましたか。
(名古屋市)
入庁前はデスクワークが中心のイメージでしたが、想像していたよりも現場等に出る機会が多かったです。実際に現場に出て学ぶことも多いため、良い意味でのギャップでした。
(人事院中部事務局)
採用されてすぐに、一人前の人事院職員として頼りにされ、業務を任せていただけたのが良いギャップでした。もちろん、採用時は右も左も分からない状態ですので、周りの職員からのサポートは手厚く、配属した部署の担当者として、採用1年目から責任感を持って業務に携わることができる環境であるため、成長機会が多いです。
入庁前はデスクワークが中心のイメージでしたが、想像していたよりも現場等に出る機会が多かったです。実際に現場に出て学ぶことも多いため、良い意味でのギャップでした。
(人事院中部事務局)
採用されてすぐに、一人前の人事院職員として頼りにされ、業務を任せていただけたのが良いギャップでした。もちろん、採用時は右も左も分からない状態ですので、周りの職員からのサポートは手厚く、配属した部署の担当者として、採用1年目から責任感を持って業務に携わることができる環境であるため、成長機会が多いです。
Q7. 勉強時間はどれくらいですか
(名古屋市)
私は大学3年生の秋から公務員予備校で本格的に勉強を開始しました。スタートが遅く、対面式の講座には間に合わなかったので、通信講座を受講しました。
(人事院中部事務局)
私は勉強をしていないと不安になるタイプだったので、大学の図書館や公務員予備校で比較的長い時間勉強していました。平日は2~3時間、休日は5~7時間ほどだったと思います。一人で勉強しているとだんだん辛くなることもあるので、お昼ご飯や夕ご飯を友達と一緒に食べに行き、リフレッシュする時間を挟みながら過ごしていました。
私は大学3年生の秋から公務員予備校で本格的に勉強を開始しました。スタートが遅く、対面式の講座には間に合わなかったので、通信講座を受講しました。
(人事院中部事務局)
私は勉強をしていないと不安になるタイプだったので、大学の図書館や公務員予備校で比較的長い時間勉強していました。平日は2~3時間、休日は5~7時間ほどだったと思います。一人で勉強しているとだんだん辛くなることもあるので、お昼ご飯や夕ご飯を友達と一緒に食べに行き、リフレッシュする時間を挟みながら過ごしていました。
Q8. 作文の内容を教えていただきたいです。
(名古屋市)
過去に出題した論文試験の課題は、名古屋市公式ウェブサイト(名古屋市職員採用案内)に掲載していますので、参考としてください。
(人事院中部事務局)
大卒程度試験では論文試験になりますが、試験問題に記載されている資料を読み取り、問題点を整理し、自身の考えを述べるものとなっています。文章による表現力や課題に対する理解力が求められます。
過去に出題した論文試験の課題は、名古屋市公式ウェブサイト(名古屋市職員採用案内)に掲載していますので、参考としてください。
(人事院中部事務局)
大卒程度試験では論文試験になりますが、試験問題に記載されている資料を読み取り、問題点を整理し、自身の考えを述べるものとなっています。文章による表現力や課題に対する理解力が求められます。
Q9. 地方公務員から国家公務員になる人は、周りにいらっしゃいましたか。また、それは転職の扱いになるのでしょうか。
(名古屋市)
改めて該当の採用試験を受ける必要があるため、転職の扱いになります。他の自治体や国家公務員から名古屋市に転職して来られた方もいらっしゃいます。
(人事院中部事務局)
地方公務員から国家公務員になる人もいます。ご参考ですが、国家公務員採用試験に最終合格すると、例えば総合職試験や一般職大卒程度試験では5年間(総合職試験教養区分では6年半、一般職大卒試験教養区分では6年間)採用候補者名簿という名簿に名前が載ることになり、この名簿に名前が載っている間は採用試験を受け直さず、希望する省庁で面接(官庁訪問)をして合格するだけで国家公務員になれます。国家公務員採用試験に合格だけしてしまえば、例えば、一度民間企業や地方公務員で働いた後に「また国家公務員になりたい!」と思われた際に、再度試験を受け直すことなく、希望する府省で面接(官庁訪問)だけ受ければ良いといったことも可能となります。
改めて該当の採用試験を受ける必要があるため、転職の扱いになります。他の自治体や国家公務員から名古屋市に転職して来られた方もいらっしゃいます。
(人事院中部事務局)
地方公務員から国家公務員になる人もいます。ご参考ですが、国家公務員採用試験に最終合格すると、例えば総合職試験や一般職大卒程度試験では5年間(総合職試験教養区分では6年半、一般職大卒試験教養区分では6年間)採用候補者名簿という名簿に名前が載ることになり、この名簿に名前が載っている間は採用試験を受け直さず、希望する省庁で面接(官庁訪問)をして合格するだけで国家公務員になれます。国家公務員採用試験に合格だけしてしまえば、例えば、一度民間企業や地方公務員で働いた後に「また国家公務員になりたい!」と思われた際に、再度試験を受け直すことなく、希望する府省で面接(官庁訪問)だけ受ければ良いといったことも可能となります。
Q10. どのように勉強のモチベーションを保っていたのか知りたいです。
(名古屋市)
私は公務員専願でしたがスタートが遅かったこともあり、背水の陣という気持ちで自分を追い込んでモチベーションを保っていました。私は自分を追い込んだ方がモチベーションになるタイプでしたが、ご自身にあった方法を採ることが良いと思います。
(人事院中部事務局)
業務説明会や座談会に参加して、ここで働きたい!国家公務員になりたい!という気持ちを持つことがモチベーションに繋がっていました。併願先についても、裁判傍聴をしたり、志望する特別区に足を運んで職員の働く姿を見に行ったりしました。
やはりずっと公務員試験の勉強をしているとしんどくなる時期もあると思いますが、そういう時は公務員予備校や大学の友達が頑張っている姿を見て、また、切磋琢磨して自分も頑張ろうと思っていました。あとは就職浪人を恐れる気持ちもモチベーションになっていたと思います。
私は公務員専願でしたがスタートが遅かったこともあり、背水の陣という気持ちで自分を追い込んでモチベーションを保っていました。私は自分を追い込んだ方がモチベーションになるタイプでしたが、ご自身にあった方法を採ることが良いと思います。
(人事院中部事務局)
業務説明会や座談会に参加して、ここで働きたい!国家公務員になりたい!という気持ちを持つことがモチベーションに繋がっていました。併願先についても、裁判傍聴をしたり、志望する特別区に足を運んで職員の働く姿を見に行ったりしました。
やはりずっと公務員試験の勉強をしているとしんどくなる時期もあると思いますが、そういう時は公務員予備校や大学の友達が頑張っている姿を見て、また、切磋琢磨して自分も頑張ろうと思っていました。あとは就職浪人を恐れる気持ちもモチベーションになっていたと思います。
Q11. 若い時から規模の大きい仕事に取り組むことができるとおっしゃっていましたが、先輩職員のサポートはありましたか?
(名古屋市)
初めて本庁部署に異動した際には、規模の大きい仕事を担当することもありましたが、先輩職員や上司の方を含めて、周囲の方にもサポートしていただきながら、取り組むことができました。
(人事院中部事務局)
周りの職員のサポートはもちろんあります。2、3年で人事異動がありますので、採用時だけではなく人事異動の際も、新しい業務に携わる際は周りの職員や前任者が丁寧に教えてくれますのでご安心ください。逆に自分自身も、後任者や後輩職員へのサポートは積極的に行うようにしており、頼りにされることへの嬉しさも感じています。
初めて本庁部署に異動した際には、規模の大きい仕事を担当することもありましたが、先輩職員や上司の方を含めて、周囲の方にもサポートしていただきながら、取り組むことができました。
(人事院中部事務局)
周りの職員のサポートはもちろんあります。2、3年で人事異動がありますので、採用時だけではなく人事異動の際も、新しい業務に携わる際は周りの職員や前任者が丁寧に教えてくれますのでご安心ください。逆に自分自身も、後任者や後輩職員へのサポートは積極的に行うようにしており、頼りにされることへの嬉しさも感じています。
Q12. 残業はありますか?
(名古屋市)
月平均の超過勤務時間数は13.7時間(令和5年度実績)です。全職員の平均のため、職場や時期によっても異なります。
(人事院中部事務局)
残業は全くないわけではありませんが、部署によって繁忙期や閑散期は様々です。残業が必要な時もありますが、繁忙期も1年中続くわけではありませんし、閑散期はほとんど定時で帰ることができます。年休も自由に取得できますので、繁忙期は周りの職員と協力してひと踏ん張りして、閑散期にリフレッシュする等、メリハリをつけています。
月平均の超過勤務時間数は13.7時間(令和5年度実績)です。全職員の平均のため、職場や時期によっても異なります。
(人事院中部事務局)
残業は全くないわけではありませんが、部署によって繁忙期や閑散期は様々です。残業が必要な時もありますが、繁忙期も1年中続くわけではありませんし、閑散期はほとんど定時で帰ることができます。年休も自由に取得できますので、繁忙期は周りの職員と協力してひと踏ん張りして、閑散期にリフレッシュする等、メリハリをつけています。
Q13. 実際の面接で受けた質問で、印象に残ったものはありますか?
(名古屋市)
私が受験した時は、事前に準備した内容を中心に対応できたので、変わった質問等は無かったと記憶しています。
(人事院中部事務局)
志望動機や自己PR等、典型的な質問は一通り受けますが、面接を進める中で、「面接は面接官との『会話』を通じてどのような人なのかを見る場なんだ。必要以上に緊張してしまったらもったいないな。」というのを強く感じたのは、趣味について聞かれた時でした。私は旅行が趣味なので伊勢神宮に旅行した時の話をしたのですが、イメージしていた面接とは異なり、穏やかに会話をしていた印象でした。一緒に働きたい人かどうかを見る場なんだと感じ、リラックスして素の自分を出すことができました。
私が受験した時は、事前に準備した内容を中心に対応できたので、変わった質問等は無かったと記憶しています。
(人事院中部事務局)
志望動機や自己PR等、典型的な質問は一通り受けますが、面接を進める中で、「面接は面接官との『会話』を通じてどのような人なのかを見る場なんだ。必要以上に緊張してしまったらもったいないな。」というのを強く感じたのは、趣味について聞かれた時でした。私は旅行が趣味なので伊勢神宮に旅行した時の話をしたのですが、イメージしていた面接とは異なり、穏やかに会話をしていた印象でした。一緒に働きたい人かどうかを見る場なんだと感じ、リラックスして素の自分を出すことができました。
Q14. 面接ではニコニコしているのと真面目なのとどちらが好ましいですか?
(名古屋市)
試験を実施する立場としてはお答えできないので、私が面接を受けた際に心がけたこととしてお答えします。 面接はコミュニケーションだと思いますので、その点を意識しました。真面目さ(誠実さ)が伝わるように意識しながらも、一緒に働きたいと思ってもらえるような印象を与えられるように意識しました。
(人事院中部事務局)
もしも私が面接官だったらという個人的な意見になってしまいますが、面接は面接官との「会話」ですので、ずっと緊張で顔がこわばっているより、自然な笑顔で面接官の質問に真摯に回答していただけたら嬉しく思います。ただ、不自然にずっと笑ってる必要はないと思います。
試験を実施する立場としてはお答えできないので、私が面接を受けた際に心がけたこととしてお答えします。 面接はコミュニケーションだと思いますので、その点を意識しました。真面目さ(誠実さ)が伝わるように意識しながらも、一緒に働きたいと思ってもらえるような印象を与えられるように意識しました。
(人事院中部事務局)
もしも私が面接官だったらという個人的な意見になってしまいますが、面接は面接官との「会話」ですので、ずっと緊張で顔がこわばっているより、自然な笑顔で面接官の質問に真摯に回答していただけたら嬉しく思います。ただ、不自然にずっと笑ってる必要はないと思います。
Q15. 公務員は、旧型の体系が問題視されがちですが、実態はどのようになっているのでしょうか。また、今後改善の兆しは見えていますか?
(名古屋市)
公務の特性上、法令や手続きを経ないといけない場面は多いですが、市民サービスの向上と働き方改革のため、デジタルの活用など業務の効率化に取り組んでいます。また、人事異動においては、庁内公募制度や立候補型異動希望申告制度など、自ら挑戦し、活躍の場所を広げる制度もあります。
(人事院中部事務局)
多くの業務でデジタル化は進んでおり、紙や押印の文化は見直されています。 また、上司の言うことには絶対に従うといったような文化は全くなく、採用当初から自分の意見を出しやすい風通しの良い職場だと思います。
公務の特性上、法令や手続きを経ないといけない場面は多いですが、市民サービスの向上と働き方改革のため、デジタルの活用など業務の効率化に取り組んでいます。また、人事異動においては、庁内公募制度や立候補型異動希望申告制度など、自ら挑戦し、活躍の場所を広げる制度もあります。
(人事院中部事務局)
多くの業務でデジタル化は進んでおり、紙や押印の文化は見直されています。 また、上司の言うことには絶対に従うといったような文化は全くなく、採用当初から自分の意見を出しやすい風通しの良い職場だと思います。
Q16. 面接練習はトータル何回くらい練習しましたか?
(名古屋市)
筆記試験の仕上げで余裕がなく、公務員予備校での模擬練習等は行いませんでした。他自治体等の面接を通じて経験を重ねました。
(人事院中部事務局)
私は面接への苦手意識が強かったので、可能な限り公務員予備校の模擬面接の予約を入れていました。模擬面接は全て1対1で15分程度行い、トータルで31・32回くらい練習したと記憶しています。
筆記試験の仕上げで余裕がなく、公務員予備校での模擬練習等は行いませんでした。他自治体等の面接を通じて経験を重ねました。
(人事院中部事務局)
私は面接への苦手意識が強かったので、可能な限り公務員予備校の模擬面接の予約を入れていました。模擬面接は全て1対1で15分程度行い、トータルで31・32回くらい練習したと記憶しています。
Q17. 名古屋市職員採用試験に新設された社会人枠について詳しく教えていただきたいです。
(名古屋市)
26~39歳を対象とした試験です。職務経験は問いません。第1次試験に適性検査(SPI3)を導入します(技術区分では専門試験もあります)。公務員試験対策が不要で受験していただきやすい試験となっています。
26~39歳を対象とした試験です。職務経験は問いません。第1次試験に適性検査(SPI3)を導入します(技術区分では専門試験もあります)。公務員試験対策が不要で受験していただきやすい試験となっています。
Q18. 週休三日制について、現場を知る立場からどう考えていらっしゃいますか。
(名古屋市)
本市においては、フレックスタイム制は実施していますが、週休3日制は導入していません。行政サービスの質を維持しつつ、業務を円滑に進められるようにする必要があると思いますが、多様で柔軟な働き方を推進するための手法の一つとして、研究していく必要はあると思います。
(人事院中部事務局)
最近ではテレワークやフレックスタイム制など様々な働き方が浸透していますし、休暇制度も充実しているため自身の業務都合と相談しながら自由に休暇を取得しています。このように働き方改革が進んでいる中で、さらに働き方が柔軟になるのではないかと思います。
本市においては、フレックスタイム制は実施していますが、週休3日制は導入していません。行政サービスの質を維持しつつ、業務を円滑に進められるようにする必要があると思いますが、多様で柔軟な働き方を推進するための手法の一つとして、研究していく必要はあると思います。
(人事院中部事務局)
最近ではテレワークやフレックスタイム制など様々な働き方が浸透していますし、休暇制度も充実しているため自身の業務都合と相談しながら自由に休暇を取得しています。このように働き方改革が進んでいる中で、さらに働き方が柔軟になるのではないかと思います。
Q19. 面接で質問が難しくて、言葉が詰まってしまった場合の対応の仕方を教えていただきたいです。
(名古屋市)
(私自身が受験した時に意識した点としてお答えします)質問が難しいと感じた時は、質問の趣旨や意図を確認し、認識がずれたまま回答しないように注意しました。また、難しいと感じた質問はシンプルに回答し、追加質問で対応するようにしていました。
(人事院中部事務局)
どうしても面接官の質問に対して頭が真っ白になってしまう時もあると思います。面接に苦手意識があるのであれば、できるだけそのような状態にならないように、面接の練習を繰り返して適度な緊張感で面接に臨めるようにしましょう。また、繰り返し掘り下げた質問をしてもらうことで回答の幅が広がると思います。自問自答で深掘りするのでもいいと思います。
それでも難しいと感じる質問をされる時もあるかもしれませんが、一度深呼吸し、自分なりに真摯に回答をすれば十分だと思います。また、すぐに回答するのが難しい場合には、「少しお時間いただいてよいでしょうか?」と素直に伝えても、問題ありません。
(私自身が受験した時に意識した点としてお答えします)質問が難しいと感じた時は、質問の趣旨や意図を確認し、認識がずれたまま回答しないように注意しました。また、難しいと感じた質問はシンプルに回答し、追加質問で対応するようにしていました。
(人事院中部事務局)
どうしても面接官の質問に対して頭が真っ白になってしまう時もあると思います。面接に苦手意識があるのであれば、できるだけそのような状態にならないように、面接の練習を繰り返して適度な緊張感で面接に臨めるようにしましょう。また、繰り返し掘り下げた質問をしてもらうことで回答の幅が広がると思います。自問自答で深掘りするのでもいいと思います。
それでも難しいと感じる質問をされる時もあるかもしれませんが、一度深呼吸し、自分なりに真摯に回答をすれば十分だと思います。また、すぐに回答するのが難しい場合には、「少しお時間いただいてよいでしょうか?」と素直に伝えても、問題ありません。
Q20. 二点お伺いしたいことがございます。地方公務員、国家公務員において、実際にどのような方がご活躍されているのか、活躍されている方々の共通してあげられる特徴などあれば教えていただきたいです。また、これまでご自身が1番きつかった、苦しかったと感じる仕事を教えていただきたいです。
(名古屋市)
主体性を持って個人としても力を発揮されていますが、周囲の方も巻き込むことで、より大きな成果を発揮されていると感じます。 一番苦しかったと感じた仕事は、採用6年目の時に担当した上下水道局の広報に関する計画を作成した時です。局内の様々な関係部署の意見を調整して、一つにまとめることは大変でしたが、その時の経験はその後の仕事にも非常に活かされていると感じます。
(人事院中部事務局)
国家公務員は、国民のニーズを聞き取ることが必要になりますので、他人の意見に真摯に耳を傾け、意図を汲み取る力がある方が多いと思います。
今年度試験係として担当した、国家公務員採用一般職試験(高卒者・社会人)と税務職員採用試験において、台風の影響で試験の実施が延期になったことです。「試験の延期=今まで準備していたことが1からやり直し」ということで、限られた時間の中で迅速かつ正確に業務を進める大変さを体感しました。しかし、とても心強いことに周りの職員が全面サポートしてくれたので、無事に試験を実施することができましたし、このようなイレギュラー対応を乗り越えた時の達成感ややりがいは今までで一番大きかったです。
主体性を持って個人としても力を発揮されていますが、周囲の方も巻き込むことで、より大きな成果を発揮されていると感じます。 一番苦しかったと感じた仕事は、採用6年目の時に担当した上下水道局の広報に関する計画を作成した時です。局内の様々な関係部署の意見を調整して、一つにまとめることは大変でしたが、その時の経験はその後の仕事にも非常に活かされていると感じます。
(人事院中部事務局)
国家公務員は、国民のニーズを聞き取ることが必要になりますので、他人の意見に真摯に耳を傾け、意図を汲み取る力がある方が多いと思います。
今年度試験係として担当した、国家公務員採用一般職試験(高卒者・社会人)と税務職員採用試験において、台風の影響で試験の実施が延期になったことです。「試験の延期=今まで準備していたことが1からやり直し」ということで、限られた時間の中で迅速かつ正確に業務を進める大変さを体感しました。しかし、とても心強いことに周りの職員が全面サポートしてくれたので、無事に試験を実施することができましたし、このようなイレギュラー対応を乗り越えた時の達成感ややりがいは今までで一番大きかったです。
Q21. 実際に働いていらっしゃるお二方から見た、職場の雰囲気を教えていただきたいです。
(名古屋市)
組織として仕事をする意識が高いので、お互いにフォローし合いながら協力して仕事を進める雰囲気があります。
(人事院中部事務局)
正直、公務員に対して堅苦しいイメージを持っていましたが、全然そんなことはありませんでした。業務は自分一人で行うものではなく、周りの職員と協力しながら進めるので、若手職員から幹部職員まで、雑談も含めたコミュニケーションが多く、和気藹々としています。日々のコミュニケーションがあるからこそ、困ったときは周りがすぐに察知してサポートしてくれますし、若手職員ならではの視点での意見を求められることも多いです。周りの職員を巻き込み、巻き込まれながら一体となって業務を進めている印象です。
組織として仕事をする意識が高いので、お互いにフォローし合いながら協力して仕事を進める雰囲気があります。
(人事院中部事務局)
正直、公務員に対して堅苦しいイメージを持っていましたが、全然そんなことはありませんでした。業務は自分一人で行うものではなく、周りの職員と協力しながら進めるので、若手職員から幹部職員まで、雑談も含めたコミュニケーションが多く、和気藹々としています。日々のコミュニケーションがあるからこそ、困ったときは周りがすぐに察知してサポートしてくれますし、若手職員ならではの視点での意見を求められることも多いです。周りの職員を巻き込み、巻き込まれながら一体となって業務を進めている印象です。
Q22. 公務員で働かれている方の中には中途採用の方で活躍されてる方はどのくらいいますか?
(名古屋市)
割合として明確な数字はお示しできませんが、中途採用で活躍している職員も多く、役職者として活躍している職員もいます。普段の業務において「新卒採用」か「中途採用」かを意識することはないと感じます。
(人事院中部事務局)
各府省及び各機関によって異なりますが、中途採用の方も活躍されています。受験資格を満たしている方であれば、国家公務員採用試験を受験いただくこともできますし、各府省及び各機関で選考採用も行われています。選考採用については、興味のある府省等のHPをご確認ください。また、経験者採用試験も行っていますので、詳細は以下のURLからご確認ください。
https://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo/sonota/sonota.html
割合として明確な数字はお示しできませんが、中途採用で活躍している職員も多く、役職者として活躍している職員もいます。普段の業務において「新卒採用」か「中途採用」かを意識することはないと感じます。
(人事院中部事務局)
各府省及び各機関によって異なりますが、中途採用の方も活躍されています。受験資格を満たしている方であれば、国家公務員採用試験を受験いただくこともできますし、各府省及び各機関で選考採用も行われています。選考採用については、興味のある府省等のHPをご確認ください。また、経験者採用試験も行っていますので、詳細は以下のURLからご確認ください。
https://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo/sonota/sonota.html
Q23. 今の時期は何時間くらい勉強されていましたか?また、参考書は何冊ぐらい使用していましたか?
(名古屋市)
公務員予備校の通信講座のテキストや問題集のみでした。(私自身のスタートが遅かったこともありますが)一つの科目で複数の参考書に手を出すよりは、一つのものをしっかりと仕上げることを意識しました。
(人事院中部事務局)
今の時期は、大学の講義や公務員予備校の授業を受けつつ、空いている時間で繰り返し問題演習を行い、不得意分野を洗い出していました。勉強時間は平日は2~3時間、休日は5~7時間ほどだったと思います。
参考書は市販の過去問の他に、公務員予備校のテキストを使用していました。
公務員予備校の通信講座のテキストや問題集のみでした。(私自身のスタートが遅かったこともありますが)一つの科目で複数の参考書に手を出すよりは、一つのものをしっかりと仕上げることを意識しました。
(人事院中部事務局)
今の時期は、大学の講義や公務員予備校の授業を受けつつ、空いている時間で繰り返し問題演習を行い、不得意分野を洗い出していました。勉強時間は平日は2~3時間、休日は5~7時間ほどだったと思います。
参考書は市販の過去問の他に、公務員予備校のテキストを使用していました。
Q24. 適性検査はどんな対策しましたか?
(名古屋市)
私が受験した当時は、まだ公務員試験に適性検査が導入されていない時期でした。
(人事院中部事務局)
国家公務員採用一般職試験(高卒者・社会人)及び税務職員採用試験で適性試験があり、15分間で120問の問題を正確に解く必要があります。実際に試験を受験した職員に伺ったところ、とにかく繰り返し過去問を解いて、パターンを体にたたき込むことが大事とのことです。当日は緊張等もあると思いますので、過去問を解く際は、15分120問を必ず満点取れるようにしていたそうです。
私が受験した当時は、まだ公務員試験に適性検査が導入されていない時期でした。
(人事院中部事務局)
国家公務員採用一般職試験(高卒者・社会人)及び税務職員採用試験で適性試験があり、15分間で120問の問題を正確に解く必要があります。実際に試験を受験した職員に伺ったところ、とにかく繰り返し過去問を解いて、パターンを体にたたき込むことが大事とのことです。当日は緊張等もあると思いますので、過去問を解く際は、15分120問を必ず満点取れるようにしていたそうです。
Q25. 参考書はなにを使って勉強されていましたか?
(人事院中部事務局)
市販の過去問の他には、公務員予備校のテキストを使用していました。問題演習を繰り返しながら、自分の得意分野や不得意分野を見つけていくと効率よく勉強が進められると思います。
市販の過去問の他には、公務員予備校のテキストを使用していました。問題演習を繰り返しながら、自分の得意分野や不得意分野を見つけていくと効率よく勉強が進められると思います。
Q26. 子どもがいても採用して頂けますか?子どもがいる受験者を採用する時に、心配事などはありますでしょうか?
(名古屋市)
ご家族の状況が試験に影響することはございません。
(人事院中部事務局)
お子さんがいらっしゃる場合も、採用に関してご心配いただく必要はありません。国家公務員は育児等に関する両立支援制度が充実しており、例えば育児休業の取得率についても、男女ともに圧倒的に高いです。これは、一般社会に普及させるべき勤務条件は、国家公務員が率先して実施し、民間企業や地方公務員に示すという政策上の背景があります。
ご家族の状況が試験に影響することはございません。
(人事院中部事務局)
お子さんがいらっしゃる場合も、採用に関してご心配いただく必要はありません。国家公務員は育児等に関する両立支援制度が充実しており、例えば育児休業の取得率についても、男女ともに圧倒的に高いです。これは、一般社会に普及させるべき勤務条件は、国家公務員が率先して実施し、民間企業や地方公務員に示すという政策上の背景があります。
Q27. 名古屋市役所では、面接の時どんなところをみて評価されますか?
(名古屋市)
本市の目指す職員像として「自律・協働・成長」を掲げており、それらを踏まえて面接を行っています。目指す職員像については、名古屋市人財戦略ビジョンをご覧ください。
本市の目指す職員像として「自律・協働・成長」を掲げており、それらを踏まえて面接を行っています。目指す職員像については、名古屋市人財戦略ビジョンをご覧ください。
Q28. 名古屋市の論文対策はどのように行いましたか?
(名古屋市)
私自身が受験した時は、公務員予備校のテキストで頻出テーマについて準備する中で、そのテーマに関連する名古屋市の情報を確認するようにしました。
私自身が受験した時は、公務員予備校のテキストで頻出テーマについて準備する中で、そのテーマに関連する名古屋市の情報を確認するようにしました。
Q29. 地方公務員の志望動機で「○○ならでは」という点を考えるのが難しいと感じています。どのように志望動機を構成されましたか?
(名古屋市)
ベースとして、なぜ公務員になりたいか、その中でもなぜ市役所職員なのかという共通する部分を固めることを意識しました。そこにその自治体ならではの要素を足しました。
ベースとして、なぜ公務員になりたいか、その中でもなぜ市役所職員なのかという共通する部分を固めることを意識しました。そこにその自治体ならではの要素を足しました。
Q30. 民間企業と比べて、デメリットだなと感じるところはありますか?
(名古屋市)
公務の特性上、法令や手続きを経ないといけない場面は多いかもしれません。
(人事院中部事務局)
正直なところ、あまりデメリットと感じるところはありませんが、強いて言うなら、公務員の仕事は、影響力が大きいので、意思決定に慎重にならざるをえない場面も少なくないので、速やかに動きたい時に、手続きに手間取って大変だと感じることはあります。ですが、素早く判断することだけが価値ではないので、誤った判断をして県や市、国にとってマイナスの影響をもたらしてしまうことのないよう、慎重に判断することは私は必要なことだと思っています。
公務の特性上、法令や手続きを経ないといけない場面は多いかもしれません。
(人事院中部事務局)
正直なところ、あまりデメリットと感じるところはありませんが、強いて言うなら、公務員の仕事は、影響力が大きいので、意思決定に慎重にならざるをえない場面も少なくないので、速やかに動きたい時に、手続きに手間取って大変だと感じることはあります。ですが、素早く判断することだけが価値ではないので、誤った判断をして県や市、国にとってマイナスの影響をもたらしてしまうことのないよう、慎重に判断することは私は必要なことだと思っています。
Q31. 特別な挑戦や経験のエピソードがなくても面接対策は可能だと思われますか?
(名古屋市)
エピソード自体が特別なものである必要はないと思います。ご自身がどんな事に挑戦し、何を考え、何を学んだのか、その経験を踏まえて今後どうしたいのかが大切であると思います。
(人事院中部事務局)
個人的には可能だと思います。特別な挑戦や経験がなかなか思いつかない場合でも、必ず自分で考え、選択して行動しているはずです。その経験の中でどのように立ち回ったか等、自分自身の取り組む姿勢をもう一度振り返ってみると自分の強みが見えてくるかもしれません。面接は皆さんの人となりを見る場なので、取り繕ったエピソードではなく、ご自身の等身大のエピソードを自己分析を通して磨いてみてください。
エピソード自体が特別なものである必要はないと思います。ご自身がどんな事に挑戦し、何を考え、何を学んだのか、その経験を踏まえて今後どうしたいのかが大切であると思います。
(人事院中部事務局)
個人的には可能だと思います。特別な挑戦や経験がなかなか思いつかない場合でも、必ず自分で考え、選択して行動しているはずです。その経験の中でどのように立ち回ったか等、自分自身の取り組む姿勢をもう一度振り返ってみると自分の強みが見えてくるかもしれません。面接は皆さんの人となりを見る場なので、取り繕ったエピソードではなく、ご自身の等身大のエピソードを自己分析を通して磨いてみてください。
Q32. 公務員という身分を獲得したことによって困ったことなどがあればお聞きしたいです。
(名古屋市)
困ったことではありませんが「公務員の身分」という点であれば、仕事中だけでなく、勤務時間外の私生活においても公務員としての立場を意識した行動が求められます。
(人事院中部事務局)
困ったことは特にございませんが、強いて言うなら、公務員として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する必要があるので、常に身を引き締めています。
困ったことではありませんが「公務員の身分」という点であれば、仕事中だけでなく、勤務時間外の私生活においても公務員としての立場を意識した行動が求められます。
(人事院中部事務局)
困ったことは特にございませんが、強いて言うなら、公務員として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する必要があるので、常に身を引き締めています。
Q33. 民間から公務員に転職した人の場合、仕事内容は民間の業界に近くなるのでしょうか? それとも全く別の仕事を経験できるのでしょうか?
(名古屋市)
民間の業界に近い業務の方もいれば、全く別の仕事をされている方もいます。また、最初の配属は民間の業界と近い仕事の方も、その後の異動で全く別の仕事を経験することもあります。
(人事院中部事務局)
採用される部署や業務内容については、各府省及び各機関によって異なりますので明確なご回答はできかねますが、民間企業での経験を活かすことができる関連部署への配属の可能性もありますし、より多くの経験をしていただくために、採用当初から全く別の業務に携わることができる可能性もあると思います。
民間の業界に近い業務の方もいれば、全く別の仕事をされている方もいます。また、最初の配属は民間の業界と近い仕事の方も、その後の異動で全く別の仕事を経験することもあります。
(人事院中部事務局)
採用される部署や業務内容については、各府省及び各機関によって異なりますので明確なご回答はできかねますが、民間企業での経験を活かすことができる関連部署への配属の可能性もありますし、より多くの経験をしていただくために、採用当初から全く別の業務に携わることができる可能性もあると思います。
Q34. ゼミやサークルに入っていないことはやはり面接において不利になりますか?
(名古屋市)
ゼミやサークルに所属していないことで、不利になることはありません。単に所属しているかどうかではなく、どのようなことに取り組み、そこから何を得たのかが大切であると思います。
(人事院中部事務局)
個人的には不利にならないと思います。ご自身の人生の中で経験したこと、乗り越えたこと、成長したことのエピソードとして取り上げやすいのはゼミやサークルでの活動かもしれませんが、それらに入っていないことで不利になることはありません。自己分析を進めてみて、今まで頑張ってきたことや力を入れてきたことを深掘りしてみて、ご自身にしかない長所や短所を見つけてみてください。その長所が働いていく中で活かすことができる大きな強みになるはずですし、短所を見つけることで自分の乗り越え方に向き合うことができると思います。
ゼミやサークルに所属していないことで、不利になることはありません。単に所属しているかどうかではなく、どのようなことに取り組み、そこから何を得たのかが大切であると思います。
(人事院中部事務局)
個人的には不利にならないと思います。ご自身の人生の中で経験したこと、乗り越えたこと、成長したことのエピソードとして取り上げやすいのはゼミやサークルでの活動かもしれませんが、それらに入っていないことで不利になることはありません。自己分析を進めてみて、今まで頑張ってきたことや力を入れてきたことを深掘りしてみて、ご自身にしかない長所や短所を見つけてみてください。その長所が働いていく中で活かすことができる大きな強みになるはずですし、短所を見つけることで自分の乗り越え方に向き合うことができると思います。
Q35. 業務の中で課題に感じていることを教えていただきたいです。(個人的なことでも、市・国家としてでも構いません)
(名古屋市)
個人として感じていることとしてお答えします。上下水道局時代も含めて、広報に携わる機会が比較的多くありました。防災など市民に必要な情報を伝えるために、限りある予算の中で、どのように興味関心を持っていただくかは難しさを感じながら、試行錯誤していました。
(人事院中部事務局)
今年度任用係を担当して個人的に課題に感じたことは、SNSをより柔軟に活用できるようになればいいなということです。任用係では、国家公務員の魅力発信や志望者に向けた業務説明会等の運営・実施を行っています。国家公務員の魅力を発信し、受け手にとって身近に感じてもらうためには、現状よりも多くのSNS媒体を利用することや発信力が必要になるのではないかと思い、将来的にも引き続く課題だと思っています。
個人として感じていることとしてお答えします。上下水道局時代も含めて、広報に携わる機会が比較的多くありました。防災など市民に必要な情報を伝えるために、限りある予算の中で、どのように興味関心を持っていただくかは難しさを感じながら、試行錯誤していました。
(人事院中部事務局)
今年度任用係を担当して個人的に課題に感じたことは、SNSをより柔軟に活用できるようになればいいなということです。任用係では、国家公務員の魅力発信や志望者に向けた業務説明会等の運営・実施を行っています。国家公務員の魅力を発信し、受け手にとって身近に感じてもらうためには、現状よりも多くのSNS媒体を利用することや発信力が必要になるのではないかと思い、将来的にも引き続く課題だと思っています。
Q36. 必ず、毎年各職種に募集がされるとは限らないと聞きました。そこで、早期選考において志望職種が募集されていない場合、秋の募集もない可能性が高いと思った方が良いのでしょうか。
(名古屋市)
毎年、年間の試験日程を公開する際に実施予定の試験区分もお知らせしています。 それ以外の試験区分については、組織や人員の状況に応じて、実施する可能性もありますので、過去の実施状況等も参考に、各試験案内公表の際にご確認ください。
(人事院中部事務局)
採用人数については、各府省及び各機関によって異なり、採用がない年もございます。詳細は各府省及び各機関のHPでご確認ください。
毎年、年間の試験日程を公開する際に実施予定の試験区分もお知らせしています。 それ以外の試験区分については、組織や人員の状況に応じて、実施する可能性もありますので、過去の実施状況等も参考に、各試験案内公表の際にご確認ください。
(人事院中部事務局)
採用人数については、各府省及び各機関によって異なり、採用がない年もございます。詳細は各府省及び各機関のHPでご確認ください。
Q37. 実際の試験時間で問題を解く練習や、論文試験対策はどのような教材を使用して練習されていましたか?
(名古屋市)
基本的には公務員予備校の教材を使用していましたが、直前期は予想問題集も使用しました。
(人事院中部事務局)
問題については、公務員予備校から提供されたものを利用していました。論文試験対策については、公務員予備校で文章の構成を教えていただき、添削してもらいながらブラッシュアップしていきました。
基本的には公務員予備校の教材を使用していましたが、直前期は予想問題集も使用しました。
(人事院中部事務局)
問題については、公務員予備校から提供されたものを利用していました。論文試験対策については、公務員予備校で文章の構成を教えていただき、添削してもらいながらブラッシュアップしていきました。
Q38. 最近だと時代に合わせて行政の手続きなどもAI利用などスマート化しているかと思います。国家一般、地方公務員関わらず、DXに対応してけるような取り組みが内部、外部であると思うのですが、そういった情報関係における知識やスキルは事前にあった方が良いですか?
(名古屋市)
事前にそうした知識がなくても、入庁後に研修や業務を通じて、必要な知識を習得している職員もいます。情報関係に限らず、どのような知識やスキルをお持ちかということは、その方の強みや個性であると思います。なお、情報関係の専門的な知識を活かして業務に従事する「情報区分」もあります。
(人事院中部事務局)
情報関係における知識やスキルが事前にあれば、それは業務に必ず活かすことができるので強みになりますが、事前の知識がなくても全く問題ないのでご安心ください。採用されてから必要な知識は身につけていくことができますので、極論を言ってしまえば、Excelに文字を打つことができれば十分だと思います。
個人的には、タッチタイピングができるようになっていたのは、タイピングにストレスがないので良かったなと思いました。
事前にそうした知識がなくても、入庁後に研修や業務を通じて、必要な知識を習得している職員もいます。情報関係に限らず、どのような知識やスキルをお持ちかということは、その方の強みや個性であると思います。なお、情報関係の専門的な知識を活かして業務に従事する「情報区分」もあります。
(人事院中部事務局)
情報関係における知識やスキルが事前にあれば、それは業務に必ず活かすことができるので強みになりますが、事前の知識がなくても全く問題ないのでご安心ください。採用されてから必要な知識は身につけていくことができますので、極論を言ってしまえば、Excelに文字を打つことができれば十分だと思います。
個人的には、タッチタイピングができるようになっていたのは、タイピングにストレスがないので良かったなと思いました。
Q39. 面接で答えるのが難しいと感じた質問があれば教えていただきたいです。
(名古屋市)
私が受験した時は、特に難しいと感じた質問はありませんでした。最初は難しいと感じた質問も面接はコミュニケーションと捉えて、やり取りを重ねる中で、どのような点を聞かれているのかを考えて対応しました。
(人事院中部事務局)
個人的にドキッとした質問は、人事院本院の官庁訪問の際の質問で「霞が関に関する最近のニュースで気になることはなんですか?」というものでした。とっさに思いつかず、頭をフル回転させて自分なりの精一杯の回答をした記憶があります。国家公務員だけでなく、地方公務員も含めて共通することですが、やはり、関連する情報のアンテナは敏感に張っていた方がいいなと痛感した瞬間でした。
私が受験した時は、特に難しいと感じた質問はありませんでした。最初は難しいと感じた質問も面接はコミュニケーションと捉えて、やり取りを重ねる中で、どのような点を聞かれているのかを考えて対応しました。
(人事院中部事務局)
個人的にドキッとした質問は、人事院本院の官庁訪問の際の質問で「霞が関に関する最近のニュースで気になることはなんですか?」というものでした。とっさに思いつかず、頭をフル回転させて自分なりの精一杯の回答をした記憶があります。国家公務員だけでなく、地方公務員も含めて共通することですが、やはり、関連する情報のアンテナは敏感に張っていた方がいいなと痛感した瞬間でした。
Q40. 自分が採用の面接官だったら、どんな質問をしますか? なぜその質問をしたいのか背景も交えて教えてもらえたら嬉しいです。
(名古屋市)
本市の目指す職員像として「自律・協働・成長」を掲げており、それらの要素を踏まえた質問をすると思います。
(人事院中部事務局)
実際に官庁訪問で面接官を何度かやりましたが、私は“一緒に働きたい人かどうか”という観点で質問をすることが多いです。志望動機や興味がある業務についての質問は、本当に志望度が高いのかという観点で質問しますが、それよりも、受験者の皆さんの経験に基づいた考え方や行動をお伺いし、「この方が一緒に働く仲間になったら・・・」とイメージしながら面接を行っています。
本市の目指す職員像として「自律・協働・成長」を掲げており、それらの要素を踏まえた質問をすると思います。
(人事院中部事務局)
実際に官庁訪問で面接官を何度かやりましたが、私は“一緒に働きたい人かどうか”という観点で質問をすることが多いです。志望動機や興味がある業務についての質問は、本当に志望度が高いのかという観点で質問しますが、それよりも、受験者の皆さんの経験に基づいた考え方や行動をお伺いし、「この方が一緒に働く仲間になったら・・・」とイメージしながら面接を行っています。
Q41. 来年度3年生になるのですが、民間のインターンにいきながら公務員の勉強をするのは可能ですか? どちらかに絞った方がいいですか?
(名古屋市)
(個人の状況にも寄りますが)不可能ではないと思います。名古屋市の試験では、教養型やプレゼンテーション型など筆記試験の負担が少ない試験区分もあるため、こうした試験区分を活用することで両立しやすくなる面もあると思います。
(人事院中部事務局)
個人的には可能だと思いますが、幅広く手を付けて全てが中途半端になってしまうととてももったいないので、もしも厳しいと感じたら、取捨選択も必要になってくるかと思います。民間企業も公務員も就職先として選択肢を広げていれば、自分の中で志望度がはっきりしてくるかもしれません。
(個人の状況にも寄りますが)不可能ではないと思います。名古屋市の試験では、教養型やプレゼンテーション型など筆記試験の負担が少ない試験区分もあるため、こうした試験区分を活用することで両立しやすくなる面もあると思います。
(人事院中部事務局)
個人的には可能だと思いますが、幅広く手を付けて全てが中途半端になってしまうととてももったいないので、もしも厳しいと感じたら、取捨選択も必要になってくるかと思います。民間企業も公務員も就職先として選択肢を広げていれば、自分の中で志望度がはっきりしてくるかもしれません。
Q42. 社会人の試験では、社会人経験が直接どのように活かせるか重視されますか?長く子育てや主婦をメインでしていた場合は、志望できない、または対象外ですか?
(名古屋市)
春と秋に実施する社会人枠は職務経験を問いません。年齢が26歳から39歳の方であれば対象となります。
(人事院中部事務局)
面接の際は、前職での経験等について質問されることもあるかもしれませんが、それだけが重要視されるわけではありません。前職での経験が採用先の府省及び機関で活かすことができれば、それに越したことはありませんが、全く別の業務に携わる可能性もあります。また、子育てや主婦を長い間していても全く問題ありませんのでご安心ください。
春と秋に実施する社会人枠は職務経験を問いません。年齢が26歳から39歳の方であれば対象となります。
(人事院中部事務局)
面接の際は、前職での経験等について質問されることもあるかもしれませんが、それだけが重要視されるわけではありません。前職での経験が採用先の府省及び機関で活かすことができれば、それに越したことはありませんが、全く別の業務に携わる可能性もあります。また、子育てや主婦を長い間していても全く問題ありませんのでご安心ください。
Q43. 社会人試験の受験者に対して求めることはどういったことでしょうか? 大卒程度の一般枠との違いはどのようなことになりますか?
(名古屋市)
26~39歳を対象とした試験です。職務経験は問いません。第1次試験に適性検査(SPI3)を導入します(技術区分では専門試験もあります。)。公務員試験対策が不要で受験していただきやすい試験となっています。
(人事院中部事務局)
社会人の方を対象とした試験は、人事院が行っているものですと、国家公務員採用一般職試験(社会人試験(係員級))(試験の区分は基本的に技術系のみ)や経験者採用試験があります。また、受験年度に30歳未満である場合には、国家公務員採用総合職試験・一般職試験(大卒程度試験)の受験も可能です。
なお、人事院が行っているもの以外にも、各府省で選考採用を行っている場合もあります(詳細は後述のHPもご参照ください。)。
主に社会人を対象とする一般職試験(社会人試験(係員級))や経験者採用試験、各府省の選考採用については、職場である程度即戦力として働いてもらうことを期待されているものと思いますので、社会人としてどのような経験を積んできて、どのようなスキルを身につけてきたかを面接で話ができると良いものと思います。 https://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo/sonota/sonota.html
26~39歳を対象とした試験です。職務経験は問いません。第1次試験に適性検査(SPI3)を導入します(技術区分では専門試験もあります。)。公務員試験対策が不要で受験していただきやすい試験となっています。
(人事院中部事務局)
社会人の方を対象とした試験は、人事院が行っているものですと、国家公務員採用一般職試験(社会人試験(係員級))(試験の区分は基本的に技術系のみ)や経験者採用試験があります。また、受験年度に30歳未満である場合には、国家公務員採用総合職試験・一般職試験(大卒程度試験)の受験も可能です。
なお、人事院が行っているもの以外にも、各府省で選考採用を行っている場合もあります(詳細は後述のHPもご参照ください。)。
主に社会人を対象とする一般職試験(社会人試験(係員級))や経験者採用試験、各府省の選考採用については、職場である程度即戦力として働いてもらうことを期待されているものと思いますので、社会人としてどのような経験を積んできて、どのようなスキルを身につけてきたかを面接で話ができると良いものと思います。 https://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo/sonota/sonota.html
Q44. 受けられるものは受けられるだけ受けたとおっしゃっていましたが、市役所試験に関して、自治体研究は志望先の自治体全て同程度で深掘りを進めていましたか?
(名古屋市)
自治体研究は筆記試験に通過してから深掘りしました。自己分析やなぜ公務員になりたいかという共通部分をしっかりと固めておいて、そこに各都市の情報を必要に応じて追加したようなイメージです。時間的な制約もあり、正直なところ志望度に応じて深掘りの差はあったと思います。
(人事院中部事務局)
地方公務員上級で受験した市役所については、試験当日までに市の特徴や特色、政策等をしっかり調べてから臨みました。私は国家公務員への志望度が高かったので第2次試験以降の面接試験は受験しませんでしたが、第1次試験の論文試験の出題内容は、その市の特徴等を交えながら自分の考えを述べるものだったので、深掘りしておいて良かったと思いました。
自治体研究は筆記試験に通過してから深掘りしました。自己分析やなぜ公務員になりたいかという共通部分をしっかりと固めておいて、そこに各都市の情報を必要に応じて追加したようなイメージです。時間的な制約もあり、正直なところ志望度に応じて深掘りの差はあったと思います。
(人事院中部事務局)
地方公務員上級で受験した市役所については、試験当日までに市の特徴や特色、政策等をしっかり調べてから臨みました。私は国家公務員への志望度が高かったので第2次試験以降の面接試験は受験しませんでしたが、第1次試験の論文試験の出題内容は、その市の特徴等を交えながら自分の考えを述べるものだったので、深掘りしておいて良かったと思いました。
Q45. 今後の説明会の予定がありましたら教えて頂きたいです
(名古屋市)
名古屋市人事委員会事務局X・Instagramで参加情報を随時発信しています。ぜひ、ご覧ください。
https://www.city.nagoya.jp/shisei/category/65-21-0-0-0-0-0-0-0-0.html
(人事院中部事務局)
今後の中部管内の説明会やセミナーの予定は、人事院中部事務局のHPに掲載しますので、随時ご確認ください。また、人事院中部事務局のXでも試験や説明会についての情報発信を行っています。こちらも是非フォローいただけると嬉しいです。
HP:https://www.jinji.go.jp/chubu/saiyo/event.html
X:https://x.com/NPA_jinchubu
名古屋市人事委員会事務局X・Instagramで参加情報を随時発信しています。ぜひ、ご覧ください。
https://www.city.nagoya.jp/shisei/category/65-21-0-0-0-0-0-0-0-0.html
(人事院中部事務局)
今後の中部管内の説明会やセミナーの予定は、人事院中部事務局のHPに掲載しますので、随時ご確認ください。また、人事院中部事務局のXでも試験や説明会についての情報発信を行っています。こちらも是非フォローいただけると嬉しいです。
HP:https://www.jinji.go.jp/chubu/saiyo/event.html
X:https://x.com/NPA_jinchubu
Q46. インターンや説明会に参加していなくても意欲は伝わりますか?
(名古屋市)
インターンシップやガイダンスへの参加・不参加が受験に影響することはありません。
(人事院中部事務局)
インターンや説明会に参加していなくても問題ないと思いますが、実際に足を運ぶことで業務内容を詳細に知ることができますし、何より職員の生の声を聞くことができて職場の雰囲気を知ることができると思います。様々なインターンや説明会に参加することでご自身の選択肢も広がり、モチベーション向上にも繋がると思うので、是非足を運んでみてください。
インターンシップやガイダンスへの参加・不参加が受験に影響することはありません。
(人事院中部事務局)
インターンや説明会に参加していなくても問題ないと思いますが、実際に足を運ぶことで業務内容を詳細に知ることができますし、何より職員の生の声を聞くことができて職場の雰囲気を知ることができると思います。様々なインターンや説明会に参加することでご自身の選択肢も広がり、モチベーション向上にも繋がると思うので、是非足を運んでみてください。
Q47. 教養試験は社会人経験がある方の方が採用率が高いのでしょうか
(名古屋市)
22歳から25歳を対象とする行政(教養型)の試験のことを指すのであれば、社会人経験(職務経験)の有無自体は評価に直接関係ありません。
(人事院中部事務局)
国家公務員採用総合職試験の教養区分は、受験資格があればどなたでも受験することができるので、社会人経験がある方が採用率が高いというわけではありません。なお、2025年の試験から国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)でも試験の区分で教養区分が新設されますので、興味のある方は是非ご確認ください。
22歳から25歳を対象とする行政(教養型)の試験のことを指すのであれば、社会人経験(職務経験)の有無自体は評価に直接関係ありません。
(人事院中部事務局)
国家公務員採用総合職試験の教養区分は、受験資格があればどなたでも受験することができるので、社会人経験がある方が採用率が高いというわけではありません。なお、2025年の試験から国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)でも試験の区分で教養区分が新設されますので、興味のある方は是非ご確認ください。
Q48. 国家公務員の建築職には、どのようなお仕事がありますか。また、どのような職場の環境ですか。(インターンで地方公務員について学んだことと比較したいため)高専卒より大学卒の方が有利でしょうか。 技術職の場合、採用においてより多くの専門知識を持っている方が有利でしょうか。
(人事院中部事務局)
国家公務員の建築職には様々な道があります。全てを詳細に紹介するのは難しいので、一部を紹介します。国土交通省では設計業務の発注を行っていたり、財務省では国家公務員の共同住宅である宿舎の整備を行ったり、外務省では大使館などの在外公館施設の整備を行ったり、法務省では刑務所のような矯正施設の工事・調整を行ったりしています。国土交通省は建築のイメージがあるかと思いますが、財務省、外務省、法務省などで建築の仕事があるのは意外に思われる方もいるのではないでしょうか。他にもその省庁ごとの特色を活かした建築の活躍のフィールドがありますので是非調べてみてください。
高専卒が大卒と比べて不利になることはありません。採用後のキャリアパスも含め、差異が設けられることはありません。
採用に当たって、専門知識の多い少ないがクリティカルな要素になることはあまりないと思います。もちろん、知識があるに越したことはありませんが、どの省庁であっても採用後に勉強できる機会、研修制度も充実していますので、気にしすぎる必要はないと思います。
国家公務員の建築職には様々な道があります。全てを詳細に紹介するのは難しいので、一部を紹介します。国土交通省では設計業務の発注を行っていたり、財務省では国家公務員の共同住宅である宿舎の整備を行ったり、外務省では大使館などの在外公館施設の整備を行ったり、法務省では刑務所のような矯正施設の工事・調整を行ったりしています。国土交通省は建築のイメージがあるかと思いますが、財務省、外務省、法務省などで建築の仕事があるのは意外に思われる方もいるのではないでしょうか。他にもその省庁ごとの特色を活かした建築の活躍のフィールドがありますので是非調べてみてください。
高専卒が大卒と比べて不利になることはありません。採用後のキャリアパスも含め、差異が設けられることはありません。
採用に当たって、専門知識の多い少ないがクリティカルな要素になることはあまりないと思います。もちろん、知識があるに越したことはありませんが、どの省庁であっても採用後に勉強できる機会、研修制度も充実していますので、気にしすぎる必要はないと思います。