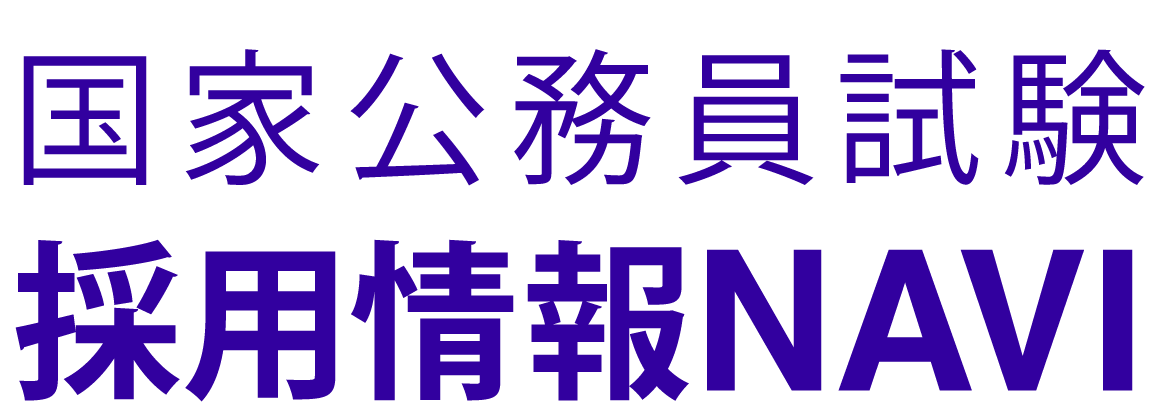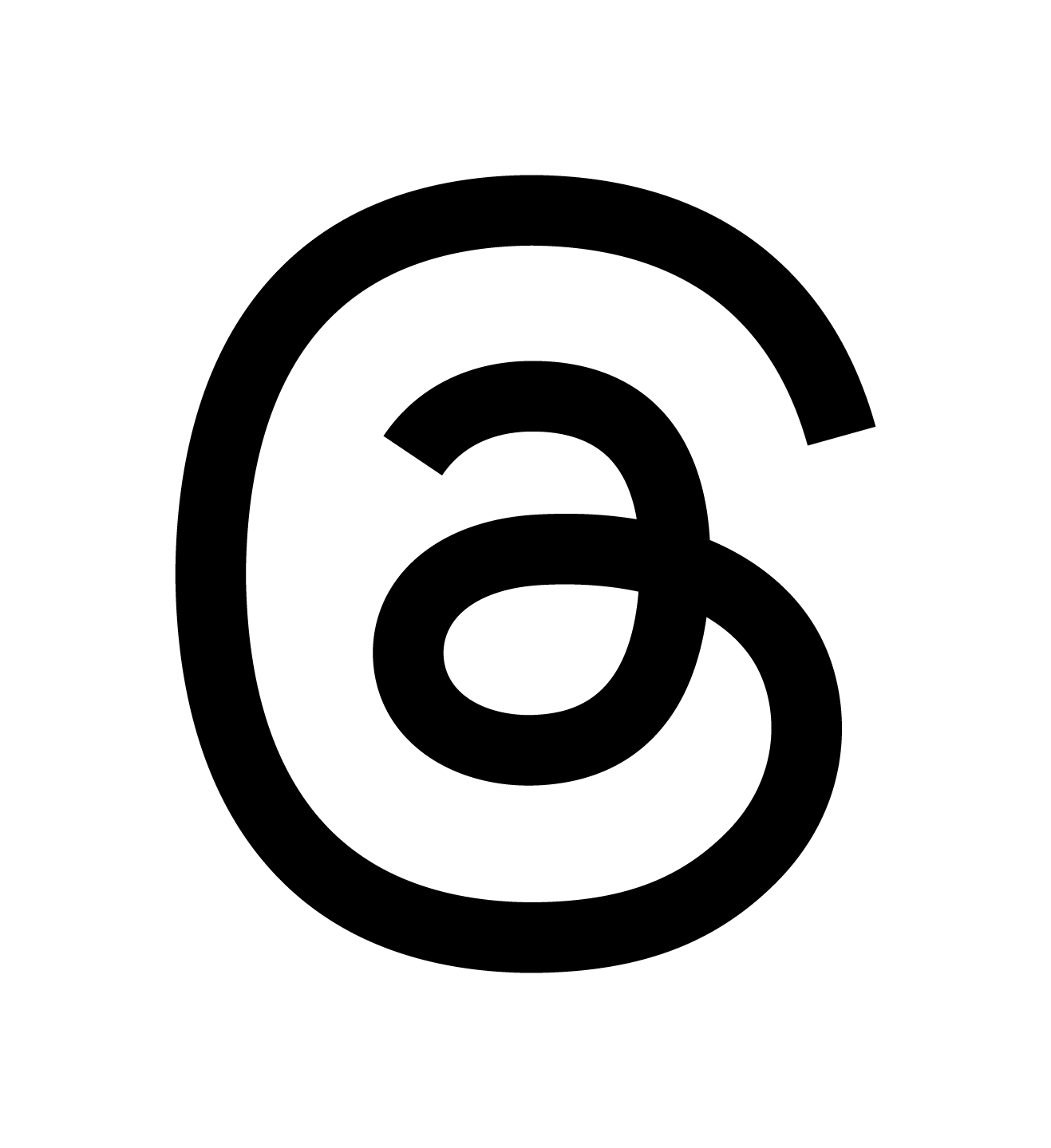「自然共生サイト」認定ロゴマーク
環境省では、民間企業や団体等の方々によって保全に貢献する取組がなされている場所(企業の森、里地里山、都市の緑…など)を「自然共生サイト」として認定する仕組みを2023年4月から開始しました。認定サイトは、生物多様性条約COP15で採択された国際目標のひとつ「30by30目標」の達成にも貢献します。企業や地方公共団体等と連携してオールジャパンで取り組むことが、人々の暮らしを支える自然資本を保全していくことにつながります。
|
|

生物多様性条約COP15における集合写真
2022年12月、生物多様性条約COP15が開催され、環境省は、日本の立場についての発信や、生物多様性関連の途上国支援を行うことについて表明しました。この会議で採択された生物多様性保全のための新たな世界目標「昆明・モントリオール生物多様性枠組」を踏まえ、日本は世界に先駆けて新たな生物多様性国家戦略を策定しました。新たな国家戦略には、2030年ネイチャーポジティブの実現に向けた様々な取組を位置付けています。こうした計画や仕組みづくりには、レンジャー(自然系技官)の現場感覚が欠かせません。
|
|

神の箱庭こと久美浜湾の里風景(山陰海岸国立公園・兜山展望台)
国立公園をご存じですか?
日本を代表する34箇所の自然の風景地であり、生活・文化・歴史の凝縮された物語がある場所です。その魅力を伝え、唯一無二の感動体験を来訪者や地域の皆さんに約束する場所です。
環境省のレンジャー(自然系技官)は現場と霞が関を股にかけ、日本の国立公園の魅力を守り高めて発信する仕事に携わります。自ら大自然を体感しながら、地域の人々と協力して取り組む仕事です。
|
|

国立公園の利用拠点整備
阿寒摩周国立公園の観光の拠点である川湯温泉地区において、自然環境の展示、解説を行う『川湯ビジターセンター』の改修を実施しました。改修に伴って、従来から存在した展示や解説に加えて、軽食を提供するカフェラウンジ、北海道の自然を感じられる開放的なテラスなどを導入し、来館者が快適に過ごせる空間を創出しました。
|
|

アメリカザリガニによる在来生物への影響を説明するパンフレット
アメリカザリガニは身近な生き物ですが、日本の自然環境へ侵入すると、在来の水草や水生昆虫等に壊滅的な影響を与える外来生物です。従来の特定外来生物に指定し、飼育を厳しく規制すると、野生下へ大量に捨てられるおそれがあるため、法律(外来生物法)を改正し、厳しい飼育規制をかけずに、野生下への放出などに限定して規制する新たな制度をつくりました。制度を大きく変えたことで、希少な水辺の保護や身近な水辺の再生を進めることができるようになります。
|
|

帰還困難区域と除染により発生した土壌等を貯蔵する施設
現場の事務所では、福島県内の除染により発生した土壌等を貯蔵するための中間貯蔵施設の整備を行っています。本省でも、福島復興の事業を行う現場事務所をサポートしつつ、さらに今後の展開へ向けた制度構築に取り組んでいます。特に、福島のいまだ残る帰還困難区域の環境再生を更に進める制度をつくるため、現場で得た経験や目線も生かしながら、復興庁を始めとする関係省庁との折衝や国会対応等を行っています。
|
|

地域の再エネ導入拡大を促進すため、ため池等を活用した太陽光発電の導入の支援を行っています。
環境省では、自家消費型・地産地消型の再エネ導入促進をすすめております。ため池や営農地、廃棄物処分施設など、地域の中で新たに太陽光発電設備が設置可能な場所に対して、補助金を創設し、太陽光発電設備の導入拡大を進めています。
|
|

第46回ロンドン条約及び第17回ロンドン議定書科学グループ会合(SG46)各国代表団(2023年3月、カサブランカ(モロッコ))
海洋環境の保護及び保全を目的として、船舶からの廃棄物の海洋投棄についてはロンドン条約及びロンドン議定書により国際的に規制されており、日本でも海洋汚染等防止法によりこれを担保しています。環境省職員は、ロンドン条約及びロンドン議定書の締約国会合や技術的議論が行われる科学グループ会合に日本の代表として出席し、国際的な動向を把握するとともに、それに基づく国内制度の検討及び適正な実施を行っています。
|
|

地域の再生可能エネルギー施設の視察
地方環境事務所に新設された地域脱炭素創生室では、地域の脱炭素を推進するため、様々な関係者と連携しながら日々仕事をしています。例えば、地方公共団体が脱炭素を通じて地域課題を解決できるよう、現地の様子を視察したうえで、どのような手が打てるか一緒になって考え、助言を行っています。また、各省庁の地方支分部局や企業、金融機関等とも意見交換を行い、地域のリアルな声をキャッチしながら、「地域のため」の支援を着実に進めています。
|
|

災害廃棄物の仮置場確認
石川県能登地方で地震が起きた際、環境省の地方環境事務所職員が現地に向かい、仮置場(被災した家屋等から排出される災害廃棄物を一時的に保管する場所)での災害廃棄物排出状況を確認しました。具体的には、指定された分別区分のとおり排出されているか、危険物や有害廃棄物といった持ち込みができないものが排出されていないか、仮置場内での発火の危険性がないか、などを確認しています。
|
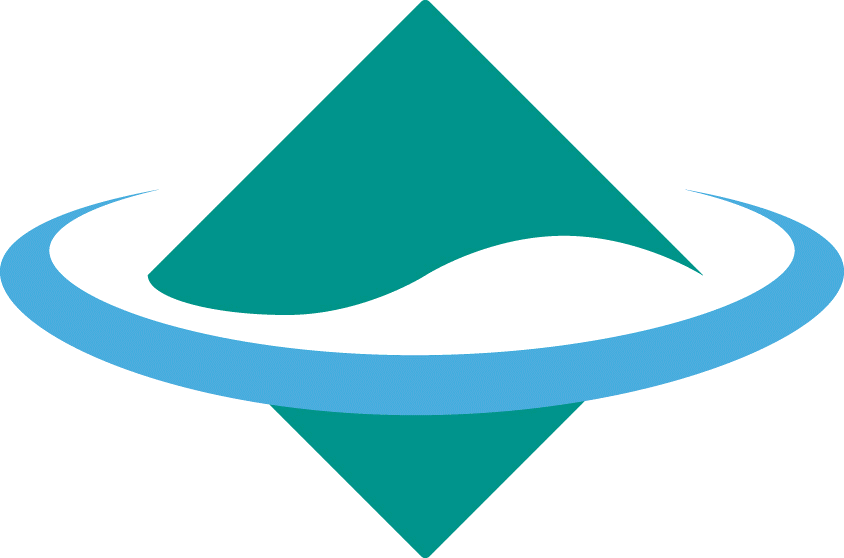 環境省
環境省