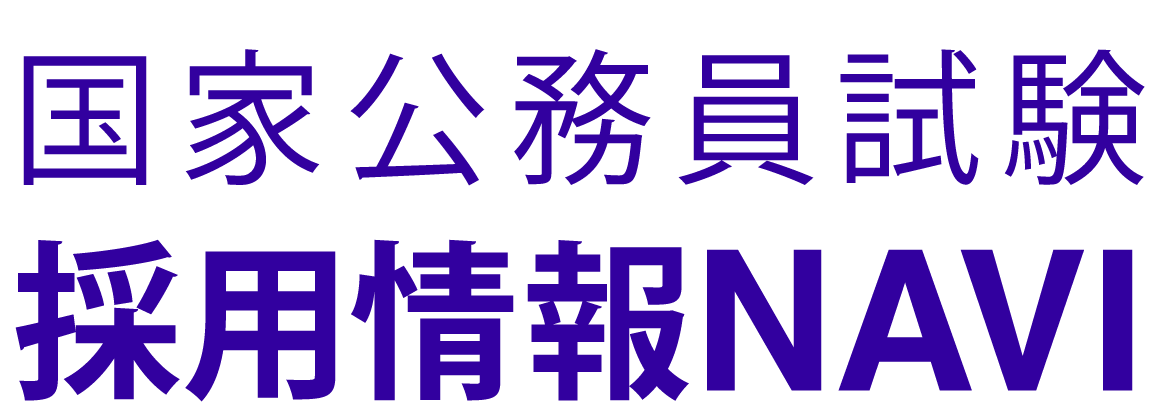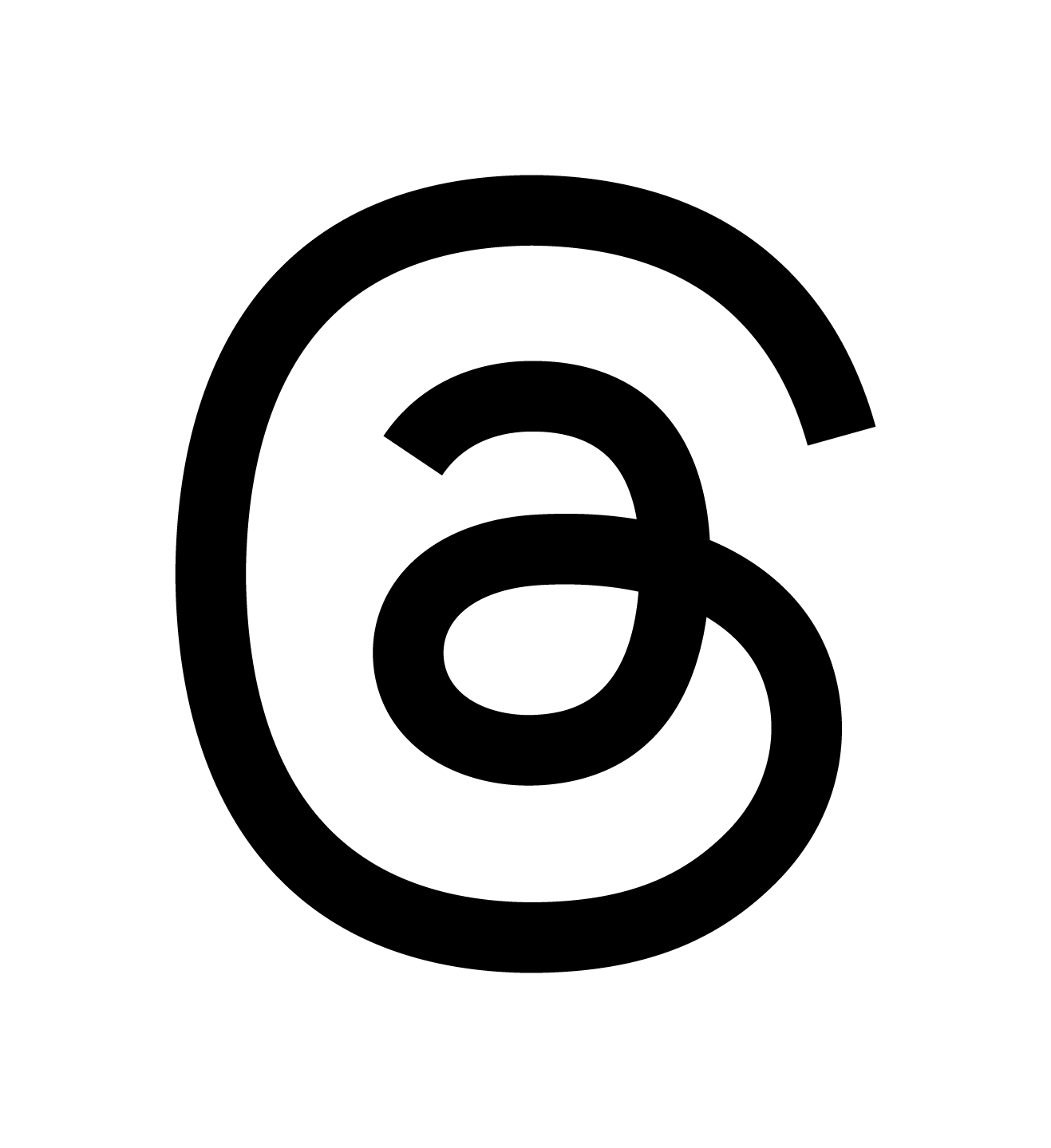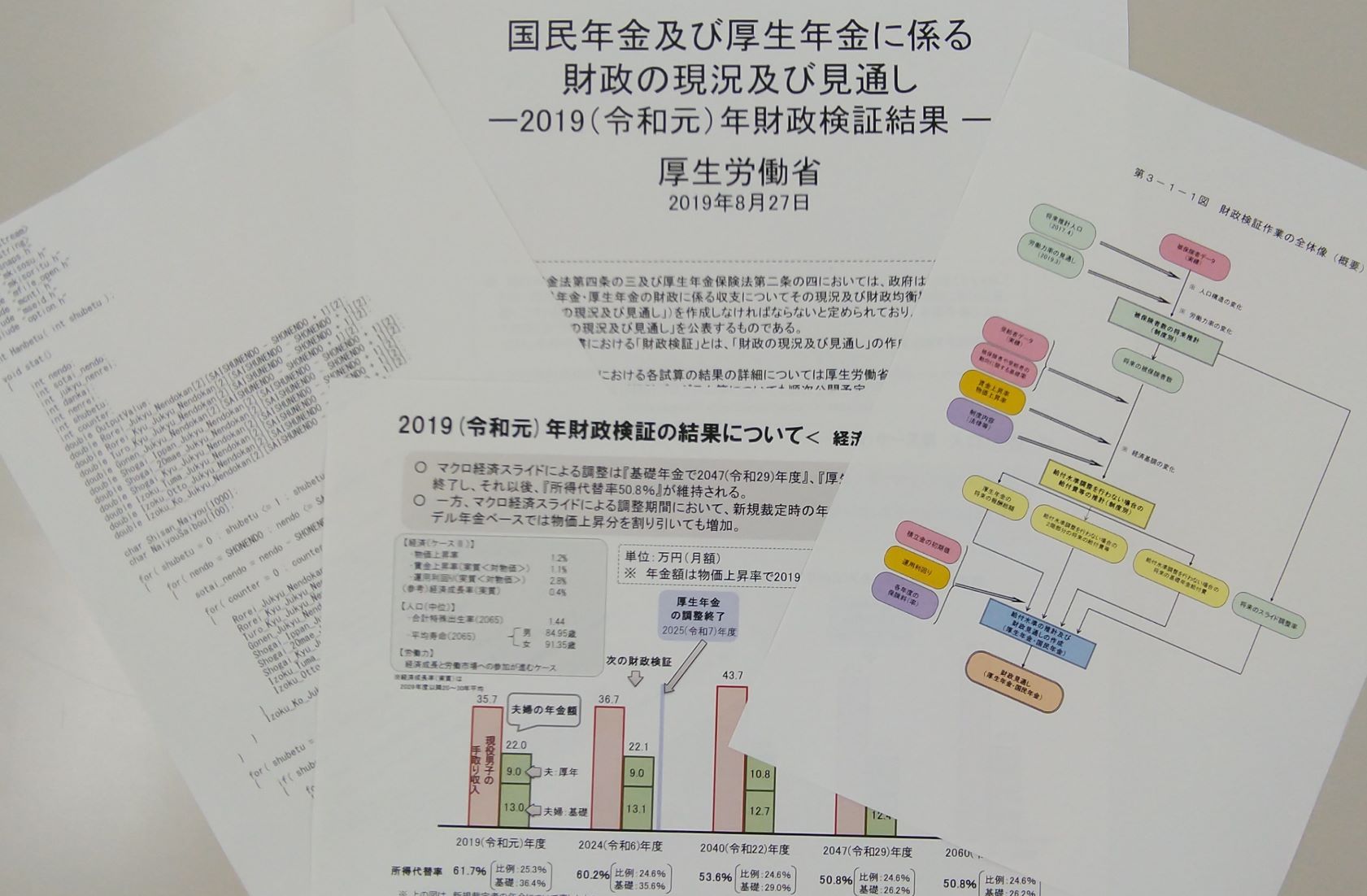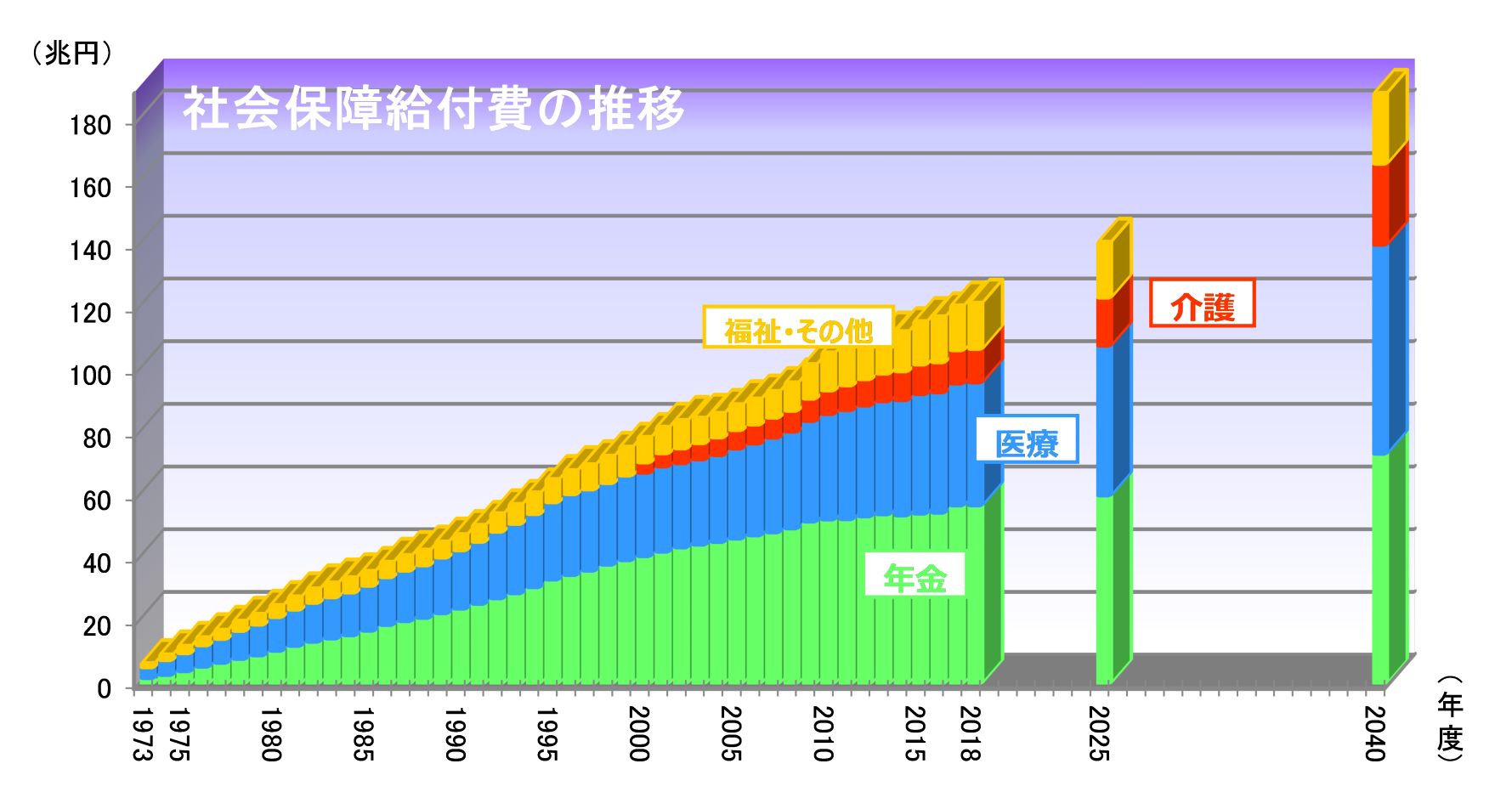| |

厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課
産業保健支援室メンタルヘルス対策係
総合職(工学)
2020年 厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課
2022年 厚生労働省北海道労働局労働基準部安全課
2022年 厚生労働省北海道労働局札幌東労働基準監督署安全衛生課
2022年 現職
※職員の所属(役職)は、原稿執筆時のものを記載しています。
「やり甲斐」を日々感じる職場です!
|
| |
| ◇ 国家公務員になろうと思ったきっかけ |
国民の命を守る仕事に就きたいと漠然と思ったことがきっかけです。利益を顧みずに、また対象を限定させずに国民の命を守ることができるのは、国家公務員だけだと当時は考えたため、志望しました。
|
| ◇ 記憶に残っている業務 |
G7倉敷労働雇用大臣会合に上司の随行で参加させていただいたことが特に印象に残っています。私が担当の一人である「労働者のメンタルヘルス対策」がセッションテーマの一つとなり、メンタルヘルスに係る問題意識や対策等について、G7各国の代表者が熱く議論を交わす場に同席できたことは、非常に良い経験になったと感じております。
|
| ◇ 日々の仕事 |
現在は、労働者のメンタルヘルス対策を担当しています。具体的には、働く人のメンタルヘルスポータルサイト「こころの耳」に係る委託業者との調整や、事業主団体等が傘下の中小企業等に対し、産業保健サービスを提供した場合にその費用を助成する「団体経由産業保健活動推進助成金」の運営等を担当しています。一人で黙々と作業することは全くなく、班や室の皆様に助けていただきながら日々の業務をなんとか乗り越えています。
|
| ◇ 仕事の面白み、やり甲斐 |
「やり甲斐」は間違いなくあります。家族や友人等との会話やニュース等において、自分が担当する制度(例えばストレスチェックや墜落制止用器具)が話題に上がって、実際に利用したとの話を聞くと、仕事に対するモチベーションが上がります。また、「仕事がしんどい。ゆううつだ。」との声を聞くと、他人事に思ってはいけないので、もっとがんばろうと思いますし、「やり甲斐」も感じます。
|
| ◇ テレワークの経験 |
緊急事態宣言下は、週に2,3回ほどテレワークをしておりました。執務室にいると電話対応や他部署からの照会等忙しなく時間が過ぎてしまいますが、テレワークでは主に、考え込む必要がある業務(都道府県労働局からの疑義照会等)を中心に取り組み、より効率的に業務に取り組むことができたと思います。
|
| ◇ フレックス勤務の経験 |
緊急事態宣言下は、感染拡大防止のため、毎日1.5時間早く出勤しておりました。通勤電車のピーク時間をかわすことができたと同時に、退勤後の時間も確保できていたので、非常に有意義な時間の使い方ができていたと思います。最近も、自身の都合に応じてフレックス勤務は可能ですので、非常に風通しの良い職場だと日々感じております。
|
| ◇ ある1日のスケジュール |
09:30 登庁、登庁後すぐメールチェック
10:00 メンタルヘルスポータルサイト「こころの耳」に係る委託業者との打合せ、
10:00 終了後今後の方針を上司に相談
11:00 メールを読み漁り、依頼に応じてたたき台作成、不明箇所は上司にすぐ相談
12:30 昼食(日比谷公園でランチ)
14:00 メンタルヘルスに係る関係会議準備、他部局、他省庁との調整に苦労する
18:15 退庁
19:00 友人とゴルフバーで疲れを発散
|
|
| 他府省の記事も見てみる |
 厚生労働省
厚生労働省