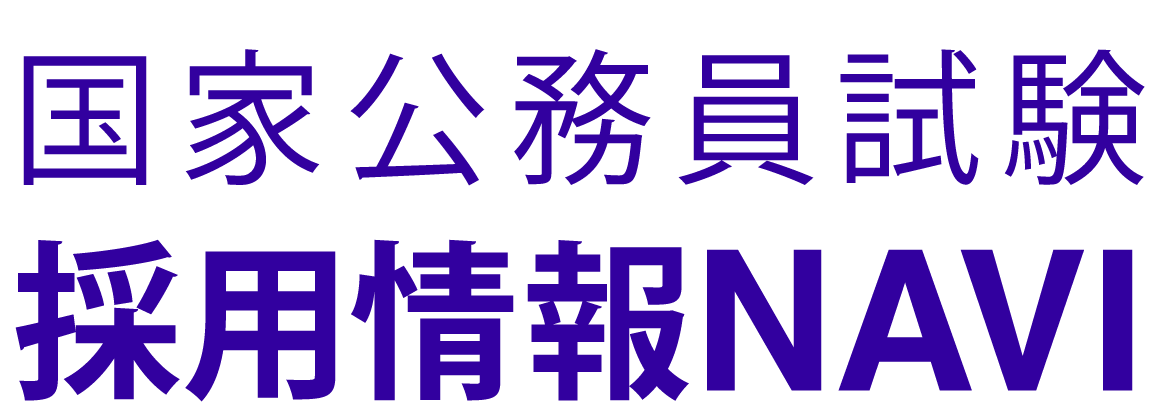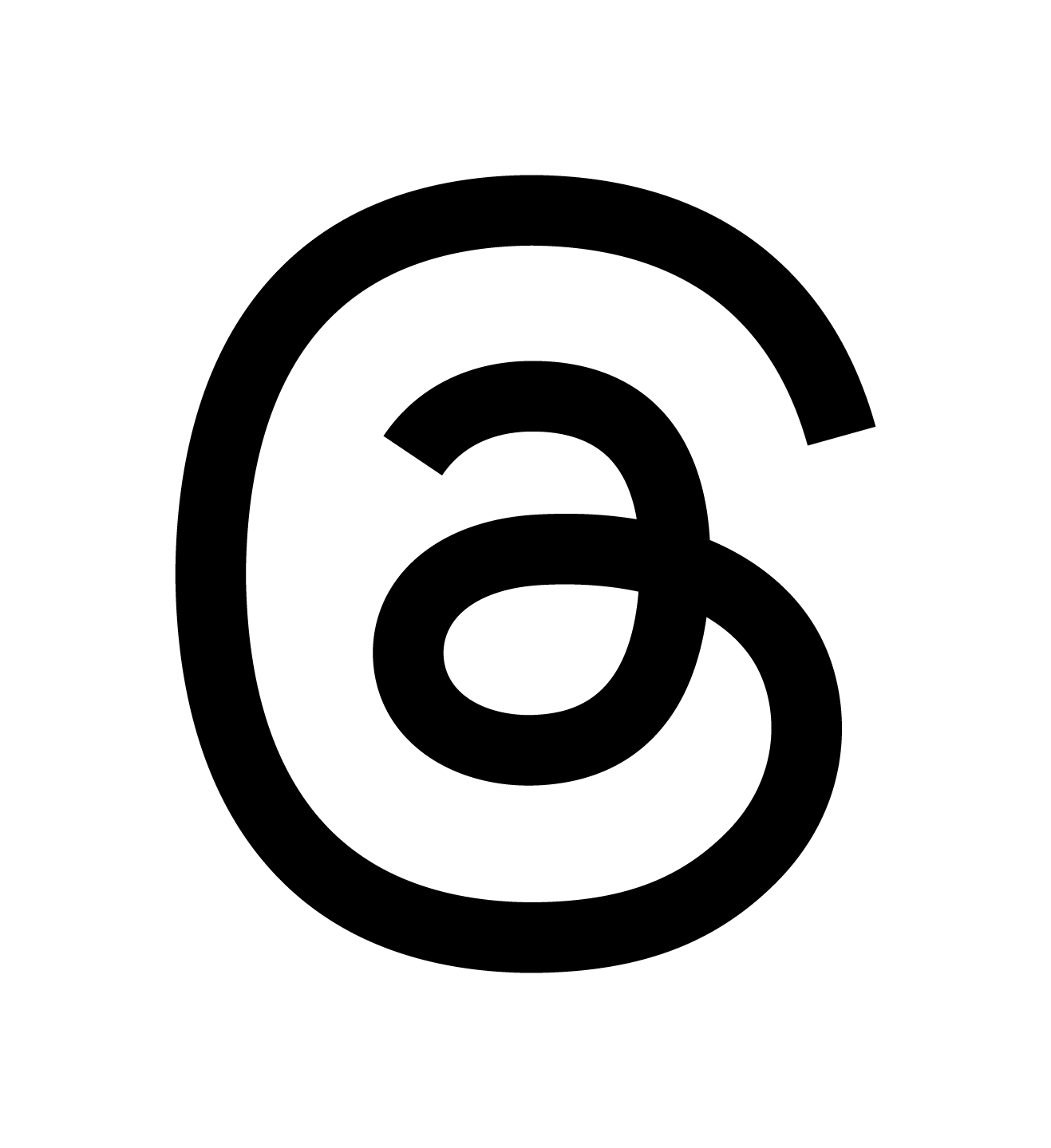企業が管理するブドウ畑も自然共生サイトに認定
(キリンホールディングス株式会社・シャトー・メルシャン 椀子ヴィンヤード)
2030年までに生物多様性の損失を止め、回復軌道に乗せる、ネイチャーポジティブの実現に向けては、企業や地方公共団体など様々な主体による取組を促進することが重要です。環境省では民間等の取組によって生物多様性の保全が図られている場所を「自然共生サイト」として認定する取組を令和5年度から開始し、全国184か所を認定しました。また、取組をさらに促進していくために「地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律」を新たに制定するなど、オールジャパンでネイチャーポジティブの実現に取組むための制度づくりを進めています。
|
|

被災自治体での情報収集等 (能登半島地震)
環境省では、災害時にペットを飼育している方の安全や命を守るため、平時から自治体でのペット同行避難訓練の支援や、ペット同行避難等に関するガイドラインの作成、周知などを行っています。
能登半島地震においては、発災後直後から職員が現地に入り、ペットの同行避難の状況の情報収集などを行いました。その結果を踏まえて、避難所での被災者のペット飼育スペースの確保のためのトレーラーハウスの設置、被災した犬猫の県保健所での収容力確保のための他県への収容猫の譲渡、応急仮設住宅の入居者向け説明会でのペット関連説明の支援などの対応を行っています。 |
|

知床連山より知床岳を望む(知床国立公園)
国立公園をご存じですか?
日本を代表する自然の風景地であり、生活・文化・歴史が凝縮された物語がある場所です。国立公園は来訪者や地域の皆さんに、唯一無二の感動体験を約束してくれます。
環境省のレンジャー(自然系採用職員)は現場と霞が関を股にかけ、日本の国立公園の魅力を守り高めて発信する仕事に携わります。自ら大自然を体感しながら、地域の人々と協力して取り組む仕事です。
|
|

国立公園の利用拠点整備(富士箱根伊豆国立公園)
富士箱根伊豆国立公園の田貫湖野営場のテラスを再整備しました。テラスの高さを湖面に近づけることにより、湖面の広がりを感じることができるようになりました。また、柵は視線を遮らないよう工夫し、富士山の雄大な眺望を確保することにより、来訪者が自然を間近に感じ、ゆったりと滞在して満喫できる空間を創出しました。
|
|

クマ類による被害防止と人間とのすみ分け
クマ類(ツキノワグマ・ヒグマ)は我が国の森林生態系での重要な構成種です。しかし、2023年度のクマ類の人里への大量出没により過去最多の人身被害が発生しました。クマ類による被害を防止することは、自然と共生する社会の構築に向けた重要な課題の一つであり、被害対策を進めるため、2024年4月に四国を除く地域でクマ類を指定管理鳥獣に指定しました。これにより、クマ類の地域ごとの個体群を維持しつつ、人の生活圏への出没防止対策を進めてすみ分けを図ることで、安心安全な環境づくりを進めていきます。
(※)指定管理鳥獣…全国的に生息数が著しく増加し、又はその生息地の範囲が拡大している鳥獣であって、生活環境、農林水産業又は生態系に深刻な被害を及ぼすために、集中的かつ広域的に管理を図る必要があるものとして環境大臣が指定するもの。
|
|

福島の環境再生と土壌等の中間貯蔵施設
環境省では、福島第一原発事故により飛散した放射性物質による環境の汚染に対して、土壌等の除染や汚染廃棄物の処理など環境再生を進めてきました。また、現場の事務所を中心に、福島県内の除染により発生した土壌等を貯蔵するための中間貯蔵施設の整備を行っています。加えて、本省では、福島復興の事業を行う現場事務所をサポートしつつ、さらに今後の展開へ向けた技術開発や制度構築に取り組んでいます。(写真は中間貯蔵施設内の土壌貯蔵施設になります。)
|
|

地域の再エネ導入拡大を促進すため、ため池等を活用した太陽光発電の導入の支援を行っています。
環境省では、自家消費型・地産地消型の再エネ導入促進をすすめております。ため池や営農地、廃棄物処分施設など、地域の中で新たに太陽光発電設備が設置可能な場所に対して、補助金を創設し、太陽光発電設備の導入拡大を進めています。
|
|

国連気候変動枠組条約第28回締約国会議(COP28)(2023年11~12月、UAE(ドバイ))
気候変動問題という国境の無い問題の解決には地球規模での対処が必要であり、多国間での合意形成を進める場であるCOPは非常に大きな役割を果たしています。環境省職員は、日本の代表として様々な会議に出席し、国際的な動向を把握するとともに、日本の考えを世界に発信してきました。またジャパンパビリオンを設置し、日本の優れた製品・サービスや気候変動への取組を紹介しました。
|
|

脱炭素先行地域の選定と伴走支援
環境省では、2050年カーボンニュートラルを実現するために、全国のモデルとなる脱炭素先行地域の取組を促進しています。脱炭素先行地域では、民生部門の電力を中心とした2030年度までの脱炭素化と、地域課題の同時解決を目指します。全国のモデルとなる地域であることから、先進性・モデル性とともに、高い実現可能性も求められるため、多様な観点からの審査と、選定後にはその実現に向けて伴走支援を行っています。(写真は、脱炭素先行地域におけるバイオガス施設の現地確認の様子です。)
|
|

令和6年能登半島地震への対応
令和6年能登半島地震への対応として、現地支援チームを被災地に派遣し、被災市町村のニーズに即してきめ細やかな対応を行っています。対応の例として、仮置場(被災した家屋等から排出される災害廃棄物を一時的に保管する場所)内の災害廃棄物排出状況を確認しました。搬入された災害廃棄物が指定された分別区分のとおり排出されているか、危険物や有害廃棄物といった持ち込みができないものが排出されていないか、仮置場内での発火の危険性がないか、といった状況を確認しています。
|
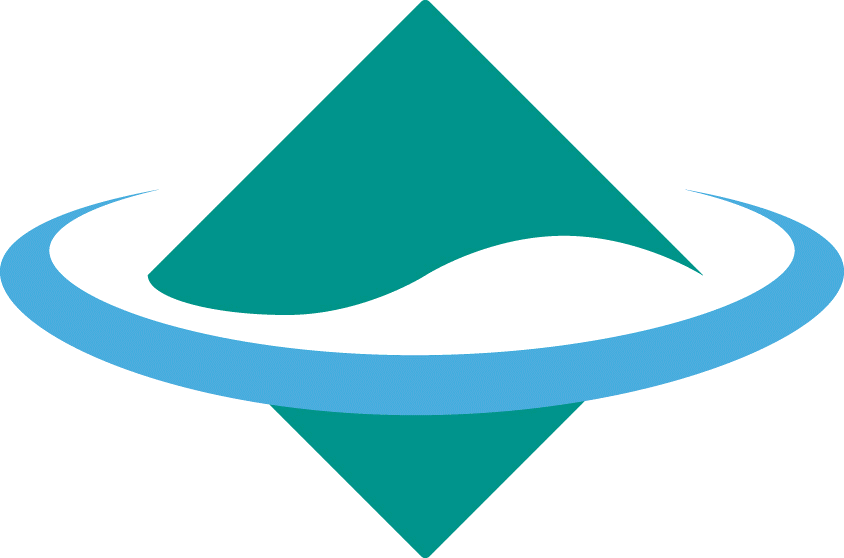 環境省
環境省