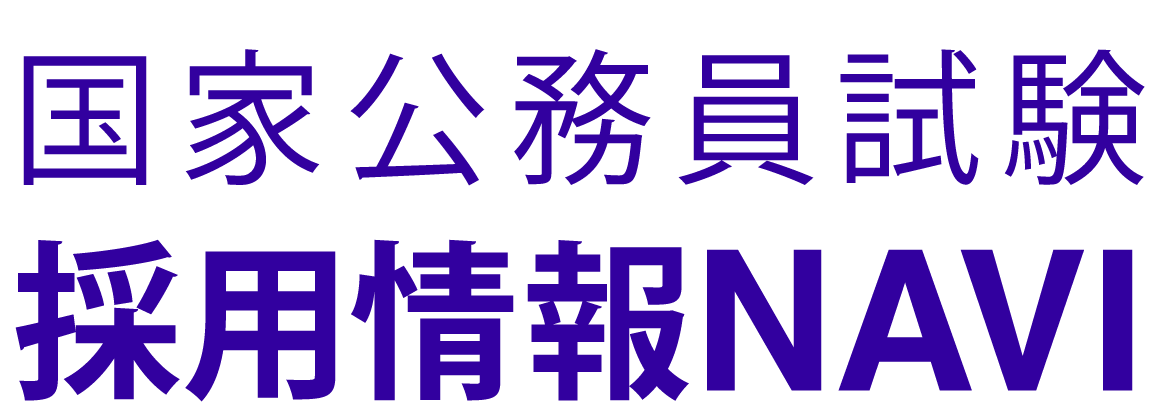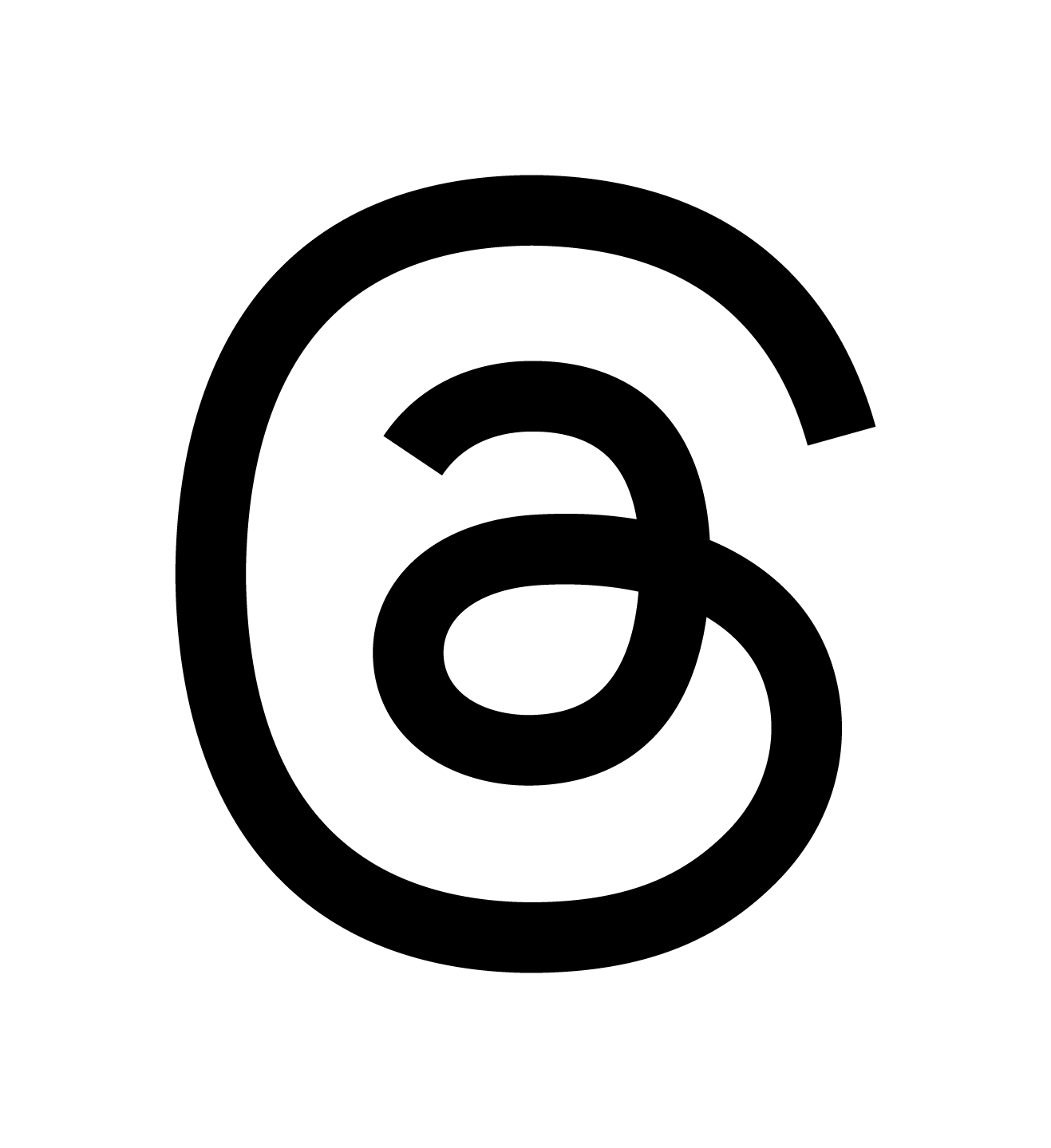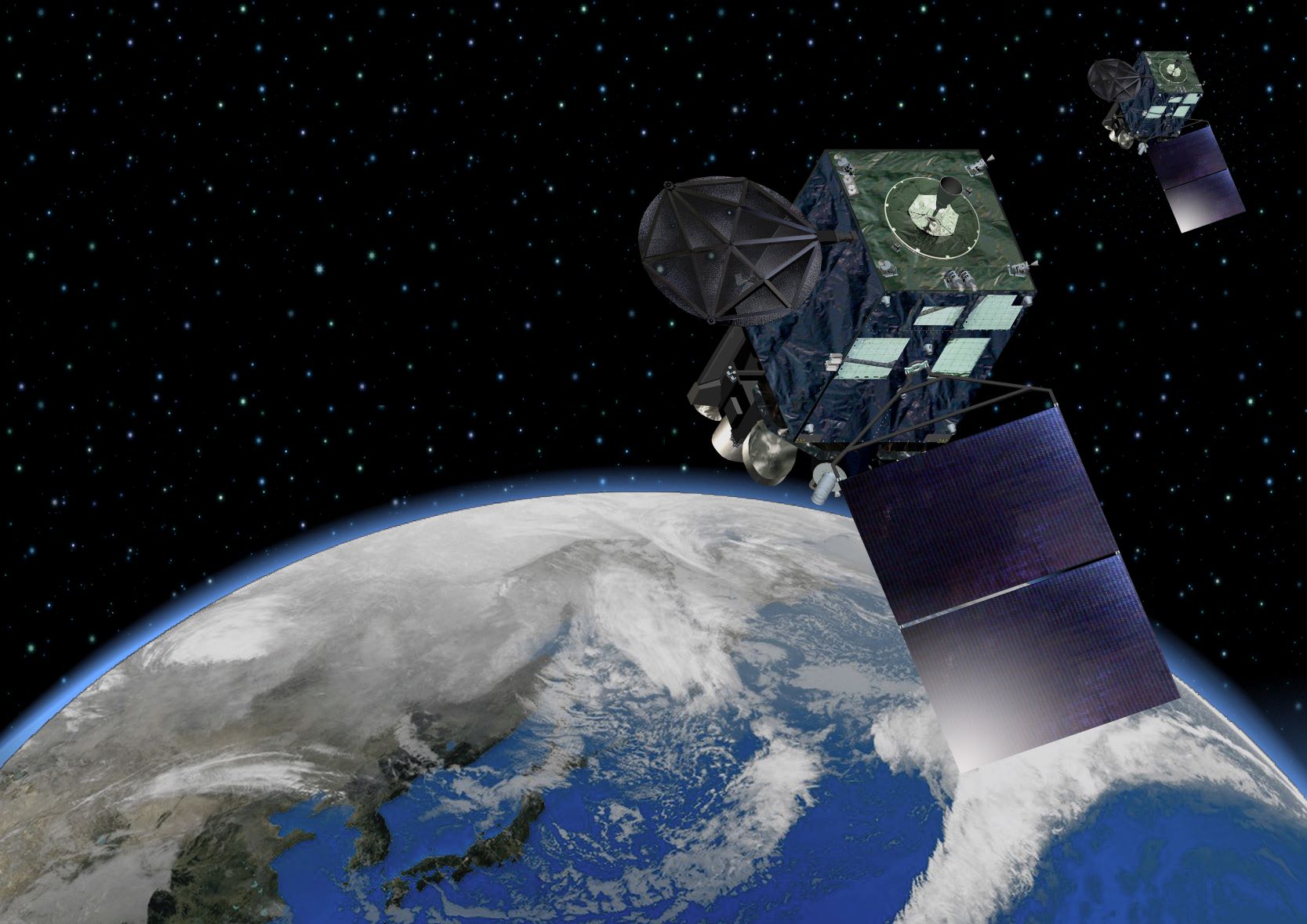| |

|
気象庁 大気海洋部 予報課 気象監視・警報センター 現業班
総合職試験(数理科学・物理・地球科学) 大卒
2019年 気象庁観測部観測課地域気象運用係 採用
2020年 大気海洋部観測整備計画課地域気象運用係(組織改編による名称変更)
2021年 沖縄気象台業務課管理係
2023年 現職
※職員の所属(役職)は、原稿執筆時のものを記載しています。
人々を守るため、プロに学び、プロを目指せる職場です。
|
| |
| ◇ 国家公務員になろうと思ったきっかけ |
中学生のときに経験した東日本大震災がきっかけです。災害の危険にさらされている人たちや、災害に遭い不安な日々を過ごす人たちに、信頼できる正しい情報を届けることができる職務に就きたいと考え、入庁しました。
|
| ◇ 国家公務員になろうと思ったきっかけ |
中学生のときに経験した東日本大震災がきっかけです。災害の危険にさらされている人たちや、災害に遭い不安な日々を過ごす人たちに、信頼できる正しい情報を届けることができる職務に就きたいと考え、入庁しました。
|
| ◇ 学生時代の専攻と現在の仕事との関係 |
大学では地球科学を専攻しており、現在の所属に関係する気象学は専門ではありませんでした。ですが、大気や海洋に関する基礎的な知識のほか、教養課程で学んだ様々な学問、さらに学外での活動も含めて、現在の仕事に活きているものは数多くあります。 気象庁の業務はとても幅広く、どの部署も高い専門性をもっています。自分の専門を活かせるだけでなく、異動のたびに学びの機会があり、少しずつ専門性を身につけていくことができるのも魅力だと感じています。
|
| ◇ 記憶に残っている業務 |
気象や地震・津波などの防災について出前講座を行う際、進行補助として同席したときのことが印象に残っています。講義に参加された方々の「生の」反応をその場で感じることができ、気象庁職員の言葉を聞き手がどんな印象を持って受け取るのか、伝えたい危機感を相手に効果的に伝えるにはどうすればよいか、自分たちの立場でどのような工夫ができるのか、そんなことを考える最初のきっかけになりました。
|
| ◇ 日々の仕事 |
現在所属している気象監視・警報センターでは、気象に関する実況監視、警報・注意報や天気予報の発表といった現業業務を担当しています。気象状況は刻々と変化し、災害の発生に繋がるような現象はいつ起きてもおかしくないことから、24時間365日、交替制勤務で監視を行っています。そのほか、自治体への防災支援のための気象解説や、予報技術のさらなる向上を目的とした事例調査などの取り組みも行っています。
|
| ◇ 仕事の面白み、やり甲斐 |
今の仕事は、自分が発信した警報が自治体の出す避難情報のトリガーになったり、天気予報がそのままテレビや新聞に載ったりするので、重大な役割であることを実感するとともに直接的なやりがいを感じることができます。 技術系職員が多くの割合を占める気象庁では、それぞれが自分の専門性や長所を活かしてさまざまな分野で業務を行っていますが、これといった専門分野を持たない私にとっては、どの部署に行っても新たな発見があり、自分の持ち味をどう活かしていくか考えながら仕事ができるのもこの職場の魅力だと感じています。
|
| ◇ テレワークの経験 |
過去の所属部署では、新型コロナ感染症対策もあってテレワークを頻繁に行っていました。メールやチャットを用いた庁内の連絡調整業務、予算要求や整備計画に関する資料作成などの業務のほか、自己研鑽などに充てていました。 出勤時と比べて自由に使える時間が多く、特に作業量の多い資料作りなどには効率が良いと感じました。また、相手の確認待ちなどで居残る必要がないため、無駄な残業を減らすことにも繋がります。
|
| ◇ ある1日のスケジュール |
(日勤)
8:30 登庁、引継ぎ
10:45 11時の府県天気予報発表
12:00 昼食
13:00 実況監視、最新の数値予報資料の確認、注意報・警報等の検討
16:45 17時の府県天気予報発表
17:00 引継ぎ、退庁
18:00 帰宅 夕食とお弁当作り、趣味の時間
翌2:30~12:30 夜勤に備えて長めの睡眠
(夜勤)
16:00 登庁、引継ぎ 実況監視、注意報・警報等の対応、仮眠
翌4:45 5時の府県天気予報発表
8:30 引継ぎ、日々の検証作業
9:30 退庁
11:00 昼食(元気があれば外食)、帰宅して就寝
18:00~ 翌日の公休までめいっぱい遊ぶ!
|
|
| 他府省の記事も見てみる |
 気象庁
気象庁