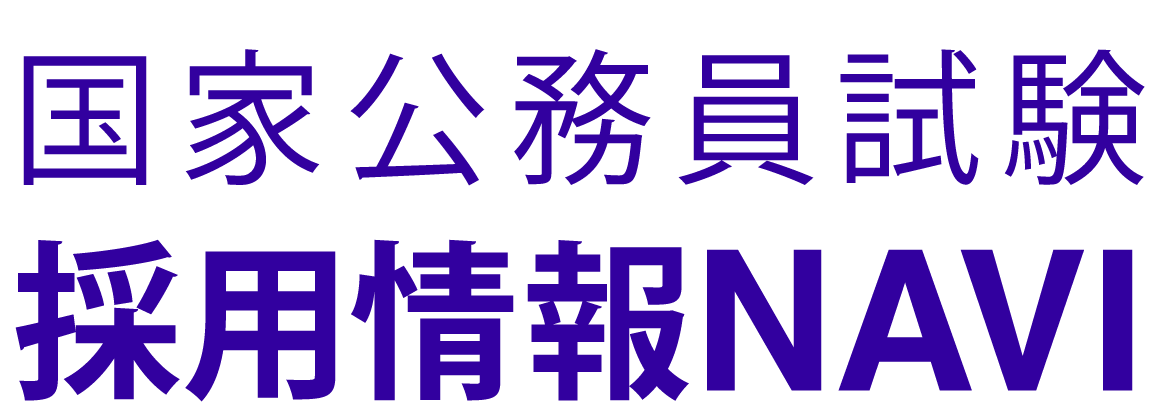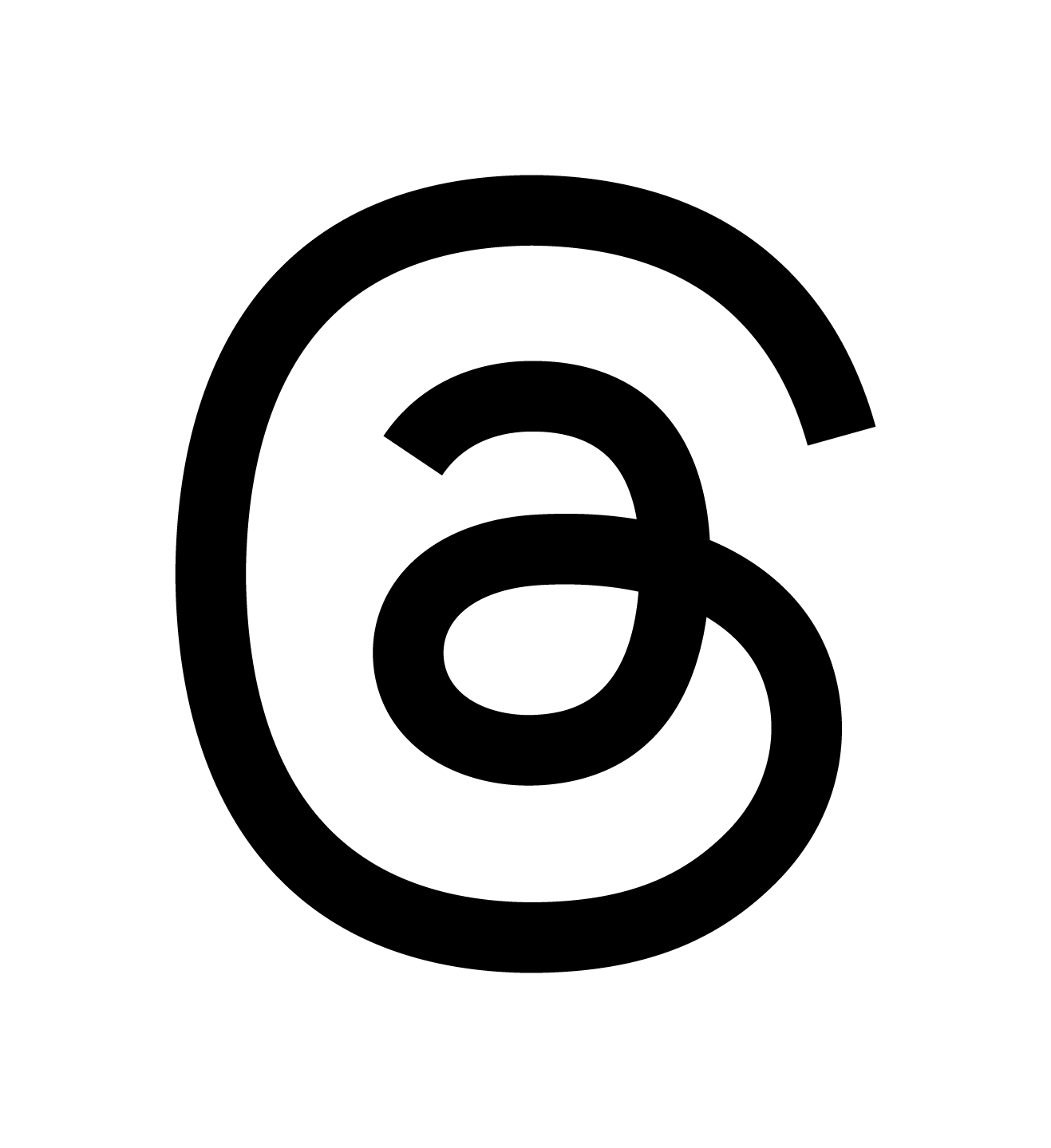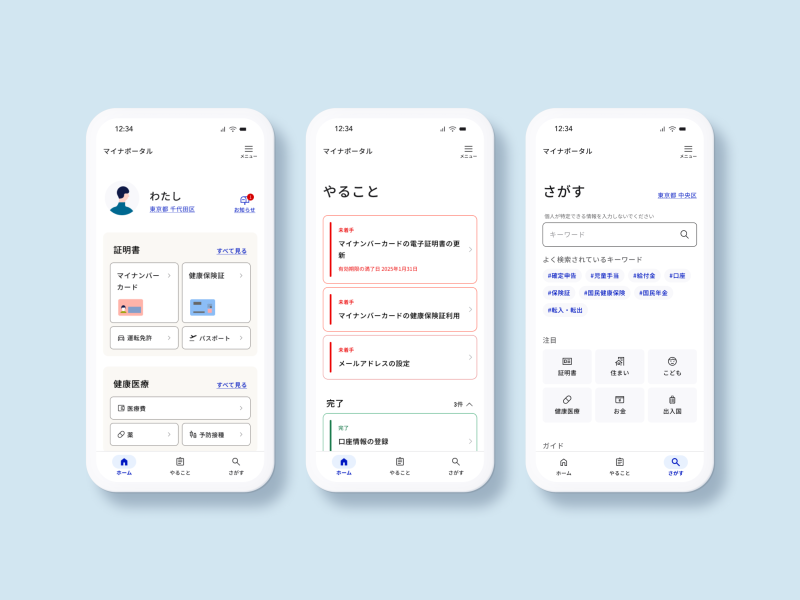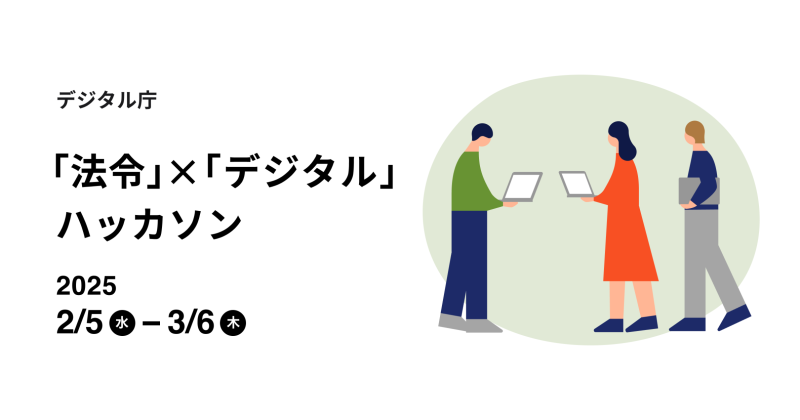|
デジタル庁 デジタル社会共通機能グループ
2023年4月 デジタル庁採用 デジタル社会共通機能グループ 総括 兼 トラスト担当 係員(現職)
デジタル時代を別の視点から見る
|
| ◇ 採用年・採用試験(区分)院卒・大卒 |
|
2023年採用 総合職試験(デジタル) 大卒
|
| ◇ 国家公務員になろうと思ったきっかけ |
いちエンジニアとして働くよりも、特定の分野に限られない広い興味・知識を活かすことができる仕事であると考え、また、デジタル庁のような組織に技術的な内容の翻訳を行うことができる人材が居てほしいと思い志望しました。
|
| ◇ 学生時代の専攻と現在の仕事との関係 |
学生時代に学んだコンピュータサイエンス分野の知識ももちろん、技術標準化やインターネットガバナンス、プライバシー等情報技術の周辺にある問題への興味が強かったことが、行政的な仕事と技術的な専門性を結びつけることに役立っています。また、特にデジタル庁の政策の多くはIDに関するものであり、IPAのセキュリティ・キャンプでIDに関する講座を受講していた経験も、現在の仕事に役立っています。
|
| ◇ 記憶に残っている業務 |
1年目に行った、多くの関係者に影響する方針の策定のために、多数のステークホルダーの元に実際に足を運び各者の事情を伺ったことは、調整役としての行政の仕事の原点であり、今でも印象に残っています。
また、有識者会議の開催のため、上司のアドバイスを受けながら日程調整から過去の経緯の調査、資料の作成、説明、報告書の執筆まで全体を任されたことは、行政における仕事の進め方の解像度が上がる貴重な経験でした。
|
| ◇ 日々の仕事 |
国会対応、他班・他省庁等とのコミュニケーション、技術・海外動向調査、有識者会議の資料作成・説明、関係者へのヒアリングなど日々の班内の議論などでも、常に新しい視点を提供することや議論の前提となる知識を正確に伝え、疑問にとことん答えることを心がけています。行政人材でありながらも専門的な知識・土地感覚を持った人材は、とくに、民間専門人材が多く所属するデジタル庁、技術と制度が深く組み合わさったデジタル分野の政策の実行においてこの間を繋ぎ効果をレバレッジする上で不可欠な役割であると考えています。
|
| ◇ 仕事の面白み、やり甲斐 |
以前より著書を読んだりSNSでフォローしていたような有識者の皆様をお呼びして、政策・課題についてご議論いただく場に、間近で議論を支える当事者として携われるのは、刺激的で、他ではない仕事であると感じています。有益な議論を頂き、より良い政策に繋げるためにも、専門的見地からの正確性を確保するためのインプット、日々変化するデジタル分野の動向を追うための努力が必要ですが、その結果として、有識者から議論の内容や取りまとめ内容について良い評価を頂けると次回以降のやる気にもつながります。
|
| ◇ テレワークの経験 |
私は夜型で朝に弱いのですが、よく、午前中はテレワークとしてメールや通知、業務関連のニュースの確認、タスクの整理等を中心に行い、お昼に移動して午後から登庁する形にするなど有効的に活用しています。また、週1回程度午後までテレワークにする日を作り、1人で集中して資料の作成等の仕事を行う日と、登庁して他の班員と議論しながら仕事を進める日のメリハリをつけるように心がけています。
|
| ◇ ある1日のスケジュール |
9:30 出勤(テレワーク) メール、チャット、ニュースの確認
11:00 資料の修正
12:00 移動
13:00 登庁
14:00 班員とのディスカッション
15:00 事業者との打ち合わせ
16:00 資料・メモ等の作成
19:45 退庁
20:15 社会人大学院の授業
23:30 帰宅
|
他府省の記事も見てみる |