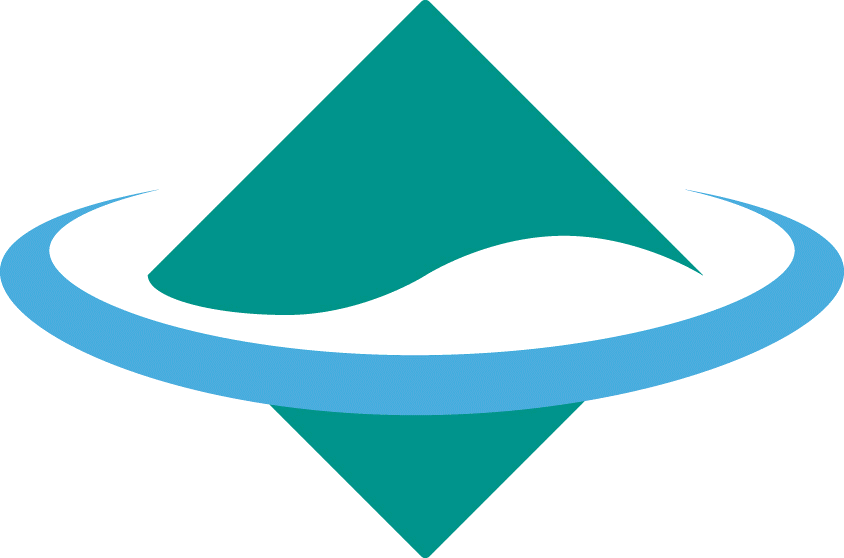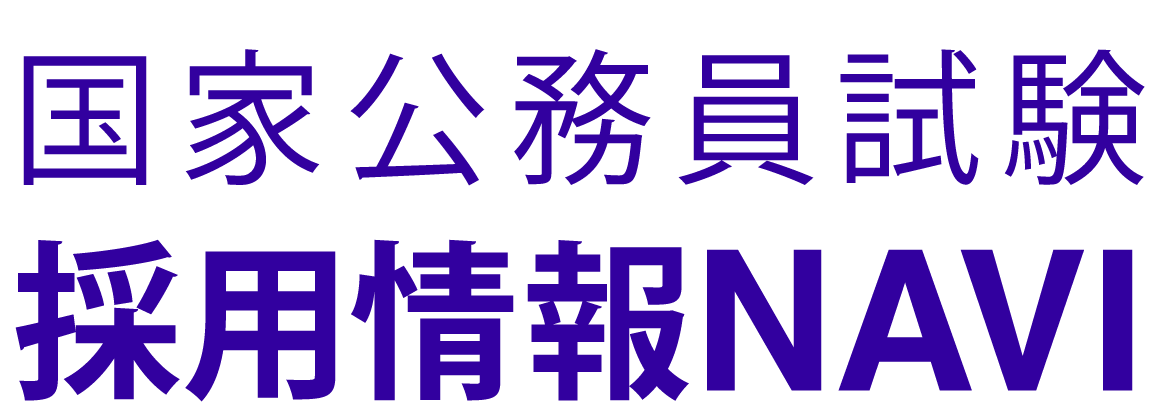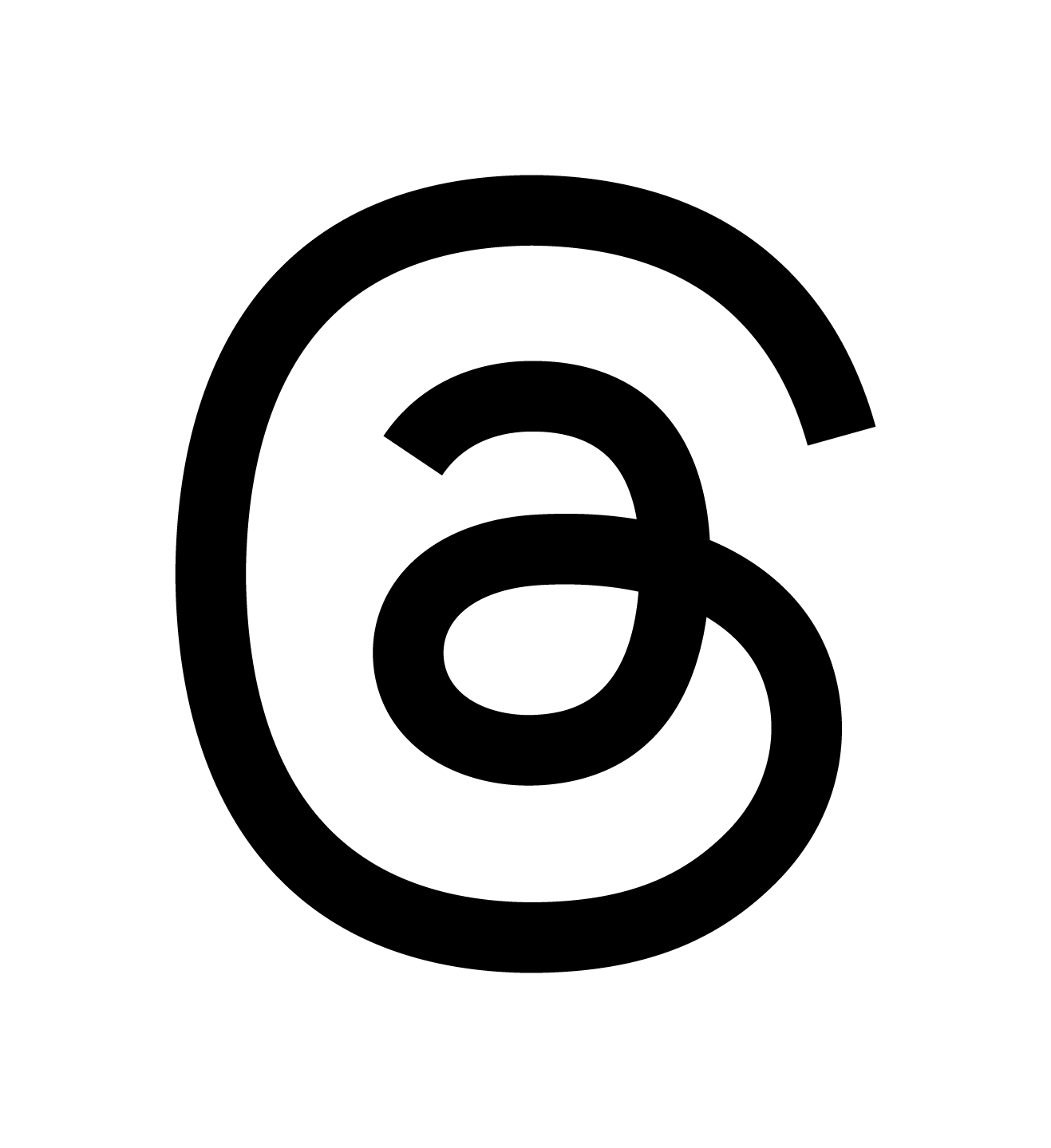●阪神タイガースファーム施設「ゼロカーボンベースボールパーク」を核とした脱炭素先行地域(兵庫県尼崎市)
地方公共団体が主導する脱炭素の取組(地域脱炭素)の主要な取組の1つが、脱炭素先行地域の実現です。2030年度までに脱炭素と地域課題解決を同時に実現し全国のモデルとなる地域として、2025年5月までに88か所を選定し、年間数百億円規模の地域脱炭素推進交付金により支援しています。兵庫県尼崎市では、2025年2月に阪神タイガースファーム(2軍)施設「ゼロカーボンベースボールパーク」が完成し、脱炭素化と地域経済活性化・市民やファン等の行動変容の同時達成に向けて取組を進めています。
|
|

●企業が管理するブドウ畑も自然共生サイトに認定
(キリンホールディングス株式会社・シャトー・メルシャン 椀子ヴィンヤード)
2030年までに生物多様性の損失を止め、回復軌道に乗せる、ネイチャーポジティブの実現に向けては、企業や地方公共団体など様々な主体による取組を促進することが重要です。環境省では民間等の取組によって生物多様性の保全が図られている場所を「自然共生サイト」として認定する取組を令和5年度から開始し、全国328か所を認定しました。また、取組をさらに促進していくために「地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律」を新たに制定するなど、オールジャパンでネイチャーポジティブの実現に取組むための制度づくりを進めています。
|
|

●国連気候変動枠組条約第29回締約国会議(COP29)アゼルバイジャン(バクー)
気温上昇に加え、大雨の発生頻度の増加、高温による農作物の生育障害など気候変動の影響は既に現れており、緊急の気候変動の取組が必要です。国際交渉の場であるCOPは世界全体の気候変動対策において大きな役割を果たしています。環境省職員は、COPに出席し、日本の考えを主張し、世界全体のルール形成や対策の推進に貢献しました。また、ジャパンパビリオンを設置し、日本の優れた製品・サービスや取組を世界に紹介しました。
|
|

●営農型太陽光発電の導入促進
環境省では、再生可能エネルギーの最大限導入のために、環境に適正に配慮し、地域に貢献する、地域共生型の再エネ事業を進めています。例えば、発電と営農が両立する営農型太陽光発電に対して設備導入の支援を行い、普及促進を図っています。
|
|

●奄美大島でのマングース根絶
1979年ごろ、ハブやネズミ対策として人為的に奄美大島に持ち込まれたフイリマングースは、分布拡大に伴い農畜産被害や地域の固有種への影響を生じさせるようになりました。これに対し、環境省は地方公共団体等と協力しながら40億円以上の事業費をかけ20年以上にわたり奄美大島マングース防除事業を実施し、令和6年9月に奄美大島におけるマングースの根絶を宣言しました。この事業は世界に例のない成功事例となった一方で、この事業に膨大な年月と資金を要したことから、外来種被害予防三原則である「入れない・捨てない・拡げない」の重要性を再確認しました。
|
|

●知床連山より知床岳を望む(知床国立公園)
環境省が管理する国立公園は日本を代表する自然の風景地であり、利用者に唯一無二の感動体験を提供するとともに生物多様性の確保にも貢献しています。環境省のレンジャー(自然系採用職員)は、国立公園の保護管理を充実させつつ魅力向上・利用促進を図り、保護と利用の好循環を生み出します。現場にて自ら大自然を体感しながら、地域の方々をはじめ様々な関係者と協力して取り組む仕事です。
|
|

●国立公園の利用拠点整備(富士箱根伊豆国立公園)
富士箱根伊豆国立公園の田貫湖野営場のテラスを再整備しました。テラスの高さや柵の構造について工夫をし、富士山の雄大な眺望を確保することにより、来訪者が自然を間近に感じ、ゆったりと滞在して満喫できる空間を創出しました。国立公園内で人や自然の環境に応じた施設や空間を創出し、保護と利用の好循環を回す仕事です。 |
|

●福島県内の除染により発生した土壌等を保管している「中間貯蔵施設」
環境省では、2011年の原発事故からの環境再生・復興に向けた取組を進めています。
現場にある福島の事務所では、地元の方々とのコミュニケーションを取りながら、除染や廃棄物処理、中間貯蔵施設の整備などの大規模な工事の発注・監督・監理などを行っています。
また、本省では、現場事務所をサポートしつつ、環境再生・復興を進めるための事業の企画・調整や制度面・技術面の検討、国内外への情報発信などを行っています。
|
|

●災害廃棄物処理(令和6年能登半島地震対応)
令和6年1月1日に発生した令和6年能登半島地震において、被災地域の早期の生活再建のため、被災した家屋等の解体・撤去や災害廃棄物の適正かつ円滑・迅速な処理が必要不可欠です。環境省職員も1月2日から被災地域に入り、公費による家屋等の解体・撤去の加速化や石川県外への災害廃棄物の搬出・処理などを支援し、早期の復旧・復興に貢献しています。
|
|

●被災ペットの災害対応
野生動物以外にも飼育動物の愛護管理の業務も行っています。災害が起きた際にペットを飼育している方の安全や命を守るため、ペット同行避難等に関するガイドラインの作成や自治体での避難訓練の支援なども行っています。
令和6年能登半島地震においては、発災後直後から職員が現地でペットの同行避難の状況などの情報を収集し、石川県や獣医師会、関係団体などと協力してペットを飼育している被災者の支援を実施するなど、現場と制度の両面から人と動物の共生社会の実現に貢献します。 |