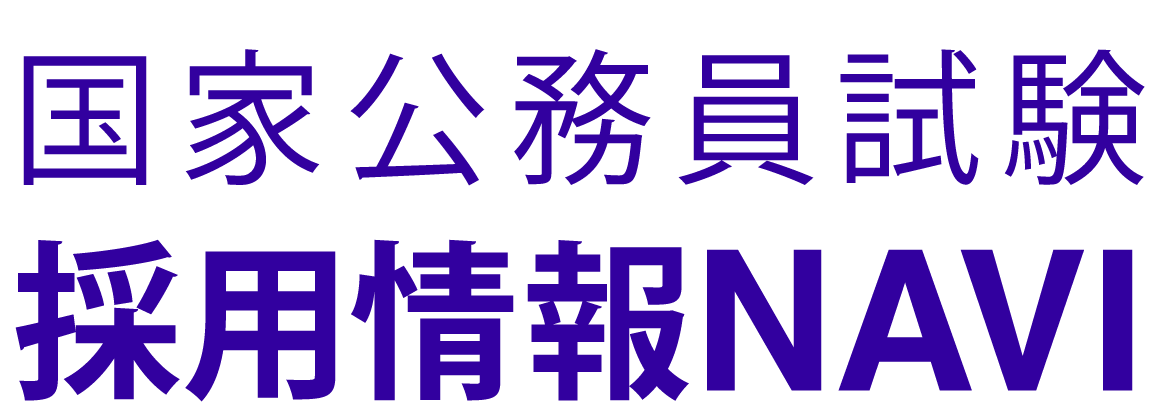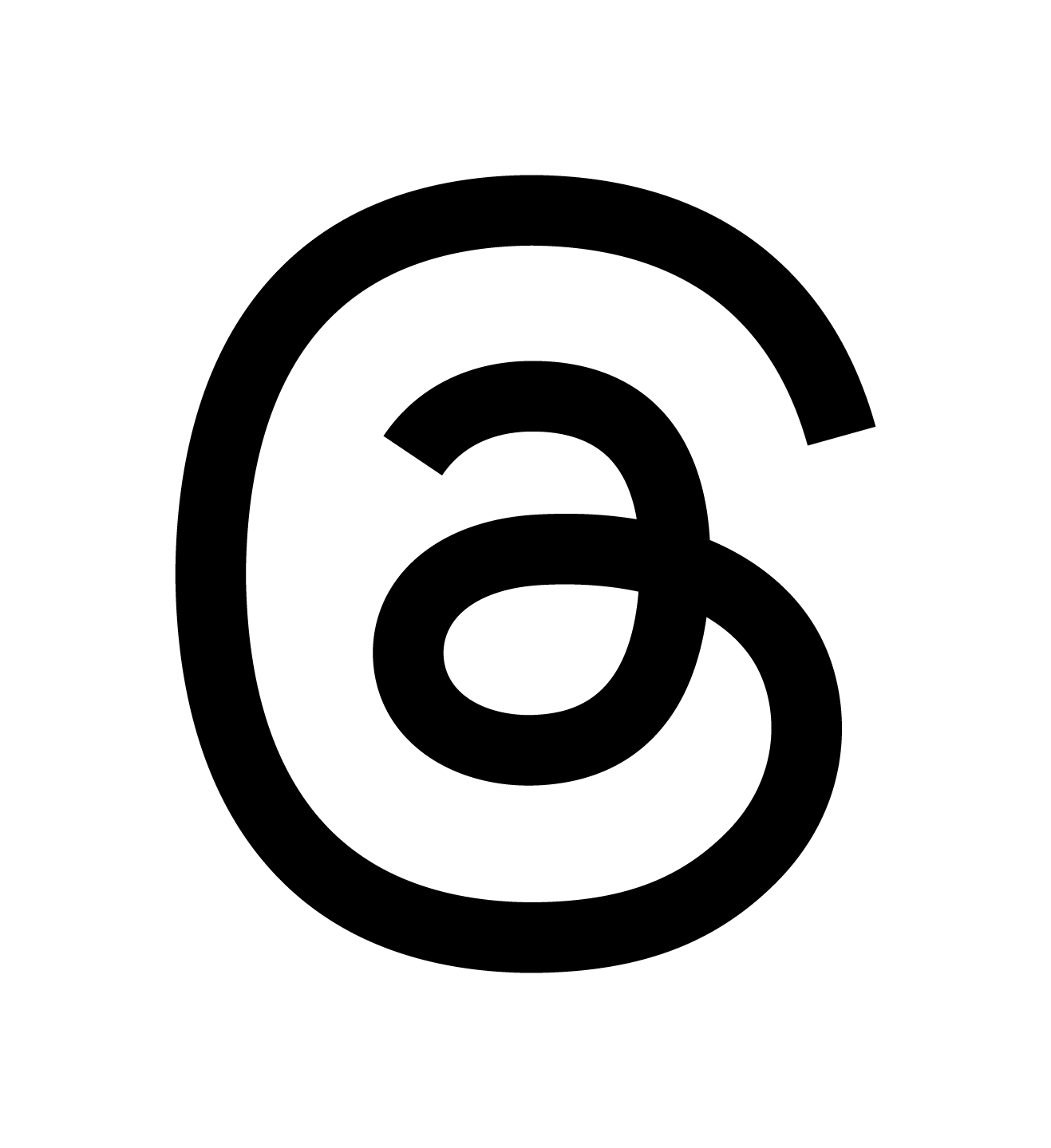|
消防庁 予防課 設備係長
2020年 消防庁採用 消防庁 消防・救急課 救急企画室
2022年 消防庁 予防課
2023年 福岡市消防局(出向)
2025年 現職
人のために、知恵を絞り、全力を尽くす
|
| ◇ 採用年・採用試験(区分)院卒・大卒 |
|
2020年採用 総合職試験(森林・自然環境) 院卒
|
| ◇ 国家公務員になろうと思ったきっかけ |
「人の役に立つことは何か」を突き詰めて考えたとき、最も必要とされるのは人の命を守る仕事だと思い、日本という広いスケールで、人命に携わることができる国家公務員を志望しました。
|
| ◇ 学生時代の専攻と現在の仕事との関係 |
大学では文化社会学を、大学院では都市計画史を専攻していました。過去の政策立案を客観的に検証する研究を行っており、行政機関による制度設計を身近に感じていました。また、資料収集や論理的な文章の作成、プレゼンテーションなど、学生時代に培ったあらゆる力が仕事に役立っています。
|
| ◇ 記憶に残っている業務 |
入庁1年目に「救急安心センター事業(♯7119)」を実施する地方自治体への財政措置の見直しを担当したことです。♯7119は、住民が救急車を呼ぶべきかどうか等の判断に悩む場合に、専門家が電話相談に応じるものです。この見直しでは、財政措置の対象範囲が拡大され、その後、事業の実施地域は着実に増えつつあります。新人ながら大仕事を任せていただいたこと、少しでも社会が変わることを、振り返って噛みしめています。
|
| ◇ 日々の仕事 |
誰でも身近にある、消火器やスプリンクラー設備、自動火災報知設備といった「消防用設備等」の技術基準の策定を担当しています。これらの設備は、火災時に人命を守る大切なものです。有識者検討会の開催等を通じて、最新の知見を取り入れた基準の策定に向けて奮闘しています。また、安心・安全に必要な「技術」だけでなく、設備の設置費用を負担する「社会」とのバランスを考え、その最大公約数を実現することが任務です。
|
| ◇ 仕事の面白み、やり甲斐 |
「社会実装」を実感できる点です。消防庁では「現場」への出向の機会があります。福岡市消防局への出向時には、消防庁で私が担当した制度が、実際に現場で運用されている場面に何度も出くわしました。政策が社会に反映されていることを体感し、嬉しかった反面、現場の制度運用の苦労もよく耳にしました。この経験を経てからは、机上の空論ではなく、理論と実践の橋渡しとして頭を悩ませることが、一つのやりがいです。
|
| ◇ テレワークの経験 |
帰省先が遠方であることや、出張の機会が多いことから、職場から遠く離れた場所でテレワークをすることがあります。もちろん、業務内容によって適・不適はあれど、テレワークを活用して場所にとらわれずに仕事を進められることは大きなメリットだと考えています。
|
| ◇ ある1日のスケジュール |
9:00 登庁
10:00 検討会資料の案について課内ミーティング
12:00 昼食(タイミングが合えば同期とランチ!)
13:30 省庁横断的な政策について、関係省庁と打合せ
16:00 事業者からの法令解釈に関する相談への対応
17:30 国会議員への説明資料の作成
18:45 退庁
19:00 職場の同僚とフットサル(月1回程度)
|
他府省の記事も見てみる |