|
| |

玉井 利明  |
文部科学省 研究振興局 ライフサイエンス課 感染症研究推進係長
平成18年採用 Ⅱ種(電気・電子・情報) |
| |
| ◇ 学生時代の専攻分野は? |
電気工学
|
| ◇ 志望動機は? |
文部科学省は取り扱う分野がとても広く、また、科学技術の分野は自分にとって大変なじみが深く、関心が高いものであったため、様々な分野での業務を通じて、自分の成長がつながると考えたためです。
|
| ◇ 採用後の経歴は? |
・大学等が保有している先端的な研究施設・設備の共同利用の推進
・国内の各地域の大学、企業の強みを活かした産学官連携の推進
・政府の科学技術の取組をまとめた報告書(科学技術白書)の企画・執筆(白書の表紙絵の一般公募を行い、選考委員をお願いしたさかなクンや宇宙飛行士の山﨑直子さんなどと一緒に選考を実施)
・夢のエネルギーと呼ばれる核融合実現に向けた国際連携プロジェクトの推進
・感染症やがん等の先端的の医科学研究の推進
|
| ◇ 日々の仕事の様子は? |
・施策の企画・立案のために、大学、研究開発法人、企業の第一線で活躍する研究者等との議論、有識者を入れた会議の開催、研究現場の視察、シンポジウムへの出席
・研究者・有識者の議論や様々な調査などを基にして、施策の企画、立案を行い、財務省に予算概算要求をするための資料の作成や財務省への説明
・予算が成立した後は、具体的な制度設計、研究課題の公募、選定(課題選定委員の任命、選定委員会の運営)、採択課題の契約、採択課題の研究進捗状況の管理(現場訪問、評価等)
・国会対応や関係省庁や関係機関との調整業務
|
| ◇ 仕事の面白み、やり甲斐は? |
最先端の分野を様々な専門家と議論をしながら、施策を作り上げていくプロセスでは分からないことが多く苦しいこともありますが、徐々に形になっていくプロセスは大変面白いと感じます。また、自分が関わった業務によって、研究をしている先生方が大きな成果などを出して、新聞やテレビで報道されると大変うれしく思います。
|
| ◇ 自己の成長を実感したエピソードは? |
国会対応業務で部局のとりまとめ部署にいたときに、1日に非常に多くの案件を処理しなければならず、一日中電話が鳴りっぱなしのような状況で、上司と2人でうまく業務を分担をして、関係者間での正確かつ迅速な情報伝達や調整をミスなく迅速に処理できたときには、自分の情報処理能力やコミュニケーション力の向上を感じました。
|
| ◇ 仕事と生活(家庭、趣味、地域活動など)の両立は? |
平日は共働きの妻に子どもの面倒を見てもらうことが多いので、休日は子どもの面倒を見るように努めてます。また、趣味のランニングも、早朝に走ったり、月に一度仲間と平日夜に走ったりと、うまくタイムマネジメントをしながらトレーニングに励み、毎年1回以上はフルマラソンに出場しています。
|
| ◇ 今後関わっていきたい政策課題などは? |
科学技術行政に長く携わってきましたが、文部科学省には科学技術以外にも教育やスポーツといった分野も幅広く所掌しているので、これまでの経験や知見を最大限生かし、科学技術行政に加え、そうした分野にもチャレンジしていきたいと思っております。
|
| (平成29年3月) |
|
|
| |

依田 洸  |
内閣官房 内閣サイバーセキュリティセンター 基本戦略第一グループ 主査 (併)副長官補(事態対処・危機管理担当)付
平成31年採用 総合職(工学)(院卒) |
| |
| ◇ 学生時代の専攻分野は? |
情報工学
|
| ◇ 志望動機は? |
大学院時代に、海外留学した際、様々な国から来ている学生と交流し、日本という国を改めて意識していく中で、日本をより良くしたいと思いが芽生え、国家公務員を志望することにしました。志望する上で、数学・情報の教員としての教育現場での経験や大学院時代にスーパーコンピュータ用いた画像認識の深層学習を研究した経験を生かすことを考えた際、教育と科学技術を所掌とする文部科学省しかないと思い志望しました。
|
| ◇ 採用後の経歴は? |
最初は、情報系の研究を所掌する参事官(情報担当)付に配属され、国会対応等の総括業務の基礎を学びつつ、AIの国家戦略である「AI戦略」の省内取りまとめや各種フォローアップ、Society5.0を実現するための研究開発事業や研究者・論文投稿データベースの運営等を行いました。 現在は、内閣官房に出向し、NISC基本戦略第一グループに配属され、専門調査会と呼ばれる我が国のサイバーセキュリティの研究開発・普及啓発・人材育成施策の方向性を議論する場を運営し、各種戦略を策定することや、各省庁等と連携をしながら戦略に基づいた政策の推進にあたっています。また、併任として、官邸危機管理センターにおいて事案対処にあたっています。
|
| ◇ 日々の仕事の様子は? |
NISCでは、基本戦略第一グループの総括として、国会対応や予算要求、調査会運営、脆弱性評価を検討する研究開発事業や、サイバーセキュリティ対策を国民へ普及啓発する事業の運営等をしています。また、官邸危機管理センターにおいては、事案の初動対処に当たっています。いずれの業務も他省庁や企業からの出向者と一緒に知恵を出し合いながら、進めていく必要があるため、内閣官房ならではの充実した日々を過ごしています。
|
| ◇ 専門性はどのように活かされていますか? |
コーディングする上で学んだ論理的な考え方、プログラムエラーにめげずあらゆる手段を駆使しながら、粘り強く考える力は、現在のあらゆるステークホルダーと調整する上で、活かされています。また、学生時代に学んだ情報全般の基礎的な知識は、AIやサイバーセキュリティの有識者との議論をする上で欠かせないものと感じています。一方、情報分野の知識は、日々アップデートされており、ニュースや有識者との議論等を通じて日々アップデートするように努めています。
|
| ◇ 仕事の面白み、やり甲斐は? |
共に仕事をする周りの方々には、サイバーセキュリティの専門家が多く、日々職務を通じ学ぶことの多い職場です。私自身も、改めて学生時代に学んだサイバーセキュリティはあくまで一側面であり、非常に奥深いものであると感じました。主な業務である各種戦略の策定・推進においては、関係省庁の協力が必要不可欠であり、乗り越えるべき課題が多いですが、その分、達成したときの喜びは一入です。
|
| ◇ 自己の成長を実感したエピソードは? |
内閣官房という官邸と非常に近い状況の中で、ステークホルダーを意識しながら、常に先を見据えて対処をすることや、あらゆる状況下においても、冷静に物事を把握し対処することは自ずと身についたと思います。実際に、突発事案においても、関係各所に連絡調整をして、迅速に初動対応をでき、事なきを得たときには、安堵とともに成長を感じました。
|
| ◇ 仕事と生活(家庭、趣味、地域活動など)の両立は? |
上司の理解もあり、夜勤があった次の日は、緊急な案件がない限り、テレワークをするといった柔軟な働き方をしています。休日であっても、緊急な出勤を要する場合もありますが、余暇は、家族と外食したり、友人と会ったりと積極的に気分転換をするように努めています。
|
| ◇ 今後関わっていきたい政策課題などは? |
GIGAスクール構想で進んでいる学校教育のデジタル化の推進や、数理・データサイエンス・AI教育やプログラミング教育の充実、また、基礎研究とデータサイエンスを掛け合わせたような融合分野の研究振興に携わりたいと思っています。
|
| (令和5年3月) |
|
|
| |

竹谷 政彦  |
文部科学省 研究開発局 開発企画課 総括係長
平成27年採用 総合職(工学) |
| |
| ◇ 学生時代の専攻分野は? |
航空宇宙工学
|
| ◇ 志望動機は? |
「日本をもっといい国にしたい!!」
当たり前ですが、このように考えて国家公務員を目指すことにしました。では、どうやったら良い国になるのだろうか?と考えたとき、これまでの人類の歴史を振り返ると科学技術の貢献は計り知れないと思いました。そして、アカデミアにおける人材育成と研究開発は科学技術の全てのベースとなるので、この土台を強化することが長期的には一番の近道だと思い、大学や研究機関の取組に一番寄与できると思った文部科学省を志望しました。
|
| ◇ 採用後の経歴は? |
1年目:科学技術の国際協力を行う部署に配属され、様々な会議の準備(会場の準備はもちろん、国際会議における日本の発言案の作成)に取り組みました。
2~4年目:情報教育の振興に関わる部署に異動し、学校現場の声もききながら、学校でのICT機器の整備やプログラミング教育の推進に取り組みました。
4~5年目:資源エネルギー庁に出向し、電力業界の規制の変更に取り組みました。
6~7年目:文部科学省に戻り、原子力分野の研究開発の推進に取り組みました。施設の廃止措置と研究を同時に進めるための予算獲得に日々奮闘していました。
現在:部局内各課の予算の配分調整を中心に、部局の総括業務に取り組んでいます。
|
| ◇ 日々の仕事の様子は? |
・関係者との意見交換:政策決定に当たっては、影響を受ける研究機関や学校、産業界など、現場の声を聞くことが不可欠です。関係者と打合せをしながら、現場で抱える問題点などを把握していきます。
・予算要求と折衝:必要な予算をしっかり精査してまずは省内で理解を得ていきます。無事に理解を得られれば予算要求することができますが、その次は要求した事業にきちんと予算が認められるよう、財務省と何度も議論を重ねています。
・国会対応:国会で自分の業務に関連する質問の通告が来た際には、やっている最中の業務を中断し、国会対応に必要な資料の作成など、優先的に国会の準備に取り掛かります。
|
| ◇ 専門性はどのように活かされていますか? |
技術一般についての知見は、どこに行っても活かすことができます。実際に私が入省してから使った専門知識は、確率論、流体力学、熱力学などがあります。確率モデルを用いた事業分析や、研究開発内容を財務省へ理解してもらうための説明など、科学技術に関する知識は、もはや行政官にとっても必須だと感じています。
|
| ◇ 仕事の面白み、やり甲斐は? |
現場の役に立てたと実感できたときには、この仕事をやっていて良かったと感じます。現場の研究者が生き生きと活躍しているという声が聞こえてきたときには、嬉しさで胸がいっぱいになりました。
|
| ◇ 自己の成長を実感したエピソードは? |
財務省の担当者と何度も調整して折り合った予算案をそれぞれの組織内で上司に説明して、自分達で出した案がそのまま通った時には、きちんと調整・交渉をやり終えることができて自分も成長したなと実感しました。
|
| ◇ 仕事と生活(家庭、趣味、地域活動など)の両立は? |
帰れるときには早く帰るようにし、家事や自己研鑽に努めています。趣味を楽しむ時間は学生時代より短くなりましたが、その分、意識的に趣味の時間を作るよう心がけています。そのため、メリハリ付けて働くよう心がけています。
|
| ◇ 今後関わっていきたい政策課題などは? |
科学技術政策以外にも、教育政策や電力政策にも携わってきましたが、機会があればどんな分野にもチャレンジし、視野をどんどん広げていきたいと考えています。
|
| (令和5年3月) |
|
|
| |

竹内 聡志  |
文部科学省 研究開発局 環境エネルギー課 エネルギー科学技術係長
平成20年採用 Ⅱ種(建築) |
| |
| ◇ 学生時代の専攻分野は? |
建築
|
| ◇ 志望動機は? |
幅広い分野の科学技術に携わることができるとともに、若いうちから大規模な研究開発プロジェクトや国際プロジェクトにも携われるので、大きく成長できる環境であると感じたので志望しました。
|
| ◇ 採用後の経歴は? |
・南仏に核融合実験炉を建設する国際プロジェクト等の核融合研究開発の推進
・フランス(パリ)の国際機関(OECD/NEA)において福島の現状等の共有
・次世代半導体、次世代蓄電池、次世代太陽電池等の従来の延長線上にない革新的な新エネルギー技術の研究開発の推進
|
| ◇ 日々の仕事の様子は? |
新規制度設計を行うための関係機関との打ち合わせ、財務省への予算要求のための資料作成、事業の推進(委託契約の締結、受託者との打ち合わせ、事業のフォローアップ等)、国際会議への出席等
|
| ◇ 専門性はどのように活かされていますか? |
建築分野そのものの知識だけではなく、大学時代に学んだ数学、物理、化学等の知識が専門的な科学技術を理解するための助けとなっています。
|
| ◇ 仕事の面白み、やり甲斐は? |
所管している事業は非常に専門的で多岐に渡っているため、内容を理解するのはとても大変で、その必要性を分かりやすく説明することにいつも苦労しますが、その作業が予算の獲得など、事業の推進につながるので、大変やりがいがあります。また、ノーベル賞受賞者と打ち合わせを行う等、日本の科学技術の最先端を直に見ることができたり、ビッグプロジェクトに携わることもできます。
|
| ◇ 自己の成長を実感したエピソードは? |
国際機関に勤務していたときに、日本との文化の違いにより、想定外の状況にたびたび遭遇しました。そのような経験を幾度も乗り超えて、想定外の状況の時にも落ち着いて対処することができるようになったと感じています。
|
| ◇ 仕事と生活(家庭、趣味、地域活動など)の両立は? |
出張等はありますが、基本的にデスクワークで運動不足になってしまうので、ジム等で運動することを心がけています。普段の仕事は大変ですが、良い気分転換になります。
|
| ◇ 今後関わっていきたい政策課題などは? |
様々な科学技術や様々な国と関わっていくことができるような仕事がしたいと思っています。
|
| (平成29年3月) |
|
|
| |

岩元 美樹  |
文部科学省 研究開発局 研究開発戦略官(核融合・原子力国際協力担当)付 企画係長
平成27年採用 一般職(物理) |
| |
| ◇ 学生時代の専攻分野は? |
物理学(核融合プラズマ)
|
| ◇ 志望動機は? |
科学技術に広く関わることができるほか、大学院時代等、これまでの自身の経験(例えば、女性研究者としての苦悩や将来のキャリアパスに対する不安、博士課程に進学したいが経済的に厳しいと感じた)が研究環境の改善等の業務に活かせると感じたため志望しました。
|
| ◇ 採用後の経歴は? |
・核燃料サイクルの研究開発の推進
・他省庁へ出向し、原子力災害時の緊急時対応策定など原子力防災関連の業務を担当
・海外勤務(原子力留学)としてOECDの原子力機関へ1年間赴任。日本の放射線防護の体制、福島事故後の変化について世界へ発信
・他省庁へ出向し、科学技術イノベーション推進を行う事務局の部局とりまとめ業務、国際業務、大学制度改革関係業務を担当
・クリーンかつ革新的なエネルギー源である核融合エネルギー実現に向けた事業の推進
|
| ◇ 日々の仕事の様子は? |
・課の総括担当として、国会対応や予算要求業務
・核融合エネルギー実現のため産業界の巻き込みや人材育成等の推進策について、大学、研究機関、産業界と議論し課題の洗い出し。海外企業や研究機関との意見交換。
・有識者による検討会の開催
|
| ◇ 専門性はどのように活かされていますか? |
大学院での経験(研究、私生活)は、大学の研究現場改善のための検討に役立つこともあります。また、現在の担当がまさしく私の専門分野なので技術的な面でも理解しやすく業務がスムーズに進みます。
|
| ◇ 仕事の面白み、やり甲斐は? |
自分で提案した政策が形になり、それにより日本の課題を解決していくことができることにやりがいを感じています。
|
| ◇ 仕事と生活(家庭、趣味、地域活動など)の両立は? |
私が入省したころはテレワークという概念がなくかつ業務も多く、将来この職場で子育て等家庭の両立ができるのか不安でしたが、現在の文部科学省はテレワークができるシステムが進んでいます。また、不要な業務を減らすため、省内の意見をアンケート調査するなど、働き方改善に励んでおり、家庭との両立がしやすい環境になったと感じています。
|
| ◇ 今後関わっていきたい政策課題などは? |
大学に出向し産学連携や大学発ベンチャー支援を行いたいです。
また、スタートアップ政策に関わりたいです。
ファンドの運用に関連した業務に携わった経験から、今後日本経済を回復させる有効策は日本がユニコーン、世界に誇る企業をどれだけ生み出せるか、日本が投資先としてどれだけ魅力的なのかを見せることだと思い、スタートアップに関連した業務を行いたいと考えております。
|
| (令和5年3月) |
|
|
| |

水田 剛  |
文部科学省 研究振興局 基礎・基盤研究課 理研係長
平成24年採用 Ⅱ種(電気・電子・情報) |
| |
| ◇ 学生時代の専攻分野は? |
物性物理学
|
| ◇ 志望動機は? |
教育、科学技術・学術、スポーツ、文化は、全て関心を持つ分野であり、ダイナミックかつ多くの方に影響力のある仕事だと感じたためです。また、説明会や官庁訪問で出会う先輩方の人柄が、自分にも合い、働きやすそうだと感じたことも大きいです。
|
| ◇ 採用後の経歴は? |
・大学における知的財産を社会に還元するための産学官連携の推進
・大学等が保有する先端的な研究施設・設備の幅広い方々への活用推進
・国立研究開発法人理化学研究所における諸活動の調整
・原子力関連技術の安全性を向上させるための研究開発推進や人材育成(経済産業省出向時)
・福島第一原子力発電所事故に係る損害賠償の指針作成
|
| ◇ 日々の仕事の様子は? |
現在の課題把握のために、大学、研究機関、民間企業などの方々との意見交換や現地訪問をしています。また、最先端の研究開発の国際的な動向や日本の研究開発に関するデータも踏まえて、今後取り組むべき課題を認識し、取組の改善、新たな取組の実施に向けた検討を行い、関係者への説明などを行っています。
日々の業務の中では、関係者との連絡調整、説明資料の作成などが主な業務になっています。
|
| ◇ 専門性はどのように活かされていますか? |
科学技術分野がより発展していくための政策を検討する上で、自身の研究経験や知識を活かしたり、大学時代の考えも思い出したりしつつ、より身近に政策の検討ができていると考えています。
|
| ◇ 仕事の面白み、やり甲斐は? |
常に最先端の科学技術に触れられること、様々な分野の科学技術の動向や知見を得られることです。また、大学などに訪問し自分自身の足で現状・課題を把握し、日本全体を良くするための政策を考えられることです。
|
| ◇ 自己の成長を実感したエピソードは? |
幅広い方々に研究施設・設備の活用を推進するための業務に携わっていた当時、大学、研究機関に年10~20機関ほど訪問し、自分の目で現状や課題を把握するとともに、集計したデータを基に、新たな政策の立案・実施を行った経験です。
|
| ◇ 仕事と生活(家庭、趣味、地域活動など)の両立は? |
仕事は仕事で時間コストも意識し取り組み、プライベートでは趣味でフットサルやランニング、旅行などを楽しんでいます。オンとオフの切り替えを大切にしています。
|
| ◇ 今後関わっていきたい政策課題などは? |
これまでのキャリアでは国家公務員という立場でしか仕事をしたことがなかったため、現在の仕事のステークホルダー(大学、研究機関、民間企業など)の立場で仕事をし、より多角的に政策の立案・実施ができるようになりたいです。
|
| (令和5年3月) |
|
|
| |
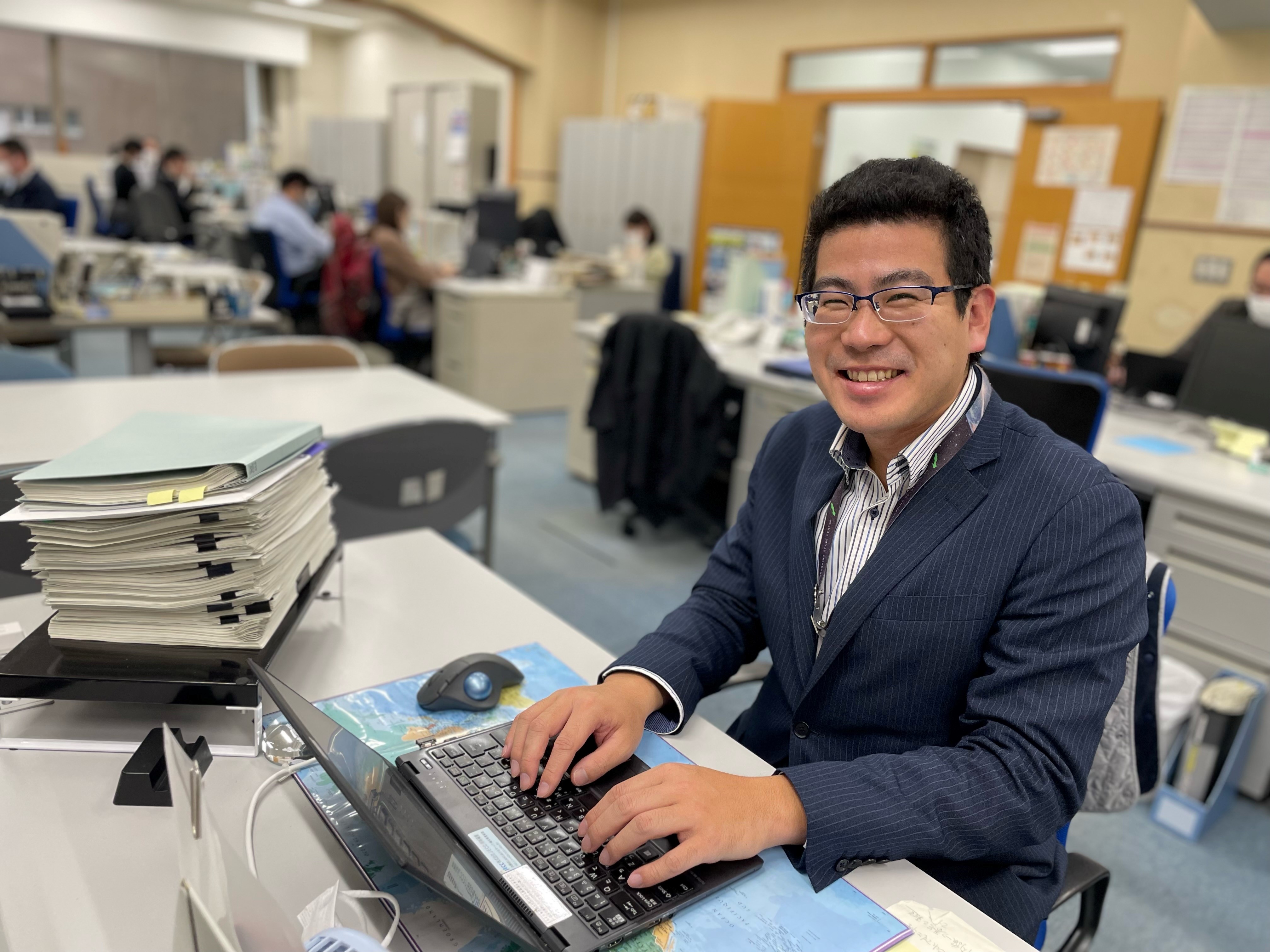
髙橋 安大  |
内閣府 健康・医療戦略推進事務局 主査
平成26年採用 総合職(数理科学・物理・地球科学)(院卒) |
| |
| ◇ 学生時代の専攻分野は? |
天文学
|
| ◇ 志望動機は? |
科学技術分野の研究開発は革新的なものになればなるほど失敗のリスクが高まるため、国が支援する必要性が高まります。国の支援により我が国の科学技術の水準が高まり、新たな製品が我が国発で生まれたり国際的なプレゼンスが高まることに貢献したいと考えたのが動機の一つです。また、自らの博士課程在籍中の経験から、その科学技術分野を支える博士人材が理不尽にも不遇な環境におかれているのではないかとも考え、待遇改善により有能な人材が適切に科学技術分野に進むような社会にすることに貢献したいと考えたことも、文部科学省を志望した理由です。
|
| ◇ 採用後の経歴は? |
文部科学省入省後は自分の専門に近い宇宙開発利用の分野に複数回携わり、ロケット・衛星開発に必要な予算の獲得やロケット打上げの安全管理に係る業務に従事してきました。これを契機として我が国の宇宙政策をどのように進めるべきか考える必要があると感じ、1年間米国に留学して宇宙政策を学ぶ機会を得ました。また、教育部局にも在籍して小中学生の学力を計測し授業改善に役立ててもらう業務にも携わりました。現在は内閣府に出向し、再生・細胞医療・遺伝子治療分野の研究開発や、国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)の組織運営に関する業務などに従事しています。
|
| ◇ 日々の仕事の様子は? |
事業の立案・推進のため関係府省との連絡・調整業務や関係する会議・打合せへの出席、予算獲得のための資料作成・説明等が大きなウエイトを占めます。また、新たな事業・政策の方向性の検討のため、有識者からヒアリングを行うこともあります。研究開発そのものを行うわけではありませんが、研究開発の現場の状況を適切に施策に反映させるため、時折、研究開発の現場への視察も行います。また、研究機関の運営管理のための資料作成等の事務的な手続きにも対応します。
|
| ◇ 専門性はどのように活かされていますか? |
研究開発の現場を実際に身をもって理解していることが重要だと考えています。研究開発のリスクや、研究者の思考回路や行動原理などを理解していることは、そうでない人よりもより研究者目線で検討ができるので、事業の組立や遂行の面で現実的な予測が立てられ、有利だと考えます。また、文部科学省は幅広い科学技術分野に携われることが特徴ですが、その中でも自分の専門に近い分野に携わることができれば、その分野固有の事情に明るいという土地鑑を使ってスムーズに議論を進めることができます。
|
| ◇ 仕事の面白み、やり甲斐は? |
自分のよいと考える施策が採用されたり、自分の発案したロジックで関係者を説得させることができた際にはやりがいを感じます。その結果、よいニュースとなって報道されることもうれしいです。一番のゴールは政策で日本がよい方向に進むこと。そのために何をすることができるのかを考えることもまた面白いと感じます。
|
| ◇ 自己の成長を実感したエピソードは? |
事案が起きた時に今後どのようなことが発生するか予測し、どのように動くべきか自ら考え行動に移せるようになったことは成長したと感じます。また、政策立案のフェーズでも、持論があったとしても一歩引いて「配慮すべき点はないか」と視野を広くもって多角的に検討したり、注意しておくべき点にすぐ気づけるようになった点は成長したところだと思います。
|
| ◇ 仕事と生活(家庭、趣味、地域活動など)の両立は? |
平日は朝、子供たちに準備をさせて学校や保育園に送り届けるのが私の役目です。平日は子供たちと関われる時間が短いので、休みの日はできるだけ一緒に出かけたり遊んだりすることを心がけています。また、以前よりもテレワークを活用して自宅で働けるようになってきたので、テレワークできる日は平日であっても家族全員で夕食をとることもできるようになりました。
|
| ◇ 今後関わっていきたい政策課題などは? |
文部科学省の所掌する幅広い科学技術分野に、これまでの経験を活かして関わるとともに、自らの専門に近い分野である宇宙開発利用の推進にもより深く関わっていきたいと考えています。また、国際的なプレゼンスの向上のため、外国との折衝・交渉にも携わってみたいと思います。
|
| (令和5年3月) |
|
|
| |
室田 優紀  |
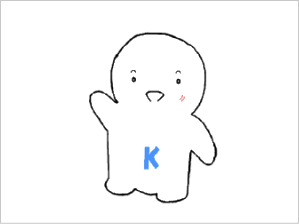
文部科学省 研究振興局 大学研究基盤整備課 資金運用企画室企画係長
平成28年採用 総合職(数理科学・物理・地球科学)(大卒) |
| |
| ◇ 学生時代の専攻分野は? |
宇宙物理学(実験)
|
| ◇ 志望動機は? |
元々科学技術が好きで、学生時代に人工衛星の開発に関わった経験から、大規模な研究開発を進めるためには国の役割が重要であることを実感し、国側から研究開発を支援したいと考えたためです。
|
| ◇ 採用後の経歴は? |
・宇宙開発・利用の推進(計13機のロケット打上げ時の危機管理を担当)
・全国学力・学習状況調査の実施(初の中学校英語調査)
・ベンチャー企業等研修(宇宙スタートアップのSynspectiveへ出向)
・10兆円規模の大学ファンドの立ち上げ(世界に伍する「研究大学」とは)
|
| ◇ 日々の仕事の様子は? |
制度設計に向けた関係省庁との調整、国立研究開発法人や大学の研究者・担当者等との議論、有識者会議等に向けた委員の任命・会議資料作成、調査研究等の委託事業、関係機関の視察、国会対応など
|
| ◇ 専門性はどのように活かされていますか? |
宇宙開発の部署では学生時代に勉強した宇宙物理の知識が直接役立ったこともありましたが、それだけでなく、元々の数学や物理等の基礎知識や学生時代に学会発表をした経験などが、専門家の方々とのコミュニケーションや説明資料作成時に活かされていると感じています。
|
| ◇ 仕事の面白み、やり甲斐は? |
現場から遠くやり甲斐を感じにくいと言われることもありますが、法律や予算といった国でしかできない仕事も多く、自分の携わった業務に関連する成果がメディアで大きく報道されていたり、実際に研究者の方々から御礼を言ってもらえたりすると、あのとき必死で頑張ってよかったと達成感を感じます。
|
| ◇ 自己の成長を実感したエピソードは? |
入省した頃は目の前の業務を処理することに必死で、気づいたら1日が終わっていたような感覚がありました。仕事は今もハードですが、情報処理能力もあがり、社会人1年目の頃から上司の思考や判断を側で学ぶことができたおかげで、計画的に仕事を進めることができるようになりました。
|
| ◇ 仕事と生活(家庭、趣味、地域活動など)の両立は? |
ジムで運動したり、美味しいうどんを食べたり、たまにはゴロゴロしたり、メリハリを大切に自己管理するように心がけています。
|
| ◇ 今後関わっていきたい政策課題などは? |
文部科学省は教育・文化・スポーツ・科学技術といった幅広い政策に携われることが魅力であり、宇宙という自分の専門分野を軸にしつつ、様々な業務経験を積んで、行政官としてレベルアップしていきたいです!
|
| (令和5年6月) |
|
|
| |

青木 沙也  |
文部科学省 研究振興局 ライフサイエンス課 ライフサイエンス係長
平成29年採用 総合職(農業科学・水産)(院卒) |
| |
| ◇ 学生時代の専攻分野は? |
植物生理学
|
| ◇ 志望動機は? |
文部科学省は科学技術だけでなく、教育、スポーツ、文化も所管しており、一つの職業の中で幅広い分野に携われることに魅力を感じました。
|
| ◇ 採用後の経歴は? |
・高速増殖原型炉もんじゅの廃止措置にかかる調整
・東日本大震災からの復興、災害対応、省改革タスクフォース等の省内取りまとめ
・科学技術基本法等の改正
・予算要求、予算執行等にかかる調整
・健康・医療分野の研究開発の推進
|
| ◇ 日々の仕事の様子は? |
現在は、主に健康・医療分野の研究開発の推進に必要な予算の取りまとめをしており、予算の要求にあたって必要な資料の作成や財務省対応等の調整を行っています。
また分野担当課として、研究開発目標等の検討も行っています。
|
| ◇ 専門性はどのように活かされていますか? |
現在の課では、基礎的な生物学の知識や、研究室時代の実験の経験が、資料作成をはじめとした業務の基盤として役立っていると感じます。
|
| ◇ 仕事の面白み、やり甲斐は? |
科学技術・学術の観点で、革新的な成果の創出に繋がるかもしれない事業の設計に携われることです。また異動が多い分、様々な分野に携わることができる点もこの職業の面白みと思います。
|
| ◇ 自己の成長を実感したエピソードは? |
対応方針をパッと立てられる仕事が増えてきたなと実感したときです。
|
| ◇ 仕事と生活(家庭、趣味、地域活動など)の両立は? |
休日は家族や友人と食事に出かけ、リフレッシュしています。
|
| (令和5年3月) |
|
|
| |
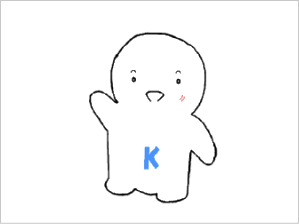
安井 里沙  |
外務省 国際協力局 国別開発協力第三課
平成31年採用 総合職(化学・生物・薬学)(院卒) |
| |
| ◇ 学生時代の専攻分野は? |
薬学
|
| ◇ 志望動機は? |
大学で薬について様々な視点から学ぶ中で、全てのものづくりは基礎研究が支えているんだと思うに至りました。基礎研究を支えるために、研究者の環境整備や未来の研究者を育てる初等・中等教育分野の制度設計等、多くのアプローチから”ひとりひとり”への支援を行うことができる文部科学省に魅力を感じました。
|
| ◇ 採用後の経歴は? |
・ビッグサイエンス(宇宙・原子力・防災・海洋・環境エネルギー)分野の科学技術政策の推進
・衛星データ等地球観測データを用いた、国境を越えた環境問題・災害への対応策の検討
・令和3年の政変を受けたアフガニスタン人への人道支援
・エジプトにおけるODAを通じた科学技術大学・公立小学校・博物館・地下鉄等の整備
|
| ◇ 日々の仕事の様子は? |
・より効果的な支援を行うための大使館・JICA・国連機関・本邦企業とのやりとり及び協議
・ODAプロジェクトの採択に向けた各省との協議
・プロジェクトの円滑な実施のための関係者とのコミュニケーション・フォローアップ
・一筋縄ではいかない案件の円滑な実施のための関係機関との調整
・国会対応
|
| ◇ 専門性はどのように活かされていますか? |
理系の専門性を持つ職員として、論理的に且つ根拠付けて物事を考え説明する力を以て、より納得感のある政策・プロジェクトの立案に貢献していると感じます。また、現職ではODAプロジェクトとして保健分野の支援を多く行っているため、思いがけず薬学の専門性が生きる瞬間があります。
|
| ◇ 仕事の面白み、やり甲斐は? |
多分野にわたるプロジェクトに関し、国境を越えた多くのプレイヤーのとりまとめ役として、如何に効果的な支援ができるか、如何にそれぞれのプレイヤーにとって動きやすい環境を作るかを日々考えています。裁量が多く責任も伴う中ですが、自分の仕事・判断が政策に反映される感覚が多くあり、大きなやりがいを感じています。
|
| ◇ 自己の成長を実感したエピソードは? |
令和3年8月のアフガニスタンの政変を受けて大至急の人道支援が必要となった際、上も下も関係なく、全課体制で各省・各関係機関との調整に取り組みました。自分の仕事が目に見えて政策に反映される状況におかれて、自らの責任の大きさと、自分が動かさねばならないという実感を改めて持つことになり、自己の大きな成長につながったと思います。
|
| ◇ 仕事と生活(家庭、趣味、地域活動など)の両立は? |
仕事のスケジュールを計画的に立てて、平日も友人と食事に行ったり、趣味のチェロ・ピアノの練習にいそしんでいます。土日も所属しているオーケストラの練習・本番や、ショッピングに出かけたりと、自分のやりたいことを存分に楽しんでいます。ときには夜間や土日の業務が発生することもありますが、計画的な休暇取得など、メリハリを持った生活を意識しています。
|
| ◇ 今後関わっていきたい政策課題などは? |
入省後様々な形で国際関連業務に関わらせていただく中で、日本、各国の持つそれぞれの文化や価値観に魅力を感じています。今後は科学技術・教育・スポーツ・文化分野の海外との橋渡しを行い、国境を越えて多様な視点や価値観を吸収・発信していきたいです。
|
| (令和5年3月) |
|
|
| |

吉岡 佑真  |
復興庁 予算会計企画班 主査
平成31年採用 総合職(農業科学・水産)(院卒) |
| |
| ◇ 学生時代の専攻分野は? |
農業経済学、開発学
|
| ◇ 志望動機は? |
官庁でのインターンに参加した際、政策を検討し実行に落とし込んでいく仕事ぶりを見て、行政官を目指すようになりました。
はじめは農業関係の専攻というバックグラウンドを生かした選択も考えましたが、説明会や官庁訪問を通じて、科学技術であれば農業にとどまらずより様々な分野に貢献できるという思いに至り、最終的に文部科学省を志望しました。科学技術という切り口で幅広い分野に関わることができることは、文部科学省ならではの魅力だと思います。
|
| ◇ 採用後の経歴は? |
・ナノテクノロジー・材料科学分野の政策を検討するため、100人以上の研究者にヒアリング
・内閣府、経済産業省とともに、我が国のナノテクノロジー・材料科学分野を強化するための「マテリアル革新力強化戦略」の策定
・研究開発のDX化や、マテリアルインフォマティクス(MI)の普及に対応するための新規事業の検討
・我が国で世界トップ研究大学を実現するための「大学ファンド」の立ち上げに必要な政省令改正
・東日本大震災からの復興に向けた取組について、毎年度の復興事業の予算編成をとりまとめ
|
| ◇ 日々の仕事の様子は? |
・研究者の方々との打合せのセッティングや資料作成、打合せへの参加
・政策を検討するための基礎となるデータの収集
・省内や各省の関係課との連絡調整や打合せ
・分野の研究者等が集まる、有識者会議の資料作成
・復興事業の次年度要求について、各省担当課からヒアリングを実施
・庁内幹部や政務に対して復興予算の概算要求内容等を説明
|
| ◇ 専門性はどのように活かされていますか? |
文部科学省は、研究者の方々との打合せなどを通じて常に新しい知識に触れることができ、とても刺激的な環境です。
そして、そうした知識をどう身に付けるかは、大学での勉強方法や調べもののスキルが役に立ちます。
|
| ◇ 仕事の面白み、やり甲斐は? |
仕事を進めるにも誰に何を聞けばいいのかもわからない、というような状況から始まることもありますが、研究者の方々は、文部科学省にがんばってほしいという思いでいろいろなことを話してくださいます。
その分プレッシャーも増えますが、いろいろな人に期待されながら、がんばって政策を形にしていくのは、国の仕事ならではと思いますし、形になった時にとても達成感があります。
|
| ◇ 自己の成長を実感したエピソードは? |
幹部の方々に質問攻めにされながらも、がんばって調べたり、どう説明したら理解してもらいやすいかを考えて話すようにしていたら、私生活でも人にものを説明するのが上手になりました。
|
| (令和5年3月) |
|
|
| |

藤光 智香  |
つくば市 政策イノベーション部長
平成25年採用 総合職(森林・自然科学)(院卒) |
| |
| ◇ 学生時代の専攻分野は? |
砂防工学
|
| ◇ 志望動機は? |
研究者とは違う観点から、サイエンスに関わることができることに興味を持ち、文部科学省に入省しました。また、科学技術や教育など、正解が必ずしも一つではないことにチャレンジできるところが、ほかの仕事にはない魅力であると感じたためです。
|
| ◇ 採用後の経歴は? |
入省後は、国立研究開発法人制度改革等に携わり、その後、水産庁出向、ウナギの完全養殖の研究をはじめとする水産研究の振興にも関わりました。直近では、地域の中核・特色ある研究大学の研究力向上やEBPMの推進など、科学技術・イノベーションの推進に携わってきています。また、留学制度を利用してドイツへ留学し、経営学についても学びました。
|
| ◇ 日々の仕事の様子は? |
文部科学省では、どうしたら我が国の研究力を向上させることができるか、どこに本質的な問題があるのか、科学技術政策はどのようにあるべきか、データ分析のほか、現場の研究者や、大学関係者とも意見を交わし日々試行錯誤しています。現在はつくば市に出向していますが、つくば市では、住民の方々の困りごとを解決できるよう、科学技術を駆使して先端的サービスの提供を行い、最先端技術の社会実装と都市機能の最適化を進めています。また、海外との交流も多く、ルクセンブルクやフィンランド、フランスなど様々な国と連携・交流を行っています。
|
| ◇ 専門性はどのように活かされていますか? |
大学の研究室に所属し、実際に研究した経験は、入省後、科学技術政策を考えるときに必ず立ち返る「原点」になっています。特に、大学時代に知り合った研究者の友人や、大学関係者とは、現在でも政策の議論をしたり、率直な意見を聞ける貴重な存在です。
|
| ◇ 仕事の面白み、やり甲斐は? |
なにより「科学技術が好き」という気持ちをとことん追求できることが、とてもやりがいに感じます。また、本当に多様な経験ができることが、とても面白く、かつ自分の成長にもなります。例えば、私は今つくば市に出向していますが、住民目線の科学技術の社会実装や、科学の在り方について日々考えさせられ、とてもやりがいのある日々を送っています。
|
| ◇ 自己の成長を実感したエピソードは? |
研究者、自治体職員、大学関係者、民間企業など、立場や組織が異なる方々と、思いを一つにして仕事にあたっている時に、自分の成長とやりがいを感じます。組織が違うと、価値観や文化が異なり難しい時もありますが、多様性をプラスに変換できるとき、行政という仕事に可能性を感じます。
|
| ◇ 仕事と生活(家庭、趣味、地域活動など)の両立は? |
休日は山登りに行ったり、趣味を満喫しています。忙しい時と、休みの時の切り替えをしっかりすることで、楽しく過ごしています。現在つくば市に出向中ですが、筑波山に登ったり、地元のグルメを堪能したり、業務と余暇を両方楽しめています。
|
| ◇ 今後関わっていきたい政策課題などは? |
科学技術によって、人々に多様な幸せ、新たな選択肢を与えていくことができるということを、仕事を通じて改めて実感をしており、今後も科学技術によって人々の可能性や、選択肢を広げられるよう貢献していきたいと思っています。
|
| (令和5年3月) |
|