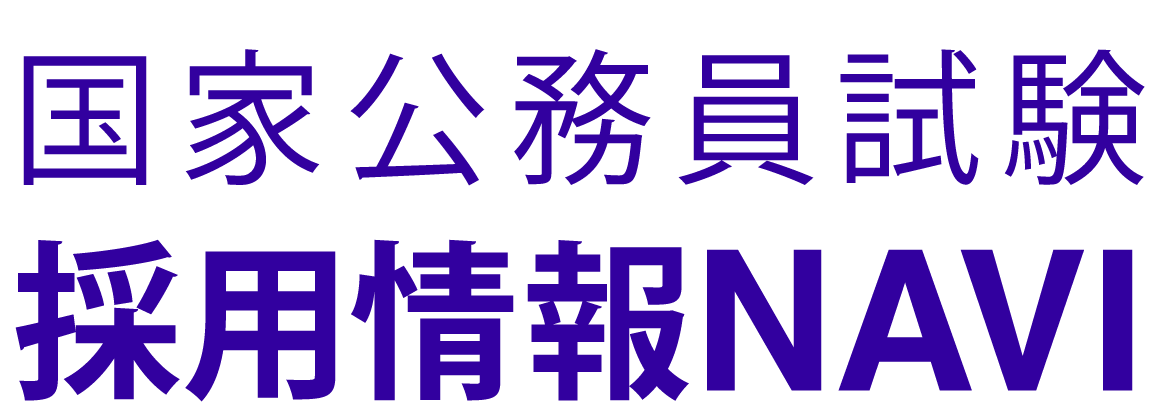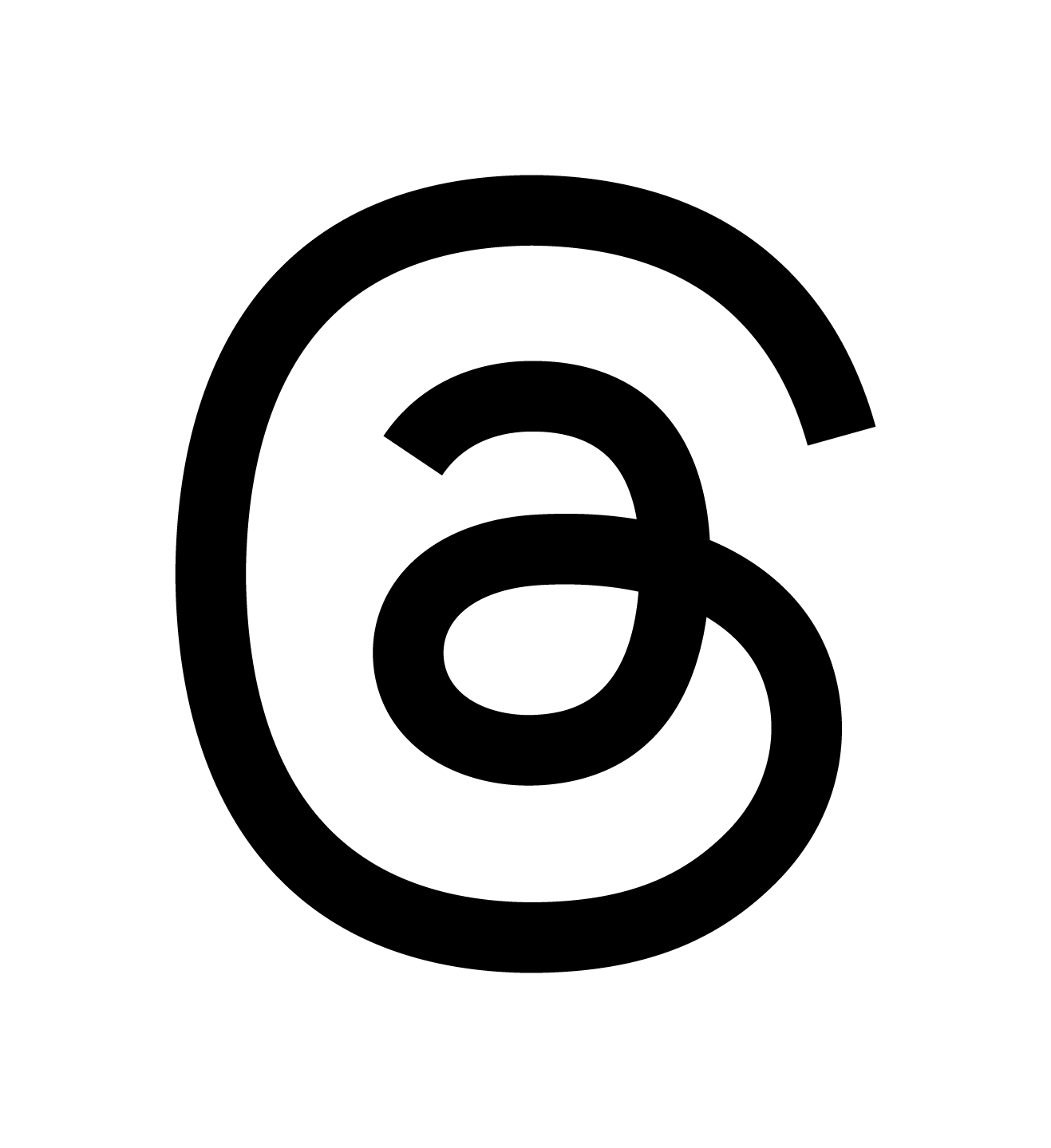|
2026年度版一般職ガイド |
||||||||||||
|
※職員の所属(役職)は、原稿執筆時のものを記載しています。
|
||||||||||||
|
||||||||||||
行 政 |
||||||||||||
|
会計検査院
 |
||||||||||||
| 会計検査院第3局環境検査課 調査官 2010年 会計検査院採用 第5局上席調査官(融資機関担当)付 事務官 2012年 第3局国土交通検査第1課 事務官 2014年 第3局国土交通検査第1課 調査官補 2015年 事務総長官房上席企画調査官付 調査官補 2018年 第3局上席調査官(道路担当)付 調査官 2020年 公正取引委員会事務総局審査局第5審査長付 審査専門官(出向) 2022年 現職 一緒に日本の未来を動かす仕事をしましょう |
||||||||||||
| ◇ 採用年・採用試験(区分) | ||||||||||||
2010年採用 国家公務員試験(Ⅱ種行政) |
||||||||||||
| ◇ 学生時代の専攻と現在の仕事との関係 | ||||||||||||
法学部出身です。非常に基本的なことにはなりますが、行政の仕事は法律に代表される多くのルールに基づいて行うこととなるため、学生時代からこれらのルールに触れる機会が多いことは強みになると思います。また、様々な現場にフィールドワークに赴くゼミに所属していたことが、全国津々浦々、様々な機関に検査に赴く検査院に興味を持つきっかけになりました。 |
||||||||||||
| ◇ 日々の仕事とやり甲斐 | ||||||||||||
日々の仕事は、出張先や検査対象事業の下調べ、検査で見つけた問題に関する資料やデータの分析、受検庁との折衝、検査報告に掲記するための文章の作成など、地道な作業の積み重ねですが、自分が携わった案件が検査報告に掲記され、業務改善に繋がることは何よりのやり甲斐です。 |
||||||||||||
| ◇ 他府省等人事交流について | ||||||||||||
検査院と公取委のどちらも「調査」を仕事としており、一見似ているようにも思えましたが、出向先はよりチームワークを重んじる職場であると感じました。調査権限に違いはありますが、調査手法や大きなチームで案件を扱うからこその仕事の進め方は検査院でも生かせるものがありました。 |
||||||||||||
| ◇ 仕事を通じて成長したと感じるエピソード | ||||||||||||
メイン担当者として携わった案件が検査報告に掲記されたことです。上司や同僚の力を借りながらも、受検庁に検査の結果とそれに対する検査院の考えを説明して理解してもらうこと、自分が作成した検査報告案について上司に説明し院内の会議をクリアするために考え工夫したことなどの、多くのハードルを乗り越えたときに成長したと感じました。 |
||||||||||||
| ◇ テレワークの経験 | ||||||||||||
仕事の前後のプライベートの予定に合わせて利用することで有効に時間を使うことができます。 |
||||||||||||
| ◇ ある1日のスケジュール | ||||||||||||
8:30 登庁 |
||||||||||||
| ◇ 執筆者と同じ試験の区分を受験しようとする人に向けてのメッセージ | ||||||||||||
視野を広く、前向きな気持ちで就職活動に取り組んでください。 |
||||||||||||
|
消費者庁
|
| 曽我 聖久 |
 |
| 消費者庁 地方協力課調整係・係員
2021年4月 消費者庁採用 地方協力課総括係 2023年1月 消費者庁総務課調整第一係 2024年7月 現職(消費者庁地方協力課調整係) 消費者行政の司令塔として、安全・安心な社会を実現する。 |
| ◇ 採用年・採用試験(区分) |
2021年採用 一般職試験(行政関東甲信越地域) |
| ◇ 学生時代の専攻と現在の仕事との関係 |
法学部で学んだ法的な知識は、法律に基づき業務を行う国家公務員の業務において役立っています。また、論点を見極め、事実や情報の裏付けを確認し、その判断について論理的に説明を行う、という、法学部で培った法的思考力は、日々、様々な判断・説明が求められる業務にあって、あらゆる場面で役に立っていると感じています。 |
| ◇ 日々の仕事とやり甲斐 |
現在は、地方公共団体における消費者行政の強化・推進に向けた取組を支援する交付金に関する制度設計を行っています。地域の消費者行政の現状や課題を把握し、交付金制度の在り方を検討するために、日々、様々な地域に足を運び、多くの関係者と意見交換を行う中で、データからは見えない地域の実情や背景を知ることができるとともに、消費者行政の旗振り役としての自己の業務の重要性を感じることができ、大きなやりがいを感じています。 |
| ◇ 仕事を通じて成長したと感じるエピソード |
総務課調整第一係に所属していた際に、庁の国会関係業務の窓口を担当し、国会での質疑対応や、日々の国会議員や政党とのやり取りなど、様々な関係者とスピード感をもって調整を行う必要がある業務を多く経験しました。これらの業務経験を通じて、国会や政党と行政機関との関係性を学ぶことができたほか、部署異動後も、国会や社会全体の動向を常に念頭に置き、広い視野を持って仕事に取り組めるようになり、自己の成長を感じました。 |
| ◇ テレワークの経験 |
テレワーク実施日は、資料作成やメール等での照会対応を中心に業務を行っています。また、テレワークでの業務環境が整備されてきたことにより、会議へのオンラインでの参加や、電話での問合せへの対応等も、在宅で行うことが可能となりました。豪雨や降雪等で、交通機関の乱れが予想される日にも、テレワークへの勤務に柔軟に切り替えることが推奨されており、多様で無理のない働き方が実現できると感じています。 |
| ◇ ある1日のスケジュール |
9:30 登庁、メール確認 |
| ◇ 執筆者と同じ試験の区分を受験しようとする人に向けてのメッセージ |
この国の未来を創る!という志の高い仲間をお待ちしています! |
 |
|
| 財務省 理財局 国有財産業務課 業務第4係長 2018年 財務省採用 大臣官房秘書課総務係 2019年 財務省理財局国有財産業務課国有財産審理室指導係 2021年 財務省主計局復興係 2022年 財務省主計局司計課司計第二係 2023年 中国財務局管財部審理課 2024年 中国財務局管財部統括国有財産管理官(第一部門) 国有財産管理官心得 2025年 現職 財政の視点から社会問題にどう取り組むべきか |
|
| ◇ 採用年・採用試験(区分) | |
2018年採用 一般職試験(行政関東甲信越地域) |
|
| ◇ 学生時代の専攻と現在の仕事との関係 | |
学生時代は会計学を専攻していました。財務省は財政制度を取り扱う省庁であり、数字を扱う機会が多い中、学生時代に会計学を通じて数字に強くなれたことは、一つの強みであると考えています。 |
|
| ◇ 日々の仕事とやり甲斐 | |
現在、私は、「所有者不明土地」に関する業務を担当しています。民間取引や土地利活用の阻害要因として社会問題となっている所有者不明土地の発生予防に資するため、法務省をはじめとする関係省庁と折衝を行いながら、日々、様々な検討を行っています。調整が難航し悩むこともありますが、議論を重ねていく中で折衷案を見つけ出し、多くの人と連携を図りながら制度を改善していくことにやり甲斐を感じています。 |
|
| ◇ 転勤について | |
財務省の地方支分部局である中国財務局へ出向し、2年間広島で過ごしました。財務局では国有地の管理処分を行う業務を担当し、実際に現地に赴いて、地域住民の方と直接関わりをもつなど、行政の最前線における実務経験を積むことができ、自らの知見を広げることができました。また、知り合いがいない土地での初めての生活でしたが、職場の仲間や広島でできた友人のおかげで、有意義な2年間を過ごすことができました。 |
|
| ◇ 仕事を通じて成長したと感じるエピソード | |
以前に私が在籍していた主計局の予算査定業務は、若手職員であっても主体的に進めていく必要があります。復興庁・内閣府の担当者として、相手省庁へのヒアリングや関係書類を通じて施策や事業の内容を把握し、折衝を重ねて作り上げた予算案について、根拠を示しながら自分の言葉で上司に説明し、了承を得ました。責任を伴い大きなやりがいのある業務を成し遂げたことで自身の成長を実感した、かけがえのない経験になりました。 |
|
| ◇ テレワークの経験 | |
本省勤務時及び地方転勤時のどちらにおいてもテレワークを実施しました。テレワークでは、オンライン研修の受講や各種資料の作成、電子決裁の確認等を行っていました。一人の環境で業務に集中することができ、また、通勤時間を必要としないことから、業務前後の時間を有効に使うことが可能です。 |
|
| ◇ ある1日のスケジュール | |
9:30 登庁、メールの確認 |
|
| ◇ 執筆者と同じ試験の区分を受験しようとする人に向けてのメッセージ | |
国家運営の根幹に関わる仕事をしてみませんか。 |
財務省税関
 |
|
| 財務省 横浜税関業務部 統括審査官(通関第2部門担当)付 2017年 財務省横浜税関採用 財務省横浜税関川崎税関支署統括審査官付 2019年 財務省横浜税関仙台空港税関支署統括監視官(第1部門担当)付 2021年 財務省横浜税関川崎外郵出張所統括審査官(通関第3部門担当)付 2022年 財務省横浜税関本牧埠頭出張所統括審査官(通関第4部門担当)付 2023年 財務省東京税関業務部総括関税鑑査官付 2024年 現職 貿易の最前線で国民の暮らしを支える |
|
| ◇ 採用年・採用試験(区分) | |
2017年採用 一般職試験(行政関東甲信越地域) |
|
| ◇ 学生時代の専攻と現在の仕事との関係 | |
学生時代の専攻と税関業務との直接的な関係は特にありませんが、大学やアルバイトで学んだコミュニケーション力、パソコンスキル等はどの業務にも役立っています。また、税関は研修が充実しており、一から教えてもらえるので、予備知識がなくても心配はありません。また、いずれの部署においても、上司や先輩の丁寧なサポートもあり、安心して業務に取り組んでいくことができます。 |
|
| ◇ 日々の仕事とやり甲斐 | |
現在、通関部門に在籍しています。通関部門では、輸出入貨物の申告が正しく行われているかどうかを審査し、貨物について必要な検査を行い、疑義がなければ許可するという業務を行っています。HSコード(関税率決定の基礎となる世界共通の番号)や申告価格が正しいかという税的側面や、密輸・不正輸出入の阻止の観点から貨物に不審点がないかという関的側面の両方から審査しています。自分が審査して通関した商品を手に取る人の姿を見ると、自分の仕事が国民の生活に繋がっていることにやりがいを感じます。 |
|
| ◇ 転勤について | |
仙台空港での勤務経験があります。転勤してよかったと感じることは、空港での幅広い業務を経験できたこと、また、雰囲気や仕事の流れ等を経験することができ、業務に対する視野が広がったことです。 |
|
| ◇ 仕事を通じて成長したと感じるエピソード | |
税関の業務は多岐に渡りますが、全体で見ると根幹で繋がっています。これまでの職場で経験してきたことが次の職場で活かされ、自分の力で対処できる業務の幅が広がったとき、これまでの学びが自分の糧になっていると実感できて、成長を感じるとともにモチベーションの向上にもつながります。 |
|
| ◇ テレワークの経験 | |
現在の部門では、私用で有休を数時間取得する場合に、テレワークと組み合わせるなどして活用しています。ビジネスチャットなどでもコミュニケーションが取れ、自宅でも集中できる環境を整えることができるため、出勤時と変わらず通関審査等の業務ができています。勤務時間を効率的に確保できるため、自分の状況にあった働き方ができるという点で魅力的だと感じています。 |
|
| ◇ ある1日のスケジュール | |
9:00 登庁 メールチェック、スケジュール確認 通関書類の審査 |
|
| ◇ 執筆者と同じ試験の区分を受験しようとする人に向けてのメッセージ | |
興味のある分野で、よりよい社会を一緒に作りましょう! |
厚生労働省
 |
|
| 厚生労働省 近畿厚生局 京都事務所 2023年 厚生労働省採用 近畿厚生局指導監査課係員 2024年 厚生労働省 近畿厚生局京都事務所係員 命を支える医療の質を守り、社会に安心と信頼をもたらす。 |
|
| ◇ 採用年・採用試験(区分) | |
2023年採用 一般職試験(行政近畿地域) |
|
| ◇ 学生時代の専攻と現在の仕事との関係 | |
学生時代は法学を中心に学び、法律の構造や考え方、条文の読み解き方を深めてきました。現在は近畿厚生局において健康保険法を扱う業務に携わっています。学生時代に健康保険法そのものを学んでいたわけではありませんが、法学を学んでいたことで法律を体系的に理解し、行政は法律に基づき活動するという基本的な考え方を自然に身につけることができました。そのため、条文を正確に読み取り、実務に応用する力が養われ、日々の業務にもスムーズに対応できています。 |
|
| ◇ 日々の仕事とやり甲斐 | |
保険医療機関の指定や施設基準の受理、適時調査などに取り組んでいます。適時調査では病院に立ち入り、診療体制や運営状況を確認しながら助言を行い、患者にとっても病院にとってもより良い医療提供につなげることができています。実際に病院から感謝されることもあり、大きなやりがいを感じます。また、保険医療機関の指定では、医療協議会において有識者と議論し、慎重に審査を重ねることで、保険診療の質を守る門番役として社会に貢献できることに誇りを持っています。 |
|
| ◇ 仕事を通じて成長したと感じるエピソード | |
日々の業務に加え、近畿厚生局独自の取組として、他課である地域包括ケア推進課の自治体支援プログラムにも参加しました。普段の業務とは異なり、自治体に直接赴き、地域の課題解決に向けた伴走型の支援に取り組みました。この経験を通じて、現場の声に丁寧に耳を傾ける姿勢が養われ、物事を多角的に捉える力も身につきました。また、自分の普段の業務が地域医療にどう役立っているかを実感でき、仕事への理解と視野がさらに深まりました。 |
|
| ◇ テレワークの経験 | |
テレワークでは、適時調査に向けた病院の事前審査・確認作業、医療協議会に向けた委員向け事前資料の作成、医療機関等からの法令や施設基準に関する照会への回答案作成等を行っています。集中力を要する業務が多いため、テレワークにより高い集中力を維持しながら効率的に業務を遂行しています。また、Teamsを活用して職場出勤者とも円滑な連携を図り、ビデオ通話を適宜用いるなど、物理的距離を感じないような環境でテレワークができています。 |
|
| ◇ ある1日のスケジュール | |
8:30 登庁 |
|
| ◇ 執筆者と同じ試験の区分を受験しようとする人に向けてのメッセージ | |
皆さんとご一緒できる日を楽しみにしています。応援しています! |
|
経財産業省
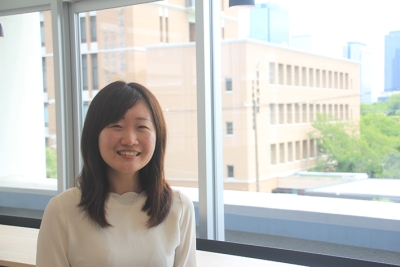 |
|
| 経済産業省 近畿経済産業局 地域経済部 地域経済課 産業人材政策係長 2017年 経済産業省 近畿経済産業局採用 流通・サービス産業課 2018年 近畿経済産業局 産業振興室 2020年 近畿経済産業局 総務課 2021年 近畿経済産業局 地域開発室 2022年 経済産業省 地域経済産業政策課(本省出向) 2024年 近畿経済産業局 地域経済課 産業振興を通じて、地域経済の成長を支える業務です。 |
|
| ◇ 採用年・採用試験(区分) | |
2017年採用 一般職試験(行政近畿地域) |
|
| ◇ 学生時代の専攻と現在の仕事との関係 | |
大学では経営学や会計学を学んでいたため、業務で企業の方へ経営課題について伺う際や、業況を把握する際に役立てることができました。入局後も、職員向け研修の受講や上司からのフォローをいただきながら、担当業務に関する最新情報や専門的な知識を習得できます。 |
|
| ◇ 日々の仕事とやり甲斐 | |
現在は産業人材政策の担当として、中堅・中小企業の方々が抱える人材課題の解決を支援しています。社会情勢が変化する中で、自社の採用・育成計画をアップデートし、成長に繋げていただくためのセミナーや、大学・銀行等と連携した取組を企画しています。所属部署だけでなく、外部の支援機関や企業の方々との対話を通じて、より良い支援を検討・実行できる点に日々やりがいを感じています。 |
|
| ◇ 転勤について | |
入局6~7年目の2年間、本省出向を経験しました。本省では、各地方支分部局の方々と連携し、全国各地の課題や取組をとりまとめ、日本全体の地域経済産業政策の検討や予算編成に携わりました。国全体としての政策検討や意思決定の流れを学ぶことができ、帰任後はより幅広い視点で、地方支分部局としての役割を意識しながら業務に取り組めるようになりました。 |
|
| ◇ 仕事を通じて成長したと感じるエピソード | |
入局当初は、目の前の業務をこなすことに精一杯でしたが、異動を重ねるごとに担当する業務以外にも視野を広げ、国全体の政策における業務の位置づけや目的を理解することで、企業や関係団体の方々との対話を通じて現状や課題を理解し、支援内容をアップデートしていく意識を持ちながら主体的に取り組むことができるようになった点が、自身の成長に繋がっていると感じています。 |
|
| ◇ テレワークの経験 | |
資料作成など集中して取り組みたい作業や、天候による交通の乱れがある際にはテレワークを活用しています。通勤時間の短縮に加え、課内での打合せや外部からの電話にも対応可能な体制が整っているため、状況に応じて使い分けることで業務効率やワークライフバランスの向上に繋がっていると思います。 |
|
| ◇ ある1日のスケジュール | |
9:00 庁、メールチェック |
|
| ◇ 執筆者と同じ試験の区分を受験しようとする人に向けてのメッセージ | |
地域の魅力・課題を共に発掘し、国の政策に繋げてみませんか? |
|
国土交通省
 |
|
| 国土交通省 近畿地方整備局 総務部 厚生課 管理係長 2013年 国土交通省採用 近畿地方整備局 総務部 契約課 2014年 国土交通省大臣官房会計課[出向] 2016年 近畿地方整備局 福知山河川国道事務所 河川管理課 河川管理係長 2019年 近畿地方整備局 木津川上流河川事務所 総務課 総務係長 2021年 近畿運輸局 観光部 観光企画課 観光産業係長[出向] 2023年 近畿地方整備局 河川部 水政課 予算係長 2025年 現職 過去から未来へ紡がれる、国民生活の根幹を支える仕事 |
|
| ◇ 採用年・採用試験(区分) | |
2012年採用 一般職試験(行政近畿地域) |
|
| ◇ 学生時代の専攻と現在の仕事との関係 | |
大学では経営学を専攻し、リーダシップと業務効率の関係性について研究する中で、リーダーのみならず所属する従業員同士の人間関係が業務効率の向上に大きく影響すると学びました。「職場の雰囲気」がより重視される現代社会ですが、業務効率へ寄与することを明確にデータとして学生時代に確認できたことで、業務上様々な年代や立場の方と接する際には、まずは人間関係の構築を行うことを意識するように心がけています。 |
|
| ◇ 日々の仕事とやり甲斐 | |
現在は、総務部厚生課で主に期間業務職員に関する事務手続き等を行っております。期間業務職員についても、近年ではフレックス・育児休暇など常勤職員の勤務形態に近づいてきており、「仕事と家庭の両立」といった環境面の整備が進んでいます。説明会等や個別相談を行う中で「今後利用する」と報告を聞く度にちょっとしたやり甲斐を感じています。 |
|
| ◇ 転勤について | |
採用されてから5年間で本省・本局・事務所の異動を経験しました。めまぐるしい異動に当初は戸惑いも覚えましたが、比較的早い段階で様々な立場で勤務できたことは非常に良い経験になったと実感しています。例えば、新しい制度施行するにあたっては、本省では制度設計に携わり・事務所では地元の方々との調整を行い・本局では両者のすり合わせ調整役を担うなど、常に物事を各立場からの視点で複合的に考えながら、業務に取り組めるようになりました。 |
|
| ◇ 他府省等人事交流について | |
同府省内ですが、近畿地方運輸局へ出向し観光行政に取り組んでおりました。とある業務の際に、過去にこれまで自分が携わっていた河川法許可等の対応が必要となり、河川法の法令解釈、観光振興の重要性など、両者の経験を活かすことで業務を円滑に進めることができました。また、日常の業務やり方ひとつとっても、職場風土が違うと感じることも多々あり、物事の考え方が柔軟になりました。 |
|
| ◇ 仕事を通じて成長したと感じるエピソード | |
河川法許認可業務を担当する課に所属していたとき、新聞等のメディアに掲載されるような案件を担当していました。事業者・自治体・省内担当など関係者多数のなか調整が難航していましたが、資料作成・各関係者の説明対応など、ひとつずつ進めていく中で一定の結果を出せたことは、現在でも自信に繋がっております。今後、困難な業務に直面した際にも経験を糧とできるよう取り組んでいきたいと考えています。 |
|
| ◇ テレワークの経験 | |
上下水道事業の補助金業務を行っていた際にテレワークを積極的に活用していました。補助金審査はシステム上で行うため、テレワークを実施することができました。片道約1時間の通勤がなくなり、自宅周辺での私用も年休を取得せずとも済ますことができるなど、限られた時間を有効に活用できていると感じています。。 |
|
| ◇ フレックス勤務経験 | |
コロナ禍を契機にフレックス勤務を開始しましたが、プライベートの用事が間に合わない場合など、かなり活用できる制度であると感じ、以降はすべての部署でフレックスを活用しております。フレックス利用にハードルを感じるかもしれませんが、私はプライベートの充実のために取得していますし、積極的に活用すべき制度と思います。 |
|
| ◇ 執筆者と同じ試験の区分を受験しようとする人に向けてのメッセージ | |
国家公務員≠同じ仕事 好奇心を幅広く! |
|
デジタル・電気・電子
総務省
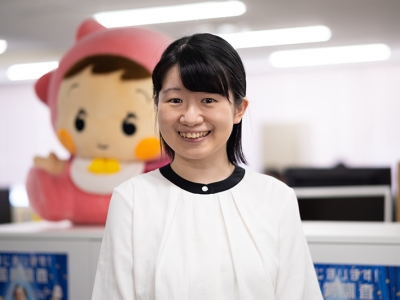 |
|
| 総務省 統計局 統計調査部 国勢統計課 統計専門職 2016年 総務省採用 統計局統計調査部経済統計課審査発表第一係 2018年 総務省統計局統計調査部消費統計課物価統計室物価指数第二係 2022年 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部国民支出課 2023年 現職 2 国の社会基盤となる統計に携わることができる仕事 |
|
| ◇ 採用年・採用試験(区分) | |
2016年採用 一般職試験(電気・電子・情報) |
|
| ◇ 学生時代の専攻と現在の仕事との関係 | |
学生時代は情報科学を専攻しておりました。これまで携わってきた業務では、結果の分析や試算等を行うことも多く、学んできた数学の知識が役立ちました。また、知識だけでなく、学生時代に培った粘り強く課題に向き合う力が、さまざまな業務に挑戦する際にも役立っていると感じています。 |
|
| ◇ 日々の仕事とやり甲斐 | |
人口関連統計を用いて、毎月の人口の推計および公表を行っています。具体的には、毎月の公表資料や年次報告書の作成および公表、外部からの照会対応や白書協議等を行っています。また、国会で議論される政策のエビデンスとして使用されるデータの確認や参考資料の作成を行うこともあります。推計を通して日本の現状を間近で見つめることができることや、公表結果が社会をより良くするための基盤として活用されているのを目の当たりにした際にやり甲斐を感じます。 |
|
| ◇ 仕事を通じて成長したと感じるエピソード | |
公表作業では、集計後の限られた時間で業務を行うことが多く、進捗状況の共有や係内で協力し合うことが欠かせません。業務を行うなかで、日々同僚の方々からサポートをしてもらった経験から、チームの一員として協力して業務を行うことの大切さを実感しました。この経験を通じ、まずは現状を把握したうえで、自分はどのような場面で周囲にサポートできそうかを考え、実行しながら業務を行うようになりました。 |
|
| ◇ ある1日のスケジュール | |
9:00 登庁 |
|
| ◇ 執筆者と同じ試験の区分を受験しようとする人に向けてのメッセージ | |
社会のために、知識や経験が幅広く活かせるのが国家公務員の魅力だと思います。 |
|
機 械
警察庁
 |
|
| 中部管区警察局 情報通信部 通信施設課 課長補佐 2004年 警察庁採用 中部管区警察局富山県情報通信部 2007年 警察庁 警察大学校警察情報通信研究センター 助手 2009年 警察庁 中部管区警察局石川県情報通信部 係長 2013年 警察庁 中部管区警察局富山県情報通信部 係長 2018年 警察庁 中部管区警察局情報通信部 係長 2019年 警察庁 警察大学校警察情報通信研究センター 助教授 2020年 警察庁 中部管区警察局岐阜県情報通信部 課長補佐 2022年 警察庁 警察大学校附属警察情報通信学校 教授心得 2024年 現職 やりたいを実現する仕事 |
|
| ◇ 採用年・採用試験(区分) | |
2004年採用 国家Ⅱ種(機械) |
|
| ◇ 学生時代の専攻と現在の仕事との関係 | |
学生時代は機械科で機械全般の勉強を行ってきました。機械科の授業では、全体像を把握するためにブロック図を使用します。ブロック図とは、要素をブロックで表し、その要素ブロックを連結して全体像を把握するものです。部品同士のつながりや役割がわかりやすく、全体像も把握しやすい、といった特性があります。現在の業務にもこの考え方を適用し、各業務やその中での役割をブロック図を使って表現しています。問題点の把握や改善点を見つけやすいので、とても重宝しています。 |
|
| ◇ 日々の仕事とやり甲斐 | |
各部署からの要望を元に事業を発案し、予算要求を行いながらプロジェクトを立ち上げ、実現できるよう計画を立案する仕事です。部署をまたいで調整し、各事業者との打ち合わせも行いながら、プロジェクトを現実化させていきます。自分の発案が具現化されていく過程は、他の業務ではなかなか味わえない貴重なものですし、やりがいもひとしおです。 |
|
| ◇ 転勤について | |
採用の富山県から、石川県、岐阜県、愛知県、東京都で勤務し、転勤を経験しました。 |
|
| ◇ 仕事を通じて成長したと感じるエピソード | |
警察大学校で職員の教育に携わり、入校生側の「基礎知識を学べる大切さ」だけでなく、組織における人材育成の重要性を実感しました。組織として存続していくためには人材育成が欠かせません。「どのような人材を育成し、どのような知識を持たせるべきか」と組織の未来像を想像しながら考えて教えるようになり、自分の成長を感じました。現在の業務におけるスタンスにもなっています。 |
|
| ◇ テレワークの経験 | |
単身赴任で東京で勤務していた時に、岐阜の自宅にしばらく戻る必要があり、テレワークを申請しました。岐阜の自宅からテレワークを実施しましたが、自宅からでも職場クラウド上にあるファイルにアクセスできるので、東京の職場にいる同僚と電話でやりとりしながら資料作成業務を進めることができ、非常に有益と感じました。 |
|
| ◇ フレックス勤務経験 | |
警察大学校では、学生入校中は勤務時間外でも学生対応をすることがあります。このため、学生入校中は勤務時間を延ばし、逆に学生がいない期間は勤務時間を短縮しました。短縮することで得た余暇時間を有効活用し、趣味の読書や単身赴任先の東京から自宅のある岐阜県に帰宅する時間に充てました。勤務にメリハリが出て、意欲が沸きました。 |
|
| ◇ ある1日のスケジュール | |
8:30 登庁 |
|
| ◇ 執筆者と同じ試験の区分を受験しようとする人に向けてのメッセージ | |
機械の知識はどこでもいかせます。自分の知識を信じて頑張ってください。 |
|
土 木
防衛省
 |
|
| 防衛省 沖縄防衛局 調達部 土木課 2023年 防衛省採用 中国四国防衛局土木課 防衛省中国四国防衛局土木課係員 2025年 現職 防衛省沖縄防衛局土木課係員 国防の裏に、土木のチカラ。 |
|
| ◇ 採用年・採用試験(区分) | |
2023年採用 一般職試験(土木) |
|
| ◇ 学生時代の専攻と現在の仕事との関係 | |
学生時代は土木を専攻し、構造、水理、測量などの基礎を幅広く学びました。しかし、実際に働き始めてみると分からないことも多く、現在は上司や現場の方々に教えていただきながら、日々勉強する心構えで業務に取り組んでいます。それでも、学生時代に学んだ知識が土台となっていると感じる場面も多く、実務を通じてその知識への理解が深まることにやりがいを感じています。 |
|
| ◇ 日々の仕事とやり甲斐 | |
日々の業務の中で、基地に出張し、工事監督官として現場を見る機会があります。自分の目で現場を確認することで、図面を見るだけでは分からなかった状況や課題に気づけることも多く、現場に足を運ぶ大切さを実感しています。普段の生活では見ることのできない基地内の特殊な建物の建設に携われるのは、防衛インフラを支えるこの仕事ならではの大きな魅力だと感じています。 |
|
| ◇ 転勤について | |
転勤が決まったときは、知らない土地で生活することに正直とても不安を感じていました。しかし、実際に暮らしてみると、新しい出会いや発見があったり、新たな現場で経験を積めたりして、転勤も案外悪くないなと思えるようになりました。転勤にはマイナスなイメージを持たれがちですが、実際にその土地に住んでみることで、自分の視野を広げられる貴重な機会だと感じています。 |
|
| ◇ 仕事を通じて成長したと感じるエピソード | |
1年目には分からなかったことが、2年目には自然と理解できるようになっていたとき、自分の成長を感じました。日々多くのことを教わる中で、すぐには使わない知識でも覚えておくことで、点と点がつながる瞬間があります。また、現場ごとに異なる課題に向き合う中で、柔軟な対応力や関係者との調整力も身についてきたと感じています。これまでの経験が少しずつ積み重なり、それが次に生かされることに気づかされました。 |
|
| ◇ ある1日のスケジュール | |
8:30 登庁 |
|
| ◇ 執筆者と同じ試験の区分を受験しようとする人に向けてのメッセージ | |
あなたも国を支える仕事に挑戦してみませんか? |
|
建 築
外務省
 |
|
| 在ガボン日本国大使館営繕班 三等理事官 2021年 外務省採用 在外公館課営繕室 2022年 在外公館課総務班 2023年 在フランス日本国大使館 語学研修員 2024年 現職 技術力と語学力、2つを武器に世界で活躍できます。 |
|
| ◇ 採用年・採用試験(区分) | |
2021年採用 一般職試験(建築) |
|
| ◇ 学生時代の専攻と現在の仕事との関係 | |
学生時代は建築意匠専攻で日本の茅葺建築についての研究を行っていました。茅葺きはかつて日本のどこにでも存在していた工法で、日本の原風景ともいえるものです。そのような土地に根付いた建築のあり方に惹かれていました。海外で大使館を計画・建設する上でも、その国・地域に馴染む建物を意識する必要があります。そういった意味で、学生時代の研究で培った考え方がそのまま仕事にいきています。 |
|
| ◇ 日々の仕事とやり甲斐 | |
現在は、在ガボン日本国大使館事務所・公邸の新築工事を担当しています。施工は現地業者とともに進めており、設計どおりに工事が進むように監督をするのが私たちの役割です。現地業者が経験のない日本の設計基準で工事を進めるため、何度も業者と打合せをして譲れるところ、譲れないところを判断しながら建物の完成に向けて調整を行っています。現地業者のコントロール次第で品質が大きく変わるため、重要な責務を担っていると思うと、やりがいを感じます。 |
|
| ◇ 転勤について | |
外務省では本省と海外の在外公館(大使館など)の異動を、数年おきに異動を繰り返すことが一般的です。それが他の公務員との大きな違いであり、外務省勤務の醍醐味でもあります。私たち技術系採用区分(営繕)では、入省からおよそ2年半後に海外での1年間の語学研修が始まり、その後在外公館での勤務をします。 |
|
| ◇ 仕事を通じて成長したと感じるエピソード | |
日本基準で現地業者に工事を進めてもらうためには、自分自身が日本の設計基準をよく理解していなければ、彼らに指示を行うことはできません。また、その技術があってもそれを表現できる語学力がなければ、伝えることはできません。現職についた当初の自分はその二つともが欠けており、上司について行くことで必死でしたが、仕事をとおして徐々に技術力も語学力も身についていることを実感しています。 |
|
| ◇ テレワークの経験 | |
外務本省では週1日程度のテレワークが推奨されていました。静かなところで黙々と行いたい作業などは、テレワークを活用することで集中して行うことができるため、うまく使えば業務がはかどります。通勤や残業時間がなくなり、プライベートの時間が増えることでメンタル・体力を整える機会となっていて、よい制度だと思います。 |
|
| ◇ ある1日のスケジュール | |
7:45 出勤 |
|
| ◇ 執筆者と同じ試験の区分を受験しようとする人に向けてのメッセージ | |
技術試験の勉強は仕事でも役に立ちます。頑張ってください! |
|
物 理
気象庁
 |
|
| 気象庁 大気海洋部予報課 予報係 2017年 気象庁採用 前橋地方気象台観測予報グループ 現業班員 2019年 名古屋地方気象台観測予報グループ 現業班員 2022年 気象庁大気海洋部予報課気象監視・警報センター 現業班員 2024年 現職 過去に学び、今を知り、未来を考える |
|
| ◇ 採用年・採用試験(区分) | |
2017年採用 一般職試験(物理) |
|
| ◇ 学生時代の専攻と現在の仕事との関係 | |
学生時代は物性物理学を専攻しており、超電導物質について研究していました。現在の仕事である気象学が専門ではありませんでしたが、学生時代に学んだ基礎的な物理学の知識は気象学を学ぶ上で大いに役に立っています。また、観測されたデータを解析し、予報に利用していく過程では、学生時代の研究で身に着けた考え方が活きていると感じます。 |
|
| ◇ 日々の仕事とやり甲斐 | |
採用されてから現職まで予報現業に関わる仕事に携わっており、天気予報や注意報・警報など各種気象情報の作成・発信を行っています。また、現職では発表する気象情報の今後のあり方についての検討なども行っており、国民の日々の生活に直結する気象情報を自分の手で作成できることにやりがいを感じています。 |
|
| ◇ 転勤について | |
群馬県で採用され、愛知県、東京都への2回の転勤を経験しました。地方気象台から地方中枢、のちに本庁と、役割の違う職場での仕事を経験したことで、業務の全体的な流れを知ることができました。また、それぞれの実情や状況も知ることができ、業務を円滑に行うという点で現在の業務に活かせていると感じています。また、予報業務という観点では、様々な地域の気象特性を知ることができ、気象への知識を深めるためにも有用と思います。 |
|
| ◇ 仕事を通じて成長したと感じるエピソード |
|
天気予報は、スーパーコンピュータが計算した気象モデルなどをもとに、予報担当者が作成しています。気象モデルで予想できていない現象を、実況の推移や観測データ、過去の事例などを根拠に自らの判断で予想し、実際に現象が発現した際には成長を感じました。 |
|
| ◇ テレワークの経験 | |
テレワーク時には、参加できなかった会議の録画視聴や調査研究、報告書やマニュアルなどの作成、予報の振り返りなどを行っています。通勤時間がないことが最大のメリットだと感じますが、その分、プライベートと仕事の切り替えが難しいため、テレワーク用のスペースを作ったり、外の空気を吸うため昼休みに散歩したりと集中力を保てるようにしています。 |
|
| ◇ ある1日のスケジュール | |
8:30 登庁 |
|
| ◇ 執筆者と同じ試験の区分を受験しようとする人に向けてのメッセージ | |
目の前のことを精一杯頑張ってください! |
|
化 学
原子力規制庁
 |
|
| 原子力規制庁 原子力規制部 核燃料施設等監視部門 係員 2023年4月 原子力規制庁採用 原子力規制部核燃料施設等監視部門 総括係員 2024年4月 現職 培った論理的思考・科学的知見は、安全へと邁進するために |
|
| ◇ 採用年・採用試験(区分) | |
2023年採用 一般職試験(化学) |
|
| ◇ 学生時代の専攻と現在の仕事との関係 | |
学生の頃は物理化学を専攻しており、分光学に関する研究を行っていました。現在所属する核燃料施設等監視部門では、原子炉で使用した核燃料の再処理を行う施設をはじめとした核燃料施設等の検査を担当していますが、所属していた研究室では、まさに使用済燃料を再処理する過程で行われる溶媒抽出に関する分光研究が行われていました。また、他にも核燃料施設では様々な化学工程があり、学生の頃に学んだ知識が役立っていると感じています。 |
|
| ◇ 日々の仕事とやり甲斐 | |
発電所の他にも核燃料の加工、再処理等を行うサイクル施設や中性子を取り出して利用する試験炉など、原子力施設は多岐にわたり、私はそれら核燃料施設等の検査の取りまとめを行っています。検査を担当する施設それぞれに応じた視点で確認する必要があるという難しさはありますが、そこに面白さを感じています。また、組織として現場を非常に大事にする風潮があり、出張で現場に赴く機会も多く、体験から得る学びはとても大きなものになっています。 |
|
| ◇ 仕事を通じて成長したと感じるエピソード | |
令和6年能登半島地震の際、原子力施設に対する事故警戒本部に緊急参集し、対応にあたりました。私は事業者から提出された原子力施設の情報を受け取り、関係者に展開する担当で、鮮度が重要な情報を確実かつ迅速に発信することが求められる、とても責任の大きい業務でした。この経験は、その後の事故警戒時の情報展開に係る運用の見直しへの貢献や後輩へのアドバイスに繋がる等、様々な場面で役立ち、成長を実感できました。 |
|
| ◇ テレワークの経験 | |
テレワークは計画的に利用しています。原子力規制庁全体でテレワークが推進されているため、活用しやすい雰囲気が醸成されています。検査報告書の作成・修正作業では周りを気にせず集中できますし、オンライン会議室を利用した研修を受講する際には非常に有効だと感じています。また、業務にかかわらず通勤時間が無くなるのはかなり嬉しい点です。その分の時間を家事やプライベートに充てられるので生活への満足度が高まります。 |
|
| ◇ ある1日のスケジュール | |
9:30 登庁 |
|
| ◇ 執筆者と同じ試験の区分を受験しようとする人に向けてのメッセージ | |
化学の力で人々の暮らしを支える大きな一翼を担ってみませんか。 |
|
農 学
農林水産省
 |
|
| 農林水産省 農産局果樹・茶グループ・工芸係長 2017年 農林水産省採用 中国四国農政局園芸特産課 2018年 農林水産省中国四国農政局生産振興課 2019年 農林水産省農林水産技術会議事務局研究開発官室 2021年 農林水産省経営局就農・女性課 2023年 内閣府食品安全委員会事務局評価第二課 2025年 現職 担当品目のエキスパートを目指せる |
|
| ◇ 採用年・採用試験(区分) | |
2017年採用 一般職試験(農学区分) |
|
| ◇ 学生時代の専攻と現在の仕事との関係 | |
学生時代は理学部生物科学専攻で、植物生理学や細胞生化学を中心に学びました。現職の担当品目の一つである葉たばこは、学生時代に実験のモデル生物として研究室内施設で栽培した経験があり、馴染みがあります。ある作物の栽培経験があることで、他の作物の栽培技術の把握も容易になります。 |
|
| ◇ 日々の仕事とやり甲斐 | |
生産振興に係る補助事業のための予算要求や運営業務を担っております。担当品目は葉たばこや薬用作物等を含む地域特産作物で、マイナー品目が多いので、全国での栽培状況や栽培技術等の知見が不足している現状があります。そのため、関係団体の研修会に参加したり、現場の声を聞く機会を設けるなどして、その作物を取り巻く状況の把握に努め、政策に生かせるよう意識しています。 |
|
| ◇ 転勤について | |
入省1、2年目は中国四国農政局に赴任しました。1年目は補助事業の担当で、中国四国地域の茶や薬用作物の生産振興に取り組みました。自分の担当品目に係る現地調査のほか、担当外の品目の現地調査にも同行の機会をいただき、品目横断的に、生まれ育った関東平野とは異なる中山間地域の現状や、農業従事者の高齢化・人手不足等の課題を目の当たりにしたことで、3年目以降の本省での生産振興や新規就農促進の業務を遂行するうえで、政策の目的を強く意識することができるようになったと思います。 |
|
| ◇ 他府省等人事交流について | |
内閣府食品安全委員会事務局に2年間出向しました。食品の健康影響を評価するリスク評価機関であり、農林水産省等のリスク管理機関からの諮問(評価要請)を受けて評価を実施するスキームのため、農薬や添加物、遺伝子組換え食品等について、農林水産省とは異なる視点で捉えることができました。また、他省庁や民間企業からの出向者が多く、業務の進め方やペーペーレス化のアイデアなど、今後の業務に取り入れたい事例に出会えたことも幸運だったと思います。 |
|
| ◇ 仕事を通じて成長したと感じるエピソード | |
国会議員からの質問事項に回答するため、担当事業の過去の要件変遷や当時の社会情勢の把握、予算要求の根拠を示すための分析作業等、自分の能力を超えていると感じる業務にあたることがありました。その度に、自分で調べ尽くすのはもちろん、周囲にアドバイスを求めたり、必要な分析スキルの習得に努めたりしました。その時は大変ですが、困難を乗り越える過程で対人関係スキルや知識、異動後も活用できるスキルを身につけることができたと後になって実感しました。 |
|
| ◇ テレワークの経験 | |
以前に所属した部署では、対面の会議がない日にテレワークをすることがありました。データ資料や報告物の作成業務では、出勤時に比べて集中して取り組むことができました。オンラインの会議には出席できますし、チャット機能や通話機能もあるので、職員同士のコミュニケーションにも困りません。 |
|
| ◇ ある1日のスケジュール | |
9:20 登庁 |
|
| ◇ 執筆者と同じ試験の区分を受験しようとする人に向けてのメッセージ | |
農学部出身でも、そうでなくても、活躍の場は無限です。 |
|
農業農村工学
内閣府
 |
|
| 内閣府 沖縄総合事務局 農林水産部 農村振興課 2022年 内閣府沖縄総合事務局採用 土地改良総合事務所保全整備課 2023年 内閣府沖縄総合事務局宮古伊良部農業水利事業所工事第二課 2025年 現職 地元農業の問題点を基盤整備で解決し、持続可能な農業を目指して |
|
| ◇ 採用年・採用試験(区分) | |
2022年採用 一般職(農業農村工学) |
|
| ◇ 学生時代の専攻と現在の仕事との関係 | |
大学では農業農村工学を専攻しており、沖縄県多良間島の地下水について研究を行っておりました。多良間島では、国営かんがい排水事業実施に向けた調査が行われており、実際の調査現場等を見ることができました。その際に、国営事業の規模の大きさや地元の期待などを身に染みて感じることができ、私も国の仕事に関わりたいと思いました。現在、担当している業務においても、多良間地区国営事業実施に向けた検討会等の企画・調整を行っております。 |
|
| ◇ 日々の仕事とやり甲斐 | |
農村振興課では、新規国営事業の計画から県や市町村への補助事業採択審査などの業務を担当しております。 |
|
| ◇ 転勤について | |
沖縄本島から西に約280kmの位置にある宮古島に転勤しました。私自身沖縄県出身であるものの、宮古島には、プライベートでは一度も訪れたことはありませんでした。そのため、赴任後は、休日を利用して様々な場所に足を運び、宮古島について色々と知ることができました。また、宮古島には、全国的にも珍しい「地下ダム」を造成していることから実際の施工状況も見ることができ、非常に勉強になりました。「転勤」は、こういった経験ができることが魅力だと思います。 |
|
| ◇ 仕事を通じて成長したと感じるエピソード | |
入局して4年目になりますが、一番成長したこととしては、主体的に動けるようになったと感じたことです。入局したばかりの時は正直なところ、受け身で業務をおこなっていましたが、年々経験を積んでいくと会議の際に自分の意見を出したり、関係機関との調整を組んだりなど業務一つ一つに対して、しっかりと何をすれば良いかということを考えて動けるようになりました。主体的に動けるようになり、業務もより一層効率的に処理できるようになったと感じてます。 |
|
| ◇ ある1日のスケジュール | |
8:30 登庁、打合せ場所(県の出先機関)へ移動 |
|
| ◇ 執筆者と同じ試験の区分を受験しようとする人に向けてのメッセージ | |
国家公務員として、スケールの大きい農業基盤整備に携わりませんか。 |
|
林 学
林野庁
 |
|
| 林野庁 中部森林管理局 木曽森林管理署治山技術官 2017年 林野庁採用 中部森林管理局南信森林管理署(治山グループ) 2019年 中部森林管理局南信森林管理署諏訪南森林事務所 2020年 林野庁林政部企画課政策評価班 2022年 関東森林管理局伊豆森林管理署河津森林事務所地域技術官 2024年 現職 荒れた渓流や崩れた斜面を豊かな森林に戻す |
|
| ◇ 採用年・採用試験(区分) | |
2017年採用 一般職試験(林学) |
|
| ◇ 学生時代の専攻と現在の仕事との関係 | |
学生時代は木材化学の研究室を目的に林学を専攻したため林業とは違う方向を探求していましたが、授業や実習で林業を学び、サークル活動で林業ボランティアに携わるうちに林業に興味が出てきて今に至ります。林野庁の仕事は一口に森林の管理と言っても、業務内容は多岐にわたります。担当によってやることが全く異なりますが、様々な業務に興味を持って関わり、過去の配属地で得た経験を思い出しながら今の仕事に取り組んでいます。 |
|
| ◇ 日々の仕事とやり甲斐 | |
治山ダムや山腹工の施工を通して荒れた渓流や崩れた斜面を復旧し、豊かな森林に戻すことを目指して工事の発注や進捗管理を行っています。天候不順で予定通り進まなかったり、施工業者からの問い合わせにうまく対応できず悔しい思いをすることもありますが、完成した構造物を目にすると、とても達成感があります。また、特定の公益目的を達成するために指定された森林「保安林」に関する手続きも担当しています。工事監督と並行するのが大変な時期もありますが、担当である治山に限らず広く業務を知ることができ、やりがいがあります。 |
|
| ◇ 転勤について | |
これまで、長野県内および静岡県内に所在する森林管理署等と、林野庁本庁で勤務しました。土地や気候が変わると、同じ樹種でも育つ速さや伐採のタイミングが違ったり、木材の搬出方法や事業発注の時期が違ったりと、転勤の度に新しい学びがあります。また、国有林現場は自分たちで目の前の山をどうするか考える機会が多い一方、本庁では、全国かつ一般の所有者さんが持つ森林まで含めた包括的な視点で物事を考えなければならない機会もあり、それぞれにやりがいと難しさがあると感じています。 |
|
| ◇ 仕事を通じて成長したと感じるエピソード | |
現職が5年ぶり2度目の治山担当です。使用するシステムが変わっていたり、自分自身が覚えていないことも多かったりと、昨年度は改めて治山事業を学ぶ期間となりましたが、入庁1~2年目に担当した頃と比べて仕事の仕方の引き出しが増えたと感じます。法律や要領の読み方に慣れて自力で調べられる範囲が広がり、知り合いが増えたことで他署の様子を参考にできるようになり、森林事務所の経験を経たことで署内の他の担当との関わりを考えられるようになりました。治山技術者としての知識はまだまだなので、日々勉強中です。 |
|
| ◇ テレワークの経験 | |
林野庁本庁勤務の期間がちょうどコロナ禍だったため、出勤しないと進まない業務とテレワークで行える業務とを自分の中で仕分けながら実施していました。自分がコロナに罹患した際には、テレワーク環境があったことで業務を進めることができました。本庁を離れてから実施する機会はまだありませんが、お子さんの行事で時間単位の休暇を取りたい方や、仕事はできるが体調が優れない方がテレワークを活用しているのを見ると、仕事と生活の両立につながっていると感じます。 |
|
| ◇ ある1日のスケジュール | |
8:30 出勤(車通勤20分程度) ラジオ体操 |
|
| ◇ 執筆者と同じ試験の区分を受験しようとする人に向けてのメッセージ | |
自然や木々と関わりながら皆さんと働ける日を楽しみにしています。 |
|