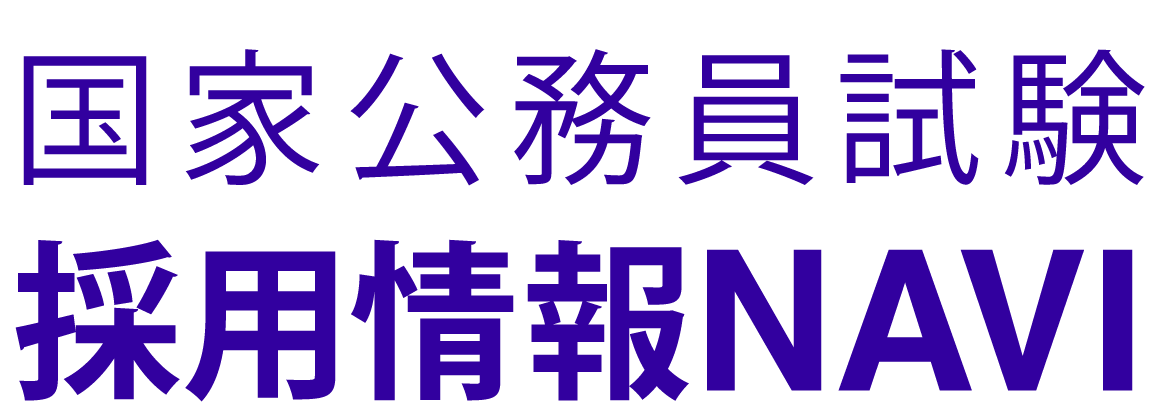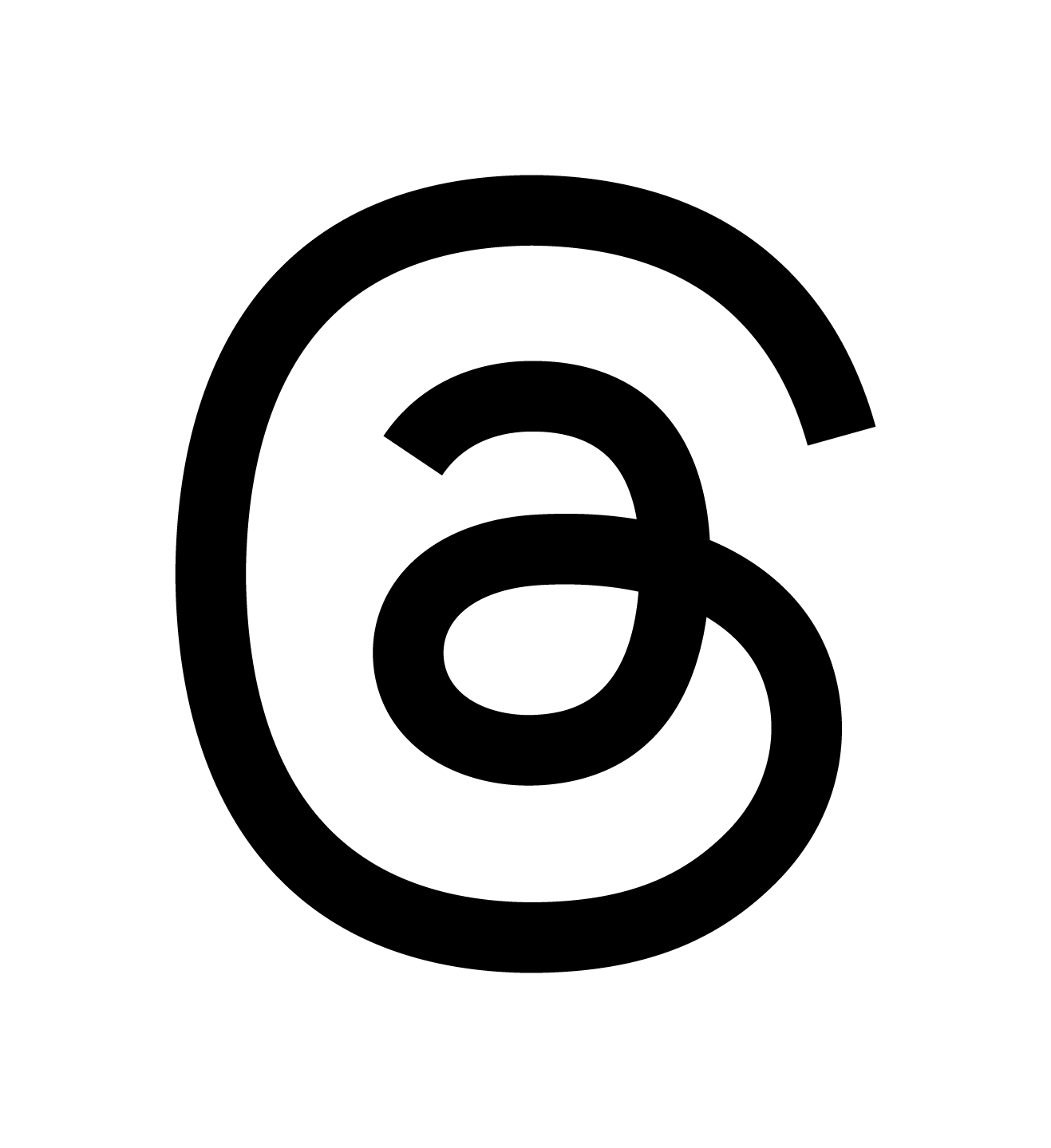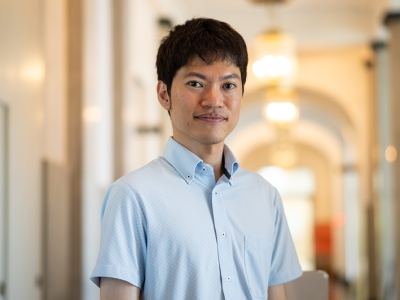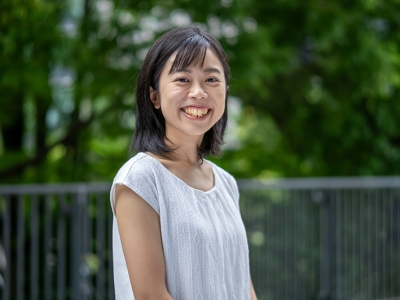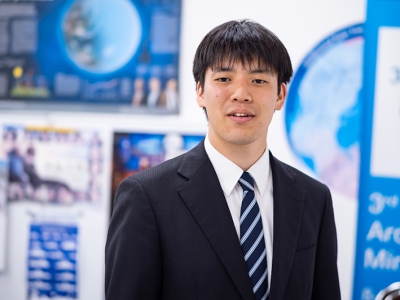|
2026年度版総合職ガイド
|
| 昨年度の記事はこちら |
| ※職員の所属(役職)は、原稿執筆時のものを記載しています。 |
|
行 政
|
| |
公正取引委員会

|
公正取引委員会事務総局 経済取引局 企業結合課 総括係長
2018年 公正取引委員会採用 官房総務課配属 総務係員
2019年 審査局第三審査上席 総括係員
2020年 経済取引局企業結合課 企画係長
2021年 (出向)消費者庁 消費者政策課
取引デジタルプラットフォーム消費者保護室 企画係長
2023年 公正取引委員会 取引部企業取引課 総括係長
2024年 経済取引局企業結合課 総括係長
自ら生み出した政策を自ら実現していく「責任」と「達成感」 |
| |
| ◇ 採用年・採用試験(区分)院卒・大卒 |
2018年採用 総合職試験(行政) 院卒
|
| ◇ 学生時代の専攻と現在の仕事との関係 |
公正取引委員会は独占禁止法を所管しておりますが、法律の条文は抽象的であるため、その執行においては必ず一つ一つの条文、文言の解釈が必要となります。私が、法科大学院で当時勉強していた独占禁止法を始めとする法に関する知識や解釈は、法執行(現職で対応している企業結合審査)の現場で必要なスキルとして日々役立てることができております。
また、基本(=法律)に立ち返る癖が身に付いているため、難しい案件においても法律からかけ離れない対応ができることも強みになっています。
|
| ◇ 記憶に残っている業務 |
皆さんが日々報道で目にする企業同士の合併等は、多くが公正取引委員会の企業結合審査を経ています。今年は航空貨物・デジタル・ドラッグストアといった分野の企業結合審査の結果を公表しました。公表される資料や文面には全て目を通し、我々がどのような審査をしたのか、少しでも分かりやすく伝わるように工夫をしています。新聞やニュースで取り上げられたり、SNS等で反応が大きいと工夫した甲斐があったと実感しています。
|
| ◇ 日々の仕事 |
独占禁止法の要件(基準)を満たした企業結合(株式取得や合併等)については、当該企業結合が実施される前に、公正取引委員会に対してあらかじめ届出を行わなければいけません。事業者から届出が行われた企業結合案件については、競争上問題がないかという観点から迅速かつ適切に審査を行う必要があるところ、私は、日々審査官を様々な角度からサポートし、円滑な企業結合審査の実施に貢献しています。
|
| ◇ 仕事の面白み、やり甲斐 |
「公正な競争」は、商品やサービスの質の向上、適正な価格設定、といった消費者にとっての恩恵を生み出します。これは、事業者が単に消費者のことを考えて商品やサービスを提供するよりも、競争というエネルギーが上乗せされた大きな効果、恩恵を生み出します。
こうした結果をイメージして、我々が考えた政策に基づき自ら法を執行していく。自分の発言や行動に責任感が常に伴いますが、「絵に描いた餅」にならないよう自ら考え、行動できることはモチベーションになっています。
|
| ◇ テレワークの経験 |
私は現在、週1回のペースでテレワークをしております。子どもが保育園に通っているのですが、朝の送りだけでなく、テレワークのおかげでたまには保育園に子どもを迎えに行って、帰宅後一緒にお風呂に入ったり、家族でご飯を食べる時間を作ることができています。
テレワークだと通勤に掛かる時間が無くなるので、仕事が忙しい中でも、家族との時間を確保しやすい点は大きなメリットだと思います。
|
| ◇ ある1日のスケジュール |
6:30 起床、朝支度
7:45 子どもを保育園に送る
9:30 登庁
10:00 朝来ているメールのチェック。各種作業依頼の対応。
11:00 審査担当班との打合せ
12:00 昼食
13:00 部下からの相談対応(様々な作業の対応方針等について)
14:00 午後のメールチェック
15:00 対応が難しい案件について上司への説明、相談
16:00 審査担当班からの相談対応
17:00 部下から作業対応の状況報告
18:15 退庁(時には、職場の仲間と飲み会に行くこともあり)
19:30 帰宅(家族で夕食、お風呂)
21:00 子どもと絵本を読みながら就寝
|
| ◇ 執筆者と同じ試験の区分を受験しようとする人に向けてのメッセージ |
皆さんの様々な個性を、国を動かす仕事にぶつけてみませんか。
|
| |
|
政治・国際・人文
|
| |
出入国在留管理庁
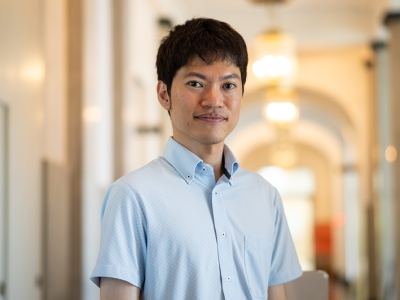 |
出入国在留管理庁 参事官室 法規企画 第二係長
2022年 出入国在留管理庁採用 総務課情報システム管理室
2023年 出入国在留管理庁 参事官室
2023年 東京出入国在留管理局調査第五部門
2024年 法務省大臣官房会計課
2025年 現職
世界とつながり、日本の未来をつくる |
| |
| ◇ 採用年・採用試験(区分)院卒・大卒 |
2022年採用 総合職試験(政治国際)大卒
|
| ◇ 学生時代の専攻と現在の仕事との関係 |
学生時代は、アジア法のゼミに所属し、東南アジアをはじめとしたアジア諸国の法や法整備支援について学ぶとともに、カンボジアへ留学し、現地の法や社会について理解を深めました。現地の事情への解像度が増したこと、外国人の立場に立って考えられることは入管庁での業務に活きています。
|
| ◇ 記憶に残っている業務 |
令和5年の入管法改正に携わったことです。送還忌避や収容の問題の解決を図った、内容が多岐にわたる改正であり、これほど大きな法改正を入庁1年目から経験できたことは貴重でした。様々な人がそれぞれの立場からの意見を持っている中で、政府の立場としてどのような政策を作るべきなのか、国民から理解を得るにはどうすればよいのかを考えさせられました。国民への広報という点では、自身が作成に携わった、現行法の課題を説明する資料がSNSで相当数閲覧されたことが印象深いです。
|
| ◇ 日々の仕事 |
現職では、主に、令和6年に成立した二つの改正法(育成就労制度の創設、マイナンバーカードと在留カードの一体化)の施行に向けて、政省令案の精査や内閣法制局審査への対応、関係省庁や入管庁内の関係課室との調整を行っています。改正された法律がその趣旨に則って実際の社会で適切に使われるためには、法律が成立した後のプロセスも重要になります。具体的な運用場面に想像力を働かせ、円滑な運用につながるよう努めています。
|
| ◇ 仕事の面白み、やり甲斐 |
どのような外国人をどのような条件でどの程度受け入れるのかは、この国のかたちをどうするのかに直結する問いです。また、外国人の出入国在留管理は、雇用、経済成長、治安など様々な分野に関係します。担当する業務によって、直接的か間接的かの違いはありますが、入管庁では、裾野が広く、チャレンジングな問いに真正面から取り組むことができるという点でやりがいを感じています。
|
| ◇ テレワークの経験 |
前の職場では、オンラインでの研修受講やまとまった作業を行いたいときにテレワークを実施しました。テレワークでは、作業の中断が少なくなるため、一人で集中できる点がメリットだと感じています。一方で、対面での議論を通じて方向性を見出すような業務には不向きなので、行っている業務の性質によって上手く使い分けできると良いと思っています。
|
| ◇ ある1日のスケジュール |
7:30 起床、朝食、子どもと触れ合い
9:30 登庁
10:00 他課室からの照会対応
12:00 昼食
14:00 政令案作成について他課室と打合せ
17:00 政令案の法制局審査資料をチェック
19:00 退庁
21:00 夕食、子どもの就寝後に妻とスイーツタイム
|
| ◇ 執筆者と同じ試験の区分を受験しようとする人に向けてのメッセージ |
幅広い分野を勉強することになるので、ぜひ試験勉強を通じて学びを得てください!
|
| |
|
法 律
|
| |
内閣府
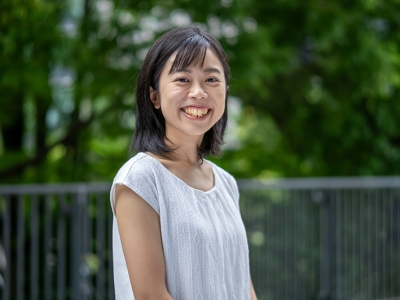 |
大臣官房 公文書管理課・専門職
2015年 内閣府採用 男女共同参画局総務課総括係
2016年 大臣官房人事課
2017年 内閣官房内閣広報室
2019年 内閣官房行政改革推進本部事務局主査
2022年 育児休業・留学
2025年 現職
歴史の重要性を理解しながら、変革に挑む |
| |
| ◇ 採用年・採用試験(区分)院卒・大卒 |
2015年採用 総合職試験(法律) 大卒
|
| ◇ 学生時代の専攻と現在の仕事との関係 |
大学時代は法学部に所属し、判例解釈を行う行政法ゼミに所属していまし た。そこで、初見で判決文を読んだときの印象と、経緯(時代背景や先行訴訟等)を調べてからもう一度読んだときの印象が、自分の中で異なっている場合があるということに驚き、興味深いなと思ったことを覚えています。業務でも、言葉の選び方ひとつにも理由があると考え、それを調べる作業が必要ですが、その重要性を最初に学んだのは法学部時代のあの体験だと思っています。
|
| ◇ 記憶に残っている業務 |
内閣広報室において、首相官邸のSNSの運用を行いました。災害時においては、信頼できるリソースからの迅速な情報発信が重要ですので、情報が少ないながらもかき集め、それをわかりやすい表現に直し、SNSで発信するという一連の作業を行いました。混乱も大きい災害対応の最中で、もっと速く正確にわかりやすく、と唱えながら、部屋の中を(文字通り)走り回りました。体も頭もフル回転で大変でしたが、それだけに記憶に残っています。
|
| ◇ 日々の仕事 |
現在所属する公文書管理課においては、公文書管理法等の各規程の運用と見直しを行っています。例えば、政府では行政文書の作成から保存、廃棄・移管までを一貫して電子的に管理できる、新しいシステムを開発中ですが、その導入のため、紙媒体の管理を正本・原本とし、職員の手作業で管理していた時代の規程を改正する必要があります。これについて、室内で議論を重ねて改正案を作成し、その上で関係省庁とも喧々諤々の議論を行っています。
|
| ◇ 仕事の面白み、やり甲斐 |
行政機関には過去作成された文書が数多く存在するため、それらを保存・整理することが必要です。また、現在の業務についても、政策の意思決定の跡づけや検証のために、文書をきちんと作成することが必要です。こういった過去や現在の文書、つまりこの国の歴史を未来に引き継ぐためのルール整備をするのが公文書管理課の業務だと考えると、未来に対する責任が重大であり、それがやりがいにつながっていると感じます。
|
| ◇ テレワークの経験 |
子どもの急な発熱の際、病児保育の空きがなかったため、テレワークをした経験があります。職場のパソコンを持って帰れば、家でも職場と同じように業務ができるので、とても便利でした。また、同僚も現在の職場の状況についてチャットで教えてくれたり、急遽打合せをオンラインに変えてくれたりしたので、それも非常に助かりました。また、子どもは慣れた環境で十分に休むことができ、早めに回復することができました。
|
| ◇ ある1日のスケジュール |
9:30 登庁、メールチェック
10:30 他省との打ち合わせ(次回の有識者会議の準備)
12:00 昼食(サークル活動の一環でランチミーティング)
13:30 幹部レク(次回の有識者会議の内容の打合せ)
14:00 他省との調整作業(公開予定文書の記載の調整)
17:45 退庁
19:15 帰宅、子どもと夕食
23:0
|
| ◇ 執筆者と同じ試験の区分を受験しようとする人に向けてのメッセージ |
法の固持では飽き足らないなら、国家公務員がおすすめです。
|
| |
|
経 済
|
| |
人事院
 |
人事院 給与局 給与第一課 労働経済班 主査
2021年 人事院採用 人材局首席試験専門官付
2023年 人事院公平審査局調整課制度班法規係
2024年 人事院給与局給与第一課労働経済班
2025年 現職
国を支える、国家公務員を支える |
| |
| ◇ 採用年・採用試験(区分)院卒・大卒 |
2021年採用 総合職試験(経済) 大卒
|
| ◇ 学生時代の専攻と現在の仕事との関係 |
学生時代はロシア文学を専攻しつつ、経済学も勉強していました。一見現在の仕事とは関係がなさそうですが、それぞれの学問で培った論理的思考力や数学的思考力等の基本的な能力は、働く上での基礎体力として現在でも活きています。
また、研修や業務説明会等も充実しているので、学生時代の専攻にかかわらず、働きながら必要に応じて勉強できる環境も整っていると感じています。
|
| ◇ 記憶に残っている業務 |
人事院では、国家公務員の給与水準を民間企業従業員の給与水準に合わせることを基本とする人事院勧告を行っており、その内容を反映した法改正がなされることによって、国家公務員の給与等が改定されます。
令和6年人事院勧告では、初任給の大幅な引上げや各種手当の整備等を打ち出し、例年の倍以上の分量となりました。そのような分量の勧告を出し、法案の審議にも携わり、国家公務員の処遇改善に貢献できたことは、大きな達成感とともに記憶に残っています。
|
| ◇ 日々の仕事 |
国家公務員の給与水準は民間給与との均衡を図った上で決定されており、人事院では、毎年国家公務員と民間の給与について調査を実施して人事院勧告を行っています。
私の所属する給与第一課では人事院勧告の取りまとめを行っており、人事院勧告で使用する各種数値の算定、院内外の関係部署との調整、人事院勧告に関する国会対応(答弁の作成、幹部への説明等)や外部からの照会への対応が主な業務です。
|
| ◇ 仕事の面白み、やり甲斐 |
私が国家公務員として経験した日々の業務は、関係者との幾度にも渡る調整等、地道な作業の積み重ねが多くを占めていました。大変だと思うこともありますが、そのような作業の積み重ねが、政策というかたちをもって少しずつ未来を変えていきます。そして、人事院は人事行政を司る役所であるため、私自身も国家公務員の1人としてその影響を受けることとなります。
地道かつ丁寧に積み上げた作業が、大きなスケールとなって未来を変えていくダイナミズムを感じるとき、国家公務員の仕事の面白みを実感します。
|
| ◇ テレワークの経験 |
データの精査や説明会原稿の作成等、1人で黙々と行う業務はテレワークの方が集中できると感じています。一方で、上司や同僚と連携しながらスピード感をもって取り組む必要のある業務は出勤した方が処理しやすいため、業務の性質に応じて出勤とテレワークを組み合わせることで、効率よく働くよう心がけています。
また、通勤時間がないため、睡眠時間や終業後の自由時間を長く確保できるのも、テレワークのメリットです。
|
| ◇ ある1日のスケジュール |
9:30 登庁後、メールとその日のスケジュールをチェック
10:00 地方自治体からの照会に対応
12:00 昼食(お弁当派です。食べ終わったら昼寝をします。)
14:00 担当施策の次年度の方向性について、幹部に説明
16:00 幹部からの指摘をメモにまとめ、上司と対応を検討
18:00 翌日の会議資料の最終確認
19:00 退庁(その日の夕食のメニューを考えながら帰路につきます。最近はキーマカレーにはまっています。)
|
| ◇ 執筆者と同じ試験の区分を受験しようとする人に向けてのメッセージ |
専門分野に縛られず、様々な場面で活躍できる職場です。応援しています!
|
| |
|
教 養
|
| |
総務省
 |
総務省 情報流通行政局 地域通信振興課 課長補佐
2018年 総務省採用 行政管理局企画調整課
2019年 内閣官房副長官補室(内政総括・財務担当)
2021年 内閣官房内閣人事局主査(働き方改革推進・業務見直し担当)
2023年 内閣官房内閣人事局総括係長
2024年 現職
困難を乗り越える、使命感と結束 |
| |
| ◇ 採用年・採用試験(区分)院卒・大卒 |
2018年採用 総合職試験(教養) 大卒
|
| ◇ 学生時代の専攻と現在の仕事との関係 |
学生時代は法学部で法律と政治学を学びました。法律の具体的な知識が直接業務に紐づくとは限りませんが、日々の業務において、法令を読み解くことで関連政策を把握する必要がある場面は多く、学生時代から法律に親しんでいたことは役に立っています。また、未知なる事象に対する学問的な探究方法は、現在の業務にも共通する点があると感じています。
|
| ◇ 記憶に残っている業務 |
新型コロナウイルス感染症が発生した直後、予備費を活用した緊急対応策を2度にわたり取りまとめるとともに、特措法の改正、政府・与野党間の政策協議の場の開催など、あらゆる施策に関わる中で、緊急時における国の責務の大きさを痛感しました。当時、上司の方々と前例のない業務にどう対応すべきか、毎日頭を悩ませ議論を重ねながら取り組んだ日々は、今でも鮮明に記憶に残っています。
|
| ◇ 日々の仕事 |
現在は、避難指示情報等の災害情報を収集し、メディアを通じて住民へ迅速かつ効率的に伝達するシステムであるLアラートの企画立案業務に携わっています。近年の災害対策における状況変化を踏まえ、将来的にLアラートとして伝達すべき情報を拡充するため、メディア関係者や情報発信元である自治体の方々へヒアリングを実施し、将来的なシステム更改に向けた取り組みを進めています。
|
| ◇ 仕事の面白み、やり甲斐 |
解決すべき困難な課題が多岐にわたる中、政策立案を行う場合、単なる思い付きではなく、実務レベルでしっかりと機能する政策であることが重要です。そのため、細部に至る丁寧な検討は地道な作業ではありますが、政策を完遂した時の達成感は格別です。また、同じ志を持つ素晴らしい同僚と協働する時間は、振り返れば充実した日々でした。
|
| ◇ テレワークの経験 |
コロナ禍以降も、午前はテレワーク、午後は出勤という形で通勤ラッシュを避けた勤務形態を多く選択しています。もちろん、急な出勤が必要となる業務も発生するため、日々、部下と適切な業務分担などを調整していますが、業務内容や自身の状況に合わせて柔軟な勤務形態を選択でき、自由な働き方を実現できています。
|
| ◇ フレックス勤務経験 |
一般的に職員の勤務開始時刻は9時30分ですが、私は朝の時間を有効活用したいため、9時始業としています。テレワークと同様に勤務時間にもある程度の裁量があるため、柔軟な働き方を実現できていると感じています。
|
| ◇ ある1日のスケジュール |
9:00 登庁
10:00 調査研究事業について、委託事業者と打ち合わせ
12:00 昼食(自宅から弁当を持参)
14:00 事業の今後の方針について局内幹部と相談
16:00 他省からの政府計画に関する案文協議が接到。上司と対応について協議
17:30 次週の他組織との打ち合わせ資料について、部下から相談を受ける
19:30 退庁
20:30 家族と夕食
|
| ◇ 執筆者と同じ試験の区分を受験しようとする人に向けてのメッセージ |
専攻にとらわれずに、様々な方の受験をお待ちしてます。
|
|
| |
| |
外務省
 |
在スペイン日本国大使館 二等書記官
2020年 外務省に入省。国際協力局地球規模課題総括課
2022年 在スペイン日本国大使館 外交官補
2022年~2024年 在外研修(スペイン語)
2024年~現在 在スペイン日本国大使館 二等書記官
世界を舞台に楽しみながら日々精進 |
| |
| ◇ 採用年・採用試験(区分)院卒・大卒 |
2020年採用 総合職試験(教養) 大卒
|
| ◇ 学生時代の専攻と現在の仕事との関係 |
大学では法学部に所属し、国際法や行政法、政治学などを学びました。わたしが大学に入学した頃は、教養区分は採用人数がまだ少なかったため、採用人数の多い法律区分での受験を見据えて法学部を選択しました。特に国際法は外交官の共通言語ともいえる知識です。現在、日本とスペインは防衛装備品・技術移転協定締結に向けた交渉を行っており、わたしも主に通訳として関わる機会があります。その際に、国際条約の批准手続きや適用範囲等、大学の授業で学んだ知識が役立っています。
|
| ◇ 記憶に残っている業務 |
選び難いのですが、先日のG7カナナスキスサミットでは非常に貴重な体験をさせていただきました。今回は行事班というポジションでサミットの会場に入り、主に日カナダと日豪首脳会談の調整を担当しました。目まぐるしく変化する状況の中で、相手国及び日本側関係者との調整を一手に担うプレッシャーは大きかったですが、各公館から集まった素晴らしいチームメンバーと助け合い、無事に首脳会談が終わった際の達成感と自分が日本外交に貢献できているという実感は得難い経験でした。
|
| ◇ 日々の仕事 |
わたしは政務・総務・儀典担当として、政治関連の案件に対応する他、館内の横断的案件の総括を担当しています。新聞やニュースだけではなく、与野党の政治家や有識者、スペイン外務省や当地外交団の方々と会い、情報収集を行うことが日々のタスクです。また、大使の地方出張に同行することも多く、州首相や市長との会談における大使の発言内容を考え、実際の現場にも同席しています。前述のカナナスキスサミットの他、ペルーAPECや大阪・関西万博のスペインナショナルデー等、国外出張の機会も多いです。
|
| ◇ 仕事の面白み、やり甲斐 |
先輩方から「外交の世界で重要なのは人格」という趣旨の言葉をよく伺っていましたが、数年前から在外勤務を開始し、その意味を実感を以て理解することができました。わたしたちは国家公務員ですので、公の場で発言する内容は制約を受けることもあります。ですが、選ぶ言葉のニュアンス、話すトーンや表情には外交官ひとりひとりの個性が表れますし、その人のそれまでの人生に裏打ちされているものです。一個人としての成長や経験が仕事に繋がる点は外交官という職業の魅力のひとつだと思います。
|
| ◇ テレワークの経験 |
本省にいた2020年~2022年はコロナ禍だったので、隔日でテレワークをしていました。現在働いている大使館においては、1週間に1回のテレワークが申請可能であり、複数の館員が制度を利用しています。
テレワークの場合、同僚とのやりとりはテキストベースになるため、いつもより丁寧に説明する等の配慮が必要になりますが、通勤時間が削られることで家事等に取り組む時間を確保できるのが利点だと思います。また、ひとりでじっくり内容を考えたい案件に取り組む際にも便利な制度です。
|
| ◇ フレックス勤務経験 |
在スペイン大では多くの職員がフレックス制度を活用しています。わたしも金曜日の終業後にスペイン語の授業があるため、金曜日は30分ほど早く退勤し、代わりに木曜日は30分長く働くようにしています。他にも、忙しい週は退勤時間を少し遅らせ、代わりに次の週は早く帰る等、柔軟に働けており、終業後に友人との時間や趣味の時間を確保することができています。
【フレックス勤務のある一日のスケジュール】
月(9:00~17:45) 早めに帰宅し、趣味の時間(ゲームなど)
火(9:00~17:45) 定時で勤務終了し、同僚と軽く食事
水(9:00~17:45) 翌週の案件に備え、資料作成や予習。1時間弱の残業
木(9:00~18:15) 今週中に終わらせたい仕事に集中。19時前に帰宅し家事などする
金(9:00~17:15) 早めに帰宅し、オンラインでスペイン語レッスン
|
| ◇ ある1日のスケジュール |
9:00 出勤。本省からのメールやチャット内容を確認。
11:00 スペイン外務省とのアポ
13:15 昼食(お弁当)後、同僚とコーヒーを買いに行く。午後 アポの記録を作成したり、数日後の案件のための資料作成や予習。
17:45 退勤。大使館近くの店で、同僚と食事
21:00 帰宅
|
| ◇ 執筆者と同じ試験の区分を受験しようとする人に向けてのメッセージ |
いろいろな人との対話経験を積むことが二次試験対策に繋がると思います。
|
| |
|
人間科学
|
| |
法務省
 |
法務省 保護局 更生保護振興課 研修企画 係長
2014年 法務省採用 福島保護観察所福島自立更生促進センター
2017年 法務省法務総合研究所研究部
2019年 法務省保護局総務課
2021年 法務省出入国在留管理庁政策課外国人施策推進室係長
2023年 法務省保護局観察課係長
2024年 法務省保護局総務課係長
2025年 現職
犯罪や非行のない安全で安心な社会を目指して |
| |
| ◇ 採用年・採用試験(区分)院卒・大卒 |
2014年採用 総合職試験(人間科学) 大卒
|
| ◇ 学生時代の専攻と現在の仕事との関係 |
学生時代に専攻した社会福祉学では、支援を必要とする人が抱える課題について、個人の視点だけではなく、社会的・環境的な要因や個人と環境との相互作用の視点から捉えることの重要性を学びました。現在携わっている更生保護の分野においても、罪を犯した人が地域社会で立ち直っていくために、非行や犯罪の背景や本人の置かれた環境に目を向ける必要があり、学生時代に身につけた上記の視点が、保護観察官としての勤務や本省での企画立案の業務等に活かされています。
|
| ◇ 記憶に残っている業務 |
初任地で保護観察官として勤務した経験が強く印象に残っています。目の前にいる少年が再び過ちを犯さないために、保護司の方と共に少年と向き合い、真剣に話し合った光景が今でも鮮明に思い出されます。この経験がその後の職業人生の原点になっているように思います。また、現場勤務で得た知見や経験も活かしながら、本省等で専門的処遇プログラムの改訂や立ち直りに関する調査研究に携わることができたことも貴重な経験でした。
|
| ◇ 日々の仕事 |
現在の部署では、「社会を明るくする運動」を担当しています。同運動は、国民の皆様に犯罪や非行の防止と犯罪や非行からの立ち直りについて理解を深めていただき、それぞれの立場で御協力いただくことで、犯罪や非行のない安全で安心な地域社会を築くことを目的とした運動です。この運動の広報啓発のために、日々、多種多様な協力企業・団体等と協議しながら、イベントの企画内容の検討や広報資材の作成等の業務を行っています。
|
| ◇ 仕事の面白み、やり甲斐 |
現場での実践と本省における施策の企画立案の両方に関われることにやり甲斐を感じています。それらの営みを支える調査研究に携わるチャンスがあることも魅力の一つです。
また、様々な関係者とコミュニケーションをとり、意見を調整しながら、合意形成を図りつつ、物事を進めていくことが国家公務員として働くことの醍醐味だと思います。色々な人との出会いの中で、自分にはない気づきやアイデアを得ることができる点にも面白さを感じています。
|
| ◇ テレワークの経験 |
テレワークでは、イベントの企画内容の検討や照会案件への対応等の業務を行っています。テレワークのメリットとして、自分一人の環境で働けるため業務に集中しやすい点のほか、通勤時間がない分、子育てや家事の時間を確保しやすい点が挙げられます(テレワークの日は、子どもの保育園への送迎を担当したり、昼休みの時間に家事を進めたりしています)。ワークライフバランスを確保しながら、柔軟に働くことができる点がテレワークの魅力だと感じています。
|
| ◇ ある1日のスケジュール |
9:30 (子どもを保育園に送り届けてから)登庁、メールチェック
10:00 書類作成・決裁等
12:00 昼食(天気の良い日は日比谷公園に出かけることもあります)
13:00 民間業者とイベントについての打合せ
15:00 イベントの企画書の作成
16:30 課内で今後の企画についての打合せ
18:15 退庁
19:15 家族と夕食、子どもとお風呂等
|
| ◇ 執筆者と同じ試験の区分を受験しようとする人に向けてのメッセージ |
専門性を生かし、磨きながら、社会に貢献できる仕事です。
|
| |
|
デジタル
|
|
|
経財産業省
 |
経済産業省 商務情報政策局 情報経済課 アーキテクチャ戦略企画室 係長
2023年 経済産業省採用 商務情報政策局情報経済課
2024年 現職
本質を突き詰めて、社会に大変革を起こす |
| |
| ◇ 採用年・採用試験(区分)院卒・大卒 |
2023年採用 総合職試験(デジタル) 院卒
|
| ◇ 学生時代の専攻と現在の仕事との関係 |
学生時代は建築学を専攻しており、建築におけるデジタル技術の利用という観点でVRやメタバースを研究していたのに加え、副専攻として科学技術政策を幅広く学んでいました。その中で、デジタル技術・産業の振興の必要性や課題、私たちの生活に与えるインパクトや求められるガバナンスなど幅広く学ぶことができ、政策立案や実行の際に、ステークホルダーの特定や巻き込み、合意形成に向けた調整をするうえで大きく活かされていると感じています。
|
| ◇ 記憶に残っている業務 |
デジタル時代の新たな社会インフラを整備するための「デジタルライフライン全国総合整備計画」の策定に事務局として関わったことです。計画の策定にあたっては、産業競争力や社会受容性、技術的な実現可能性、持続可能性など、様々な観点から議論する必要があり、多様な官民のステークホルダーとの連携・調整が必要でした。私は特に関係省庁との調整を担い、時には激しい交渉も経験しましたが、最終的に全省庁の合意を得るまでに至れたのは大変感慨深かったです。
|
| ◇ 日々の仕事 |
現職では、策定した計画の着実な実行に向けたフォローアップや検討会の運営、予算事業の企画・執行、制度の内容や運用の役割分担などに関する関係省庁との調整、骨太の方針等の政府の重要文書への打ち込みなど、様々な業務を担っています。デスクワークが中心にはなりますが、取組や実証の視察、展示会やイベントなどでの広報活動、検討会の運営など、デスクを離れて仕事をする機会もあり、日々新鮮な気分で仕事をしています。
|
| ◇ 仕事の面白み、やり甲斐 |
現在取り組んでいる領域は関係者が膨大かつ多様で、それぞれが異なる関心や問題意識、利害を持っています。そんな複雑な状況であっても事を成すには、みんなが共通で納得できるように本質を突き詰める必要があります。これほどまでに賛同を得て動いてもらうのは難しいものかと思った経験は何度もありますが、それを乗り越え、関係者が一丸となった時は、本当に大きくことが動きます。鳥肌が立つほどのダイナミズムや人の力強さを間近で体験できるのはこの仕事の醍醐味だと思います。
|
| ◇ テレワークの経験 |
私自身は、執務室の方が仕事がしやすいためテレワークを積極的には活用しておりませんが、同じ課室にはご家庭の事情や集中作業のためといった理由で積極的にテレワークを活用している職員も多くいます。業務もテレワークの職員がいる前提で組まれており、会議は原則オンラインでも入れるように設定したり、限られた職員での口頭のコミュニケーションではなく、みんなが見れるチャット上でのコミュニケーションを中心にしたり等、様々な工夫をしています。
|
| ◇ ある1日のスケジュール |
8:30 登庁、メールの確認
10:00 室内の朝会で業務の進捗管理や情報共有
11:00 事業者との意見交換
12:00 昼食
13:00 検討会の開催
16:00 委託事業受託企業との定例
17:00 予算関連資料の作成
19:00 メールの確認
20:00 退庁してジムへ
|
| ◇ 執筆者と同じ試験の区分を受験しようとする人に向けてのメッセージ |
国は皆さんが思っている100倍はデジタル人材を求めています!ぜひ霞が関へ!
|
| |
|
工 学
|
| |
防衛省
 |
防衛装備庁 プロジェクト管理部 事業監理官(宇宙・地上装備担当)付専門官
2020年 防衛省採用 整備計画局情報通信課
2021年 防衛装備庁調達管理部調達企画課
2022年 防衛装備庁調達事業部艦船調達官付誘導武器室
2023年 防衛装備庁プロジェクト管理部事業計画官付企画室
2025年 現職
我が国の安心安全を"もの"から支える |
| |
| ◇ 採用年・採用試験(区分)院卒・大卒 |
2020年採用 総合職試験(工学) 院卒
|
| ◇ 学生時代の専攻と現在の仕事との関係 |
学生時代は情報工学を専攻しており、新しい計算機の設計に係る研究を行っていました。講義や研究内容が直接的に防衛省の業務に繋がることは多くはありませんが、ものづくりに関わる理解や経験、理系の知識は、装備品に係る技術的な議論や防衛産業関連企業とのやり取りなど、防衛装備品に纏わる多くの業務に役立っていると感じています。
|
| ◇ 記憶に残っている業務 |
1か月近くの期間、陸上自衛隊の大規模演習に参加したことです。自分が検討に加わり導入に至った装備品が実際のオペレーションの中でいかに活用されていくのかを、いち部隊員として見ることができました。また参加されていた米軍の方と意見交換等もできたことから、自身の業務のその先を知ることに繋がり、それ以降の仕事のやりがいに繋がっています。
|
| ◇ 日々の仕事 |
宇宙関連機材、特殊車両、レーダーのほか、被服といった需品などを含む多種多様な装備品に対し、必要な時に問題なく活用できるよう、装備品の構想から研究開発、量産、運用、廃棄といったライフサイクルを横断的に管理し取得などの最適化を行っていく取組を推進しています。規模や技術分野も様々であり、変化も早いことから幅広い知識を日々求められており、一日一進の毎日です。
|
| ◇ 仕事の面白み、やり甲斐 |
装備品を実際に使用する各自衛隊や製造する防衛関係企業、技術協力や移転で関係する外国政府等多くのステークホルダーとの調整を行いつつプロジェクトを良い方向に導いていく必要があります。難解な課題に直面することも多々ありますが、同僚や関係者と協力し課題を乗り越え成果を出せた際の嬉しさはひとしおです。
|
| ◇ テレワークの経験 |
資料作成や確認業務など集中して効率的に作業をしたい場合などにテレワークを行うことがあります。テレワークの日は、通勤時間を家事や自分の趣味といった業務以外の事に当てられるため、より充実した一日を送れています。
|
| ◇ ある1日のスケジュール |
9:30 登庁
10:00 他課室等との調整業務
11:30 企業の要請対応
12:00 昼食(同期とランチ)
13:00 装備移転に関する調整業務
15:00 省内で実施されたJAXAの講義を聴講
17:30 国会対応(資料作成)
20:00 退庁
21:00 帰宅(友人と通話しながら趣味に邁進)
|
| ◇ 執筆者と同じ試験の区分を受験しようとする人に向けてのメッセージ |
工学の知識は、日々進歩する科学技術の基礎となる知識です。
どんな分野でも勉強した知識は自分の強みに変えることができます。
|
| |
|
|
| |
警察庁
 |
警察庁 交通局 交通企画課 自動運転企画室 課長補佐
2018年4月 入庁
2019年6月 警察庁情報通信局通信施設課係長
2020年2月 警察庁長官官房企画課係長
2022年4月 警察庁サイバー警察局サイバー企画課係長
2022年8月 米・カーネギーメロン大学(留学)
2024年7月 現職
技術的知見を活かした活躍のフィールドの拡大
|
| ◇ 採用年・採用試験(区分)院卒・大卒 |
2018年採用 総合職試験(工学) 大卒
|
| ◇ 学生時代の専攻と現在の仕事との関係 |
学生時代は、情報工学を専攻しており、卒業研究ではマルチエージェントシミュレーションを用いて金融機関の倒産リスクを推定する研究を行っていました。現在は、自動運転の社会実装に関する業務に携わっており、金融市場とは直接関係はありませんが、所属した研究室で学んだ人工知能やセキュリティに関する基本的な知識・スキルは、自動運転の実装方法を理解し、安全性を含めた検討を行うために非常に役立っております。
|
| ◇ 記憶に残っている業務 |
警察庁に新組織として、サイバー警察局を設置した業務が印象に残っています。国境を越えて敢行されるサイバー犯罪が増加する中、国内外から迅速な対応が求められおり、早急に新組織を設置することが必要でした。そのため、新組織の設置に関するチームが編成され、有識者会議を開催した後に、提言をまとめてサイバー警察局を設置することができました。ゼロから組織を立ち上げることはなかなか経験できないことであり、やりがいを感じた業務経験になりました。
|
| ◇ 日々の仕事 |
現在は、交通企画課自動運転企画室において、協調型自動運転の実現に向けたプロジェクトに携わっております。具体的には、信号灯色の予定情報(何秒後に青信号に変化する、または、何秒後に赤信号に変化する)をどのように自動運転車に誤差なく提供できるかについて、関係機関とともに研究開発を行っております。
|
| ◇ 仕事の面白み、やり甲斐 |
社会的インパクトの大きい仕事に携われたり、時代の転換点に立ち会えることです。これまでも自分が携わった有識者会議や新組織の設置が大きく報道されるという経験をしました。また、現所属の自動運転でも、米国Waymoの自動運転タクシーが、日本で試験走行を開始するなど、完全無人のロボットタクシーが社会実装される未来が近いことが想像されます。科学技術により大きく社会が変わりつつある今こそ、技術系国家公務員は新しい社会を方向付ける当事者となり得る仕事だと感じています。
|
| ◇ テレワークの経験 |
前所属のサイバーセキュリティ対策の部署では、有識者会議の調整業務でテレワークを多く活用していました。一人で作業することが多い業務では、テレワークを活用することで効率も上がります。テレワークを実施した日は、通勤時間を削減できますので、1日の中で自分のために使える時間が増えることもメリットだと感じています。
|
| ◇ ある一日のスケジュール |
9:30 登庁、メールの確認
10:00 関係省庁からの意見照会対応
12:00 昼食
13:00 自動運転技術に関する幹部説明資料の作成
14:00 幹部へのレク
15:00 関係事業者との打ち合わせ
17:00 他課との自動運転に関する打ち合わせ
18:30 退庁
19:00 皇居ランでリフレッシュ
|
| ◇ 執筆者と同じ試験の区分を受験しようとする人に向けてのメッセージ |
研究活動との両立は大変だと思いますが、頑張ってください。
|
| |
|
数理科学・物理・地球科学
|
| |
厚生労働省
 |
(株)三菱総合研究所 DXコンサルティング本部 研究員
2021年 厚生労働省採用 年金局事業企画課調査室
2023年 厚生労働省年金局事業企画課システム室
2024年 現職
データで社会保障を最適化、持続可能な未来へ |
| |
| ◇ 採用年・採用試験(区分)院卒・大卒 |
2021年採用 総合職試験(数理科学・物理・地球科学) 大卒
|
| ◇ 学生時代の専攻と現在の仕事との関係 |
大学では情報科学を専攻し、プログラミングや数値計算を通じて、データに基づき物事を分析する力を養いました。この能力は、統計業務における複雑な社会課題に対する政策立案のためのデータ分析や、客観的な根拠に基づく効果検証を行う上で活かされています。統計以外の業務においても、高度なデータ処理や業務プロセスの効率化など、プログラミングスキルを実務に幅広く応用できていると感じます。
|
| ◇ 記憶に残っている業務 |
前職では、年金業務システムの刷新プロジェクトで予算要求から契約手続き、開発の調整・管理業務を担当しました。開発スケールは人や予算の面で通常では経験できないほど大きく、日々その責任の重さを感じながら業務に取り組んでいました。日本年金機構や多数の開発ベンダーといった関係者が多く、円滑な情報共有や合意形成を図ることには苦労しましたが、この経験を通じて、コミュニケーション能力や調整力が培われたと実感しています。
|
| ◇ 日々の仕事 |
主に民間企業に向けたDX戦略の策定から、その推進に係るコンサルティングを行っています。また、IT技術を活用した業務改革の支援も行っており、例えば、紙や対面で行っていた業務プロセスをデジタルに移行することで、業務の効率化を図ります。企業が抱えるこれらの課題は、官公庁での業務とも共通する点が多く、ここで培った知見は幅広い分野で活かせると考えています。
|
| ◇ 仕事の面白み、やり甲斐 |
業務内容が多岐にわたるため、それぞれの職員が持つ専門知識や技術を存分に発揮できる多様な活躍の場が用意されており、それがやりがいに繋がっています。特に根拠に基づく政策立案(EBPM)が重視される近年、どの分野でもデータ分析などの数理的スキルが必要とされていることを実感しています。また、地方自治体や民間企業などへ出向の機会があることは、そこで得た多様な視点を行政の現場に活かせるだけでなく、自身の成長にとっても非常に価値があり、恵まれた環境だと感じています。
|
| ◇ テレワークの経験 |
現職では勤務日の半分をテレワークとしています。自宅が都心から少し離れているため、通勤時間を大幅に短縮でき、その時間を私生活の充実や十分な睡眠の確保に充てられることで、日々の生活にゆとりが生まれていると感じます。また、新しいツールの作成や詳細な数値分析といった、集中力を要する業務に取り組む際には、自宅の落ち着いた環境が作業効率の向上にも繋がっていると実感しており、効果的にテレワークを活用しています。
|
| ◇ フレックス勤務経験 |
入省して間もない頃から、学位取得のためにフレックス制度を活用していました。この制度がなければ、仕事と学業を両立させることは現実的に難しく、学位取得に挑戦する機会も持てなかったと思います。フレックス精度は、育児や介護といった目的での利用が多いですが、興味のある分野の研究活動などは、自分自身のスキルアップにもつながるため、学問分野での活用も有効だと考えています。
【フレックス勤務のある一日のスケジュール】
月(9:00~17:15) 翌日の出勤が朝早いため、早めに帰宅
火(8:00~15:15) 朝の当番業務をこなし、退庁後は講義に出席
水(9:00~18:45) 月・火にたまった業務をこなす
木(9:00~18:15) 昼間に打合せが立て込み、20:00まで残務整理
金(9:00~18:15) 今日は定時退庁日、終業後はビールで乾杯
|
| ◇ ある1日のスケジュール |
9:30 出社、打合せ準備
10:30 顧客先との打合せ
12:00 プロジェクトメンバーと昼食(打合せの振り返り)
13:00 打合せ議事録作成
14:00 社内での進捗報告会議
15:00 先輩職員や同僚にプロジェクトの進め方相談
15:30 打合せ資料作成
17:30 先輩職員に1週間の状況報告
18:00 退社
19:00 趣味のホットヨガでリフレッシュ
|
| ◇ 執筆者と同じ試験の区分を受験しようとする人に向けてのメッセージ |
皆さんの探究心と分析力を活かして、豊かな社会を実現しましょう!
|
| |
|
化学・生物・薬学
|
| |
文部科学省
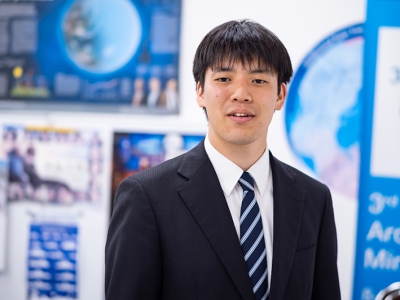 |
文部科学省 研究開発局 海洋地球課 調整・機構係
※5.1付で高等教育局医学教育課企画係(併)医師養成係に異動
2023年 文部科学省採用 初等中等教育局教育課程課企画調査係
2024年 現職
国の未来を現場と共に創る |
| |
| ◇ 採用年・採用試験(区分)院卒・大卒 |
2023年採用 総合職試験(化学・生物・薬学) 院卒
|
| ◇ 学生時代の専攻と現在の仕事との関係 |
学時代は化学を専攻し、金属有機構造体の合成・活用の研究に関わっており、専攻や研究分野が現在の業務に直接関係しているわけではありません。しかし、学生時代の学会等に向けて専門外の人にも理解してもらえるように資料を作成した経験や、幅広い分野の論文から知見を得て自分の研究の方向性を決めた経験は、所管分野の研究開発に関する次年度の予算要求や、国として定める戦略目標の検討に関する業務に役立っています。
|
| ◇ 記憶に残っている業務 |
当課で予算を措置している国立研究開発法人 海洋研究開発機構(JAMSTEC)の北極域研究船「みらいⅡ」が2025年3月に命名・進水式を迎えました。文部科学副大臣や国会議員の方々の対応に携わり、その際に国会議員、ひいては国民の応援・理解があってこそ、各政策を進められるということを実感しました。国費を使用していることもあり、その視点は忘れずに今後の業務にも取り組もうと思います。
|
| ◇ 日々の仕事 |
海洋・極域分野の研究開発に関する予算に係る業務や、国会対応業務、各種計画のフォローアップ調査等の照会業務を担当しています。予算要求については係長以上がメインで検討することが多いですが、公表資料の調整等については、所管法人であるJAMSTECや事業担当係と連携しながら対応しています。また、JAMSTECや国立極地研究所のイベント広報にも関わっており、幅広い層の方々に興味を持ってもらえるよう、メールマガジンの文をインターンの学生と協力しながら作成しています。
|
| ◇ 仕事の面白み、やり甲斐 |
どうしたら今後日本がより良い国になるのか、教育現場や研究現場の第一線で活躍されている方々と一緒に検討し実践していけることが、この仕事の大きな魅力であると考えています。教育や研究は打ち出した政策がすぐに結果に結びつくことは必ずしも多くありませんが、政策が届く現場を想像し、少しでも未来を良くするために様々な立場の方々と協力し、様々な手段を活用しながら政策を推進することに面白さを感じています。
|
| ◇ テレワークの経験 |
国会が閉会している間など、他律的な業務が比較的少ない時期は積極的(週1~2回)にテレワークするようにしています。業務はメールやチャットで進めることが多く、上司に業務について相談するときもメールやチャット、ビデオ通話を使用することが多いので、テレワークでも業務に支障はあまりありません。
また、文部科学省ではノートパソコンの他に公用携帯が貸与されるため、出勤しているときと同じ感覚で手軽に電話で相談することも可能です。
テレワークにより通勤時間の分、睡眠や趣味に充てられるので、より効率的に働けていると感じています。
|
| ◇ フレックス勤務経験 |
夜に用事があり、定時より前に帰りたい日や、資料作成など人があまりいない時間帯に集中して取り組みたい業務があるときは朝に前倒しして勤務しています。
省内では男女問わず育児に参加している職員を中心にフレックス勤務にしている人が多く、働きやすい職場づくりが進んでいるように思います。
【フレックス勤務のある一日のスケジュール】
月(8:30~19:00) 水曜日の会議に向けて早めに登庁し作業
火(9:30~18:15) 会議に向けた調整が無事完了、定時帰宅
水(9:30~19:00) 国会対応が発生したので残業
木(11:00~18:15) 市役所に行く用事があったので遅めに登庁
金 計画年休(係内で全員が月1回休めるよう調整しています)
|
| ◇ ある一日のスケジュール |
7:30 ジムで軽く運動して
9:30 登庁
10:00 JAMSTECと予算に関する打合せ、終了後概要メモ作成
12:00 この日は弁当持参して見晴らしのいい省内のスペースで昼食
13:30 課内で国会対応に関する打合せ
14:00 省内の若手政策検討チームの活動(有識者との打ち合わせ)に参加
16:00 事業担当係に作成を依頼していた翌日の打合せ資料の確認・調整
18:30 退庁
19:00 大学の同期とバッティングセンターへ
|
| ◇ 執筆者と同じ試験の区分を受験しようとする人に向けてのメッセージ |
研究に携わった際に得た能力は必ず活かせます。
応援しています。
|
| |
| |
特許庁
 |
特許庁 審査第三部環境化学 審査官補
2023年 特許庁採用 審査第三部 環境化学 審査官補
最先端技術を支え、産業の発展に寄与する |
| |
| ◇ 採用年・採用試験(区分)院卒・大卒 |
2023年採用 総合職試験(化学・生物・薬学) 大卒
|
| ◇ 学生時代の専攻と現在の仕事との関係 |
学生時代は、環境応用化学を専攻し、金触媒を扱う研究室に所属していました。現在は環境化学の担当部署に所属し、審査官補として、指導審査官の指導の下、水処理、金属精錬、触媒などの特許審査を担当しています。学生時代に培った理系の基礎知識、実験や論文を熟読した経験などが、日々の業務における出願書類や先行技術の理解、拒絶理由通知書などの起案に活かされています。
|
| ◇ 記憶に残っている業務 |
出願人との対面での面接審査です。通常、出願人とのやり取りは書面を通じて行われますが、書面では伝わりにくい発明の詳細や従来技術との比較、さらにはその技術分野における一般常識などについて、直接説明をしてもらう機会があります。その機会を通じて、研究に対する熱意や特許出願への思いを肌で感じ、特許審査という仕事の重みを改めて実感しました。この経験を通じて、出願人のニーズに応えられる一人前の審査官を目指していきたいと考えています。
|
| ◇ 日々の仕事 |
特許審査業務では、出願書類を精読し、発明のポイントを把握した上で、検索システムを用いて先行技術調査を行います。その後、先行技術調査で発見した先行技術文献と本願発明を対比して、特許性の有無を判断します。また、特許審査業務の他、関連法令の研修、外部講師による技術研修、工場・研究所見学、展示会の視察の機会などがあり、これらの機会を通じて、審査業務に必要な専門知識を深め、より質の高い審査を目指しています。
|
| ◇ 仕事の面白み、やり甲斐 |
特許審査官の仕事の特徴は、最先端技術に日々触れられることです。新しい技術が次々と登場し、その進化に柔軟に対応することが求められます。日々新たな知識を習得し続けることは大変ではありますが、審査業務を通じて、技術や産業の発展に寄与できる点に大きなやりがいを感じています。発明者のアイデアを理解し、社会に新たな価値を提供する手助けができることは、非常に魅力的です。
|
| ◇ テレワークの経験 |
私は週に約1回、テレワークを活用しています。テレワーク用の審査支援システムを利用し、自宅で審査業務を行っています。検索システムを用いて先行技術調査を行い、オンラインで指導審査官と協議するなど、整備されたオンライン業務環境により、登庁時と変わらずスムーズに審査を進めることが可能です。通勤時間がなくなるため、少し手の込んだ夕食を作ったり、自己研鑽に時間を充てられるため、非常に便利です。
【フレックス勤務のある一日のスケジュール】
月( 8:00~16:45) 登庁。特許審査。20:00退庁。
火(10:00~18:45) 登庁。翌日のテレワーク時に、特許審査する案件の下準備を行う。20:00退庁。
水( 8:00~16:45) テレワーク。拒絶理由通知書を起案。
木( 8:00~17:45) 登庁。前日のテレワークで作成した書類を提出。
金( 7:30~15:15) テレワーク。勤務終了後は残業せずに趣味の映画鑑賞へ。
|
| ◇ ある一日のスケジュール |
8:00 登庁、発明内容の理解
9:30 出願人への電話対応(補正案・意見書案の検討結果を伝える)
10:00 先行技術調査
12:00 昼食(同期とランチ)
13:00 午前中に引き続き先行技術調査
16:00 指導審査官と担当案件の協議
17:00 拒絶理由通知書の起案
18:30 退庁
(退庁後は、夕食作りをしたり同僚とテニスをしたりします。)
|
| ◇ 執筆者と同じ試験の区分を受験しようとする人に向けてのメッセージ |
専門知識や経験を国の将来に役立てていきませんか?
|
| |
|
| |
農業科学・水産
|
| |
環境省
 |
| 環境省 大臣官房 環境保健部 化学物質安全課・化学物質情報第一係長
2020年 環境省採用 環境省大臣官房環境保健部環境安全課(現化学物質安全課)
2022年 関東地方環境事務所小笠原自然保護官事務所 自然保護官
2024年 現職
3つの世界的危機に、国際・地域の両方の視点をもって取り組む |
| |
| ◇ 採用年・採用試験(区分)院卒・大卒 |
2020年採用 総合職試験(農業科学・水産) 院卒
|
| ◇ 学生時代の専攻と現在の仕事との関係 |
学生時代は生物・生態学や農業・環境経済学を学んでいましたが、現在の仕事と直接的ではないものの、化学物質管理も生物多様性分野や金融(管理努力の見える化・価値評価)など他分野との相互連携などを検討することが求められてきていることから、化学物質管理側だけではない視野を持って業務に取り組むことができていると考えています。
|
| ◇ 記憶に残っている業務 |
化学部室安全課に係長として着任し、世界的危機の一つである「汚染」の防止のための各国の化学物質管理制度に関する国際会議について、2024年11月に会合出席のため初めて海外に出張しました。国連の会議場で日本の取り組みを(もちろん英語で)発表したときには、学会も含めて英語のみでの発表と質疑が初めてだったことから非常に緊張しましたが、同様の化学物質管理制度をもつ他国の担当者と意見を交わすこともでき、交流を深めることができたのは印象に残っています。
|
| ◇ 日々の仕事 |
法律に基づく化学物質管理制度について、事業者や地方公共団体からの質問への対応や運用面での改善、また制度の課題に対する対応策の検討(調査や有識者へのヒアリング等を踏まえた対応策の検討、研究機関との連携による具体的な対応策の推進、関係する課室・他の省庁との調整など)に取り組みつつ、国際会議での情報収集や日本の情報発信、化学物質管理制度や化学物質そのものに関する普及啓発など、多岐にわたる業務を行っています。
|
| ◇ 仕事の面白み、やり甲斐 |
よかれ悪しかれ関わる方が多い仕事であり、自分の経験だけでは知り得ないことを省の先輩方だけでなく様々な主体からの出向者や関わる事業者さん、専門家の先生や他省庁の方々から学びながら、時には正反対の意見をぶつけたりしてよりよい施策を考えていく、というのは、農学・水産系の学部出身者が就く職種ではなかなかない仕事なので、好奇心旺盛な自分にとっては魅力的な環境です。
|
| ◇ テレワークの経験 |
午前のみテレワーク、などを組み合わせて週1日程度のテレワークをしています。とりわけ、早朝や夜に他国の方とのWEB打合せなどがある場合には通勤時間を短縮できたり、定時に退庁して帰宅してから対応するなど時差出勤と組み合わせた柔軟な対応が可能なため、有効に活用しています。新型コロナの流行以降、全面オンラインの会議が続く日もあり、そうしたときには周囲を気にせず自宅の静かな環境で会議に参加できます。
|
| ◇ ある一日のスケジュール |
9:30 登庁:メールチェック、打合せ資料作成など
11:00 化学物資管理関係のシステムについて事業者と打合せ(オンライン)
12:00 昼食
13:30 他課室からの照会事項にかかる打合せ
14:00 月末の国際会議のプレゼン資料作成
16:00 補佐と法制度見直し業務について打合せ
18:15 打合せ内容をメモ化。メール対応等
19:30 退庁(移動)・夕飯休憩
21:00 自宅にて他国の担当者とオンライン打合せ
22:00 退勤(テレワーク終了)
22:30 友人と夏季休暇の旅行についてオンラインで相談♪
|
| ◇ 執筆者と同じ試験の区分を受験しようとする人に向けてのメッセージ |
行政の施策は科学的な知見にも基づいていることから、活躍できる場面がたくさんあるはずです!
|
| |
|
農業農村工学
|