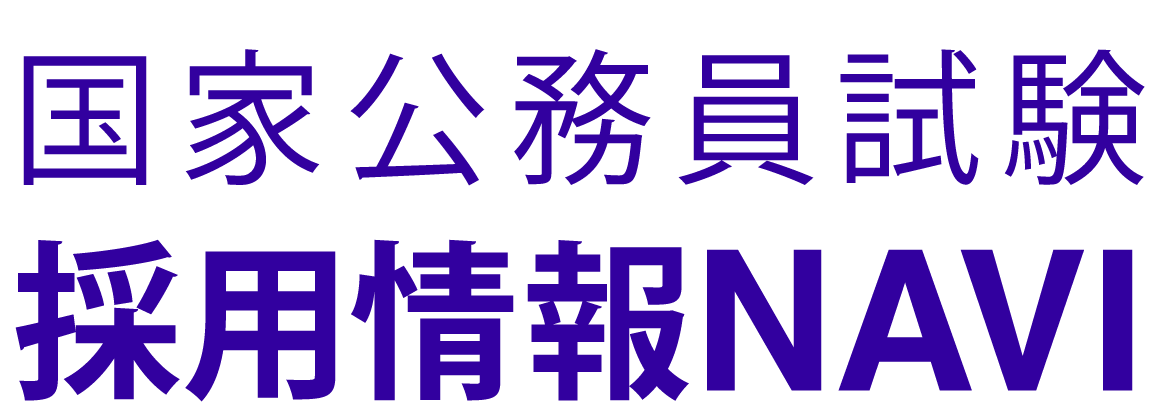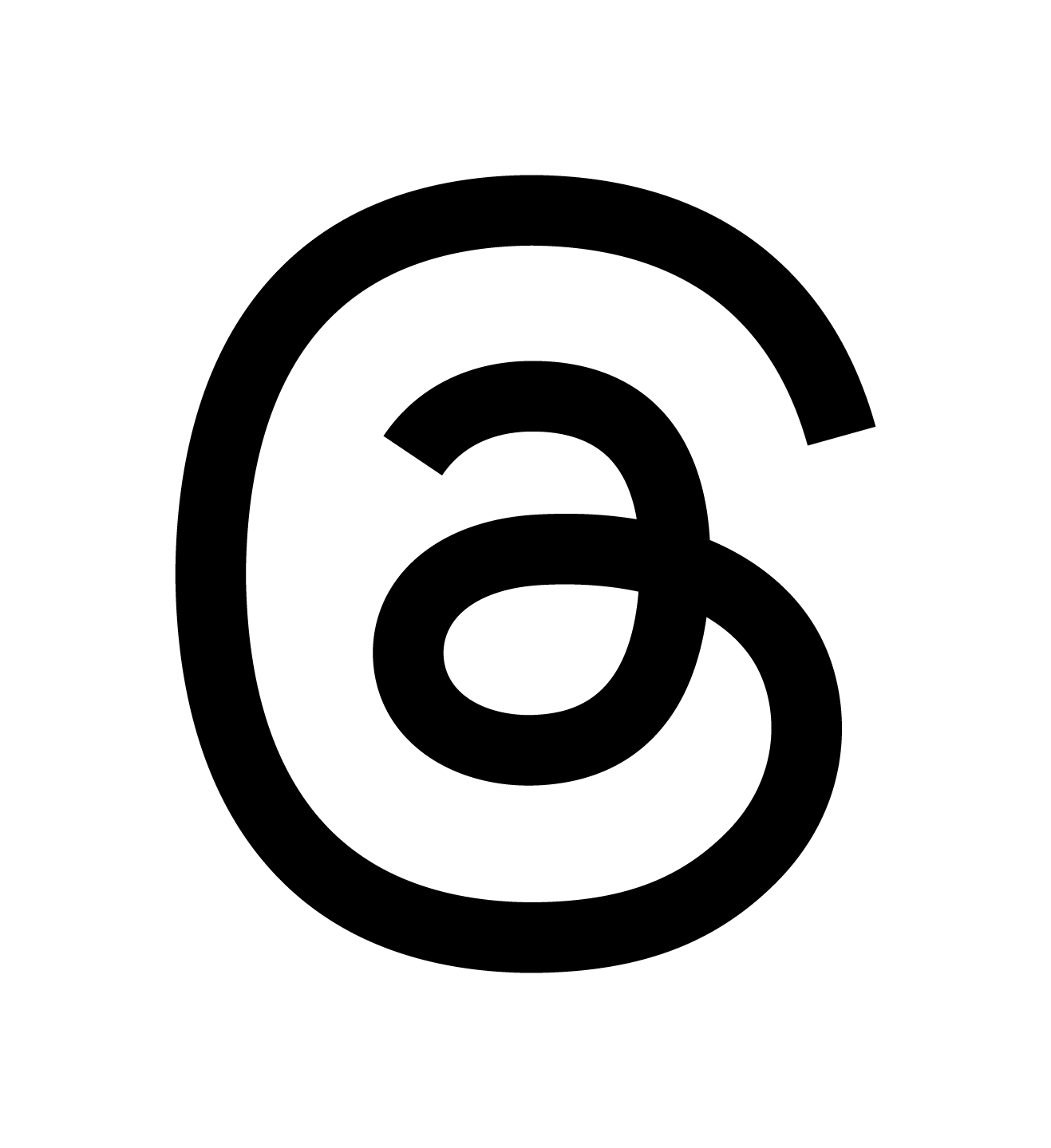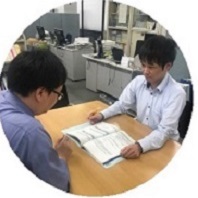三重労働局 労働基準部 監督課 課長 平成28年採用 総合職(工学) |
|
| ◇ 学生時代の専攻分野は? | |
建築 |
|
| ◇ 志望動機は? | |
専攻していた建築という分野において、そこで実際に働く人々の安全・健康を守っているのが厚生労働省であると知り、自分のこれまでの経験や学んできたことを活かすことができるかもしれないと思い志望しました。 |
|
| ◇ 採用後の経歴は? | |
入省後は本省(霞が関)で資格関係の業務や局内の仕事の総合調整業務を行い、厚生労働省の地方組織である労働局・労働基準監督署での研修では管内の現場の安全指導やクレーン等の機械の検査等の業務も行いました。また、環境省に出向して環境系スタートアップ企業の支援等を行っていた時期もあります。 現在は労働局で地域の働き方改革を進めるための仕事や労働基準監督署のとりまとめ等を行っています。 |
|
| ◇ 日々の仕事の様子は? | |
現在、労働局の課長という立場にあるため、日々様々な案件の相談を受けます。これまでの経験に基づいてどのように対応するか考えるのですが、後からもっとこうした方が良かったかな、と思うことが絶えません。また、県内の様々な団体に要請を行ったり、意見交換をしたりする機会も多く、腰を落ち着けて黙々と作業をするよりは、いろんなところに行ったり、多くの方と話しながら仕事をしています。 |
|
| ◇ 専門性はどのように活かされていますか? | |
労働基準監督署では働く現場で事故が起こった際にその原因の調査、再発防止に向けた指導等を行います。工場や建設現場等で事故が起こったときは、どのような力が加わったかやどのような化学物質が影響したのかなど、その原因を調べるために理系的な知識を求められる事が多々あります。また、報告書の中身などが専門分野から少し外れていても内容がすっと理解できることが技術系の強みだと思います。 |
|
| ◇ 仕事の面白み、やり甲斐は? | |
政策立案の現場にいることもあれば、地方で現場の声を聴きながら、制度の円滑な施行に携わることもあります。そういう経験を通じて自分たちの仕事が世の中に広まっていくのを感じることができることが仕事のやり甲斐の一つだと思います。 |
|
| ◇ 仕事と生活(家庭、趣味、地域活動など)の両立は? | |
各種休暇制度を所管している省であるため、仕事と生活の両立が大切であるという認識を皆が共有しており、休みが取りやすかったり様々な事情を考慮してもらえたりと非常に理解のある職場だと思います。 |
|
| (令和6年4月) |
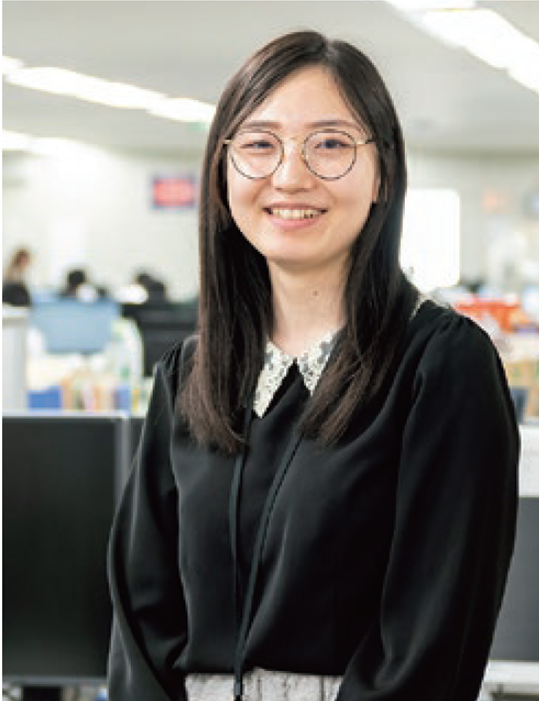
厚生労働省 労働基準局 安全衛生部 労働衛生課 産業保健支援室 令和4年採用 総合職(数理科学・物理・地球科学) |
|
| ◇ 学生時代の専攻分野は? | |
情報工学 |
|
| ◇ 志望動機は? | |
就職活動の際は、人々がより良い人生を送る手助けをしたいということを軸にしていました。より良い人生には様々な考え方があると思いますが、世の中の多くの人は、人生の中でかなりの時間を「労働者」として過ごしているはずです。自分の就活の軸が、働く方の健康と安全を守るというミッションに合うと思い、厚生労働省を志望しました。 |
|
| ◇ 採用後の経歴は? | |
入省後は、労働衛生課産業保健支援室に配属され、産業医制度をはじめとする産業保健体制や事業主健診に関する調整業務などに携わっています。 |
|
| ◇ 日々の仕事の様子は? | |
制度設計にあたってはエビデンスに基づいた考え方が重要だと理解していますが、研究者の先生方からいただいた情報などをもとに、使用者(企業)側の方々、労働者側の方々、その他関係団体の方々と調整を重ねることが欠かせません。日々の業務のなかで、省内外への説明用の資料作成及び調整などを行いますが、どのように情報を伝えるかに注意し、上司と相談しながら進めています。 |
|
| ◇ 専門性はどのように活かされていますか? | |
学生時代から、研究室内外で自分の研究についてかみくだいて説明をする機会が多くありましたが、就職してからも様々な立場の方に制度の内容等を説明する力は日々活かす機会があると感じています。 また、全体として最近はDXやAIの活用といった流れもあると思いますので、理系で培った基礎的な素養は、理解の下地になっていると感じています。 |
|
| ◇ 仕事の面白み、やり甲斐は? | |
学生のときは、労働ということに対するイメージがあまり湧かなかったのですが、仕事をする中で、様々な立場の方の思いをお伺いする機会があり、勉強になると感じています。 |
|
| ◇ 自己の成長を実感したエピソードは? | |
はじめは電話のお問い合わせに対応することも難しく感じられましたが、今では会議等に向けた事前説明や議員秘書さんへの所管制度のご説明もできるようになりました。入省後に、法令の読み方など一から教わりましたが、少しは身についているのかなと感じています。 |
|
| ◇ 今後関わっていきたい政策課題等は? | |
まだ安全衛生行政分野の中でも一部にしか携わったことがないため、幅広い業務を経験し、広い視野を身につけたいと思っています。 |
|
| (令和6年4月) |

厚生労働省 職業安定局 総務課 公共職業安定所運営企画室 平成20年採用 Ⅰ種(人間科学Ⅰ) |
|
| ◇ 学生時代の専攻分野は? | |
心理学(社会・認知心理学) |
|
| ◇ 志望動機は? | |
大学・大学院において心理学を学んでおり、学んだ知識を活かすことができ、かつ、社会に貢献できる仕事に就ければと考えていました。そうした中、就職活動で中々思うようにいかなかった経験もあり、「働く」ということを強く意識し、自分と同じような悩みを抱える方々に対して支援を行うことができる、厚生労働省の人間科学職を志望しました。 |
|
| ◇ 採用後の経歴は? | |
人間科学職で採用されると、職業安定行政を中心に仕事をすることとなります。私はこれまで、ハローワークにおける職業紹介業務や障害者雇用、国と地方公共団体の雇用対策の連携に関する企画立案・現場の指導業務、雇用機会が不足している地域において雇用創出を図るための企画立案業務、事業主への支援業務(雇用管理改善支援や事業主への助成)の企画立案業務などの仕事をしてきました。 |
|
| ◇ 日々の仕事の様子は? | |
現在は、国と地方公共団体の連携した雇用対策を推進する部署にいます。具体的には、国と地方公共団体がそれぞれの役割を果たし、一緒に雇用対策に取り組み、地域の課題に対応するための「雇用対策協定」や、国(ハローワーク)が行う無料職業紹介と地方公共団体が行う各種支援を一体的に実施する「一体的実施事業」を推進しています。この関係で、国と地方公共団体の連携状況を確認するための会議を開催しており、開催に当たっての資料作成や、会議に参加する方(地方公共団体の代表者)への説明を行います。また、新たに一体的実施事業を実施する施設が開設された際には、その開所式に参加し、来賓として挨拶をすることもあります。 |
|
| ◇ 専門性はどのように活かされていますか? | |
制度を構築する上では、既存の法律やそれに基づく制度、社会全体で何が求められているのかはもとより、一人ひとりが抱える課題等も十分に考慮する必要があると考えます。それに当たっては、人間科学を学ぶ上で培ってきた「人を視る視点」が活かされています。 |
|
| ◇ 仕事の面白み、やり甲斐は? | |
憲法に規定されてる勤労権の保障を十分に行うために、多様なバックグランドを持つ関係者が知恵を出し合い、制度構築をできることは魅力の1つだと考えています。 |
|
| ◇ 自己の成長を実感したエピソードは? | |
少し前までは自分は研修を受ける立場と思っていましたが、今では研修講師として新入職員や労働局・ハローワークの中堅職員に説明をする機会があり、ふとした時に自分は成長したなと感じます。 |
|
| ◇ 仕事と生活(家庭、趣味、地域活動など)の両立は? | |
妻と子ども(2歳)の3人暮らしです。子どもの成長に一喜一憂しつつ、日々、子育てに奮闘しています。また、マラソンを趣味としており、日々トレーニングに励んでいます。こうした子育てや趣味に時間を充てることができるよう、仕事に効率的に取り組むよう心掛け、残業は極力少なくしています。また、保育園からの急な呼び出しがあった場合には職場の仲間に助けてもらえているので、大変助かっています。 |
|
| ◇ 今後関わっていきたい政策課題などは? | |
自分の子どもが、将来、何らかの仕事に就こうと思ったときに、心から「働きたい」と思える環境や働くに当たっての支援を整備したいと漠然と思いました。このため、どのような形になるかはわかりませんが、引き続き、職業安定行政に携わっていきたいと考えています。 |
|
| (令和元年11月) |

厚生労働省 職業安定局 雇用開発企画課 産業対策係長 平成25年採用 総合職(人間科学) |
|
| ◇ 学生時代の専攻分野は? | |
教育心理学 |
|
| ◇ 志望動機は? | |
大学時代に心理学を学んでいた身としては、「心理学の知識を直接生かせる仕事」というのを将来の仕事として漠然と考えていました。ただ、心理学関連の仕事というと、カウンセリング系の仕事が多く、自分がそのような仕事をするイメージが沸きませんでした。そのような中、官庁訪問で厚生労働省の先輩職員の方々の話を聞き、国民生活に密着した施策を扱う厚生労働省の仕事に魅力を感じ、志望するに至りました。 |
|
| ◇ 採用後の経歴は? | |
入省後は、障害者雇用からはじまり、労働者派遣・職業紹介事業、雇用保険、ハローワークの運営業務、新しい外国人材の受入(特定技能制度)、雇用調整助成金といった幅広い業務を経験させていただきました。 |
|
| ◇ 日々の仕事の様子は? | |
事業主が経済上の理由等(現在はコロナの影響含む)で休業を余儀なくされ、それに伴って労働者の方に休業手当を支払った場合に、その助成を行う「雇用調整助成金」について、制度の運用面や対外的な説明を主に担当しています。コロナ禍において、雇用調整助成金の申請件数は過去最高となっており、多くの事業主の方にご利用いただいている制度となっているため、非常にやりがいのある業務となっています。 |
|
| ◇ 専門性はどのように活かされていますか? | |
制度設計や見直しにあたっては、マクロな視点はもちろんのこと、ミクロな視点も重要となります。ひとつひとつの意見を「そういう意見もある」と片付けるのではなく、「大きな声」に埋もれた「小さな声」にも耳を傾ける必要があります。心理学は、まさにそういったひとつひとつの声を聞き、昇華させることを学問として行っているので、その経験が生かされているものと感じています。 |
|
| ◇ 仕事の面白み、やり甲斐は? | |
制度見直しに直接関わり、それが実際に日本社会の中で反映される様子やニュース等で取り上げられると、大きな仕事と責任を感じ、やりがいを感じます。 |
|
| ◇ 自己の成長を実感したエピソードは? | |
己の判断のみで対応する案件が多くなってきたなぁとふと感じると、自己の成長を感じます。 |
|
| ◇ 仕事と生活(家庭、趣味、地域活動など)の両立は? | |
育児休業を約1年取得したことで、子育ての大変さは十分身にしみているため、自分もできるだけ早く家に帰り、子供をお風呂に入れるなど平日でも子育てに関わることを(子育ては「手伝うもの」ではなく、「協力し合うもの」であること含め)意識しています。そのためにも、早く帰る日を週に2,3日設定しておき、その日に早く帰るため、週の業務スケジュールを意識して業務を行うようにしています。スケジュール管理をすることで、独身時代にはあまり意識していなかった日々のメリハリづけ(この日に早く帰るために前日は残業する等)ができるようになりました。 |
|
| ◇ 今後関わっていきたい政策課題などは? | |
様々な立場や状況の人の意見を聞く機会が多く、心理学とも親和性が高い障害者福祉施策に携わりたいと考えています。 |
|
| (令和3年10月) |