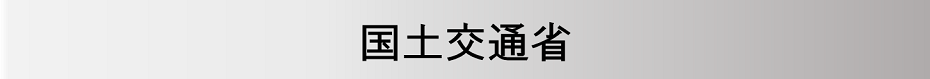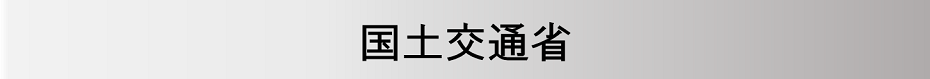|
| |

川井 拓弥  |
国土地理院 地理空間情報部 情報普及課 ウェブシステム係長
平成27年採用 総合職(工学) |
| |
| ◇ 学生時代の専攻分野は? |
情報科学
|
| ◇ 志望動機は? |
幼い頃から地図を眺めたり描いたりすることが何故か大好きだったので、中学生の頃には既に国土地理院に興味を持っていました。
大学では情報系の学部に進みました。就職に際して、長く働くならやはり好きなものに関わる仕事をしたいと思ったことと、昔に比べて地図の電子化が進んできていたので、情報系の学部で得た知識も役立つだろうとの考えから、国土地理院を志望しました。
|
| ◇ 採用後の経歴は? |
1~3年目は志望したとおりウェブ地図「地理院地図」(※1)を運用・開発している部署に配属されました。4・5年目は内閣官房内閣サイバーセキュリティセンター(NISC)に出向し、グループ内の取りまとめや国会答弁作成、各府省庁との意見調整等の総括業務に従事しました。6年目に元の部署に戻り、今に至ります。
※1 地理院地図 https://maps.gsi.go.jp/
|
| ◇ 日々の仕事の様子は? |
地理院地図は、我が国の基本図である国土地理院の地形図を始め、現在・過去の空中写真、土地の凹凸や成り立ちがわかる地図、災害に関する情報など、様々な情報をインターネット上で見ることができるウェブ地図です。私は主にこのシステムの運用と開発を行っています。
|
| ◇ 専門性はどのように活かされていますか? |
地理院地図等の運用にあたっては、情報を掲載するための設定ファイルを日々更新するだけでなく、職員自らウェブサイトやデータ作成ツールのプログラムを修正することもあります。このような業務においては、大学の授業や研究においてプログラミングを経験していたことで、おそらく他の人より比較的抵抗を感じずに取り組むことができています。
また、地理院地図を紹介したり、業務内容を発表したりする際には、学会発表のためにわかりやすい資料を作った経験が大いに役立っています。
|
| ◇ 仕事の面白み、やり甲斐は? |
国土地理院の業務は、各種測地観測データや研究成果、「地理院地図」に載る地図や空中写真等として、自分が携わったことが目に見える成果となって世に公開されるものが多く、とても面白い仕事だと思います。地図が好きなら尚更、仕事を楽しめる職場です!
|
| ◇ 自己の成長を実感したエピソードは? |
出向先のNISCには、各府省庁・民間企業等様々な背景を持つ人たちが働いており、このような中で働くうちに、徐々にサイバー攻撃の潮流やそれらに対するサイバーセキュリティの技術動向、各機関の役割分担などに面白味を感じるようになりました。同時に、NISCでの仕事の進め方・さばき方もわかり、自己の成長に繋がったと考えています。
|
| ◇ 仕事と生活(家庭、趣味、地域活動など)の両立は? |
昨年度から新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、在宅勤務が多くなりました。在宅勤務は通勤時間が節約できるメリットがある一方、運動不足気味になるので、休日にはシェアサイクルを利用して大きい公園等に散歩に行ったりしています。
また、国土地理院の始業時刻は標準では8:30ですが、私は朝の混雑回避のため、出勤日はフレックスタイム制を利用して9:30に出勤しています。
|
| (令和3年12月) |
|
|
| |

岡 滉  |
国土交通省 大臣官房官庁営繕部 計画課 長期計画係長
平成29年採用 総合職(工学) |
| |
| ◇ 学生時代の専攻分野は? |
電気電子情報工学
|
| ◇ 志望動機は? |
志望動機は主に2点、「恩返し」と「ものづくり」です。人生30年弱生きてまいりましたが、衣食住に困ることはなく、十分な教育と医療を与えてもらい、何不自由ない生活を謳歌してきました。それはひとえに両親と環境のおかげだと思います。中でも環境は先人が長い年月をかけて作りあげてきたものです。自分も後世に自分が与えてもらった以上の環境を残す一助になれば、という思いで公務員を志望し、なかでも自分の好きな「ものづくり」ができる国土交通省の官庁営繕部を志望しました。
|
| ◇ 採用後の経歴は? |
1年目は九州地方整備局に配属され、税務署や警察学校等の官庁施設について、電気設備の設計・積算などを担当していました。その後、3年目に本省へと異動となり、電気設備の設計・工事において用いる技術基準の作成や業務の予算要求・執行等を行っていました。5年目には本省内で別の課に異動となり、国の建築物に関する中長期計画や老朽化対策、防災関係の業務等を行っています。
|
| ◇ 日々の仕事の様子は? |
現在は、経歴にも挙げているとおり、官庁施設の長期計画および防災に関する業務を行っています。長期計画業務としては、各省庁や地方整備局に依頼をかけて得られたデータのとりまとめや施策のフォローアップを行うとともに、中長期計画の策定などを行っています。また、防災関連業務として、防災訓練の実施や、災害やコロナ等の発生に際し、被害を最小限にするべく、関係者との連絡・調整を行っています。
|
| ◇ 仕事の面白み、やり甲斐は? |
自分が設計や工事等に関与した建物ができあがることで、成果が形に残る喜びがあると思っています。また、もともと建築関係に関する知識はほぼゼロの状態からのスタートでしたが、学ぶための環境が整っており、効率よく知らない知識が手に入ることにも面白みを感じています。
|
| ◇ 自己の成長を実感したエピソードは? |
自分の視点の変化を感じています。これまで目についても気にも留めなかった、建物の立地、形状、屋内の照明設備、空調設備等、あげればきりがありませんが、そういったものに目を配り、疑問や関心を抱くことができるようになったと実感しています。
|
| ◇ 仕事と生活(家庭、趣味、地域活動など)の両立は? |
業務時間内にできる限り集中して業務に取り組み、オンオフをはっきりさせるよう意識して仕事をしています。そのおかげもあってか、残業時間も比較的少なく、計画的な休暇も取得できており、休みの日などは妻と一緒に料理やお菓子作りをして楽しんでいます。
|
| (令和3年12月) |
|
|
| |

森田 早紀  |
国土交通省 関東運輸局 鉄道部 技術・防災第一課
平成27年採用 総合職(工学) |
| |
| ◇ 学生時代の専攻分野は? |
材料工学
|
| ◇ 志望動機は? |
世の中を良くする仕事がしたいと漠然と思っていました。就職活動を通して色々な会社の話を聞く中で、法律や規則といったルールを考えることで、物事を根本から変えることが出来る行政官の仕事に魅力を感じました。加えて、面接してくださった方の誠実に対応してくださる姿が印象的で、ここで働きたいという気持ちになり、入省を希望しました。
|
| ◇ 採用後の経歴は? |
鉄道に関する国際協力に係る業務や駅ホームにおける視覚障害者の転落防止対策等の鉄道の安全対策に係る業務を担当しました。省内のとりまとめ部署にいた際は、各種案件を各局と調整する業務を行いました。
現在は運輸局で補助金審査業務や鉄道施設に係る工事の許認可業務などを担当しております。
|
| ◇ 日々の仕事の様子は? |
現在は運輸局で勤務しており、事業者から鉄道施設に係る工事をするにあたって国への手続き方について相談を受けたり、補助金を活用して事業を実施する場合は、申請内容を確認したり、事業が完了した際には適切に事業が実施されているか審査をしたりというような業務を行っております。本省は制度の大きな枠組みや方針を決めるような仕事が比較的多く、それに比べると運輸局は法律に基づく手続きを実際に処理することが多く、事業者とも距離感が近く感じており、現場に行く機会も多いように思います。
|
| ◇ 専門性はどのように活かされていますか? |
法律をベースとして作業をすることが多いですが、日々の業務の中で事業者等から相談を受けたり、実際に現場でモノを見た際に、どういう現状が起こっているのか、技術的な観点から想像していくことは非常に重要だと思うので、そういう意味で専門性を活かす機会は多いと思います。また、事業者等から相談を受けた際に専門用語に臆せず会話できる点では、勉強していてよかったと思います。(実際は知らないことも多く、後で調べることも多々ありますが。)
|
| ◇ 仕事の面白み、やり甲斐は? |
自分が関わった政策によって、人々の安全が確保されていると思えた時にやりがいを感じます。実際に何か成果物として物になることはあまりありませんが、テレビのニュースで見たり、鉄道に係る政策の場合は駅のポスターや構内放送で見聞きする場面が多く、人々の生活に身近なところで関われていると感じることは多々あります。
|
| ◇ 自己の成長を実感したエピソードは? |
入省して最初の数年間は、聞こえてくる用語や手続き方、省内の資料作成や幹部報告の際のお作法等わからないことが多く、毎日四苦八苦しておりました。最近はどのくらいのスピード感で物事を進めたらよいか等、仕事の全体像がなんとなくイメージが出来るようになり、気持ちに余裕が出てきたと思います。それにより、周りで働く人たちの動きにアンテナを張ることや案件の内容を自分なりに咀嚼して考えること等が徐々に出来るようになってきたと思います。
|
| ◇ 仕事と生活(家庭、趣味、地域活動など)の両立は? |
現在、保育園に通っている2歳の子供がおります。夫は単身赴任しているため、一ヶ月の内、2/3くらいは関西にいる実家の母が手伝いにきており、1/3くらいはワンオペで回しております。正直なところ、数年前のテレワークが浸透していなかった頃であればなかなか仕事と家庭の両立は厳しいという実感ですが、最近は男性も含めてテレワークが普通になっており、子育て世代の人への理解もかなりあるように感じています。とはいえ、どうしても保育園への送り迎え等で時間的制約があり、時間内に対応出来ない仕事がどうしても出てきてしまうため、周囲の職員のお力を借りて仕事をしており、感謝する毎日です。
|
| ◇ 今後関わっていきたい政策課題などは? |
人々の生活に密着しており、必要不可欠である鉄道インフラの安全確保のための仕事をこれからも取り組んでいきたいと思っております。特に、地方の鉄道においては人口減少や少子高齢化に伴う担い手不足、自然災害の激甚化等により、これからますます維持管理していくことが困難になっていくと思います。そのため、そういった地域の鉄道が抱える課題を事業者に寄り添った形で考えていければと考えております。
|
| (令和3年12月) |
|
|
| |

堀口 和希  |
国土交通省 水管理・国土保全局 砂防部砂防計画課 地震・火山砂防室 砂防情報係長
平成29年採用 総合職(工学) |
| |
| ◇ 学生時代の専攻分野は? |
通信工学
|
| ◇ 志望動機は? |
主な動機は2点あります。1点目ですが、親類に公務員が多く、行政の仕事というのがどういうものか聞く機会や見る機会が人よりも多かったため、自然と行政で働くことが主たる選択の中にあったことです。2点目ですが、3.11を仙台にて被災した経験から、インフラ整備や防災対策や「ものづくり」に関心がありました。これらの理由を踏まえた上で、自分が大学で修めた電気通信系にも関連がある組織はどこかと考えた結果、国交省を志望しました。
|
| ◇ 採用後の経歴は? |
最初の2年間は国道を管理する国道事務所に配属され、国道沿いの機器の更新・改修や防災設備の管理のほか、当時の総事業費で2000億円を超える国道整備事業において各種調査や設計の業務発注などを担当し、現場に出ることも多い2年間でした。
3年目からは総務省電波部に出向し、電波政策の観点から自動運転推進を行うべく、ITS関連施策に係る予算要求や執行、実験試験局許諾に関わる業務などを行っていました。日本のITSシステムを宣伝するため、インドでセミナーを実施したこともあります。
5年目(現在)は砂防部に所属し、センサーやカメラなどの観測機器の管理や、新たな技術の導入や仕組みの検討など、土砂災害発生情報をいち早く把握し、住民の命を守り、被災地の早期復旧に繋げるための企画を行っています。
|
| ◇ 日々の仕事の様子は? |
現在は、砂防に関する情報通信技術や情報発信関係の業務を担当しています。例えば、危険な場所でも5Gによる遠隔操作で安全に工事ができる無人化施工技術やカメラ画像のAI解析による土砂災害のおそれの検知技術等の様々な最新技術の導入検討を行ったり、出前講座で住民に防災教育を行ったり、災害時にはJAXAと連携して人工衛星による被災状況調査を行ったりしています。
砂防事業の高度化や被災状況の早期把握に向けて情報通信技術の担う役割は大きく、日々、技術の改善や運用の効率化等を進めていくための議論を行い、必要な予算をまとめて要求等も行っています。
情報通信技術は日進月歩で進歩していますので、電通職として常に最新の技術にキャッチアップし、土砂災害の防災に貢献できるよう頑張っていきたいと思います。
|
| ◇ 専門性はどのように活かされていますか? |
大学の研究室ではアンテナ設計などを行っていたこともあり、電気や電波関連の基礎知識が多少あったため、電通関連の業務を行う上で活かされています。
|
| ◇ 仕事の面白み、やり甲斐は? |
自分が関わった業務が実際に形となり見えるところだと思います。国交省は全国に事務所や現場を持つ組織ですので、自分の取り組んだ業務の結果がどのように運用されているのか、わかりやすい形で見えてくるところが面白くもあります。
|
| ◇ 自己の成長を実感したエピソードは? |
日々対応する多数の業務に対し、どういったプロセスで処理すべきかを自然と考えられ、その通りに対応できた時や、業務内容について他者に説明する際に、以前よりも短時間で簡潔に伝えられ効率的な対応が出来た時などに思います。
その他、街中を歩く際や新聞やニュースを見る際に、これまでは特に気に留めなかった情報に対する意識の変化に気づいた際なども実感します。
|
| ◇ 仕事と生活(家庭、趣味、地域活動など)の両立は? |
情報共有をしておけば休暇も取りやすく、残業が奨励される風潮もないため、現在は仕事と生活を両立出来る環境だと思います。もちろん、災害対応を行う部署ですので、時間外対応や休日出勤等が発生することもありますが、基本的には当番制でありますし、テレワーク対応もある程度可能なため、事前に備えておくこともできます。
災害が起こらなければ基本的に土日は休みですので、趣味である神社巡りやバイクでのツーリングなどをしています。
|
| ◇ 今後関わっていきたい政策課題などは? |
国土交通省のインフラDXはローカル5G、VR/ARなど最先端技術導入の取組に積極的ですので、ぜひDX推進に関わる仕事をしたいと考えています。色々な場面で取りざたされる人手不足の解消や労働時間の適正化などにおいても有用であると思いますので、運用・普及の側面を適切に踏まえた上で、最新技術の導入を促進できればと思います。
電気通信以外の分野であれば、地元が人口減少の進む田舎であるため、都市整備や地域活性化に係る業務にも関心があります。
|
| (令和3年12月) |
|
|
| |

清水 陽介  |
国土交通省 航空局安全部安全企画課 国際調整官
平成22年採用 Ⅰ種(工学理工Ⅰ) |
| |
| ◇ 学生時代の専攻分野は? |
機械航空工学科
|
| ◇ 志望動機は? |
大学で疲労亀裂を研究する過程で、疲労亀裂が原因となる事故をなくすための技術的手法・政策的手法を調査したところ、国土交通省では技術の進展を踏まえて、交通インフラの安全を守るためのルールメイキングに携わることができると知ったからです。
また、国家公務員の発言は「日本代表の言葉」として扱われることも多いと知り、日本を背負って仕事ができる感覚は、幼い頃から部活動で「日本代表になりたい」と夢見ていたことに形は違えど近づけるのではないかと思って志望しました。
|
| ◇ 採用後の経歴は? |
入省1年目から今日に至るまでに、自動車・海事・航空と様々な交通モードに関する政策立案に携わり、また、東北運輸局や海外(留学)と多様な土地での業務を経験しました。
業務内容は予算要求・法改正業務・東日本大震災で被災した中小造船業の復興支援、国際機関対応など非常に多岐にわたります。
現在は、航空分野を中心として専門性に磨きをかけているところですが、たくさんのことを幅広く学びたいという前向きな気持ちで業務に臨み、業務経験を通じて自分の知見を広げられていることに満足感を得られています。
|
| ◇ 日々の仕事の様子は? |
現在は、空港に違法に侵入するドローンを検知するシステムの導入を進めるために、予算要求や空港事務所と設置調整等を行っています。
また、ICAO(国際民間航空機関)において無人航空機(Remotely Piloted Aircraft System)に関する国際ルールを策定する検討を進めており、航空局関係各課と我が国の対処方針を整理し、各国と調整する役割を担っています。
一般的に、配属部署や時期によって働き方や業務内容は大きく異なりますが、航空局ではテレワークを現在推奨しており、私の業務チームは週1又は週2の出勤体制で業務しています。また、一人で考え抱え込むことがないよう、チームで相談・意思決定ができるようコミュニケーションをとって仕事ができています。
|
| ◇ 専門性はどのように活かされていますか? |
大学で学んだ専門性をそのまま仕事に活かすというよりも課題を評価・分析し、専門家の知見を課題解決や制度設計に活用していく筋道を一生懸命頭を使って検討していくことが求められると思います。
従って、研究を通じて学んだ「何故こうなるんだろう?」「何を改善すればこの課題が解決されるんだろう?」という思考プロセスは間違いなく業務で活かされていますので、皆さんも、大学・大学院で取り組んでいる研究等の課題に対する思考プロセスを鍛える機会を大切にしてください。
|
| ◇ 仕事の面白み、やり甲斐は? |
自分が考えたことが仕事の軸になり、それが国家制度の根幹になることを実感できます。自分が携わった法律が公布されるのを見た時は達成感で満たされました。
また、人事異動のタイミングで仕事内容が大きく変わり、すぐに「専門家」として業務をしなければならないという大きなプレッシャーに晒され、社内転職を繰り返しているような感覚に陥りますが、新たな知識を吸収していく機会がたくさんあるとも考えられ、やり甲斐は長く続くと感じています。
|
| ◇ 自己の成長を実感したエピソードは? |
ドローンの利活用を進めるための航空法の改正に携わりましたが、人の上空を飛行することを可能にする社会に大きな変革をもたらす改正であったため、多数の既存事業者との調整や他省庁の意向を踏まえた条文調整、過去の法改正との整合性を踏まえた改正内容を検討するといった作業に多大な時間・労力を費やし、改正案について国会議員へのレクを行う等、文字通り身を粉にして働きましたが、無事に国会審議を終えた時にはすべての努力が報われ、違った景色を見ることができました。
ダメだと思うシーンもありましたが、上司や同僚、そして家族の支援があって乗り越えることができたこの経験が今の自分の糧になっています。
|
| ◇ 仕事と生活(家庭、趣味、地域活動など)の両立は? |
テレワークが推奨されており、現在は週1出勤で朝7:30~16:15の勤務体系で業務をしています。おかげで夕方は子ども達の習い事に付き合ったりすることができ、家庭との両立はしっかり出来ています。
ただし、配属される部署によってミッションが大きく異なる「部署ガチャ」、上司の仕事スタイルによって求められる仕事スタンスが変わる「上司ガチャ」などコントロール出来ない部分は少なからずありますが、自分がコントロール出来る範囲を見極めて、WLBを向上させる工夫をするのも組織マネジメントの一環として楽しんでいます。
|
| ◇ 今後関わっていきたい政策課題などは? |
今後は、航空の専門分野を学んだ上で、ICAOで日本代表として国際ルールを制定する場で堂々と我が国の主張を代弁したり、各国と衝突する意見の落としどころを見いだせるファシリテーターとして活躍したいと考えています。
これまで培ってきた知識や交渉術、組織マネジメントなどを最大限活かせる場所を見つけ、I have control の精神で邁進していきたいと思います。
皆さんも将来のビジョンと希望を持って選択をしてください。The choice is yours.
|
| (令和3年12月) |
|
|
| |

岡本 由仁  |
国土交通省 関東地方整備局 企画部施工企画課長
平成22年採用 Ⅰ種(理工Ⅰ) |
| |
| ◇ 学生時代の専攻分野は? |
航空宇宙工学
|
| ◇ 志望動機は? |
道路、河川、ダム、さらにはそれに付随する巨大な機械設備等、人の生活を支えるために何十年も先の将来にも残るインフラを仕事とする国土交通省に惹かれました。
|
| ◇ 採用後の経歴は? |
スタートは北陸地方整備局信濃川河川事務所に配属されて、2年間、河川機械設備の管理、土木工事の発注等を担当しました。
その後4年間、本省で最新の建設機械技術の推進、建設機械の環境法令事務、建設現場へのUAV・ロボット技術の活用等に携わりました。
さらに、3年間、中部地方整備局飯田国道事務所で道路の調査、計画及び設計を担い、当時に携わった道路のいくつかは既に開通し、地域の暮らしに役立てられています。
続いて2年間、環境省へ出向し、電動重量車の開発や排出ガス対策等の施策を推進しました。
|
| ◇ 日々の仕事の様子は? |
技術革新はどのような分野においても目覚ましく、建設業においても新たな技術が次々と現れています。これら技術革新に乗り遅れることがないように、さらには技術開発を先導するために、企画部施工企画課は、建設現場での新技術の普及・開発に係る施策を担当しています。クラウドサービスの利用、UAVの活用、建設機械の自動化等、有用な技術を整備局の発注工事に取り入れるだけではなく、建設業界、地方自治体等が活用するお手伝いもしています。
また、ダムゲート、河川水門等の整備局が持つ機械設備の管理、さらに、排水ポンプ車をはじめとした災害対策車等の管理も担っています。人々の命を守るこれら機械が大雨・地震等の災害時に活躍しています。
現在は管理職という立場上、マネジメントが主となりますが、課の方針を示すためにも常に学び続ける必要があります。
|
| ◇ 専門性はどのように活かされていますか? |
実際の業務は改めて基本から学ぶことがほとんどでしたが、学生時代に培った工学の基礎及び知識等も業務に役立っています。
|
| ◇ 仕事の面白み、やり甲斐は? |
現場の事務所で、自身が携わった道路、設備ができあがり、形になって残ることはとても嬉しく、子供に「これをお父さんが作ったんだよ」と自慢しています。
また、本省での仕事は施策や方針を示すことであり、形あるものを作りあげることではありませんが、担当した施策等に基づき、全国を動かしていく責任感を感じられます。
|
| ◇ 自己の成長を実感したエピソードは? |
入省したばかりの頃は、いち担当者として自身の仕事だけを見ていれば良かったですが、ステップアップしていくにつれて、担当する幅が増えていき、マネジメントをする立場となってきます。
|
| ◇ 仕事と生活(家庭、趣味、地域活動など)の両立は? |
仕事は時期によっては遅くなることもありますが、休日には家族と出掛けて楽しんでいます。
引っ越しを伴う異動をした際には、近くの観光地を次々巡り、その地域のグルメを堪能していました。
|
| ◇ 今後関わっていきたい政策課題などは? |
これまで携わったことのない業務では更なる経験が得られますし、これまでのバックグラウンドを活かせる業務では新たな気付きがあります。どのような業務にも自分に出来ることを果たしていこうと思います。
|
| (令和3年12月) |
|
|
| |

田中 洋介  |
国土交通省 大臣官房 技術調査課 課長補佐
平成22年採用 Ⅰ種(理工Ⅰ) |
| |
| ◇ 学生時代の専攻分野は? |
土木工学(地盤工学)
|
| ◇ 志望動機は? |
小学生の時に沖縄県の離島に住んでいだ経験があり、台風など悪天候時に物流がストップし不便な思いをすることが多く、道路や港湾など物流インフラが、日常生活を送る上で重要な役割を担っていることを認識しました。
そのため、日本全国規模での物流インフラ整備に関与でき、インフラ整備を通じた経済活性化に貢献できる国土交通省の仕事に魅力を感じ、志望しました。
|
| ◇ 採用後の経歴は? |
入省後、道路分野や港湾分野の整備や政策立案の業務を経験しました。その中でも道路分野の経験が長く、本省の係長時には、老朽化した高速道路の模更新・修繕に向けた計画策定に携わり、東北地方整備局の課長時には、東日本大震災から10年目となる年の復興道路の整備・開通に携わりました。
また海外勤務の経験として、外務省在ミャンマー日本国大使館に出向し、建設分野のアタッシェとして、日系企業の進出支援やODAによるインフラ整備支援を担当しました。
|
| ◇ 日々の仕事の様子は? |
現在は、技術系職員の人材育成や新規採用を担当しています。業務説明会などの採用イベントを開催し、国土交通省の業務紹介や職員の勤務内容を通して、学生向けに国土交通省の技術系職員の仕事の魅力を紹介しています。このほか、全国の大学に出張する機会も多く、大学教官と学生の就職動向について意見交換を行ったり、国土交通省を志望する学生からの相談に対応することもあります。
|
| ◇ 専門性はどのように活かされていますか? |
例えば、新たな道路計画を策定する際に、都市計画との整合性を確認したり、交通量推計により利用交通量を確認したり、地質状況を踏まえた工法の検討など、土木工学の基礎知識が必要になります。さらに業務内容に応じて専門知識は異なりますが、新たに専門知識を取得し、専門性を高めるための基礎知識として、大学で学んだ土木工学の知識が大いに役立っています。
|
| ◇ 仕事の面白み、やり甲斐は? |
勤務先が本省だけに限らず、地方勤務や海外勤務など幅広い勤務経験を通した成長機会を与えられることが、国家公務員総合職の魅力の一つだと思っています。
地方勤務では、インフラ整備や管理の最前線で仕事をすることになり、インフラの必要性や地域の課題を住民や利用者の方から直接聞くことができます。私が東北地方で、東日本大震災からの復興に向けた道路整備を進めている中で、自治体職員の方から、目に見えてインフラ整備が進むことが被災地域の希望の光になっているとの話を聞いた時に、国交省技術系職員としてやりがいを強く感じました。また、地域ごとの実情や課題を理解して、本省での政策立案に反映させることが出来ることも、国交省技術系職員としての業務の魅力だと感じています。
|
| ◇ 自己の成長を実感したエピソードは? |
東北地方整備局の課長として、担当する道路事業の進め方を審議する有識者委員会に、説明者として出席する機会がありました。国交省が進める事業の必要性を、どのように分かりやすく伝えて理解してもらうか、最初は強いプレッシャーを感じながら準備・対応していました。課長として何度も説明する機会が与えられ、説明や質疑を行っていく中で、人前に出て説明することを苦に感じることなく対応できるようになり、自身の成長を実感しました。
|
| ◇ 仕事と生活(家庭、趣味、地域活動など)の両立は? |
転勤が多い仕事なので、家族と一緒に転勤先での生活を楽しむように心がけています。海外駐在時は、休暇を活用して赴任国内の観光地へ旅行したり、近隣国へ物資調達も兼ねたリフレッシュ旅行に行ったりしました。東北勤務時には、スキー場へ家族でソリ滑りに行ったり、温泉旅行に行ったりと、北国ならではの経験ができ、家族との貴重な思い出を作ることが出来ました。
平日に良い仕事をするためにも、週末の家族との過ごす時間が大切と感じています。
|
| ◇ 今後関わっていきたい政策課題などは? |
現在の日本は人口減少社会を迎えており、働き手の減少を上回る生産性向上のため、国土交通分野においても、デジタルデータを活用した社会課題を解決するための取り組みの深化が求められています。
その中でも、AIを用いたインフラの点検、維持管理の効率化など行政側の取り組みだけでなく、行政手続きの効率化・迅速化など、利用者にとっても裨益するような施策に関与する仕事をしていきたいと思っています。
|
| (令和3年12月) |
|
|
| |

佐藤 嘉哉  |
国土交通省 港湾局 海洋・環境課 海洋エネルギー係長
平成30年採用 総合職(工学) |
| |
| ◇ 学生時代の専攻分野は? |
土木工学
|
| ◇ 志望動機は? |
人や物の移動に必要不可欠な交通運輸の維持・発展に携わりたいと思い志望しました。また、それぞれの地域に異動する機会もあり、地域の現場の声を聞いて政策に反映することができることも魅力に感じました。
|
| ◇ 採用後の経歴は? |
1年目は航空分野におけるバイオ燃料の導入促進やCO2排出量の削減に向けた施策に携わりました。国際会議のために海外出張も行いました。
2年目は港湾に関する統計調査の実施やデータの取り扱いに携わりました。
3年目からは現在に至るまで、洋上風力発電の導入促進に携わっています。
|
| ◇ 日々の仕事の様子は? |
洋上風力発電の促進区域を占用する事業者を選定するための公募の実施や風車の建設に必要な基地港湾に関する検討を行っています。
具体的な業務としては、共同で洋上風力発電の導入促進に取り組んでいる資源エネルギー庁との調整や、審議会等の各種会議の運営、政府計画の内容の調整等を行っています。
国会議員からのレクチャーの要求も度々あるため、そのための資料作成や、説明や資料をお渡しするために議員会館へ行く機会も多いです。
|
| ◇ 仕事の面白み、やり甲斐は? |
2050年カーボンニュートラル宣言以降、洋上風力発電はより一層注目されており、また、事業規模が大きいことから、自らの業務が社会に与えるインパクトの大きさを実感しています。また、行う業務の一つ一つが新しいことであるため、自らが仕事を進めることにより施策が進んでいることを実感し、やり甲斐を感じます。
|
| ◇ 自己の成長を実感したエピソードは? |
様々な会議において上司が説明することが多かったところ、最近は自ら説明する機会も多くなり、回数を重ねるにつれて、徐々にですがどのような段取りで説明をすれば相手に分かりやすく伝わるのかというコツが分かってきたと実感します。今後は国会議員に説明する機会もあると思いますが、短時間で要点を抑えて説明ができるようになりたいと思います。
|
| (令和3年12月) |
|
|
| |

藤井 佳人  |
国土交通省 大臣官房官庁営繕部整備課 技術管理係長
平成29年採用 総合職(工学) |
| |
| ◇ 学生時代の専攻分野は? |
建築
|
| ◇ 志望動機は? |
大学で建築の実態調査を行った際に、設計者が考えた空間が利用者のニーズと合わずに使われなかったり、すぐに改修されてしまった事例に触れました。そうした経験から、建築を、発注者、設計者、施工者、利用者、管理者など、様々な立場で考えることに興味を持つようになりました。官庁営繕部は、建築の企画から、設計施工、その後の保全まで、建物のライフサイクル全体に関わる仕事に加え、公共建築の先導的な役割も担っている組織であり、建築に対して様々な関わり方で課題解決ができる点に魅力を感じました。
|
| ◇ 採用後の経歴は? |
採用1、2年目は四国地方整備局営繕部に配属され、税務署や気象台、労働局等の設計の発注業務を担当しました。
採用3年目から国土交通省の本省に異動した後は、2年間、建設現場で働く労働者の処遇改善に関する施策の企画・立案を担当し、5年目からは現在の部署で官庁施設の設計業務発注のための技術基準の作成を担当しています。
|
| ◇ 日々の仕事の様子は? |
設計業務発注のための制度設計を行っています。関係法令の改正や、環境問題、働き方改革といった政府全体で取り組まなければいけない課題など、その時代のニーズに応じて制度を変えていく仕事ですが、当然、変わった制度は現場の運用実態に沿った制度でなければなりません。大きな目標を一つ一つの実務に落とし込んでいくために、現場の職員や業界団体など、様々な関係者との意見交換を行い、取り組んでいます。
|
| ◇ 専門性はどのように活かされていますか? |
設計業務・工事の受注者との打合せや、業界団体の方との意見交換の場では、専門的な話になる場面もあるため、専門性が活かされていると感じます。
また、仕事を始めてからも日々勉強ですが、基礎的な知識があるため、新しい知識の習得もスムーズになっていると感じています。
|
| ◇ 仕事の面白み、やり甲斐は? |
異動が多い国家公務員総合職では、異動する度に新しい仕事を一から勉強することになります。一見関係なさそうな仕事でも、どこかで自分が前にやっていた仕事とつながっていることがあり、そうすると今の仕事に対して、新しい立場から考えるきっかけになります。物事に対していろいろな立場で関わることで、多角的に知見を得ることができ、自分のこれまでの経験から新しい提案をできたりすることが、この仕事ならではの面白さだと思います。
|
| ◇ 自己の成長を実感したエピソードは? |
仕事の面白さの部分とつながりますが、過去の仕事で培った人脈や知識が現在の仕事で役に立ったときは、これまでの自分のキャリアが自分ならではの力になっていると強く感じます。
|
| ◇ 仕事と生活(家庭、趣味、地域活動など)の両立は? |
事前に調整しておけば長期の休暇も可能で、周囲もそれをサポートしてくれます。
子供が生まれた際には育児休暇を取得しました。育児休暇明けも休暇やテレワークにより、家族との時間を確保することができています。小さい時の子どもの成長を見れることは大切な思い出になっています。(写真はテレワークの日のお昼休みでの子供とのお散歩です。)
|
| (令和3年12月) |
|
|
| |

岡田 奈穂美  |
国土交通省 航空局航空ネットワーク部近畿圏・中部圏空港課
平成31年採用 総合職(工学) |
| |
| ◇ 学生時代の専攻分野は? |
建築
|
| ◇ 志望動機は? |
学生時代に地元の駅がリニューアルしたことで周辺地域も活性化していく様子を見て、インフラの整備に興味を持ちました。人々の暮らしや地域の経済を支えるインフラ整備に携わる仕事がしたいと考える中で、災害が頻発し人口減少など社会を取り巻く状況が変化していることを踏まえ、インフラ整備自体だけでなく制度設計や今後の在り方の検討に携わりたいと思い、国土交通省を志望しました。
|
| ◇ 採用後の経歴は? |
入省から現在に至るまで本省で勤務しています。最初の1年半は、航空分野の政策立案を行う部署に在籍し、主に国際航空分野におけるCO2排出削減の枠組みの国内運用に携わりました。丁度運用開始の時期でしたので、事業者と協議しながら制度設計を行い、また省令改正も担当しました。現在の部署では、関西圏の空港を担当をしています。
|
| ◇ 日々の仕事の様子は? |
現在、関西圏の空港を担当をしていますが、国が管理する航空保安施設の更新に関する予算要求やコロナ禍においても航空ネットワークを維持していくための企画立案などを担当しています。時には、国会議員への説明資料の作成や関係団体からの要望への対応等も行っており、業務は多岐に渡ります。現在はコロナ禍ということもあり出張の機会は減っていますが、担当している事業の進捗を確認するために視察に行くこともあります。
|
| ◇ 仕事の面白み、やり甲斐は? |
やはり自分が関わった案件が完成し実際に利用されているところを見た際にやり甲斐を感じます。国土交通省は所管している現場が非常に多いため、携わった業務が形になり直接見ることができる点が魅力の1つだと思っています。
|
| ◇ 自己の成長を実感したエピソードは? |
当初は現状を把握することで精一杯でしたが、経緯を理解するだけでなく他の案件との関係性を把握し、次に求められる事を想定しながら業務を進められたときです。
|
| ◇ 仕事と生活(家庭、趣味、地域活動など)の両立は? |
やはり忙しい日が多いので、平日は仕事中心の生活になることが多いため、休日は好きなことをしてリフレッシュし、オンオフを切り替えるようにしています。
|
| (令和3年12月) |
|
|
| |

湯浅 翔  |
国土交通省 近畿地方整備局建政部 住宅整備課長
平成27年採用 総合職(工学) |
| |
| ◇ 学生時代の専攻分野は? |
建築
|
| ◇ 志望動機は? |
制度設計ができる点に魅力を感じました。私は、建築や都市計画に関わる仕事がしたいと考えていましたが、規制、誘導、プロジェクトなど、何かしようと思った時、ベースにはそれをするための制度があります。そうした土台がどうあるべきかを考えることができるところが、一番の志望動機です。実際に入省してみて、制度設計といってもやることは本当に幅広いんだなと改めて思います。どう制度設計をしていくか、経験豊富な先輩から学べることは多く、今後も日々勉強しながら仕事をしたいと思います。
|
| ◇ 採用後の経歴は? |
採用からこれまで、異動が4度ありました。これまで関わった主な仕事は、エレベーターの定期検査項目の見直し、都市計画の土地利用規制制度の見直し、全国の公営住宅関係予算の確保などです。いずれも、地方公共団体がそういった法令や予算を運用して初めて形になるので、関わった仕事が形になるまでは時間がかかりますが、こうした制度設計に技術職として関わることができるのが、建築職の良い点だと思います。
|
| ◇ 日々の仕事の様子は? |
本省では、例えば公営住宅の予算確保について、地方公共団体との意見交換、各種調査を行い、将来どれくらいの予算が必要になるのか、民間活用をもっと進められないか、といった検討を行い、次年度の予算について財務省に要求する、といった仕事をしていました。令和3年度からは、地方整備局へ出向し、そうした予算の地方公共団体への配分などを行っているほか、地方勤務のメリットを生かし、実際の事業を積極的に現地で見て、デスクワークに終始しないよう心がけています。
|
| ◇ 専門性はどのように活かされていますか? |
建築計画、構造、設備等の専門知識は、業務上必要だと感じます。例えば業務上よく読む建築基準法やその関係規定は、専門用語のオンパレードですが、大学ではそれらを掘り下げて勉強しますよね。(正確にそれらを覚えているかは別として・・・)そういった経験をしていることが、業務を円滑に進める上で非常に役に立っていると感じます。
|
| ◇ 仕事の面白み、やり甲斐は? |
異動が非常に多い(1~2年に1度)ですが、そこが面白みでもあります。異動直後は、必ずといっていいほど、すごく勉強します。慣れた頃にはまた異動、というのを繰り返すことになりますが、多くの部署を経験することで多くの知見を得ることができ、住宅・建築分野に広く関われていることが実感できるので、非常にやり甲斐があります。
|
| ◇ 自己の成長を実感したエピソードは? |
あるポストにいたとき、異動に際して、仕事で毎週のように会っていた関係団体の重役の方から、「すごく成長したね」と言ってもらったことがあります。そのポストでは、関係団体に対して、時に厳しい依頼や指導をすることも必要で、異動したばかりの頃は、上からの指示を伝えるだけ、といった事もあったように思います。仕事にも慣れ、異動も近づく頃には、その団体がどういった団体なのか、我々との関係で求めている事は何なのか、といった相手の事も段々と考えることができるようになり、仕事も円滑に進むようになってきたなと感じていました。そんな頃に、そう言って頂けたことがとても嬉しく、相手の事を考えることが重要だと感じることができ、少し成長したなと感じることができました。
|
| ◇ 仕事と生活(家庭、趣味、地域活動など)の両立は? |
休日は家族で出かけることが多く、仕事のリフレッシュにもなります。また、テレワークの時は通勤時間がないため、平日でも夕食を作ったりできます。子供が小さいので、テレワークや休暇の取得等について職場の理解があることが、とてもありがたいです。自らも管理職として、課員のマネジメントにも十分に気を配り、適切な業務遂行ができるよう心がけています。
|
| ◇ 今後関わっていきたい政策課題などは? |
最近は、脱炭素として住宅の省エネ化に関する取組に注目が集まっていますが、これも住宅の「量から質へ」という流れの一環だと思っています。住宅の質を上げることは、住宅政策の大きな役割だと思います。今後は、こうした規制、誘導等の取組にも関わっていきたいです。
|
| (令和3年12月) |
|
|
| |

田篭 幸大  |
国土交通省 北海道開発局 旭川開発建設部 農業計画課
平成26年採用 一般職(化学) |
| |
| ◇ 学生時代の専攻分野は? |
応用生命化学
|
| ◇ 志望動機は? |
生きていくために必要な衣食住の中で、食に大きく関係する農業に携わろうと考えており、日本の耕地の約4分の1を占め、食料供給基地として大きな役割を果たしている北海道であることはもちろん、農業以外の河川、道路、港湾等と北海道を総合的に開発する機関であることに魅力を感じたためです。
|
| ◇ 採用後の経歴は? |
入局当初から現在に至るまで、国自ら行う土地改良事業に関する調査計画に携わっており、主な業務として、将来の地域農業のあるべき姿を描く営農計画の策定や事業が経済的な合理性を有しているか判断するための経済効果の算定を行っています。また、農林水産省が行う政策評価の一環として、事業着工前に行う事前評価、事業実施中に行う期中評価(再評価)、事業実施後に行う事後評価に携わっています。
|
| ◇ 日々の仕事の様子は? |
上記の業務を遂行するために必要な現地調査などによる適切な実態の把握、営農計画の策定に向けた各関係機関との協議調整や農家との意見交換のほか、事業実施後を見据えた先進的な営農技術(リモートセンシングや自動収穫機など)の実演会や講習会への参加を行っています。
|
| ◇ 専門性はどのように活かされていますか? |
大学で学んだ農業薬剤化学、植物栄養学や土壌化学などは、営農計画を策定する際に役に立っています。
|
| ◇ 仕事の面白み、やり甲斐は? |
これまで道内の様々な地域の調査計画に関わってきましたが、調査を進めていくと地域ごとに異なる特徴や考え方、将来像が明らかになってきます。それらの違いを前提とした整備構想を練り上げて事業計画を作っていくのですが、事業によって地域農業が何を目指すのか、整備が進むと農業生産がどう変わっていくのかに触れることができるのは面白いですし、やり甲斐を感じています。
|
| ◇ 自己の成長を実感したエピソードは? |
まだまだ若輩者ですが、各関係機関との打合せにおいて、自分の説明が先方に理解され、納得し、了解を得られた時です。
また、受益農家の営農上の課題を伺い、解決に向けた土地改良事業の整備構想を説明し、事業計画として位置付けたことを喜んでいただいたことです。
|
| ◇ 仕事と生活(家庭、趣味、地域活動など)の両立は? |
ワークライフバランスに取り組んでおり、両立はしやすい環境だと思います。
やむを得ず残業することはありますが、組織的に業務を行っているため、有給休暇も取りやすく、福岡県出身の私も年末年始などには帰省しており、北海道総合開発計画でも「世界の北海道」として、「食」と「観光」を戦略的産業として位置付けているため、交通の便もさらに良くなるものと考えています。
また、最近はテレワークにも取り組んでおり、よりフレキシブルに業務を行える環境となっています。
|
| ◇ 今後関わっていきたい政策課題などは? |
農業従事者の減少、所有者不明農地の増加、農地の粗放化、食料自給率・食料自給力の低下等、日本農業の課題から持続可能な開発目標などの世界的な課題まで、様々あります。しかし、どんなに素晴らしい政策でも正しく実行し、適切に情報発信を行い、その内容が正しく伝わらなければ評価されないと考えていますので、微力でもその一助となるような業務に携われればと考えています。
|
| (令和3年12月) |
|
|
| |

伊藤 充  |
国土交通省 北海道開発局 農業水産部 農業設計課
平成28年採用 一般職(農業農村工学) |
| |
| ◇ 学生時代の専攻分野は? |
農業土木
|
| ◇ 志望動機は? |
北海道での就職を考えており、大学時代にアルバイト等で農家の方々にお世話になった機会が多く、その方々のために役に立てる職に就きたいと考えていたため、北海道で大規模な農業農村整備事業を実施している北海道開発局を志望しました。
|
| ◇ 採用後の経歴は? |
1~2年目は、事業実施のための地区調査に携わりました。
3~5年目は、平成30年北海道胆振東部地震で被災した厚真町の農業水利施設の災害復旧事業を担当しました。
現在は、工事に係る各種基準の改訂、工事費用を計算するシステム等の各種システムを使いやすくする業務等を担当しています。
|
| ◇ 日々の仕事の様子は? |
現在は、工事費用を計算するシステムの改訂業務を担当しています。毎年改訂される工事に関する基準をもとにシステムを改訂するだけでなく、職員からの要望やこれまで自分が使用してきた経験を踏まえてシステム改良を行っています。
関係課やSEと内容を相談しながら日々の業務に当たっています。
|
| ◇ 専門性はどのように活かされていますか? |
技術系職員として、大学で学んだ専門知識が役に立つと感じることは、多々あります。工事担当の際は、工事車両が走行する地盤の安定性確認やコンクリート構造物の現場監督等において、大学で学んだ構造力学、材料力学や土質力学等の基礎知識が役に立ちました。
現在の職場でも、各種基準の改訂内容検討の際に、専門知識を活用して取り組んでいますが、大学で専門的に学んでいない分野や知識が不足することもあるため、専門書を読んだり、上司に教えて貰いながら、日々取り組んでいます。
|
| ◇ 仕事の面白み、やり甲斐は? |
毎日新しい知識を吸収しレベルアップすること、覚えることは沢山ありますが、逆に成長する喜び・面白さがあり、覚えたことを発揮して仕事がスムーズに進んだときにやり甲斐を感じます。
また、様々な業務に携わっていますが、大きな目的である農業の持続的な発展のために仕事をしているので、農家や地域住民の方々から感謝されたときは仕事をやってきて良かったなと感じます。
|
| ◇ 自己の成長を実感したエピソードは? |
工事を担当している事務所に初めて配属されたときに、胆振東部地震を経験しました。工事担当1年目で何もわからないまま、災害復旧工事に携わりましたが、うまく対応できないことが多々あり、悔しい経験をしました。そこから3年経過し、異動前に地元担当者へ挨拶に行った際に「最後まで残ってほしかった」と言われたときには3年間の頑張りが認められた気がしました。
|
| ◇ 仕事と生活(家庭、趣味、地域活動など)の両立は? |
災害や突発的な事故が発生した際の対応など、必要な残業はあります。そうでないときは定時で帰ってのんびり過ごしたり、職場の同僚や知人と過ごしたりして、仕事のオン・オフをきっちり分けています。北海道ということもあり、冬にはスキーに行き、北海道の長い冬を満喫しています。
|
| ◇ 今後関わっていきたい政策課題などは? |
北海道は日本の食料供給基地としての役割を期待され、北海道農業は高い競争力と潜在力を持っていると思います。
北海道開発局の農業部門が行う業務は、北海道農業の発展に繋がっており、大学での専門知識やこれまでの経験を活かし、できるだけ多くのものに触れ、幅広い仕事ができるようになっていきたいと思います。
|
| (令和3年12月) |
|
|
| |

小杉 恵  |
国土交通省 近畿地方整備局紀伊山系砂防事務所調査課長
平成27年採用 総合職(森林・自然環境) |
| |
| ◇ 学生時代の専攻分野は? |
森林科学(砂防)
|
| ◇ 志望動機は? |
学生時代に土砂災害の被災現場(2011年紀伊半島大水害、2013年伊豆大島、2014年広島災害)に行く機会がありました。一瞬にして人命・財産に大きなダメージを与える土砂災害の恐ろしさを実感するとともに、砂防堰堤など施設整備の重要性や警戒避難のありかたを考えさせられました。土砂災害から一人でも多くの人々の「いのち」と「くらし」を守る仕事をしたい、と感じた瞬間でした。
日本国内だけでなく、世界をもフィールドとして土砂災害対策に携わりたいと思い、国家公務員総合職を志望しました。
|
| ◇ 採用後の経歴は? |
1年目:地方の事務所(長野県駒ヶ根市)係員。主に河川事業の調査・設計に携わりました。
2~3年目:新潟県へ出向。地すべり・急傾斜地・雪崩対策のほか、土砂災害防止法に基づく基礎調査などに携わりました。
4~5年目:林野庁へ出向。民有林における直轄治山事業に携わりました。
6年目:本省係長。財務省への予算要求などを担当しました。
7年目~:地方の事務所課長。紀伊半島大水害後の復興事業に携わっています。
|
| ◇ 日々の仕事の様子は? |
紀伊半島大水害(2011年)の被災地での直轄砂防事業を管轄する紀伊山系砂防事務所で、今後の計画の策定や、計画に基づく施設の測量・設計などに取り組んでいます。これまでの施設の整備状況とその効果、これからの施設の整備計画とその効果をとりまとめていく中で、気候変動の影響や住まい方の変化なども踏まえる必要があり、なかなか一筋縄ではいかない・・・と思わされる日々ですが、砂防事業を通して今後の国づくりに携われる喜びや楽しみを感じています。
従来の技術だけでなく、無人化施工や自動化施工、UAVの自律飛行による調査・点検など、DXを積極的に導入して作業をより迅速化・効率化することで、地域社会の安全・安心を早期に確保できるよう取り組みを進めています。砂防の現場は急峻な山々に囲まれるなど、厳しい条件であるからこそ、DXの導入効果も大きく、また見えやすいと感じています。
今後も先人から受け継がれた砂防技術にDXを組み合わせながら、土砂災害から人々の「いのち」と「くらし」を守る土砂災害対策をさらに推進していきます。
|
| ◇ 仕事の面白み、やり甲斐は? |
本省だけでなく地方事務所、研究所など、様々なフィールドでの仕事を経験しながらキャリアアップしていけることが、国家公務員総合職の面白みであると感じています。様々な立場から物事を見ることで、施策・事業のあるべき姿を考え、それを少しずつ形にしていければと思っています。
|
| ◇ 仕事と生活(家庭、趣味、地域活動など)の両立は? |
2~3年に一度は異動があり、新たな土地で新たなお気に入りスポット(居酒屋・ドライブコース・温泉など)を開拓していけることがとても楽しいです。特に、休日に管内を車で走り回ることでよいリフレッシュになると同時に、関係市町村の位置関係や町の様子を知り、関係県や市町村の方と話をする際にも1つの話題とすることができたときには、趣味が仕事にも活きていると実感しています。
|
| (令和3年8月) |
|
|
|