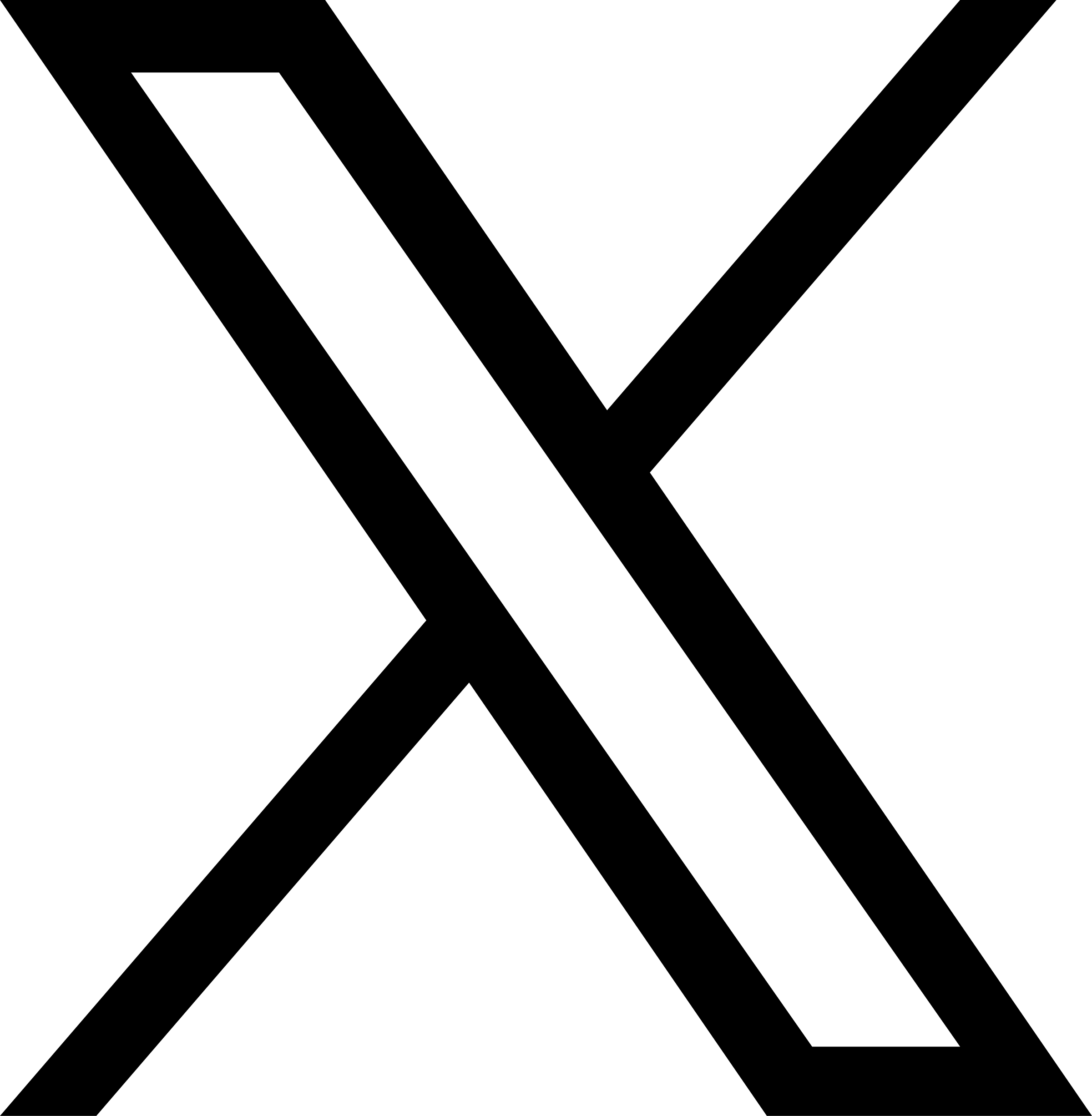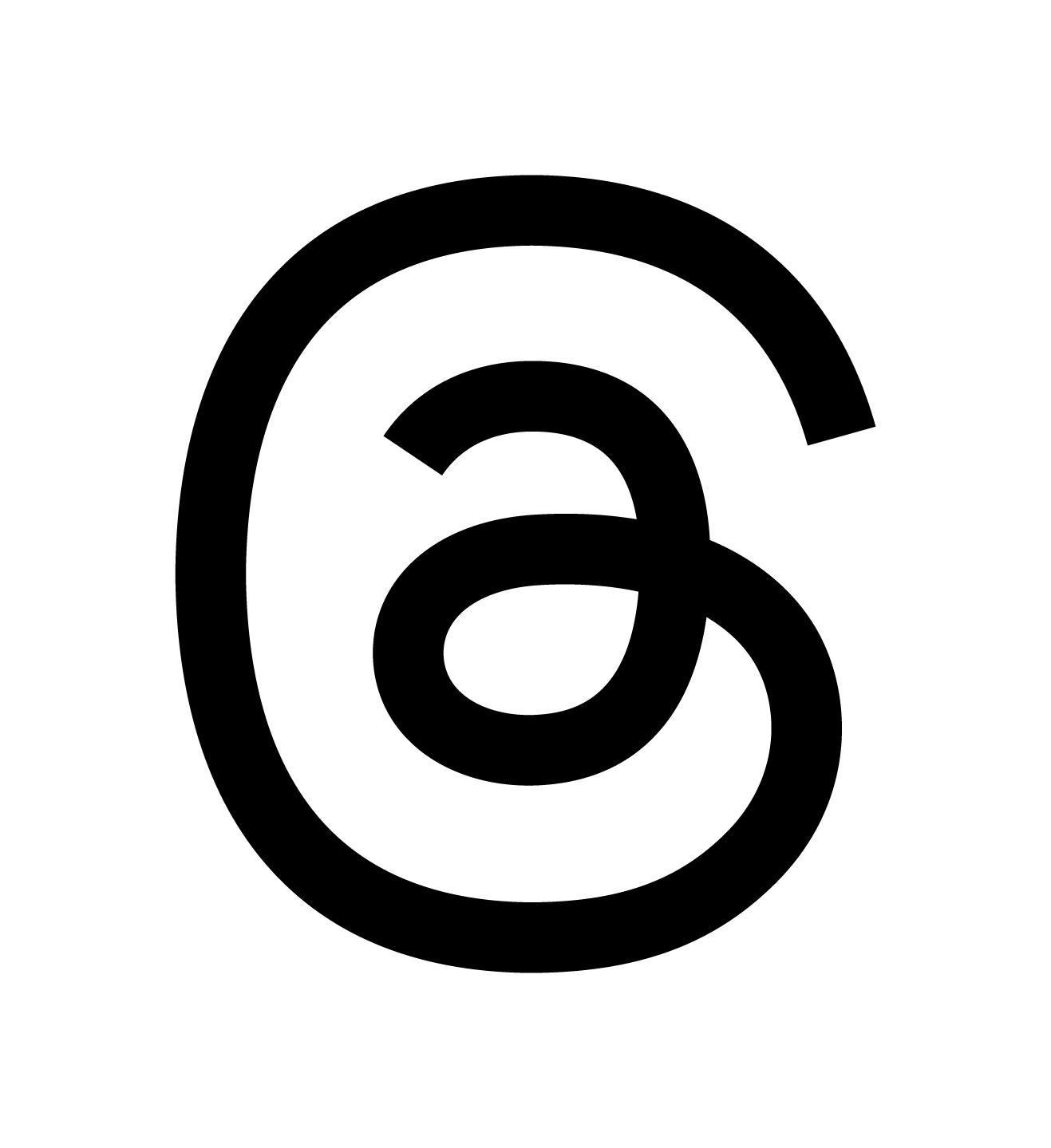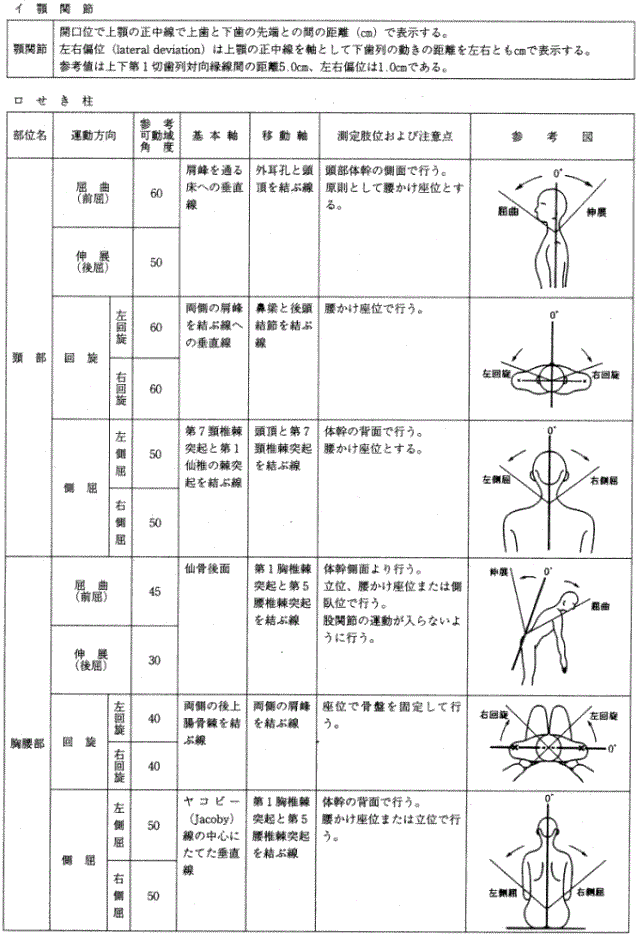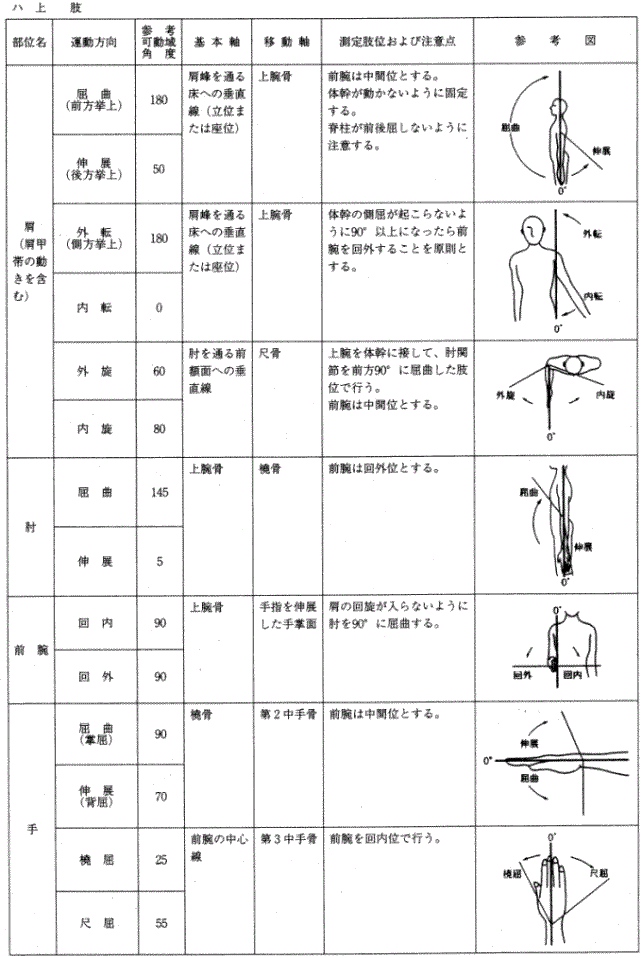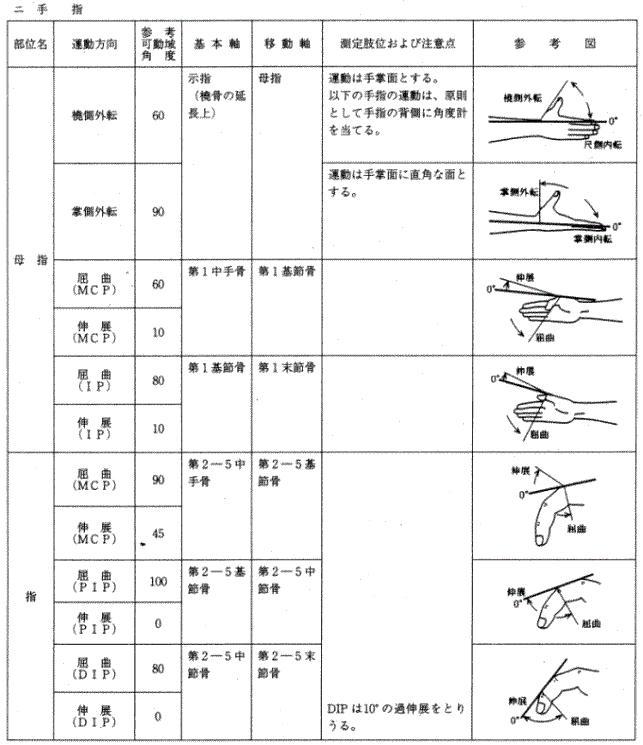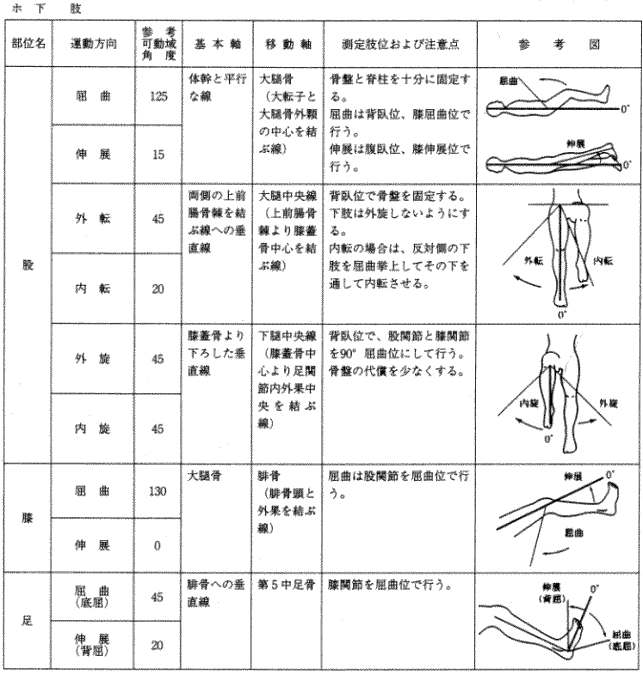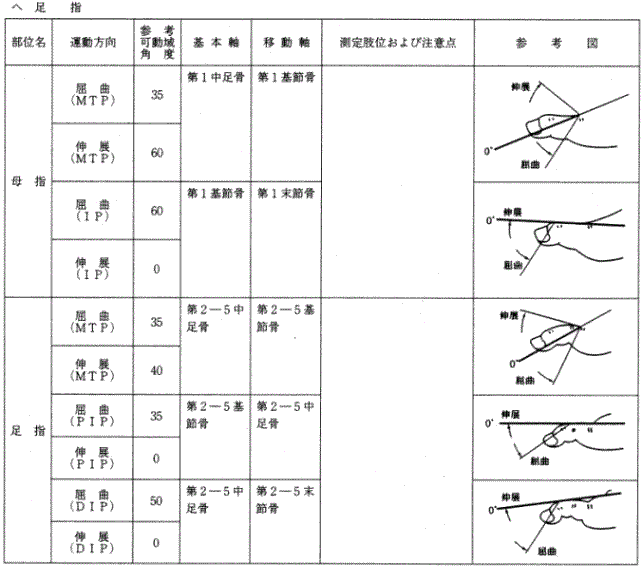障害等級の決定について
(昭和51年8月30日職補―557)
(人事院事務総局職員局長発)
最終改正:平成23年2月15日職補―45
今般、災害補償制度の運用について(昭和48年11月1日職厚―905人事院事務総長。以下、「運用通達」という。)の記の第10障害補償関係の全部が改正されましたが、障害等級の決定の細目等については、下記によつてください。
記
第1 運用通達の意義等
1 運用通達記の第10の1関係
(1) 障害等級の決定は、原則として「治ったとき」に行うものであるが、療養の効果を期待し得ない状態(以下「療養の終了」という。)となつた場合において、なお、残存する症状が自然的経過によつて到達すると認められる最終の状態(以下「症状の固定」という。)に至るまで相当長期間を要すると見込まれるときは、医学上妥当と認められる期間を待って障害等級を決定するものとし、6か月以内の期間において症状の固定の見込みが認められないものにあつては、療養の終了時において、将来固定すると認められる症状によつて等級を決定するものとする。
(2) (3)の「序列に服する」とは、例えば、次のような場合が該当する。
ア 併合して等級を決定すると、障害の序列を乱すことになるため、別途、障害の序列に従つて等級を決定する場合
(例) 「1上肢を手関節以上で失い」(第5級第4号)、かつ、「他の上肢をひじ関節以上で失つた」(第4級第4号)場合には、併合繰り上げすると第1級となるが、当該障害は「両上肢をひじ関節以上で失つたもの」(第1級第5号)の障害の程度には達しないので第2級とする。
イ 併合の方法を用いて準用等級を決定すると、障害の序列を乱すことになるため、別途、障害の序列に従い、直近上位又は直近下位の等級に決定する場合
(例1) 直近上位の等級に決定する場合
1手の「中指の用を廃し」(第12級第10号)、かつ、同1手の「小指を失った」(第12級第9号)場合には、併合の方法を用いると第11級となるが、当該障害は「1手の母指以外の2の手指の用を廃したもの」(第10級第7号)より重く、「1手の母指以外の2の手指を失ったもの」(第9級第12号)より軽いので、第10級とする。
(例2) 直近下位の等級に決定する場合
「1上肢の3大関節中の2関節の用を廃し」(第6級第6号)、かつ、「他の1関節の機能に著しい障害を残した」(第10級第10号)場合には、併合の方法を用いると第5級となるが、「1上肢の用を廃した」(第5級第6号)障害の程度には達しないので直近下位の第6級とする。
ウ 併合等級又は準用級を定める場合において、欠損障害は、労働能力の完全喪失であつて同一部位に係る最上位の等級として評価されるため、同一部位に欠損障害以外のいかなる障害(両上肢又は両下肢の機能の全廃を除く。)を残したとしても、その程度は欠損障害の程度に達することはないものとして取り扱う場合
(例) 「右手の5の手指を失い」(第6級第8号)、かつ、「右上肢の3大関節中の1関節(手関節)の用を廃した」(第8級第6号)場合には、併合の方法を用いると準用等級第4級となるが、「1上肢を手関節以上で失つたもの」(第5級第4号)には達しないので、その直近下位の第6級とする。
2 運用通達記の第10の2関係
(1) (1)には、次のような場合が該当する。
(例) 「臭覚脱失」等の鼻の機能障害、「味覚脱失」等の口腔の障害は、神経障害そのものではないが、全体としては神経障害に近い障害とみなされているところから、一般の神経障害の等級として定められている「局部に頑固な神経症状を残すもの」(第12級第13号)を準用して準用等級第12級と決定する場合
(2) (2)には、次のような場合が該当する。
(例) 「1上肢の3大関節中の1関節(手関節)の用を廃し」(第8級第6号)、かつ、「同上肢の他の1関節(ひじ関節)の機能に著しい障害を残した」(第10級第10号)場合に、併合の方法を用いて準用等級第7級と決定する場合
なお、運用通達記の第10の1の(3)の後段の規定により、「同一の系列に属する障害」として取り扱うこととされる場合において、系列区分に応じた部位別に2以上の障害を残し、それらが運用通達記の第10の2の(1)から(4)までのいずれかに該当するものであるときは、各系列区分ごとに準用等級を定めた上、当該複数の準用等級について併合の方法を用いて、最終的な準用等級を決定するものとする。
(3) (3)には、次のような場合が該当する。
(例) 1上肢に全面積の2分の1程度を超える醜状を残した場合に、「外貌に醜状を残すもの」(第12級第14号)に相当するものとして、準用等級第12級と決定する場合
(4) (4)には、次のような場合が該当する。
(例) 「1下肢を足関節以上で失い」(第5級第5号)、「同下肢の大腿骨に偽関節を残し」(第7級第10号)及び「1眼の視力が0.1以下になった」(第10級第1号)場合に、まず同一下肢の欠損障害と変形障害とを準用して、下肢の準用等級を定め(併合の方法によると第3級となるが、「1下肢をひざ関節以上で失ったもの」(第4級第5号)には達しないので準用等級第5級とする。)、これと視力障害(第10級)とにより併合等級第4級と決定する場合
(5) 併合の方法を用いて準用等級を決定した場合には、補償法第13条第7項の規定の例によることはないものとする。
3 運用通達記の第10の3関係
(1) (1)の「なお書」には、次のような場合が該当する。
(例) 「大腿骨に変形を残した」(第12級第8号)ため、「同一下肢を1センチメートル短縮した」(第13級第9号)場合に、上位の等級である第12級をもつて当該障害の等級と決定する場合
(2) (2)の「組合せ等級に該当する場合」には、次のような場合が該当する。
(例) 「1上肢をひじ関節以上で失い」(第4級第4号)、かつ、「他の上肢をひじ関節以上で失つた」(第4級第4号)場合に、併合繰上げを行うことなく「両上肢をひじ関節以上で失つたもの」(第1級第5号)に該当するものとして第1級に決定する場合
(3) (3)の「通常派生する関係にある場合」には、次のような場合が該当する。
(例) 「1下肢に偽関節を残し、著しい障害を残す」(第7級第10号)とともに、当該箇所に「頑固な神経症状を残した」(第12級第13号)場合に、上位の等級である第7級をもつて当該障害の等級と決定する場合
(4) (4)には、次のような場合が該当する。
(例) 「1上肢を手関節以上で失い」(第5級第4号)、「両眼の視力が0.1以下になり」(第6級第1号)及び「1下肢に偽関節を残した」(第8級第9号)場合に、第5級と第6級を併合繰上げして併合等級第3級と決定する場合
4 運用通達記の第10の4関係
(1) 既存の障害が公務又は通勤によるものであつて、現に障害補償年金が支給されている場合において、当該障害を公務又は通勤により加重したときは、既存障害及び加重後の障害に対し、それぞれ障害補償年金が支給されるものであること。
(2) (2)の「同一系列の範囲内に属するもの」とは、原則として、障害系列表に掲げる1から35までの系列区分に対応する身体の部位を指すものであるが、異なる系列に属する障害であつても、運用通達記の第10の1の(3)又は第10の2において、1の障害として評価すべきものとされているものにあつては、これを「同一部位」に該当するものとして取り扱う。
(3) (2)のアには、次のような場合が該当する。
(例) 既に「1足の足指の全部を失つていた」(第8級第10号、503日分の一時金)者が、新たに「他の足指の全部を失つた場合」に、「両足の足指の全部を失つたもの」(第5級第8号、184日分の年金)に該当するものとして、第5級に決定し、規則16―0第26条の規定により、184日分から503日分の25分の1を控除して163.88日分の障害補償年金を支給する場合
(4) (2)のイには、次のような場合が該当する。
(例) 「1上肢の手関節及びひじ関節の用を廃していた」(第6級第6号、156日分の年金)者が、新たに「同一上肢をひじ関節以上で失つた場合」(第4級第4号、213日分の年金)に、57日分の障害補償年金を支給する場合
(5) (3)には、次のような場合が該当する。
(例) 「1上肢に偽関節を残し」(第8級第8号)、かつ「両眼の視力が0.1以下になつていた」(第6級第1号)者が、「両眼の視力が0.06以下になつた」(第4級第1号、213日分の年金)場合に、視力障害を加重したものとして取り扱い、第4級(213日分)と第6級(156日分)の差額57日分を障害補償年金として支給する場合
(6) (4)には、次のような場合が該当する。
既に、「1下肢を1センチメートル短縮していた」(第13級第9号)者が、新たに「同一下肢を3センチメートル短縮」(第10級第8号)し、かつ、「1手の小指を失つた」(第12級第9号)場合に、同一部位の加重後の障害(第10級)と他の部位の新たな障害(第12級)を併合して、第9級と決定し、第9級(391日分)と第13級(101日分)との差額290日分を障害補償一時金として支給する場合
(7) (5)の「新たな障害」とは、次に掲げる障害をいう。
ア 既に障害を有している手指若しくは足指又は相対性器官に障害を加重した場合における、当該新たに生じた障害
イ 同一部位を加重するとともに、他部位に新たな障害を残した場合における、当該他部位について生じた新たな障害
ウ 他部位に新たな障害を残した結果、組合わせ等級に該当することとなつた場合における、当該他部位について生じた新たな障害
(8) (5)による「職員の有利な方による障害補償の額」は、次に掲げる額のうち、最も高いものとなる。
ア 加重障害として、規則16―0第26条の規定による控除計算を行つた場合の額
イ 上記(7)のアの障害に係る額
ウ 上記(7)のイ又はウの障害に係る額
(例1) 「1手の示指を失つていた」(第11級第8号)者が、新たに「同一手の環指を失つた」(第11級第8号)場合、現存する障害は「1手の母指以外の2の手指を失つたもの」(第9級第12号)に該当するが、現存する障害の障害補償の額(第9級、391日分の一時金)から既存の障害補償の額(第11級、223日分の一時金)を差し引くと、障害補償の額は168日分となり、新たな障害(第11級、223日分の一時金)のみが生じた場合の障害補償の額より少なくなるので、上記イにより、新たな障害のみが生じたものとみなして223日分の障害補償一時金を支給する。
(例2) 「1手の中指、環指及び小指の用を廃していた」(第9級第13号)者が、「新たに同一手の小指を失つた」(第12級第9号)場合、現存する障害は「1手の母指以外の3の手指を失つた」(第8級第3号)程度に達しないので第9級となり、支給すべき補償額は0となるが、新たに障害が生じた小指について着目すると、現存する障害(第12級第9号)の障害補償の額(156日分の一時金)から「1手の小指の用を廃したもの」(第13級第7号)という既存障害の障害補償の額(101日分の一時金)を差し引くと補償額が55日分となるので、上記イにより小指の加重障害として、55日分の障害補償一時金を支給する。
(例3) 「1上肢を手関節以上で失つていた」(第5級第4号)者が、新たに「他の上肢を手関節以上で失つた」場合、現存する障害は組合せ等級により「両上肢を手関節以上で失つたもの」(第2級第5号)に当たり、第2級(277日分の年金)から第5級(184日分の年金)を差し引くと93日分の年金となるが、新たな障害(第5級第4号、184日分の年金)のみが生じたものとして取り扱つた方が有利であるので、上記ウにより、第5級として184日分の障害補償年金を支給する。
(例4) 「1下肢の足関節の機能に障害を残していた」(第12級第7号)者が、「当該足関節に著しい機能障害を残す」(第10級第11号)とともに、新たに、「1眼の視力を0.06以下に減じた」(第9級第2号)場合は、加重後の障害等級は第8級となり、第8級(503日分の一時金)から第12級(156日分の一時金)を差し引くと347日分の一時金となるが、新たに「1眼の障害」(第9級第2号、391日分の一時金)のみが生じたものとして取り扱つた方が有利であるので、上記ウにより、第9級として391日分の障害補償一時金を支給する。
(9) (5)の「ただし書」には、次のような場合が該当する。
(例) 「1眼の視力が0.6以下であつた」(第13級第1号)者が、新たに「他眼を失明した」(第8級第1号)場合、現存する障害は「1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になつたもの」(第7級第1号)に当たるので、新たな障害のみに係る第8級の503日分の一時金を支給することなく、加重後の障害等級第7級の131日分の年金から第13級の101日分を25で除して得た額を差し引いた額の障害補償年金を支給する場合
第2 部位別障害等級決定の取扱い細目等
Ⅰ 眼(眼球及びまぶた)の障害
1 障害の等級及び程度
(1) 眼の障害について、規則16―0別表第5(以下「規則別表第5」という。)に定める障害の等級及び程度は次のとおりである。
ア 眼球の障害
(ア) 視力障害(系列区分1)
第1級第1号 両眼が失明したもの
第2級第1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になつたもの
第2級第2号 両眼の視力が0.02以下になつたもの
第3級第1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になつたもの
第4級第1号 両眼の視力が0.06以下になつたもの
第5級第1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になつたもの
第6級第1号 両眼の視力が0.1以下になつたもの
第7級第1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になつたもの
第8級第1号 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になつたもの
第9級第1号 両眼の視力が0.6以下になつたもの
第9級第2号 1眼の視力が0.06以下になつたもの
第10級第1号 1眼の視力が0.1以下になつたもの
第13級第1号 1眼の視力が0.6以下になつたもの
(イ) 調節機能障害(系列区分2)
第11級第1号 両眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの
第12級第1号 一眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの
(ウ) 運動障害(系列区分3)
第10級第2号 正面視で複視を残すもの
第11級第1号 両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの
第12級第1号 1眼の眼球に著しい運動障害を残すもの
第13級第2号 正面視以外で複視を残すもの
(エ) 視野障害(系列区分4)
第9級第3号 両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの
第13級第3号 1眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの
イ まぶたの障害
(ア) 欠損障害(系列区分5・6)
第9級第4号 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
第11級第3号 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
第13級第4号 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの
第14級第1号 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの
(イ) 運動障害(系列区分5・6)
第11級第2号 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
第12級第2号 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
(2) 規則別表第5に定められていない眼の障害については、規則16―0第25条の4第2項の規定により、その障害の程度に応じて、規則別表第5に定める他の障害に準じて等級を決定するものとする。
2 障害等級決定の基準
(1) 眼球の障害
ア 視力障害
(ア) 視力の測定は、原則として、万国式試視力表による。
(イ) 「視力」とは、矯正視力(眼鏡、医学的に装用可能なコンタクトレンズ又は眼内レンズにより矯正した視力)をいう。
ただし、矯正が不能な場合は、裸眼視力とする。
(ウ) 矯正視力の測定に当たっては、次による。
a 角膜の不正乱視が認められず、かつ、眼鏡による完全矯正を行っても不等像視を生じない者については、眼鏡により矯正した視力を測定する。
b a以外の者であつて、コンタクトレンズの装用が医学的に可能と認められ、かつ、コンタクトレンズによる矯正を行うことにより良好な視力が得られるものについては、コンタクトレンズにより矯正した視力を測定する。
なお、コンタクトレンズの装用が医学的に可能と認められるものは、1日に8時間以上の連続装用が可能である場合とし、コンタクトレンズの装用の可否及び視力の測定は、コンタクトレンズを医師の管理下で3か月間試行的に装用した後に行う。
c a以外の者であって、コンタクトレンズの装用が医学的に不能なものについては、眼鏡により矯正した視力(不等像視を生ずる者にあっては、眼鏡矯正の程度を調整して不等像視の出現を回避し得る視力)を測定する。
(エ) 「失明」とは、眼球を亡失(摘出)したもの、明暗を弁じ得ないもの及びようやく明暗を弁ずることができる程度の視力(光覚弁(明暗弁)又は手動弁)のものをいう。
「光覚弁(明暗弁)」とは、暗室にて被検者の眼前で照明を点滅させ、明暗を弁別できる視力をいい、「手動弁」とは、検者の手掌を被検者の眼前で上下左右に動かし、動きの方向を弁別できる視力をいう。
(オ) 両眼の視力障害については、規則別表第5に掲げている両眼の視力障害の該当する等級をもって決定するものとし、1眼ごとの等級を定め併合繰上げの方法を用いて準用等級を定める取扱いは行わないものとする。
ただし、両眼の視力障害の該当する等級よりも、いずれか1眼の視力障害の該当する等級が上位である場合は、その1眼のみに障害があるものとみなして、等級を決定するものとする。
(例) 「右眼の視力が0.02となり」(第8級第1号)、かつ、「左眼の視力が0.2となつた」(第13級第1号)場合は、両眼を対象とすると第9級第1号(両眼の視力が0.6以下になつたもの)に該当するが、右眼のみを対象とすると第8級となるので、この場合は第8級に決定する。
イ 調節機能障害
(ア) 「眼球に著しい調節機能障害を残すもの」とは、調節力が2分の1以下になったものをいう。
調節力とは、明視できる遠点から近点までの距離的な範囲をレンズに換算した値(単位はジオプトリー(D))であり、これは年齢とともに衰えるものである。
(イ) 被災した眼が1眼のみであって、他眼の調節力に異常がない場合は、当該他眼の調節力との比較により行う。
(ウ) 両眼が被災した場合及び被災した眼は1眼のみであるが他眼の調節力に異常が認められる場合は、年齢別の調節力を示す次表の調節力値との比較により行う。
なお、年齢は、治癒時における年齢とする。
年齢別の調節力表
| 年齢(歳) |
15~19 | 20~24 | 25~29 | 30~34 | 35~39 | 40~44 | 45~49 | 50~54 | 55~59 | 60~64 | 65~69 |
| 調節力(D) | 9.7 |
9.0 |
7.6 |
6.3 |
5.3 |
4.4 |
3.1 |
2.2 |
1.5 |
1.35 |
1.3 |
(エ) (イ)の場合であって、被災していない眼の調節力が1.5D以下であるときは、実質的な調節の機能は失われていると認められるので、障害補償の対象としないものとする。
また、(ウ)の場合であって、年齢が55歳以上であるときは、障害補償の対象とはしないものとする。
ウ 運動障害
(ア) 「眼球に著しい運動障害を残すもの」とは、眼球の注視野の広さが2分の1以下になったものをいう。
(注) 眼球の運動は、各眼3対、すなわち6つの外眼筋の作用によって行われる。この6つの筋は、一定の緊張を保っていて、眼球を正常の位置に保たせるものであるから、もし、眼筋の1個あるいは数個が麻痺した場合は、眼球はその筋の働く反対の方向に偏位し(麻痺性斜視)、麻痺した筋の働くべき方向において、眼球の運動が制限されることとなる。
なお、注視野とは、頭部を固定し、眼球を運動させて直視できる範囲をいう。注視野の広さは相当の個人差があるが、多数人の平均で、単眼視では各方面約50度、両眼視では各方面約45度である。
(イ) 複視
「複視」とは、右眼と左眼の網膜の対応点に外界の像が結像せずにずれているため、ものが二重に見える状態であり、麻痺した眼筋によって複視が生ずる方向が異なるものである。
a 「複視を残すもの」とは、次のいずれにも該当するものをいう。
(a) 本人が複視のあることを自覚していること
(b) 眼筋の麻痺等複視を残す明らかな原因が認められること
(c) ヘススクリーンテストにより、患側の像が水平方向又は垂直の目盛りで5度以上離れた位置にあることが確認されること
b 「正面視で複視を残すもの」とは、ヘススクリーンテストにより正面視で複視が中心の位置にあることが確認されたものをいい、「正面視以外で複視を残すもの」とは、前記以外のものをいう。
(注1) 「ヘススクリーンテスト」とは、指標を赤緑ガラスで見たときの片眼の赤像、他眼の緑像から両眼の位置ずれを評価する検査方法であり、例えば、右外転神経麻痺の場合、右眼に赤ガラスを通して固視させると、左眼に緑ガラスを通して見た点は右方へ大きくずれるが、左眼に赤ガラスを通じて固視させると、右眼に緑ガラスを通して見た点は交叉性に小さくずれることとなる。
(注2) 複視を残す場合、併せて頭痛等の神経症状を残すことが多いが、これらは複視によって派生的に生じているものであり、症状としても複視とは別途に独立して評価する必要はない程度のものである。
また、複視の原因である眼筋の麻痺等は、「眼球の著しい運動障害」である注視野の減少の原因でもあり、「眼球の著しい運動障害」に該当する眼筋の麻痺等がある場合には、通常複視をも残すこととなる。
(注3) 複視には、単眼性(1眼のもの)複視があり、単眼性複視とは、水晶体亜脱臼、眼内レンズ偏位等によって生ずるもので、眼球の運動障害により生ずるものではないので、視力障害として評価すべきものである。
エ 視野障害
(ア) 視野の測定は、ゴールドマン型視野計による。
(イ) 「視野」とは、眼前の一点をみつめていて、同時に見得る外界の広さをいう。
なお、日本人の視野平均値は、次表のとおりとされている。
| 方向 視標 |
上 |
上外 |
外 |
外下 |
下 |
下内 |
内 |
内上 |
| V/4 |
60 (55~65) |
75 (70~80) |
95 (90~100) |
80 (75~85) |
70 (65~75) |
60 (50~70) |
60 (50~70) |
60 (50~70) |
(ウ) 「半盲症」、「視野狭さく」及び「視野変状」とは、V/4視標による8方向の視野の角度の合計が、正常視野の角度の合計の60%以下になった場合をいう。
なお、暗点は絶対暗点を採用し、比較暗点(V/4指標では検出できないが、より暗い又はより小さな視標では検出される暗点をいう。)は採用しないものとする。
(2) まぶたの障害
ア 欠損障害
(ア) 「まぶたに著しい欠損を残すもの」とは、閉瞼時(普通にまぶたを閉じた場合)に、角膜を完全におおい得ない程度のものをいう。
(イ) 「まぶたの一部に欠損を残すもの」とは、閉瞼時に角膜を完全におおうことができるが、眼球結膜(しろめ)が露出している程度のものをいう。
(ウ) 「まつげはげを残すもの」とは、まつげ縁(まつげのはえている周縁)の2分の1以上にわたってまつげのはげを残すものをいう。
イ 運動障害
「まぶたに著しい運動障害を残すもの」とは、開瞼時(普通に開瞼した場合)に瞳孔領を完全におおうもの(例えばまぶたの下垂れ)又は閉瞼時に角膜を完全におおい得ないもの(例えば兎眼)をいう。
3 併合等の取扱い
(1) 併合
ア 両眼球の視力障害、運動障害、調節機能障害、視野障害の各相互間は、同一の系列に属するものとして取り扱われるので、併合の取扱いはしないものとする。
イ 左右のまぶたに障害を残した場合(組合せ等級に該当する場合を除く。)には、併合して等級を決定するものとする。
(例) 「1眼のまぶたに著しい欠損を残し」(第11級第3号)、かつ、「他眼のまぶたに著しい運動障害を残した」(第12級第2号)場合は、併合等級第10級とする。
(2) 準用
ア 同一眼球に、系列区分を異にする2以上の障害を残した場合は、併合の方法を用いて準用等級を定めるものとする。
(例1) 「1眼の視力が0.08となり」(第10級第1号)、かつ、「同眼に著しい運動障害を残した」(第12級第1号)場合は、準用等級第9級とする。
(例2) 「1眼の視力が0.02となり」(第8級第1号)、かつ、「同眼に視野狭さくを残した」(第13級第3号)場合は、併合の方法を用いると準用等級第7級となるが、1眼の障害については「失明」(第8級第1号)が最高等級であるので、序列を考慮し、準用等級第8級とする。
イ 外傷性散瞳等の取扱いについては、次による。
(ア) 1眼の瞳孔の対光反射が著しく障害され、著明な羞明(まぶしさ)を訴え勤務に支障をきたすものは、準用等級第12級とする。
(イ) 1眼の瞳孔の対光反射はあるが不十分であり、羞明を訴え勤務に支障をきたすものは、準用等級第14級とする。
(ウ) 両眼について(ア)に該当するときは準用等級第11級、また、(イ)に該当するときは準用等級第12級とする。
(エ) 外傷性散瞳とともに視力障害又は調節機能障害を残した場合は、併合の方法を用いて準用等級を定めるものとする。
(オ) 眼外傷による変視症については、これが他覚的に証明される場合は、準用等級第14級とする。
(3) 加重
ア 眼については、両眼球を同一部位とするので、次に掲げる場合等は、加重として取り扱うものとする。
(ア) 1眼を失明し、又は1眼の視力を減じていた者が、新たに他眼を失明し、又は他眼の視力を減じた場合
(イ) 両眼の視力を減じていた者が、更に1眼又は両眼の視力を減じ、又は失明した場合
(ウ) 1眼の視力を減じていた者が、更にその視力を減じ、又は失明した場合
(エ) 両眼の眼球に著しい運動障害を残していた者が、更に1眼の視力を減じ、又は失明した場合
イ 「1眼に障害を有していた」者が、新たに他眼に障害を生じた場合において、規則16―0第26条の規定により算定した障害補償の額が、他眼のみに新たな障害が生じたものとした場合の障害補償の額に満たないときは、その新たな障害のみが生じたものとみなして障害補償の額を算定する。
(例) 既に「右眼の視力が0.1となつていた」(第10級第1号、302日分の一時金)者が、新たな障害により「左眼の視力が0.6となつた」(第13級第1号、101日分の一時金)場合、現存する障害は「両眼の視力が0.6以下となつた」(第9級第1号、391日分の一時金)場合に該当するが、この場合の障害補償の額は、左眼の障害のみが生じたものとみなして、第13級の101日分を支給する。
また、「両眼に障害を有していた」者が、その1眼について障害の程度を加重した場合において、規則16―0第26条の規定により算定した障害補償の額が、その1眼に新たな障害のみが生じたものとした場合の障害補償の額に満たないときは、その新たな障害のみが生じたものとみなして障害補償の額を算定する。
(例) 既に「両眼の視力が0.4となつていた」(第9級第1号、391日分の一時金)者が、新たな障害により、「1眼の視力が0.05となつた」(第9級第2号、391日分の一時金)場合、現存する障害は、「両眼の視力が0.6以下となった」(第9級第1号、391日分の一時金)場合に該当することとなるが、この場合の障害補償の額は、その1眼に障害が加重したものとして、第9級(391日分)と第13級(101日分)との差額290日分を支給する。
Ⅱ 耳(内耳等及び耳殻)の障害
1 障害の等級及び程度
(1) 耳の障害について、規則別表第5に定める障害の等級及び程度は次のとおりである。
ア 聴力障害(系列区分7)
(ア) 両耳の障害
第4級第3号 両耳の聴力を全く失つたもの
第6級第3号 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
第6級第4号 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
第7級第2号 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
第7級第3号 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
第9級第7号 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
第9級第8号 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの
第10級第5号 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの
第11級第5号 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
(イ) 1耳の障害
第9級第9号 1耳の聴力を全く失つたもの
第10級第6号 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
第11級第6号 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
第14級第3号 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
イ 耳殻の欠損障害(系列区分8・9)
第12級第4号 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
(2) 規則別表第5に定められていない耳の障害については、規則16―0第25条の4第2項の規定により、その障害の程度に応じて、規則別表第5に定める他の障害に準じて等級を決定するものとする。
2 障害等級決定の基準
(1) 聴力障害
ア 聴力障害については、純音による聴力レベル(以下「純音聴力レベル」といい、デシベル(dB)で表す。)の測定結果及び語音による聴力検査結果(以下「明瞭度」といい、%で示す。)を基礎として、次により障害等級を決定するものとする。
(ア) 両耳の障害
| 規則別表第5に掲げる障害の程度 | 平均純音聴力レベル(dB)及び最高明瞭度(%) |
| 両耳の聴力を全く失つたもの (第4級第3号) |
両耳が90dB以上のもの、又は両耳が80dB以上・30%以下のもの |
| 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの (第6級第3号) | 両耳が80dB以上のもの、又は両耳が50dB以上・30%以下のもの |
| 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの (第6級第4号) |
1耳が90dB以上で、かつ、他耳が70dB以上のもの |
| 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの (第7級第2号) | 両耳が70dB以上のもの、又は両耳が50dB以上・50%以下のもの |
| 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの (第7級第3号) |
1耳が90dB以上で、かつ、他耳が60dB以上のもの |
| 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの (第9級第7号) |
両耳が60dB以上のもの、又は両耳が50dB以上・70%以下のもの |
| 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの (第9級第8号) | 1耳が80dB以上で、かつ、他耳が50dB以上のもの |
| 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの (第10級第5号) | 両耳が50dB以上のもの、又は両耳が40dB以上・70%以下のもの |
| 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの (第11級第5号) |
両耳が40dB以上のもの |
(イ) 1耳の障害
| 規則別表第5に掲げる障害の程度 | 平均純音聴力レベル(dB)及び最高明瞭度(%) |
| 1耳の聴力を全く失つたもの (第9級第9号) |
1耳が90dB以上のもの |
| 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの (第10級第6号) | 1耳が80dB以上のもの |
| 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では、普通の話声を解することができない程度になつたもの (第11級第6号) | 1耳が70dB以上のもの、又は1耳が50dB以上・50%以下のもの |
| 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの (第14級第3号) |
1耳が40dB以上のもの |
イ 両耳の聴力障害については、規則別表第5に掲げている両耳の聴力障害の該当する等級をもつて決定するものとし、1耳ごとの等級を定め併合繰上げの方法を用いて準用等級を定める取扱いは行わないものとする。
ウ 騒音性難聴については、強烈な騒音を発する場所における業務に従事している限り、その症状は漸次進行する傾向が認められるので、等級の決定は、当該職員が強烈な騒音を発する場所における業務を離れたときに行うものとする。
エ 聴力検査は、次により行うものとする。
(ア) 聴力検査の実施時期
a 騒音性難聴
騒音性難聴については、85dB以上の騒音にさらされた日以後7日間は聴力検査を行わないものとする。
b 騒音性難聴以外の難聴
騒音性難聴以外の難聴については、療養効果が期待できることから、療養が終了し症状が固定した後に聴力検査を行うものとする。
(イ) 聴力検査の方法
a 聴力の検査法
聴力検査は、日本聴覚医学会制定の「聴覚検査法(1990)」により行うものとする(語音による聴力検査については、日本聴覚医学会制定の「聴覚検査法(1990)」における語音聴力検査法が制定されるまでの間は、日本オージオロジー学会制定の「標準聴力検査法のⅡの語音による聴力検査」により行うものとし、検査用語音は、57式、67式、57S式又は67S式のいずれかを用いるものとする。)。
b 聴力検査の回数
聴力検査は日を変えて3回行うものとし、オに掲げる場合は、更に行うものとする。
ただし、聴力検査のうち語音による聴力検査の回数は、検査結果が適正と判断できる場合には1回で差し支えないものとする。
c 聴力検査の間隔
検査と検査の間隔は7日程度空ければ足りるものとする。
オ 障害等級の決定に当たって用いる平均純音聴力レベルは、聴力検査の2回目と3回目の測定値の平均(2回目と3回目の平均純音聴力レベルに10dB以上の差がある場合には、更に行った検査も含めた2回目以降の検査の中で、その差が最も小さい2つの平均純音聴力レベル(差は10dB未満とする。)の平均)とする。
カ 平均純音聴力レベルは、周波数が500ヘルツ、1000ヘルツ、2000ヘルツ及び4000ヘルツの音に対する聴力レベルを測定し、6分法(前掲の各ヘルツの音に対する純音聴力レベルを、それぞれA、B、C及びDdBとして、「(A+2B+2C+D)÷6」の式により求める。)により算定するものとする。
(2) 耳殻の欠損障害(「耳殻」については、以下「耳介」という。)
ア 「耳介の大部分の欠損」とは、耳介軟骨部の2分の1以上を欠損したものをいう。
イ 耳介軟骨部の2分の1以上の欠損に達しないものは醜状障害として評価する。
(例) 耳介軟骨部の一部を欠損した場合は、第12級第14号とする。
ウ 耳介の大部分を欠損したものについては、耳介の欠損障害として評価した場合の等級と外貌の醜状障害として評価した場合の等級のうち、いずれか上位の等級によるものとする。
(例) 「耳介の大部分の欠損」は、外貌の著しい醜状障害として、第7級第12号とする。
3 併合等の取扱い
(1) 併合
ア 聴力障害と耳介の欠損障害とを残した場合、それぞれの該当する等級を併合して決定するものとする。
イ 両耳の耳介を欠損した場合には、1耳ごとに等級を定め、これを併合して決定するものとする。
なお、耳介の欠損を醜状障害として評価する場合は、上記イのような1耳ごとの等級を定めこれを併合する取扱いは行わないものとする。
(2) 準用
ア 鼓膜の外傷性穿孔による耳漏は、治癒後に聴力障害が障害等級に該当しない程度のものであつても、常時耳漏があるものは準用等級第12級とし、その他のものについては準用等級第14級とする。また、外傷による外耳道の高度の狭さくで耳漏を伴わないものについては準用等級第14級とする。
イ 難聴に伴い著しい耳鳴が常時あると耳鳴検査によって評価できるものは、準用等級第十二級とする。また、難聴に伴い耳鳴が常時あることが合理的に説明できるものは、準用等級第14級とする。
(ア) 「耳鳴検査」とは、ピッチ・マッチ検査及びラウドネス・バランス検査をいう。
(イ) 「難聴に伴い」とは、公務上の災害と判断された難聴に伴って耳鳴がある場合をいい、聴力が回復した後もなお耳鳴がある場合も含む。
(ウ) 耳鳴検査により耳鳴が存在すると医学的に評価できる場合には、「著しい耳鳴」があるものとして取り扱う。
(エ) 「耳鳴が常時あることが合理的に説明できる」とは、耳鳴の自訴があり、かつ、耳鳴のあることが騒音ばく露歴や音響外傷等から合理的に説明できることをいう。
(オ) 夜間のみ耳鳴の自覚症状を有する場合であっても、昼間は外部の音によって耳鳴が遮へいされるため自覚症状がないと認められるときは、耳鳴が常時あるものとして取り扱う。
ウ 内耳の損傷による平衡機能障害については、神経系統の機能の障害について定められている障害等級決定の基準に準じて等級を定めるものとする。
エ 内耳の機能障害のため、聴力障害と平衡機能障害とを残したものについては、併合の方法を用いて準用等級を定めるものとする。
(3) 加重
ア 耳については、両耳を同一部位とするので、1耳に聴力障害が存する者が、新たに他耳に聴力障害を生じた場合には、加重として取り扱うものとする。
(例) 「1耳の聴力を全く失つていた」(第9級第9号、391日分の一時金)者が、新たに「他耳の聴力を全く失つた」場合は、「両耳の聴力障害」(第4級第3号、213日分の年金)に該当するものとして、第4級に決定し、213日分から391日分の25分の1を控除した額の年金を支給する。
イ 既に両耳の聴力を減じていた者が、1耳について障害の程度を加重した場合において、規則16―0第26条の規定により算定した障害補償の額が、その1耳に新たな障害のみが生じたものとした場合の障害補償の額に満たないときは、その新たな障害のみが生じたものとみなして障害補償の額を算定するものとする。
(例) 既に「両耳の聴力レベルが50dBであつた」(第10級第5号、302日分の一時金)者が、新たな障害により、「1耳の聴力レベルが70dB」(第11級第6号、223日分の一時金)に減じた場合は、「両耳の聴力レベルが50dB以上」(第10級第5号、302日分の一時金)に該当することとなり、障害補償の額は0となるが、1耳の聴力のみについてみると、聴力レベル40dB以上(第14級第3号、56日分の一時金)が聴力レベル70dB以上(第11級第6号)に加重したものであるので、第11級(223日分)と第14級(56日分)との差額167日分を一時金として支給する。
Ⅲ 鼻の障害
1 障害の等級及び程度
(1) 鼻の障害について、規則別表第5に定める障害の等級及び程度は次のとおりである。
欠損及び機能障害(系列区分10)
第9級第5号 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
(2) 鼻の欠損を伴わない機能障害については、規則16―0第25条の4第2項の規定により、その障害の程度に応じて、規則別表第5に定める他の障害に準じて等級を決定するものとする。
2 障害等級決定の基準
(1) 「鼻の欠損」とは、鼻軟骨部の全部又は大部分の欠損をいう。
(2) 鼻の欠損が、鼻軟骨部の全部又は大部分の欠損に達しないものは、醜状障害として評価する。
(例) 鼻軟骨部の一部を欠損したものは、第12級第14号とする。
(3) 鼻を欠損したものについては、鼻の障害として評価した場合の等級と外貌の醜状障害とした場合の等級のうち、いずれか上位の等級によるものとする。
(例) 鼻軟骨部の全部又は大部分を欠損したものはその機能に著しい障害を残したか否かにかかわらず、外貌の著しい醜状障害として、第7級第12号とする。
(4) 「機能に著しい障害を残すもの」とは、鼻呼吸困難又は嗅覚脱失をいう。
3 準用の取扱い
鼻に、「鼻の欠損」を伴わない機能障害を残す場合の取扱いについては、次による。
ただし、鼻軟骨部の一部の欠損を伴った場合等で、醜状障害のとしても評価され得る場合は、いずれ上位の等級(同じ場合は醜状障害の等級)によるものとする。
(1) 嗅覚脱失又は鼻呼吸困難については、準用等級第12級とする。
(2) 嗅覚の減退については、準用等級第14級とする。
(3) 嗅覚脱失及び嗅覚の減退については、T&Tオルファクトメータによる基準嗅力検査の認知域値の平均嗅力損失値により、次のように区分する。
5.6以上 嗅覚脱失
2.6以上5.5以下 嗅覚の減退
なお、嗅覚脱失については、アリナミン静脈注射(「アリナミンF」を除く。)による静脈性嗅覚検査による検査所見のみによって確認しても差し支えないものとする。
Ⅳ 口の障害
1 障害の等級及び程度
(1) 口の障害について、規則別表第5に定める障害の等級及び程度は次のとおりである。
ア そしやく及び言語機能障害(系列区分11)
第1級第2号 そしやく及び言語の機能を廃したもの
第3級第2号 そしやく又は言語の機能を廃したもの
第4級第2号 そしやく及び言語の機能に著しい障害を残すもの
第6級第2号 そしやく又は言語の機能に著しい障害を残すもの
第9級第6号 そしやく及び言語の機能に障害を残すもの
第10級第3号 そしやく又は言語の機能に障害を残すもの
イ 歯牙障害(系列区分12)
第10級第4号 14歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
第11級第4号 10歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
第12級第3号 7歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
第13級第5号 5歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
第14級第2号 3歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
(2) 規則別表第5に定められていない口の障害については、規則16―0第25条の4第2項の規定により、その障害の程度に応じて、規則別表第5に定める他の障害に準じて等級を決定するものとする。
2 障害等級決定の基準
(1) そしやく及び言語機能障害
ア そしやく機能の障害は、上下咬合及び排列状態並びに下顎の開閉運動等により、総合的に判断するものとする。
イ 「そしやく機能を廃したもの」とは、流動食以外は摂取できないものをいう。
ウ 「そしやく機能に著しい障害を残すもの」とは、粥食又はこれに準ずる程度の飲食物以外は摂取できないものをいう。
エ 「そしゃく機能に障害を残すもの」とは、固形食物の中にそしゃくができないもの又はそしゃくが十分にできないものがあり、そのことが医学的に確認できる場合をいう。
(ア) 「固形食物の中にそしゃくができないもの又はそしゃくが十分にできないものがあり」の例としては、ごはん、煮魚、ハム等はそしゃくできるが、たくあん、らっきょう、ピーナッツ等の一定の固さの食物中にそしゃくができないもの又はそしゃくが十分にできないものがあるなどの場合をいう。
(イ) 「医学的に確認できる」とは、そしゃくができないもの又はそしゃくが十分にできないものがあることの原因が、不正咬合、そしゃく関与筋群の異常、下顎関節の障害、開口障害、歯牙損傷(補てつができない場合)等にあると医学的に確認できることをいう。
オ 「言語の機能を廃したもの」とは、4種の語音(口唇音、歯舌音、口蓋音、喉頭音)のうち、3種以上について発音不能のものをいう。
カ 「言語の機能に著しい障害を残すもの」とは、4種の語音のうち、2種の発音不能のもの又は綴音機能に障害があるため、言語のみを用いては意思を疎通することができないものをいう。
キ 「言語の機能に障害を残すもの」とは、4種の語音のうち、1種の発音不能のものをいう。
(2) 歯牙障害
「歯科補てつを加えたもの」とは、現実にそう失又は著しく欠損した歯牙に対する補てつをいう。したがって、有床義歯又は架橋義歯等を補てつした場合における支台冠又は鈎の装置歯やポスト・インレーを行うに留まつた歯牙は、補てつ歯数に算入せず、また、そう失した歯牙が大きいか又は歯間に隙間があつたため、そう失した歯数と義歯の歯数が異なる場合はそう失した歯数により等級を決定するものとする。
(例) 3歯のそう失に対して、4本の義歯を補てつした場合は、3歯の補てつとして取り扱う。
3 併合等の取扱い
(1) 併合
そしやく又は言語機能障害と歯牙障害を残した場合において、そしやく又は言語機能障害が歯牙障害以外の原因(例えば顎骨骨折や下顎関節の開閉運動制限等による不正咬合)に基づく場合は、併合して等級を決定するものとする。
ただし、歯科補てつを行つた後に、なお歯牙損傷に基づくそしやく又は言語障害が残つた場合は、各障害に係る等級のうち、いずれか上位の等級に決定するものとする。
(2) 準用
ア 舌の異常、咽喉支配神経の麻痺等によつて生ずる嚥下障害については、その障害の程度に応じて、そしやく機能障害に係る等級を準用するものとする。
イ 味覚障害の取扱いについては、次による。
(ア) 頭部外傷その他顎周囲組織の損傷及び舌の損傷によって生じた味覚障害については、濾紙ディスク法における最高濃度液による検査により、基本4味質すべてが認知できないものを「味覚脱失」といい、その等級は準用等級第12級とし、基本4味質のうち1以上が認知できないものを「味覚減退」といい、その等級は準用等級第14級とする。
(イ) 検査を行う領域は、舌とす。
(ウ) 味覚障害については、その症状が時日の経過により漸次回復する場合が多いので、原則として療養を終了してから6か月を経過したのちに等級を決定するものとする。
ウ そしやく及び言語機能障害で、規則別表第5上組合せ等級が定められていないものについては、各障害の該当する等級により併合の方法を用いて準用等級を定めるものとする。
(例1) 「そしやく機能に著しい障害を残し」(第6級第2号)、かつ、「言語機能に障害を残した」(第10級第3号)場合は、準用等級第5級とする。
(例2) 「そしやく機能を廃し」(第3級第2号)、かつ、「言語機能に著しい障害を残した」(第6級第2号)場合は、併合の方法を用いると第1級となるが、「そしやく及び言語機能を廃したもの」(第1級第2号)が最高等級であるので、序列を考慮し、準用等級第2級とする。
エ 声帯麻痺よる著しいかすれ声は、準用等級第12級とし、その程度に達しないものは、準用等級第14級とする。
オ 開口障害等を原因としてそしゃくに相当の時間を要する場合は、準用等級第12級とする。
(ア) 「開口障害等」とは、開口障害のほか、不正咬合、そしゃく関与筋群のぜい弱化等が該当する。
(イ) 「そしゃくに相当の時間を要する場合」とは、日常の食事において食物のそしゃくはできるものの、食物によってはそしゃくに相当の時間を要することがある場合であり、そのことが医学的に確認できるときをいう。なお、開口障害等の原因から、そしゃくに相当の時間を要することが医学的に確認できれば、「相当の時間を要する場合」に該当するものとして取り扱って差し支えない。
(3) 加重
何歯かについて歯科補てつを加えていた者が、更に歯科補てつを加えた結果、上位等級に該当するに至つたときは、加重として取り扱うものとする。
Ⅴ 神経系統の機能又は精神の障害
1 障害の等級及び程度
(1) 神経系統の機能又は精神の障害について、規則別表第5に定める障害の等級及び程度は次のとおりである。
ア 神経系統又は精神の障害(系列区分13)
第1級第3号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
第2級第3号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
第3級第3号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
第5級第2号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
第7級第4号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
第9級第10号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
イ 局部の神経系統の障害(系列区分13)
第12級第13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
第14級第9号 局部に神経症状を残すもの
(2) 中枢神経系に分類される脳又はせき髄の損傷による障害は、複雑な症状を呈するとともに身体各部にも様々な障害を残すことが多いことから、中枢神経系の損傷による障害が複数認められる場合には、末梢神経による障害も含めて総合的に評価し、その決定に当たっては神経系統の機能又は精神の障害の障害等級によるものとする。
ただし、脳又はせき髄の損傷により生じた障害が単一であって、かつ、当該障害について規則別表第5上、該当する等級(準用等級を含む。)がある場合には、神経系統の機能又は精神の障害の障害等級によることなく、その等級により決定するものとする(後記3参照)。
2 障害等級決定の基準
(1) 脳の障害に係る障害等級の決定は、次による。
ア 器質性の障害
脳の器質性障害については、「高次脳機能障害」(器質性精神障害)と「身体性機能障害」(神経系統の障害)に区分して障害等級を決定するものとする。
また、「高次脳機能障害」と「身体性機能障害」とが併存する場合には、それぞれの障害の程度を踏まえ、全体病像を総合的に評価して障害等級を決定するものとする。
(ア) 高次脳機能障害
脳の損傷による高次脳機能障害については、意思疎通能力、問題解決能力、作業負荷に対する持続力及び持久力、社会行動能力(以下「4能力」という。)の各々の喪失の程度に着目して評価するものとする。ただし、高次脳機能障害による障害が第3級以上に該当する場合には、介護の要否及び程度を踏まえて決定すること。その際、複数の障害が認められるときには、障害の程度が最も重篤なものを目安として、各障害相互作用に着目して評価するものとする。
なお、高次脳機能障害は、脳の器質的病変に基づくものであることから、原則としてMRI、CT等によりその存在が認められることが必要である。
a 「高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するもの」は、第1級とする。
高次脳機能障害のため、食事、入浴、用便、更衣等に常時介護を要するもの、又は高次脳機能障害による高度の痴ほうや情意の荒廃があるため、常時監視を要するものが、これに該当する。
b 「高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随時他人の介護を要するもの」は、第2級とする。
高次脳機能障害のため、食事、入浴、用便、更衣等に随時介護を要するもの、高次脳機能障害による痴ほう、情意の障害、幻覚、妄想、頻回の発作性意識障害等のため、随時監視を必要とするもの、又は高次脳機能障害のため、自宅内の日常生活動作は一応できるが、外出の際には介護を必要とするなど、随時介護を必要とするものが、これに該当する。
c 「生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、高次脳機能障害のため、労務に服することができないもの」は、第3級とする。
4能力のいずれか1つ以上の能力の全部が失われているもの、又は4能力のいずれか2つ以上の能力の大部分が失われているものが、これに該当する。
(例1) 意思疎通能力が全部失われている例
職場で他の人と意思疎通を図ることができない場合
(例2) 問題解決能力が全部失われている例
課題を与えられても手順どおりに仕事を全く進めることができず、働くことができない場合
(例3) 作業負荷に対する持続力及び持久力が全部失われている例
作業に取り組んでもその作業への集中を持続することができず、すぐにその作業を投げ出してしまい、働くことができない場合
(例4) 社会行動能力が全部失われている例
大した理由もなく突然感情を爆発させ、職場で働くことができない場合
d 「高次脳機能障害のため、極めて軽易な労務のほか服することができないもの」は、第5級とする。
4能力のいずれか1つの能力の大部分が失われているもの、又は4能力のいずれか2つ以上の能力の半分程度が失われているものが、これに該当する。
(例) 問題解決能力の大部分が失われている例
1人で手順どおりに作業を行うことは著しく困難であり、頻繁な指示がなければ対処できない場合
e 「高次脳機能障害のため、軽易な労務のほか服することができないもの」は、第7級とする。
4能力のいずれか1つの能力の半分程度が失われているもの、又は4能力のいずれか2つ以上の能力の相当程度が失われているものが、これに該当する。
(例) 問題解決能力の半分程度が失われている例
1人で手順どおり作業を行うことに困難を生じることがあり、時々助言を必要とする場合
f 「通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの」は、第9級とする。
4能力のいずれか1つの能力の相当程度が失われているものが、これに該当する。
(例) 問題解決能力の相当程度が失われている例
1人で手順どおりに作業を行うことに困難を生じることがあり、たまに助言を必要とする場合
g 「通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、多少の障害を残すもの」は、第12級とする。
4能力のいずれか1つ以上の能力が多少失われているものが、これに該当する。
h 「通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、軽微な障害を残すもの」は、第14級とする。
MRI、CT等による他覚的所見は認められないものの、脳損傷があることが医学的にみて合理的に推測でき、わずかな能力喪失が認められるものが、これに該当する。
(イ) 身体性機能障害
脳の損傷による身体性機能障害については、麻痺の範囲(四肢麻痺、片麻痺及び単麻痺)及びその程度(高度、中等度及び軽度)並びに介護の要否又はその程度に着目して評価するものとする。
麻痺の程度については、運動障害(運動性、支持性、巧緻性及び速度についての支障)の程度をもって判断するものとし、麻痺の範囲及びその程度については、身体的所見及びMRI、CT等によって裏付けることのできることを要するものとする。
(注1) 四肢麻痺とは両側の四肢の麻痺、片麻痺とは1側の上下肢の麻痺、対麻痺とは両側上肢又は両下肢の麻痺、単麻痺とは上肢又は下肢の1肢のみの麻痺をいい、脳の損傷による麻痺については、通常対麻痺が生じることはない。
(注2) 高度の麻痺とは、障害を残した上肢又は下肢の運動性、支持性がほとんど失われ、当該上肢又は下肢の基本動作(上肢においては物を持ち上げて移動させること、下肢においては歩行や立位)ができないものをいい、次のようなものが該当する。
① 完全強直又はこれに近い状態にあるもの
② 上肢においては、3大関節及び5の手指のいずれの関節も自動運動によっては可動させることができないもの又はこれに近い状態にあるもの
③ 下肢においては、3大関節のいずれも自動運動によっては可動させることができないもの又はこれに近い状態にあるもの
④ 上肢においては、随意運動の顕著な障害により、当該上肢では物を持ち上げて移動させることができないもの
⑤ 下肢においては、随意運動の顕著な障害により、当該下肢の支持性及び随意的な運動性をほとんど失ったもの
(注3) 中等度の麻痺とは、障害を残した上肢又は下肢の運動性、支持性が相当程度失われ、当該上肢又は下肢の基本動作にかなりの制限があるものをいい、次のようなものが該当する。
① 上肢においては、障害を残した1上肢では仕事に必要な軽量の物(おおむね500g)を持ち上げることができないもの又は障害を残した1上肢では文字を書くことができないもの
② 下肢においては、障害を残した1下肢を有するため杖若しくは硬性装具なしには階段を上ることができないもの又は障害を残した両下肢を有するため杖若しくは硬性装具なしには歩行が困難であるもの
(注4) 軽度の麻痺とは、障害を残した上肢又は下肢の運動性、支持性が多少失われており、当該上肢又は下肢の基本動作を行う際の巧緻性及び速度が相当程度損なわれているものをいい、次のようなものが該当する。
① 上肢においては、障害を残した1上肢では文字を書くことに困難を伴うもの
② 下肢においては、日常生活はおおむね独歩であるが、障害を残した1下肢を有するため不安定で転倒しやすく、速度も遅いもの又は障害を残した両下肢を有するため杖若しくは硬性装具なしには階段を上ることができないもの
a 「身体性機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するもの」は、第1級とする。
① 高度の四肢麻痺が認められるもの
② 高度の片麻痺又は中等度の四肢麻痺であって、食事、入浴、用便、更衣等に常時介護を要するもの
が、これに該当する。
b 「身体性機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随時他人の介護を要するもの」は、第2級とする。
① 高度の片麻痺が認められるもの
② 中等度の四肢麻痺であって、食事、入浴、用便、更衣等に随時介護を要するもの
が、これに該当する。
c 「身体性機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが労務に服することができないもの」は、第3級とする。
中等度の四肢麻痺が認められるものが、これに該当する。
d 「身体性機能障害のため、極めて軽易な労務のほか服することができないもの」は、第5級とする。
軽度の四肢麻痺、中等度の片麻痺又は高度の単麻痺が認められるものが、これに該当する。
e 「身体性機能障害のため、軽易な労務のほか服することはできないもの」は、第7級とする。
軽度の片麻痺又は中等度の単麻痺が認められるものが、これに該当する。
f 「身体性機能障害のため、通常の労務に服することはできるが就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの」は、第9級とする。
軽度の単麻痺が認められるものが、これに該当する。
g 「身体性機能障害のため、通常の労務に服することはできるが多少の障害を残すもの」は、第12級とする。
運動障害がほとんど認められない程度の軽微な麻痺を残すもの、運動障害は認められないものの、広範囲にわたる感覚障害が認められるものが、これに該当する。
イ 非器質性の障害
脳の器質的損傷を伴わない精神障害(以下「非器質性精神障害」という。)の障害等級については、次による。
(ア) 非器質性精神障害の後遺障害が存しているというためには、次のaの精神症状のうち1つ以上の精神症状を残し、かつ、bの能力に関する判断項目のうち1つ以上の能力に障害が認められることを要するものとする。
a 精神症状
① 抑うつ状態
② 不安の状態
③ 意欲低下の状態
④ 慢性化した幻覚・妄想性の状態
⑤ 記憶又は知的能力の障害
⑥ その他の障害(衝動性の障害、不安愁訴等)
b 能力に関する判断項目
① 身辺日常生活
② 仕事・生活に積極性・関心を持つこと
③ 通勤・勤務時間の遵守
④ 普通に作業を持続すること
⑤ 他人との意思伝達
⑥ 対人関係、協調性
⑦ 身辺の安全保持、危機の回避
⑧ 困難・失敗への対応
(イ) 就労意欲低下等による区分
a 就労している者又は就労していないが就労意欲のある者
現に就労している者又は就労意欲はあるものの就労していない者については、 (ア)のaの精神症状のいずれか1つ以上が認められる場合に、(ア) のbの能力に関する判断項目(以下「判断項目」という。)のそれぞれについて、その有無及び助言・援助の程度(「時に」又は「しばしば」必要)により障害等級を決定するものとする。
b 就労意欲の低下又は欠落により就労していない者
就労意欲の低下又は欠落により就労していない者については、身辺日常生活が可能である場合に、(ア)のbの①の身辺日常生活の支障の程度により障害等級を決定するものとする。
なお、就労意欲の低下又は欠落により就労していない者とは、職種に関係なく就労意欲が低下又は欠落が認められる者をいい、特定の職種について就労意欲のある者については、aに該当するものとする。
(ウ) 非器質性精神障害は、次の3段階に区分して障害等級を決定するものとする。
a 「非器質性精神障害のため、通常の労務に服することはできるが就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの」は、第9級とする。
① (イ)のaに該当する場合には、判断項目のうち②から⑧のいずれか1つの能力が失われているもの又は判断項目の4つ以上についてしばしば助言・援助を必要とするものが、これに該当する。
(例) 対人関係業務に就けないことによる職種制限が認められる場合
② (イ)のbに該当する場合には、身辺日常生活について時に助言・援助を必要とするものが、これに該当する。
b 「非器質性精神障害のため、通常の労務に服することはできるが多少の障害を残すもの」は、第12級とする。
① (イ)のaに該当する場合には、判断項目の4つ以上について時に助言・援助を必要とするものが、これに該当する。
(例) 職種制限は認められないが、就労に当たりかなりの配慮が必要である場合
② (イ)のbに該当する場合には、身辺日常生活を適切に又はおおむねできるものが、これに該当する。
c 「非器質性精神障害のため、通常の労務に服することはできるが軽微な障害を残すもの」は、第14級とする。
(イ)のaに該当する場合で、判断項目の3つ以下について時に助言・援助を必要とするものが、これに該当する。
(例) 職種制限は認められないが、就労に当たり多少の配慮が必要である場合
(2) せき髄障害に係る障害等級の決定は、次による。
外傷などによりせき髄が損傷され、対麻痺や四肢麻痺が生じた場合には、通常、広範囲にわたる感覚障害や尿路障害(神経因性膀胱障害)などの障害が認められる。さらに、せき柱の変形や運動障害(以下「せき柱の変形等」という。)が認められる場合も多い。このようにせき髄の障害は、複雑な症状を呈する場合が多いので、麻痺の範囲及びその程度については、原則として、脳の損傷による身体性機能障害と同様に身体的所見及びMRI、CT等によって裏付けることのできることを要するものとする。
ただし、せき髄損傷に伴う胸腹部臓器の障害やせき柱の障害による障害の等級が麻痺により判断される障害の等級よりも重い場合は、それらの障害の総合評価により等級を決定するものとする。
なお、せき髄損傷による障害の等級が第3級以上に該当する場合は、介護の要否及びその程度を踏まえて総合して障害等級を決定するものとする。
ア 「せき髄症状のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するもの」は、第1級とする。
① 高度の四肢麻痺又は高度の対麻痺が認められるもの
② 中等度の四肢麻痺又は中等度の対麻痺であって、食事、入浴、用便、更衣等に常時介護を要するもの
が、これに該当する。
(例) 第2腰髄以上で損傷を受けたことにより中等度の四肢麻痺が認められ、神経因性膀胱障害及びせき髄の損傷部位以下の感覚障害が生じたほか、せき柱の変形等が認められる場合
イ 「せき髄症状のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随時他人の介護を要するもの」は、第2級とする。
① 中等度の四肢麻痺が認められるもの
② 軽度の四肢麻痺又は中等度の対麻痺であって、食事、入浴、用便、更衣等に随時介護を要するもの
が、これに該当する。
(例) 第2腰髄以上で損傷を受けたことにより両下肢の中等度の対麻痺が生じたために立位の保持に杖又は硬性装具を要するとともに、軽度の神経因性膀胱障害及びせき髄の損傷部位以下の感覚障害が生じたほか、せき柱の変形等が認められる場合
ウ 「せき髄症状のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが労務に服することができないもの」は、第3級とする。
軽度の四肢麻痺又は中等度の対麻痺が認められるものが、これに該当する。
エ 「せき髄症状のため、極めて軽易な労務のほか服することができないもの」は、第5級とする。
軽度の対麻痺又は1下肢の高度の単麻痺が認められるものが、これに該当する。
オ 「せき髄症状のため、軽易な労務のほか服することができないもの」は、第7級とする。
1下肢の中等度の単麻痺が認められるものが、これに該当する。
(例) 第2腰髄以上でせき髄の半側のみ損傷を受けたことにより1下肢の中等度の単麻痺が生じたために杖又は硬性装具なしには階段を上ることができないとともに、せき髄の損傷部位以下の感覚障害が認められる場合
カ 「せき髄症状のため、通常の労務に服することはできるが就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの」は、第9級とする。
1下肢の軽度の単麻痺が認められるものが、これに該当する。
(例) 第2腰髄以上でせき髄の半側のみ損傷を受けたことにより1下肢の軽度の単麻痺が生じたために日常生活は独歩であるが、不安定で転倒しやすく、速度も遅いとともに、せき髄の損傷部位以下の感覚障害が認められる場合
キ 「せき髄症状のため、通常の労務に服することはできるが多少の障害を残すもの」は、第12級とする。
運動障害(運動性、支持性、巧緻性及び速度についての支障)がほとんど認められない程度の軽微な麻痺を残すもの、運動障害は認められないものの、広範囲にわたる感覚障害が認められるものが、これに該当する。
(例) 軽微な筋緊張の亢進が認められる場合、又は運動障害は伴わないものの、感覚障害がおおむね1下肢にわたって認められる場合
(3) 末梢神経障害に係る障害等級の決定は、次による。
末梢神経麻痺に係る障害等級の決定は、原則として、損傷を受けた神経の支配する身体各部の器官における機能障害に係る等級により決定するものとする。
(4) 外傷性てんかんに係る障害等級の決定は、次による。
外傷性てんかんに係る障害については、発作の型、発作回数等に着目し、次により障害等級を決定するものとする。
なお、意識障害の有無を問わず転倒する発作又は意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作(以下「転倒する発作等」という。)が1か月に2回以上ある場合は、通常、高度の高次脳機能障害を伴っているので、脳の損傷による高次脳機能障害に係る第3級以上の決定基準により障害等級を決定するものとする。
ア 「転倒する発作等が1か月に1回以上あるもの」は、第5級とする。
イ 「転倒する発作等が数か月に1回以上あるもの又は転倒する発作等以外の発作が1か月に1回以上あるもの」は、第7級とする
ウ 「数か月に1回以上の転倒する発作等以外の発作があるもの又は服薬の継続により発作がほぼ完全に抑制されているもの」は、第9級とする。
エ 「発作の発現はないが、脳波上に明らかにてんかん性棘波を認めるもの」は、第12級とする。
(5) 頭痛に係る障害等級の決定は、次による。
頭痛については、頭痛の型のいかんにかかわらず、疼痛による労働又は日常生活上の支障の程度を疼痛の部位、性状、強度、頻度、持続時間及び日内変動並びに疼痛の原因となる他覚的所見により把握し、障害等級を決定するものとする。
ア 「通常の労務に服することはできるが、激しい頭痛により、時には労働に従事することができなくなる場合があるため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの」は、第9級とする。
イ 「通常の労務に服することはできるが、時には労働に差し支える程度の強い頭痛が起こるもの」は、第12級とする。
ウ 「通常の労務に服することはできるが、頭痛が頻回に発現しやすくなったもの」は、第14級とする。
(6) 失調、めまい及び平衡機能障害に係る障害等級の決定は、次による。
失調、めまい及び平衡機能障害については、その原因となる障害の部位によって分けることが困難であるので、諸症状を総合して障害等級を決定するものとする。
ア 「高度の失調又は平衡機能障害のために、生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが労務に服することができないもの」は、第3級とする。
イ 「著しい失調又は平衡機能障害のために、極めて軽易な労務のほか服することができないもの」は、第5級とする。
ウ 「中等度の失調又は平衡機能障害のために、軽易な労務のほか服することができないもの」は、第7級とする。
エ 「通常の労務に服することはできるが、めまいの自覚症状が強く、かつ、眼振その他平衡機能検査の結果に明らかな異常所見が認められ、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの」は、第9級とする。
オ 「通常の労務に服することはできるが、めまいの自覚症状があり、かつ、眼振その他平衡機能検査の結果に異常所見が認められるもの」は、第12級とする。
カ 「眼振その他平衡機能検査の結果に異常所見が認められないものの、めまいの自覚症状はあり、めまいのあることが医学的にみて合理的に推測できるもの」は、第14級とする。
(7) 疼痛等感覚障害に係る障害等級の決定は、次による。
ア 受傷部位の疼痛及び疼痛以外の感覚障害については、次により障害等級を決定するものとする。
(ア) 疼痛
a 「通常の労務に服することはできるが、時には強度の疼痛のため、ある程度差し支えがあるもの」は、第12級とする。
b 「通常の労務に服することはできるが、受傷部位にほとんど常時疼痛を残すの」は、第14級とする。
(イ) 疼痛以外の感覚障害
疼痛以外の異常感覚(蟻走感、感覚脱失等)が発現した場合は、その範囲が広いものに限り、第14級とする。
イ 特殊な性状の疼痛
(ア) カウザルギーについては、疼痛の部位、性状、強度、頻度、持続時間及び日内変動並びに疼痛の原因となる他覚的所見などにより、疼痛の労働能力に及ぼす影響を判断して、次により障害等級を決定するものとする。
a 「軽易な労務以外の労働に常に差し支える程度の疼痛があるもの」は、第7級とする。
b 「通常の労務に服することはできるが、疼痛により時には労働に従事することができなくなるため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの」は、第9級とする。
c 「通常の労務に服することはできるが、時には労働に差し支える程度の疼痛が起こるもの」は、第12級とする。
(イ) 反射性交感神経性ジストロフィー(RSD)については、関節拘縮、骨の萎縮及び皮膚の変化(皮膚温の変化、皮膚の萎縮)という慢性期の主要な症状のいずれもが、健側と比較して明らかに認められる場合に限り、カウザルギーと同様の基準により、それぞれ第7級、第9級又は第12級に決定するものとする。
3 その他
(1) 脳損傷により障害を生じた場合であって、当該障害について、規則別表第5上、該当する等級(準用等級を含む。)があり、かつ、生じた障害が単一であるときは、その等級により決定するものとする。
(例) 一側の後頭葉視覚中枢の損傷によって、両眼の反対側の視野欠損を生ずるが、この場合は、視野障害の等級として定められている第9級第3号と決定する。
(2) せき髄損傷により障害を生じた場合であって、当該障害について、規則別表第5上、該当する等級(準用等級を含む。)があり、かつ、生じた障害が単一であるときは、その等級により決定するものとする。
(例) 第4仙髄の損傷のため軽度の尿路障害が生じた場合は、胸腹部臓器の障害の等級として定められている第11級第10号と決定する。
Ⅵ 外貌(頭部、顔面、頸部)、上肢、下肢等の醜状障害
1 障害の等級及び程度
(1) 醜状障害について、規則別表第5に定める障害の等級及び程度は次のとおりである。
ア 外貌の醜状障害(系列区分14)
第7級第12号 外貌に著しい醜状を残すもの
第9級第16号 外貌に相当程度の醜状を残すもの
第12級第14号 外貌に醜状を残すもの
第12級第14号 外貌に醜状を残すもの
イ 露出面の醜状障害(系列区分20・23)
第14級第4号 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
第14級第5号 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
(2) 規則別表第5に定められていない醜状障害については、規則16―0第25条の4第2項の規定により、その障害の程度に応じて、規則別表第5に定めている他の障害に準じて等級を決定するものとする。
2 障害等級決定の基準
(1) 外貌の醜状障害
ア 「外貌」とは、頭部、顔面部及び頸部における日常露出する部分をいう。
イ 「外貌に著しい醜状を残すもの」とは、原則として、次のいずれかに該当するものをいう。
(ア) 頭部にあつては、てのひら大(指の部分は含まない。以下同じ。)以上の瘢痕又は頭蓋骨のてのひら大以上の欠損
(イ) 顔面部にあつては、鶏卵大以上の瘢痕又は10円硬貨大以上の組織陥没
(ウ) 頸部にあつては、てのひら大以上の瘢痕
ウ 「外貌に相当程度の醜状を残すもの」とは、原則として、顔面部の5センチメートル以上の線状痕をいう。
エ 「外貌に醜状を残すもの」とは、原則として、次のいずれかに該当するものをいう。
(ア) 頭部にあつては、鶏卵大以上の瘢痕又は頭蓋骨の鶏卵大以上の欠損
(イ) 顔面部にあつては、10円硬貨大以上の瘢痕又は3センチメートル以上の線状痕
(ウ) 頸部にあつては、鶏卵大以上の瘢痕
オ 外貌に係る瘢痕、線状痕及び組織陥没のうち、眉毛、頭髪等にかくれる部分については、醜状として取り扱わないものとする。
(例) 眉毛の走行に一致して3.5センチメートルの縫合創痕がありそのうち1.5センチメートルが眉毛にかくれている場合は、顔面に残つた線状痕は2センチメートルとなるので、外貌の醜状には該当しない。
カ 顔面神経麻痺による「口のゆがみ」は「醜状を残すもの」として、また閉瞼不能はまぶたの障害として取り扱うものとする。
キ 頭蓋骨のてのひら大以上の欠損により、頭部の陥没が認められる場合で、それによる脳の圧迫により神経症状がある場合は、外貌の醜状障害に係る等級と神経障害に係る等級のうちいずれか上位の等級により決定するものとする。
ク まぶた、耳介及び鼻の欠損障害については、これらの欠損障害について定められている等級と外貌の醜状に係る等級のうち、いずれか上位の等級により決定するものとする。
なお、耳介及び鼻の欠損障害に係る醜状の取扱いについては、次による。
(ア) 耳介軟骨部の2分の1以上を欠損した場合は、「著しい醜状を残すもの」とし、その一部を欠損した場合は、「醜状を残すもの」とする。
(イ) 鼻軟骨部の全部又は大部分を欠損した場合は、「著しい醜状を残すもの」とし、その一部又は鼻翼を欠損した場合は、「醜状を残すもの」とする。
ケ 2個以上の瘢痕又は線状痕が隣接し、又は相まつて1個の瘢痕又は線状痕と同程度以上の醜状を呈する場合は、それらの面積、長さ等を合算して等級を決定するものとする。
コ 火傷治癒後の黒褐色変色又は色素脱失による白斑等であつて、永久的に残ると認められ、かつ、人目につく程度以上のものでその範囲がエに該当するものは、「醜状を残すもの」として取り扱うものとする。
(2) 露出面の醜状障害
ア 上肢又は下肢の「露出面」とは、上肢にあつては、肩関節以下(手部を含む。)、下肢にあつてはひざ関節以下(足背部を含む。)の部分をいう。
イ 「2個以上の線状痕」及び「火傷治癒後の黒褐色変色又は色素脱失による白斑等」に係る取扱いについては、(1)のケ及びコの場合と同様とする。
3 併合等の取扱い
(1) 併合
次に掲げる場合にあつては、併合して等級を決定するものとする。
ア 外貌の醜状障害と露出面の醜状障害とを残した場合
イ 外貌の醜状障害と露出面以外の面の醜状障害とを残した場合
イ 外貌の醜状障害と露出面以外の面の醜状障害とを残した場合
(例) 顔面部に第12級第14号、背部に第12級相当の醜状の障害を残した場合は、併合等級第11級とする。
ウ 上肢の露出面の醜状障害と下肢の露出面の醜状障害とを残した場合
エ 外傷、火傷等により眼球を亡失するとともに、眼部周囲及び顔面の組織陥没、瘢痕等を生じた場合
(例) 1眼を亡失し(第8級1号)、かつ、その周囲の組織陥没が著しい(第7級第12号)場合は、併合等級第5級とする。
(2) 準用
次に掲げる場合にあつては、準用して等級を決定するものとする。
ア 上肢又は下肢の露出面の醜状障害で次に掲げる範囲のものは、準用等級第12級とする。
(ア) 両上肢又は1上肢に1上肢の全面積の2分の1程度を超える醜状を残したもの
(イ) 両下肢の露出面又は1下肢の露出面に1下肢の露出面の全面積に及ぶ程度の醜状を残したもの
イ 露出面以外の面の醜状障害の取扱いについては、次による。
(ア) 両大腿のほとんど全域に及ぶ醜状障害及び胸部と腹部又は背部と臀部にあつてその全面積の2分の1程度を超える醜状障害は、準用等級第12級とする。
(イ) 1側の大腿のほとんど全域に及ぶもの及び胸部と腹部又は背部と臀部にあつてその全面積の4分の1程度を超える醜状障害は、準用等級第14級とする。
(3) 加重
次に掲げる場合にあつては、加重として取り扱うものとする。
ア 既に外貌に醜状障害を残していた者が、その程度を加重した場合
イ 既に上肢又は下肢の露出面に醜状障害を残していた者が、その程度を加重した場合
ウ 既に露出面以外の面の醜状障害を残していた者が、その程度を加重した場合
(4) その他
上肢又は下肢の露出面の醜状障害と露出面以外の面の醜状障害を残した場合及び2以上の露出面以外の面の醜状障害を残した場合にあつては、おのおのの該当する等級のうち、いずれか上位の等級によるものとする。
Ⅶ 胸腹部臓器の障害
1 障害の等級及び程度
(1) 胸腹部臓器の障害について、規則別表第5に定める障害の等級及び程度は次のとおりである。
ア 胸腹部臓器の障害(系列区分15)
第1級第4号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
第2級第4号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
第3級第4号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
第5級第3号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
第7級第5号 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
第9級第11号 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
第11級第10号 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
第13級第6号 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
イ 生殖器の障害(系列区分15)
第7級第13号 両側のこう丸を失ったもの
第9級第17号 生殖器に著しい障害を残すもの
(2) 胸腹部臓器の障害に係る障害等級の決定は、次による。
ア 胸腹部臓器(生殖器を含む。)の障害の等級については、その障害が単一である場合には下記2に定める基準により決定するものとする。その障害が複数認められる場合には、併合の方法を用いて準用等級を定めるものとする。
イ 多数の臓器に障害を残し、それらが複合的に作用するために介護が必要な程度に重度の障害が残ることとなる場合のように、併合の方法により得られた等級が次の総合評価による等級を下回る場合は介護の程度及び労務への支障の程度を総合的に判断して障害等級を決定するものとする。
(ア) 「労務に服することができず、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するもの」は、第1級とする。
(イ) 「労務に服することができず、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随時他人の介護を要するもの」は、第2級とする。
(ウ) 「労務に服することはできないが、生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるもの」は、第3級とする。
(エ) 「極めて軽易な労務のほか服することができないもの」は、第5級とする 。
(オ) 「軽易な労務のほか服することができないもの」は、第7級とする。
(カ) 「通常の労務に服することはできるが、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの」は、第9級とする。
(キ) 「通常の労務に服することはできるが、機能の障害の存在が明確であって労務に支障を来すもの」は、第11級とする。
(3) 規則別表第5に定められていない胸腹部臓器の障害については、規則16―0第25条の4第2項の規定により、その障害の程度に応じて規則別表第5に定める他の障害に準じて等級を決定するものとする。
2 障害等級決定の基準
(1) 呼吸器の障害
呼吸器は、鼻腔、咽頭、喉頭、気管、気管支、細気管支、呼吸細気管支、肺胞、胸郭、横隔膜及び呼吸筋から構成されている。
呼吸機能に障害を残したものの障害等級は、原則としてアにより決定された等級によるものとする。ただし、その等級がイ又はウにより決定された等級より低い場合には、イ又はウにより決定された等級とする。
なお、アにより決定された等級が第3級以上に該当する場合は、イ又はウによる等級の決定を行わないものとする。
また、スパイロメトリーを適切に行うことができない場合は、イによらないものとする。
ア 動脈血酸素分圧と動脈血炭酸ガス分圧の検査結果による障害等級の決定は、次による。
(ア) 動脈血酸素分圧が50Torr以下のもの
a 呼吸機能の低下のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護が必要なものは、第1級とする。
b 呼吸機能の低下のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随時他人の介護が必要なものは、第2級とする。
c a及びbに該当しないものは、第3級とする。
(イ) 動脈血酸素分圧が50Torrを超え60Torr以下のもの
a 動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲(37Torr以上43Torr以下をいう。以下同じ。)にないもので、かつ、呼吸機能の低下のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護が必要なものは、第1級とする。
b 動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲にないもので、かつ、呼吸機能の低下のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随時他人の介護が必要なものは、第2級とする。
c 動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲にないもので、a及びbに該当しないものは、第3級とする。
d a、b及びcに該当しないものは、第5級とする。
(ウ) 動脈血酸素分圧が60Torrを超え70Torr以下のもの
a 動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲にないものは、第7級とする。
b aに該当しないものは、第9級とする。
(エ) 動脈血酸素分圧が70Torrを超えるもの
動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲にないものは、第11級とする。
イ スパイロメトリーの検査結果及び呼吸困難の程度による障害等級の決定は、次による。
(ア) スパイロメトリーの検査結果において、%1秒量が35以下又は%肺活量が40以下であるもの
a 高度の呼吸困難が認められ、かつ、呼吸機能の低下のために、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護が必要なものは、第1級とする。
「高度の呼吸困難」とは、呼吸困難のため、連続しておおむね100メートル以上歩けないものをいう。
b 高度の呼吸困難が認められ、かつ、呼吸機能の低下のために、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随時他人の介護が必要なものは、第2級とする。
c 高度の呼吸困難が認められ、a及びbに該当しないものは、第3級とする。
d 中等度の呼吸困難が認められるものは、第7級とする。
「中等度の呼吸困難」とは、呼吸困難のため、平地でさえ健常者と同様には歩けないが、自分のペースでなら1キロメートル程度の歩行が可能であるものをいう。
e 軽度の呼吸困難が認められるものは、第11級とする。
「軽度の呼吸困難」とは、呼吸困難のため、健常者と同様には階段の昇降ができないものをいう。
(イ) スパイロメトリーの検査結果において、%1秒量が35を超え55以下又は%肺活量が40を超え60以下であるもの
a 高度又は中等度の呼吸困難が認められるものは、第7級とする。
b 軽度の呼吸困難が認められるものは、第11級とする。
(ウ) スパイロメトリーの検査結果において、%1秒量が55を超え70以下又は%肺活量が60を超え80以下であるもの
高度、中等度又は軽度の呼吸困難が認められるものは、第11級とする。
ウ 運動負荷試験の結果による障害等級の決定は、次による。
ア及びイによる評価では障害等級に該当しないものの、呼吸機能の低下による呼吸困難が認められ、運動負荷試験の結果から明らかに呼吸機能に障害が認められるものは、第11級とする。
なお、運動負荷試験の結果から呼吸困難と判断するためには、次の事項について主治医から意見等を徴した上で呼吸器専門医の意見を求める必要がある。
① 実施した運動負荷試験(漸増運動負荷試験、時間内歩行試験(6分間・10分間等の歩行試験、シャトルウォーキングテスト等)及び50メートル歩行試験等)の内容
② 運動負荷試験の結果
③ 呼吸機能障害があると考える根拠
④ 運動負荷試験が適正に行われたことを示す根拠
⑤ その他参考となる事項
(2) 循環器の障害
ア 心機能が低下したもの
心筋梗塞、狭心症、心臓外傷等の後遺症状により心機能が低下したものの障害等級は、心機能の低下による運動耐容能の低下の程度により、次のとおり決定するものとする。
なお、心機能が低下したものについては、心機能の低下が軽度にとどまるもの、危険な不整脈が存在しないもの及び残存する心筋虚血が軽度にとどまるもののいずれにも該当する場合を除き、通常、療養を要することから、症状の固定に至ったとしないものとする。
(ア) 心機能の低下による運動耐容能の低下が中等度であるものは、第9級とする。
「運動耐容能の低下が中等度」とは、心筋に壊死を残し、わずかな身体活動の制限があるものをいう。
酸素摂取量において、おおむね6METsを超える強度の身体活動が制限されるものが、これに該当する。
(例) 平地を健常者と同じ速度で歩くのは差し支えないものの、平地を急いで歩く、健常者と同じ速度で階段を昇るという身体活動が制限されるもの
(イ) 心機能の低下による運動耐容能の低下が軽度であるものは、第11級とする。
「運動耐容能の低下が軽度」とは、心筋に壊死を残しているが、身体活動に制限はないものをいう。
酸素摂取量において、おおむね8METsを超える強度の身体活動が制限されるものが、これに該当する。
(例) 平地を急いで歩く、健常者と同じ速度で階段を昇るという身体活動に支障がないものの、それ以上激しいか、急激な身体活動が制限されるもの
イ 除細動器又はペースメーカを植え込んだものの障害等級は、次のとおり決定するものとする。
(ア) 除細動器を植え込んだものは、第7級とする。
(イ) ペースメーカを植え込んだものは、第9級とする。
ウ 房室弁又は大動脈弁を置換したものの障害等級は、次のとおり決定するものとする。
(ア) 継続的に抗凝血薬療法を行うものは、第9級とする。
(イ) (ア)に該当しないものは、第11級とする。
エ 大動脈に解離を残すものであって、偽腔開存型の解離を残すものは、第11級とする。
(3) 腹部臓器の障害
腹部臓器の障害に係る障害等級は、次の各臓器ごとに、その機能の低下の程度等により、次のとおり決定するものとする。
ア 食道の障害
食道とは、咽頭下端と胃の噴門部との間の管をいう。
食道の狭さくによる通過障害を残すものは、第9級とする。
「食道の狭さくによる通過障害」とは、次のいずれにも該当するものをいう 。
(ア) 通過障害の自覚症状があるもの
(イ) 消化管造影検査により、食道の狭さくによる造影剤のうっ滞が認められるもの
イ 胃の障害
胃は、入口の噴門と出口の幽門、2つの弯曲部(大弯と小弯)及び2つの壁(前壁と後壁)から構成される。
(ア) 胃の障害に係る障害等級は、胃の切除により生じる症状の有無により、次のとおり決定するものとする。
a 消化吸収障害、ダンピング症候群及び胃切除術後逆流性食道炎のいずれもが認められるものは、第7級とする。
b 消化吸収障害及びダンピング症候群が認められるものは、第9級とする。
c 消化吸収障害及び胃切除術後逆流性食道炎が認められるものは、第9級とする。
d 消化吸収障害、ダンピング症候群又は胃切除術後逆流性食道炎のいずれかが認められるものは、第11級とする。
e 噴門部又は幽門部を含む胃の一部を亡失したもの(b、c及びdに該当するものは除く。)は、第13級とする。
(イ) 胃の切除により生じる消化吸収障害、ダンピング症候群及び胃切除術後逆流性食道炎の症状については、次により判断するものとする。
a 「消化吸収障害が認められるもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
(a) 胃の全部を亡失したもの
(b) 噴門部又は幽門部を含む胃の一部を亡失し、低体重等(BMIが20以下であるものをいう。ただし、被災する前からBMIが20以下であったものについては、被災する前よりも体重が10%以上減少したものをいう。以下同じ。)が認められるもの
b 「ダンピング症候群が認められるもの」とは、次のいずれにも該当するものをいう。
(a) 胃の全部又は幽門部を含む胃の一部を亡失したもの
(b) 食後30分以内に出現するめまい、起立不能等の早期ダンピング症候群に起因する症状又は食後2時間後から3時間後に出現する全身脱力感、めまい等の晩期ダンピング症候群に起因する症状が認められるもの
c 「胃切除術後逆流性食道炎が認められるもの」とは、次のいずれにも該当するものをいう。
(a) 胃の全部又は噴門部を含む胃の一部を亡失したもの
(b) 胸焼け、胸痛、嚥下困難等の胃切除術後逆流性食道炎に起因する自覚症状があるもの
(c) 内視鏡検査により、食道にびらん、潰瘍等の胃切除術後逆流性食道炎に起因する所見が認められるもの
ウ 小腸の障害
小腸は、12指腸、空腸及び回腸から構成されている。
(ア) 小腸を大量に切除したものの障害等級の決定は、次による。
なお、小腸を切除したことにより人工肛門を造設したものの障害等級は、(イ)により決定するものとする。
また、小腸を大量に切除したため、経口的な栄養管理が不可能なものは、通常、療養を要することから、症状の固定に至ったとしないものとする。
a 残存する空腸及び回腸の長さが100センチメートル以下となったものは、第9級とする。
b 残存する空腸及び回腸の長さが100センチメートルを超え300センチメートル未満となったものであって、消化吸収障害が認められるもの(低体重等が認められるものに限る。)は、第11級とする。
(イ) 人工肛門を造設したものの障害等級の決定は、次による。
a 小腸内容が漏出することによりストマ周辺に著しい皮膚のびらんを生じ、パウチ等の装着ができないものは、第5級とする。
b aに該当しないものは、第7級とする。
(ウ) 小腸皮膚瘻を残すものの障害等級の決定は、次による。
a 瘻孔から小腸内容の全部又は大部分が漏出するもの
(a) 小腸内容が漏出することにより小腸皮膚瘻周辺に著しい皮膚のびらんを生じ、パウチ等の装着ができないものは、第5級とする。
(b) (a)に該当しないものは、第7級とする。
b 瘻孔から漏出する小腸内容がおおむね100ml/日以上のもの
(a) 小腸内容が漏出することにより小腸皮膚瘻周辺に著しい皮膚のびらんを生じ、パウチ等の装着ができないものは、第7級とする。
(b) (a)に該当しないものは、第9級とする。
c 瘻孔から少量ではあるが明らかに小腸内容が漏出する程度のものは、第11級とする。
「小腸皮膚瘻」とは、小腸内容が皮膚に開口した瘻孔から出てくる病態をいい、粘液瘻(排出されたものが粘液で、その障害もごく軽いものであることから、消化吸収障害等を生じるものに当たらないとさ れている。)を除く。
(エ) 小腸の狭さくを残すものは、第11級とする。
「小腸の狭さく」とは、次のいずれにも該当するものをいう。
a 1か月に1回程度、腹痛、腹部膨満感、嘔気、嘔吐等の症状が認められるもの
b 単純エックス線像においてケルクリングひだ像が認められるもの
エ 大腸の障害
大腸は、盲腸、結腸(上行結腸、横行結腸、下行結腸及びS状結腸)及び直腸から構成されるが、その機能上から、肛門管を含むものとする。
(ア) 大腸を大量に切除したものであって、結腸のすべてを切除するなど大腸のほとんどを切除したものは、第11級とする。
なお、大腸を切除したことにより人工肛門を造設したものの障害等級は、(イ)により決定するものとする。
(イ) 人工肛門を造設したものの障害等級の決定は、次による。
a 大腸内容が漏出することによりストマ周辺に著しい皮膚のびらんを生じ、パウチ等の装着ができないものは、第5級とする。
b aに該当しないものは、第7級とする。
(ウ) 大腸皮膚瘻を残すものの障害等級の決定は、次による。
a 瘻孔から大腸内容の全部又は大部分が漏出するもの
(a) 大腸内容が漏出することにより大腸皮膚瘻周辺に著しい皮膚のびらんを生じ、パウチ等の装着ができないものは、第5級とする。
(b) (a)に該当しないものは、第7級とする。
b 瘻孔から漏出する大腸内容がおおむね100ml/日以上のもの
(a) 大腸内容が漏出することにより大腸皮膚瘻周辺に著しい皮膚のびらんを生じ、パウチ等の装着ができないものは、第7級とする。
(b) (a)に該当しないものは、第9級とする。
c 瘻孔から少量ではあるが明らかに大腸内容が漏出する程度のものは、第11級とする。
(エ) 大腸の狭さくを残すものの障害等級の決定は、次による。
大腸の狭さくを残すものは、第11級とする。
「大腸の狭さく」とは、次のいずれにも該当するものをいう。
a 1か月に1回程度、腹痛、腹部膨満感等の症状が認められるもの
b 単純エックス線像において、貯留した大量のガスにより結腸膨起像が相当区間認められるもの
(オ) 便秘を残すものの障害等級の決定は、次による。
a 用手摘便を要すると認められるものは、第9級とする。
b aに該当しないものは、第11級とする。
なお、a及びbの障害の評価には、便秘を原因とする頭痛、悪心、嘔吐、腹痛等の症状が含まれるものとする。
「便秘」とは、次のいずれにも該当するものをいう。
(a) 排便反射を支配する神経の損傷がMRI、CT等により確認できるもの
(b) 排便回数が週2回以下の頻度であって、恒常的に硬便であると認められるもの
(カ) 便失禁を残すものの障害等級の決定は、次による。
a 完全便失禁を残すものは、第7級とする。
b 常時おむつの装着が必要なもの(aに該当するものを除く。)は、第9級とする。
c 常時おむつの装着は必要ないものの、明らかに便失禁があると認められるものは、第11級とする。
オ 肝臓の障害
肝臓の障害に係る障害等級の決定は、次による。
(ア) 肝硬変(ウイルスの持続感染が認められ、かつ、アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ(AST)及びアラニンアミノトランスフェラーゼ(ALT)が持続的に低値であるものに限る。)は、第9級とする。
(イ) 慢性肝炎(ウイルスの持続感染が認められ、かつ、アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ(AST)及びアラニンアミノトランスフェラーゼ(ALT)が持続的に低値であるものに限る。)は、第11級とする。
カ 胆のうの障害
胆のうを失ったものは、第13級とする。
キ すい臓の障害
(ア) すい臓の障害に係る障害等級の決定は、次による。
a 外分泌機能の障害及び内分泌機能の障害のいずれもが認められるものは、第9級とする。
b 外分泌機能の障害又は内分泌機能の障害のいずれかが認められるものは、第11級とする。
c 軽微なすい液瘻を残したために皮膚に疼痛等を生じたものは、局部の神経症状として、第12級又は第14級とする。
(イ) 「外分泌機能の障害」とは、次のいずれにも該当するものをいう。
a 上腹部痛、脂肪便(常食摂取で1日ふん便中脂肪が6g以上であるもの)及び頻回の下痢等の外分泌機能の低下による症状が認められるもの
b 次のいずれかに該当するもの
(a) すい臓を一部切除したもの
(b) BTーPABA(PFD)試験で異常低値(70%未満)を示すもの
(c) ふん便中キモトリプシン活性で異常低値(24U/g未満)を示すもの
(d) アミラーゼ又はエラスターゼの異常低値を認めるもの
(ウ) 「内分泌機能の障害」とは、次のいずれにも該当するものをいう。
なお、内分泌機能に障害があるためにインスリン投与を必要とする場合は、療養を要することから、症状の固定に至ったとしないものとする。
a 異なる日に行った経口糖負荷試験によって、境界型又は糖尿病型であることが2回以上確認されるもの
b インスリン異常低値(空腹時血漿中のCーペプチド(CPR)が0.5ng/ml以下)であるもの
c Ⅱ型糖尿病に該当しないもの
ク ひ臓の障害
ひ臓を失ったものは、第13級とする。
ケ 腹壁瘢痕ヘルニア、腹壁ヘルニア、鼠径ヘルニア又は内ヘルニアを残すもの
腹壁瘢痕ヘルニア、腹壁ヘルニア、鼠径ヘルニア又は内ヘルニアを残すものの障害等級の決定は、次による。
(ア) 常時ヘルニア内容の脱出・膨隆が認められるもの又は立位をしたときヘルニア内容の脱出・膨隆が認められるものは、第9級とする。
(イ) 重激な業務に従事した場合等腹圧が強くかかるときにヘルニア内容の脱出・膨隆が認められるものは、第11級とする。
(4) 泌尿器の障害
ア じん臓の障害
じん臓の障害に係る障害等級は、じん臓の亡失の有無及び糸球体濾過値(以下「 GFR」という。)によるじん機能の低下の程度により、次のとおり決定するもの とする。
(ア) じん臓を失っていないもの
a GFRが30ml/分を超え50ml/分以下のものは、第9級とする。
b GFRが50ml/分を超え70ml/分以下のものは、第11級とする。
c GFRが70ml/分を超え90ml/分以下のものは、第13級とする。
(イ) 1側のじん臓を失ったもの
a GFRが30ml/分を超え50ml/分以下のものは、第7級とする。
b GFRが50ml/分を超え70ml/分以下のものは、第9級とする。
c GFRが70ml/分を超え90ml/分以下のものは、第11級とする。
d a、b及びcのいずれにも該当しないものは、第13級とする。
イ 尿管、膀胱及び尿道の障害
尿管、膀胱及び尿道の障害に係る障害等級は、次のとおり決定するものとする。
(ア) 尿路変向術を行ったもの
尿路変向術を行ったものの障害等級の決定は、次による。
a 非尿禁制型尿路変向術を行ったもの
(a) 尿が漏出することによりストマ周辺に著しい皮膚のびらんを生じ、パッド等の装着ができないものは、第5級とする。
(b) (a)に該当しないものは、第7級とする。
b 尿禁制型尿路変向術を行ったもの
(a) 禁制型尿リザボアの術式を行ったものは、第7級とする。
(b) 尿禁制型尿路変向術(禁制型尿リザボアの術式及び外尿道口形成術を除く。)を行ったものは、第9級とする。
(c) 外尿道口形成術を行ったものは、第11級とする。
なお、外尿道口形成術は、外性器の全部又は一部を失ったことにより行うものであるから、外尿道口形成術を行ったものの障害等級と外性器を亡失したものの障害等級のうち、いずれか上位の等級により決定するものとする。
(d) 尿道カテーテルを留置したものは、第11級とする。
(イ) 排尿障害を残すもの
排尿障害を残すものの障害等級の決定は、次による。
a 膀胱の機能の障害によるもの
(a) 残尿が100ml以上であるものは、第9級とする。
(b) 残尿が50ml以上100ml未満であるものは、第11級とする。
b 尿道狭さくによるものの障害等級の決定は、次による。
ただし、尿道狭さくのため、じん機能に障害を来すものは、じん臓の障害の等級により決定するものとする。
(a) 糸状ブジーを必要とするものは、第11級とする。
(b) 「シャリエ式」尿道ブジー第20番(ネラトンカテーテル第11号に相当する。)が辛うじて通り、時々尿道拡張術を行う必要があるものは、準用等級第14級とする。
(ウ) 蓄尿障害を残すもの
蓄尿障害を残すものの障害等級の決定は、次による。
a 尿失禁を残すもの
(a) 持続性尿失禁を残すものは、第7級とする。
(b) 切迫性尿失禁及び腹圧性尿失禁を残すものの障害等級の決定は、次による。
① 常時パッド等を装着し、かつ、パッドをしばしば交換しなければならないものは、第7級とする。
② 常時パッド等を装着しなければならないが、パッドの交換までは要しないものは、第9級とする。
③ 常時パッド等の装着は要しないが、下着が少し濡れるものは、第11級とする。
b 頻尿を残すものは、第11級とする。
「頻尿」とは、次のいずれにも該当するものをいう。
(a) 器質的病変による膀胱容量の器質的な減少又は膀胱若しくは尿道の支配神経の損傷が認められるもの
(b) 日中8回以上の排尿が認められるもの
(c) 多飲等の他の原因が認められないもの
(5) 生殖器の障害
生殖器の障害に係る障害等級は、次のとおり決定するものとする。
ア 生殖機能を完全に喪失したもののうち、両側のこう丸を失ったものは、第7級とする。
イ 生殖機能に著しい障害を残すもの(生殖機能は残存しているものの、通常の性交では生殖を行うことができないものが該当する。)であって、次に掲げるものは、 第9級とする。
(ア) 陰茎の大部分を欠損したもの(陰茎を膣に挿入することができないと認められるものに限る。)
(イ) 勃起障害を残すもの
「勃起障害」とは、次のいずれにも該当するものをいう。
a 夜間睡眠時に十分な勃起が認められないことがリジスキャン  による夜間陰茎勃起検査により証明されるもの
による夜間陰茎勃起検査により証明されるもの
 による夜間陰茎勃起検査により証明されるもの
による夜間陰茎勃起検査により証明されるものb 支配神経の損傷等勃起障害の原因となり得る所見が、神経系検査(会陰部の知覚、肛門括約筋のトーヌス・自律収縮、肛門反射及び球海綿反射筋反射に係る検査)又は血管系検査(プロスタグランジンE1海綿体注射による各種検査)のいずれかにより認められるもの
(ウ) 射精障害を残すもの
「射精障害」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
a 尿道又は射精管が断裂しているもの
b 両側の下腹神経の断裂により当該神経の機能が失われているもの
c 膀胱頸部の機能が失われているもの
(エ) 膣口狭さくを残すもの(陰茎を膣に挿入することができないと認められるものに限る。)
(オ) 両側の卵管に閉塞若しくは癒着を残すもの、頸管に閉塞を残すもの又は子宮を失ったもの(画像所見により認められるものに限る。)
3 併合等の取扱い
(1) 併合
胸腹部臓器の障害と系列を異にする障害が通常派生する関係にある場合には、併合することなく、いずれか上位の等級により決定するものとする。
(例) 外傷により、ろっ骨の著しい変形(第12級第5号)が生じ、それを原因として呼吸機能の障害(第11級第10号)を残した場合は、上位の等級である第11級とする。
(2) 準用
ア 除細動器又はペースメーカを植え込み、かつ、心機能が低下したものの障害等級は、併合の方法を用いて準用等級を定めるものとする。
イ 胸腹部臓器(生殖器を含む。)に、障害等級に該当する障害が2以上ある場合に は、併合の方法を用いて準用等級を定めるものとする。
(例) 心機能の低下による軽度の運動耐容能の低下(第11級第10号)があり、ペースメーカを植え込み(第9級第11号)、かつ、食道狭さくによる通過障害を残した(第9級第11号)場合は、準用等級第8級とする。
ウ 生殖器の障害のみで、生殖機能を完全に喪失したものに該当する場合は、その他の生殖機能の障害に該当する障害がある場合であっても、準用等級第7級とする。
(例) 両側のこう丸を失い(第7級第13号)、かつ、器質的な原因による勃起障害(第9級第11号)がある場合は、準用等級第7級とする。
エ 生殖機能を完全に喪失したもののうち、次に掲げるものは、準用等級第7級とする。
(ア) 常態として精液中に精子が存在しないもの
(イ) 両側の卵巣を失ったもの
(ウ) 常態として卵子が形成されないもの
オ 生殖機能に障害を残すもの(通常の性交で生殖を行うことができるものの、生殖機能に一定以上の障害を残すものが該当する。)で、狭骨盤(産科的真結合線が9.5センチメートル未満又は入口部横径が10.5センチメートル未満のもの)又は比較的狭骨盤(産科的真結合線が10.5センチメートル未満又は入口部横径が11.5センチメートル未満のもの)であるものは、準用等級第11級とする。
カ 生殖機能に軽微な障害を残すもの(通常の性交で生殖を行うことができるものの、生殖機能にわずかな障害を残すものが該当する。)で、1側のこう丸を失ったもの (1側のこう丸の亡失に準ずべき程度の萎縮を含む。)又は1側の卵巣を失ったものは、いずれも準用等級第13級とする。
Ⅷ 体幹(せき柱及びその他の体幹骨)の障害
1 障害の等級及び程度
(1) せき柱及びその他の体幹骨の障害について、規則別表第5に定める障害の等級及び程度は次のとおりである。
ア せき柱の障害(系列区分16)
(ア) 変形障害
第6級第5号 せき柱に著しい変形を残すもの
第11級第7号 せき柱に変形を残すもの
(イ) 運動障害
第6級第5号 せき柱に著しい運動障害を残すもの
第8級第2号 せき柱に運動障害を残すもの
イ その他の体幹骨の障害(系列区分17)
第12級第5号 鎖骨、胸骨、ろっ骨、肩こう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
(2) 規則別表第5に定められていないせき柱及びその他の体幹骨の障害については、規則16―0第25条の4第2項の規定により、その障害の程度に応じて規則別表第5に定める他の障害に準じて等級を決定するものとする。
(3) せき柱の運動機能の評価及び測定は、以下によるほか、別添「関節の機能障害の評価方法及び関節可動域の測定要領」に準じて取り扱うものとする。
2 障害等級決定の基準
(1) せき柱の障害
ア 原則
せき柱のうち、頸椎(頸部)と胸腰椎(胸腰部)とでは、主たる機能が異なっている(頸椎は、主として頭部の支持機能を、胸腰椎は、主として体幹の支持機能を担っている。)ことから、障害等級の決定に当たっては、原則として頸椎と胸腰椎は異なる部位として取り扱い、それぞれの部位ごとに等級を決定するものとする。
イ 変形障害
変形障害については、「せき柱に著しい変形を残すもの」、「せき柱に中程度の変形を残すもの」、「せき柱に変形を残すもの」の3段階で等級を決定するものとする。
(ア) 「せき柱に著しい変形を残すもの」及び「せき柱に中程度の変形を残すもの」は、せき柱の後彎又は側彎の程度等により等級を決定するものとする。
この場合、せき柱の後彎の程度は、せき椎圧迫骨折、脱臼等(以下「せき椎圧迫骨折等」という。)により前方椎体高が減少した場合に、減少した前方椎体高と当該椎体の後方椎体高の高さを比較することにより判断する。また、せき柱の側彎は、コブ法による側彎度で判断する。
なお、後彎又は側彎が、頸椎から胸腰椎にまたがって生じている場合には、上記アにかかわらず、後彎については、前方椎体高が減少したすべてのせき椎の前方椎体高の減少の程度により、また、側彎については、その全体の角度により判断する。
(注) 「コブ法」とは、下図のとおり、エックス線写真により、せき柱のカーブの頭側及び尾側において、それぞれ水平面から最も傾いているせき椎を求め、頭側で最も傾いているせき椎の椎体上縁の延長線と、尾側で最も傾いているせき椎の椎体の下縁の延長線が交わる角度(側彎度)を測定する方法である。
〔図〕
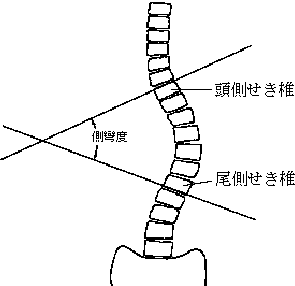 |
(イ) 「せき柱に著しい変形を残すもの」とは、エックス線写真、CT・MRI画像(以下「エックス線写真等」という。)により、せき椎圧迫骨折等を確認することができる場合であって、次のいずれかに該当するものをいう。
a せき椎圧迫骨折等により2個以上の椎体の前方椎体高が著しく減少し、後彎が生じているもの。この場合「前方椎体高が著しく減少」したとは、減少したすべての椎体の後方椎体高の合計と減少後の前方椎体高の合計との差が、減少した椎体の後方椎体高の1個当たりの高さ以上であるもの
(例) 3個の椎体の前方椎体高が減少した場合で、この3個の椎体の後方椎体高の合計が12センチメートル、減少後の前方椎体高の合計が7センチメートルであるときは、両者の差である5センチメートルが、3個の椎体の後方椎体高の1個当たりの高さである4センチメートル以上となっているので、第6級第5号に該当する。
b せき椎圧迫骨折等により1個以上の椎体の前方椎体高が減少し、後彎が生ずるとともに、コブ法による側彎度が50度以上となっているもの。この場合「前方椎体高が減少」したとは、減少したすべての椎体の後方椎体高の合計と減少後の前方椎体高の合計との差が、減少した椎体の後方椎体高の1個当たりの高さの50%以上であるもの
(例) 2個の椎体の前方椎体高が減少した場合で、この2個の椎体の後方椎体高の合計が8センチメートル、減少後の前方椎体高の合計が5,5センチメートルであるときは、両者の差である2.5センチメートルが、2個の椎体の後方椎体高の1個当たりの高さの50%である2センチメートル以上となっているので、コブ法による側彎度が50度以上の側彎を伴うものは第6級第5号に該当する。
(ウ) 「せき柱に中程度の変形を残すもの」とは、エックス線写真等によりせき椎圧迫骨折等を確認することができる場合であって、次のいずれかに該当するものは、第8級に準ずる障害として取り扱うものとする。
a 上記(イ)のbに該当する後彎が生じているもの
b コブ法による側彎度が50度以上であるもの
c 環椎又は軸椎の変形・固定(環椎と軸椎との固定術が行われた場合を含む。)により、次のいずれかに該当するもの。このうち(a)及び(b)については、軸椎以下のせき柱を可動せず(当該者にとっての自然な肢位)、回旋位又は屈曲・伸展位の角度を測定するものとする。
(a) 60度以上の回旋位となっているもの
(b) 50度以上の屈曲位又は60度以上の伸展位となっているもの
(c) 側屈位となっており、エックス線写真等により、矯正位の頭蓋底部の両端を結んだ線と軸椎下面との平行線が交わる角度が30度以上の斜位となっていることが確認できるもの
なお、環椎又は軸椎は、頸椎全体による可動範囲の相当の割合を担っている。そのため、環椎若しくは軸椎がせき椎圧迫骨折等により変形・固定している場合、又は環椎と軸椎との固定術が行われたために、環椎若しくは軸椎の可動性がほとんど失われている場合は、頸椎全体の可動範囲も大きく制限されることから、「せき柱の運動障害」(第8級第2号)に該当する例がほとんどである。
また、環椎又は軸椎が変形・固定していることについては、最大矯正位のエックス線写真等で最もよく確認できる。
(エ) 「せき柱に変形を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
a エックス線写真等によりせき椎圧迫骨折等が認められるもの
b せき椎固定術が行われたもの(移植した骨がいずれかのせき椎に吸収されたものを除く。)
c 3個以上のせき椎について、椎弓切除術等の椎弓形成術を受けたもの
ウ 運動障害
(ア) エックス線写真等では、せき椎圧迫骨折等又はせき椎固定術が認められず、また、項背腰部軟部組織の器質的変化も認められず、単に、疼痛のために運動障害を残すものは、局部の神経症状として等級を決定するものとする。
(注) 「軟部組織」とは、皮膚、筋肉、腱、血管等の組織をいい、せき柱の一部を構成する椎間板は、軟部組織には当たらない。
(イ) 「せき柱に著しい運動障害を残すもの」とは、次のいずれかにより頸部及び胸腰部が強直したものをいう。
a エックス線写真等により、頸椎及び胸腰椎のそれぞれにせき椎圧迫骨折等が確認できるもの
b 頸椎及び胸腰椎のそれぞれにせき椎固定術が行われたもの
c 項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの
(ウ) 「せき柱に運動障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
a 次のいずれかにより、頸部又は胸腰部の運動可能領域が参考可動域の2分の1以上制限されるもの
(a) エックス線写真等により、頸椎又は胸腰椎にせき椎圧迫骨折等が確認できるもの
(b) 頸椎又は胸腰椎にせき椎固定術が行われたもの
(c) 項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの
b 頭蓋と上位頸椎間に著しい異常可動性が生じたもの
(2) その他の体幹骨の変形障害
ア 「鎖骨、胸骨、ろっ骨、肩こう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの」とは、裸体となったとき、変形(欠損を含む。)が明らかにわかる程度のものをいう。したがって、その変形がエックス線写真等によって、はじめて発見し得る程度のものは、これに該当しないものとする。
イ ろっ骨の変形は、その本数、程度、部位等に関係なく、ろっ骨全体を一括して1つの障害として取り扱うものとする。
また、ろく軟骨についても、ろっ骨に準じて取り扱うものとする。
ウ 骨盤骨には仙骨を含めるが、尾骨は除いて取り扱うものとする。
3 併合等の取扱い
(1) 併合
せき柱及びその他の体幹骨の障害で、次に掲げる系列を異にする2以上の障害を残した場合は、併合して等級を決定するものとする。
ただし、骨盤骨の変形とこれに伴う下肢の短縮がある場合は、原則として、いずれか上位の等級により決定するものとする。
ア せき柱の変形障害又は運動障害とその他の体幹骨の変形障害とを残した場合
イ 骨盤骨の高度の変形(転位)によって股関節の運動障害(例えば、中心性脱臼)が生じた場合
ウ 鎖骨の著しい変形と肩関節の運動障害とを残した場合
(2) 準用
せき柱の障害のうち規則別表第5に定めのないものについては、次により等級を決定するものとする。
ア 併合の方法を用いて準用等級を定めるもの
(ア) 頸部と胸腰部のそれぞれに障害がある場合は、併合の方法を用いて準用等級を定めるものとする。
(例1) 「頸椎(環軸椎)が60度回旋位」(準用等級第8級)で、「胸腰椎にせき椎固定術が行われた」(第11級第7号)場合は、準用等級第7級とする。
(例2) 「頸部の運動可能領域が参考可動域の2分の1以上制限され」(第8級第2号)、「胸腰椎にコブ法による側彎度が50度以上の側彎」(準用等級第8級)又は「準用等級第8級の後彎を残す」場合は、併合の方法を用いると準用等級第6級となるが、「せき柱に著しい変形又は運動障害を残すもの」(第6級第5号)には達しないので、その直近下位の第7級とする。
(例3) 頸部及び胸腰部の運動可能領域がそれぞれ参考可動域の2分の1以上制限された場合(第8級第2号)についても、併合の方法を用いると準用等級第6級となるが、上記(例2)と同様にその直近下位の第7級とする。
(例4) 頸部の運動可能領域が参考可動域の2分の1以上制限され、胸腰椎に第6級に相当する後彎を残す場合は、準用等級第6級とする。
なお、頸椎及び胸腰椎にまたがる準用等級第8級の側彎又は後彎を残し、さらに、頸部又は胸腰部に第8級又は第11級の障害を残す場合は、準用等級第7級とする。
また、せき柱の頸部に複数の障害がある場合は、いずれか上位の等級で決定し、胸腰部に複数の障害がある場合の決定も同様とする。
(例) 「腰椎に圧迫骨折による変形を残す」(第11級第7号)とともに、「腰部の運動可能領域が参考可動域の2分の1以上制限された」(第8級第2号)場合は、第8級第2号とする。
(イ) その他の体幹骨の2以上の骨にそれぞれ著しい変形を残した場合は、併合の方法を用いて準用等級を決定するものとする。
(例) 鎖骨と肩こう骨のそれぞれに著しい変形障害を残した場合は、準用等級第11級とする。
イ 他の障害等級を準用するもの
荷重機能の障害については、その原因が明らかに認められる場合であって、そのために頸部及び腰部の両方の保持に困難があり、常時硬性補装具を必要とするものは準用等級第6級とし、頸部又は腰部のいずれかの保持に困難があり、常時硬性補装具を必要とするものは準用等級第8級とする。
(注) 荷重機能の障害の原因が明らかに認められる場合とは、せき椎圧迫骨折・脱臼、せき柱を支える筋肉の麻痺又は項背腰部軟部組織の明らかな器質的変化を残し、それらがエックス線写真等により認められるものをいう。
(3) 加重
胸腰椎にせき椎圧迫骨折を残していた(第11級第7号)者が、更に頸椎のせき椎固定術を行った(第11級第7号)場合は、併合の方法を用いて準用等級を決定すると第10級となるので、加重として取り扱うものとする。
(4) その他
せき髄損傷による神経系統の障害を伴うせき柱の障害については、神経系統の障害として総合的に決定するものとし、また、圧迫骨折等によるせき柱の変形に伴う受傷部位の疼痛については、そのいずれか上位の等級により決定するものとする。
Ⅸ 上肢(上肢及び手指)の障害
1 障害の等級及び程度
(1) 上肢及び手指の障害について、規則別表第5に定める障害の等級及び程度は次のとおりである。
ア 上肢の障害
(ア) 欠損障害(系列区分18・21)
第1級第5号 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
第2級第5号 両上肢を手関節以上で失ったもの
第4級第4号 1上肢をひじ関節以上で失ったもの
第5級第4号 1上肢を手関節以上で失ったもの
(イ) 機能障害(系列区分18・21)
第1級第6号 両上肢の用を全廃したもの
第5級第6号 1上肢の用を全廃したもの
第6級第6号 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
第8級第6号 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
第10級第10号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
第12級第6号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
(ウ) 変形障害(系列区分19・22)
第7級第9号 1上肢に偽関節を残し、著しい障害を残すもの
第8級第8号 1上肢に偽関節を残すもの
第12級第8号 長管骨に変形を残すもの
イ 手指の障害
(ア) 欠損障害(系列区分24・25)
第3級第5号 両手の手指の全部を失ったもの
第6級第8号 1手の5の手指又は母指を含み4の手指を失ったもの
第7級第6号 1手の母指を含み3の手指を失ったもの又は母指以外の4の 手指を失ったもの
第8級第3号 1手の母指を含み2の手指を失ったもの又は母指以外の3の手指を失ったもの
第9級第12号 1手の母指又は母指以外の2の手指を失ったもの
第11級第8号 1手の示指、中指又は環指を失ったもの
第12級第9号 1手の小指を失ったもの
第13級第8号 1手の母指の指骨の一部を失ったもの
第14級第6号 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
(イ) 機能障害(系列区分24・25)
第4級第6号 両手の手指の全部の用を廃したもの
第7級第7号 1手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの
第8級第4号 1手の母指を含み3の手指の用を廃したもの又は母指以外の4の手指の用を廃したもの
第9級第13号 1手の母指を含み2の手指の用を廃したもの又は母指以外の3の手指の用を廃したもの
第10級第7号 1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの
第12級第10号 1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの
第13級第7号 1手の小指の用を廃したもの
第14級第7号 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
(2) 規則別表第5に定められていない上肢及び手指の障害については、規則16―0第25条の4第2項の規定により、その障害の程度に応じて規則別表第5に定める他の障害に準じて等級を決定するものとする。
(3) 上肢及び手指の運動機能の評価及び測定については、以下によるほか、別添「関節の機能障害の評価方法及び関節可動域の測定要領」に準じて取り扱うものとする。
2 障害等級決定の基準
(1) 上肢の障害
ア 欠損障害
(ア) 「上肢をひじ関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
a 肩関節において、肩こう骨と上腕骨とを離断したもの
b 肩関節とひじ関節との間において上腕を切断したもの
c ひじ関節において、上腕骨と前腕骨(橈骨及び尺骨)とを離断したもの
(イ) 「上肢を手関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
a ひじ関節と手関節との間において前腕を切断したもの
b 手関節において、前腕骨と手根骨とを離断したもの
イ 機能障害
(ア) 「上肢の用を全廃したもの」とは、3大関節(肩関節、ひじ関節及び手関節)の全部が強直し、かつ、手指の全部の用を廃したものをいい、上腕神経叢の完全麻痺も含まれるものとする。
(注) 「上腕神経叢の完全麻痺」とは、第5から第7頸髄までの片側の神経根のいずれもが断裂ないし強度に圧迫等されたことにより、上肢全体が弛緩性麻痺に至った場合をいう。
(イ) 「関節の用を廃したもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
a 関節が強直したもの
肩関節にあっては、肩こう上腕関節が癒合し、骨性強直していることがエックス線写真等により確認できるものを含む。
(注) 肩関節は、肩こう上腕関節が強直しても、肩こう骨が胸郭の上を動くことにより、ある程度屈曲又は外転が可能であるため、肩関節の運動可能領域の測定結果にかかわらず、強直として取り扱うものとする。
b 関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にあるもの
「これに近い状態」とは、他動運動では可動するが、自動運動では関節の運動可能領域が健側の運動可能領域の10分の9程度以上制限されるものをいい、この「10分の9程度以上」とは、別添「関節の機能障害の評価及び関節可動域の測定要領」第1の2の(1)「関節の強直」と同様に判断する。
c 人工骨頭又は人工関節を挿入置換した関節のうち、運動可能領域が健側の運動可能領域の2分の1以上制限されるもの
(ウ) 「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
a 関節の運動可能領域が健側の運動可能領域の2分の1以上制限されるもの
b 人工骨頭又は人工関節を挿入置換した関節のうち、上記(イ)のc以外のもの
(エ) 「関節の機能に障害を残すもの」とは、関節の運動可能領域が健側の運動可能領域の4分の1以上制限されるものをいう。
(オ) 骨折部にキュンチャーを装着し、あるいは金属釘を用いたため、それが機能障害の原因となる場合は、当該キュンチャー等の除去を待って等級を決定するものとする。
なお、当該キュンチャー等が、機能障害の原因とならない場合は、創面が治癒した時期をもって「なおった」ときとする。
また、廃用性の機能障害(例えば、ギプスによって患部を固定していたために、治癒後に関節に機能障害を残したもの)については、将来における障害の程度の軽減を考慮して等級の決定を行うものとする。
ウ 変形障害
(ア) 「1上肢に偽関節を残し、著しい障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当し、常時硬性補装具を必要とするものをいう。
なお、「偽関節」とは、一般に、骨折等による骨片間の癒合機転が止まって、異常可動を示すものをいう。
a 上腕骨の骨幹部又は骨幹端部(以下「骨幹部等」という。)に癒合不全を残すもの
b 橈骨及び尺骨の両方の骨幹部等に癒合不全を残すもの
(イ) 「1上肢に偽関節を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
a 上腕骨の骨幹部等に癒合不全を残すもので、上記(ア)のa以外のもの
b 橈骨及び尺骨の両方の骨幹部等に癒合不全を残すもので、上記(ア)のb以外のもの
c 橈骨又は尺骨のいずれか一方の骨幹部等に癒合不全を残すもので、時々硬性補装具を必要とするもの
(注) 回内・回外運動の改善や手関節の安定を図るため、尺骨の一部を切り離し、尺骨の遠位端を橈骨に固定したり、切離した骨を尺骨の遠位端及び橈骨に固定する手術(「カパンジー法」等)が行われ、障害の改善を図っているにもかかわらず、手術後は、より重度の障害である「偽関節を残すもの」に該当するものとなっていた。
このため、カパンジー法による尺骨の一部離断を含め、骨片間の癒合機転が止まって異常可動を示す状態を「癒合不全」とした上で、長管骨の保持性や支持性への影響の程度に応じて障害等級を決定するものとする。
(ウ) 上肢の「長管骨に変形を残すもの」とは、次のaからfのいずれかに該当するものをいい、同一の長管骨にaからfの障害を複数残す場合でも、第12級第8号と決定するものとする。
なお、長管骨の骨折部が短縮なく癒着している場合は、たとえ、その部位に肥厚が生じていても長管骨の変形として取り扱わないものとする。
a 次のいずれかに該当するものであって、外部から想見できる程度(15度以上屈曲して不正癒合したもの)以上のもの
(a) 上腕骨に変形を残すもの
(b) 橈骨及び尺骨の両方に変形を残すもの(ただし、橈骨又は尺骨のいずれか一方のみの変形であっても、その程度が著しいものは該当する。)
b 上腕骨、橈骨又は尺骨の骨端部に癒合不全を残すもの
c 橈骨又は尺骨の骨幹部等に癒合不全を残すもので、硬性補装具を必要としないもの
d 上腕骨、橈骨又は尺骨の骨端部のほとんどを欠損したもの
e 上腕骨(骨端部を除く。)の直径の3分の1以上、又は橈骨若しくは尺骨(それぞれの骨端部を除く。)の直径の2分の1以上減少したもの
f 上腕骨が50度以上、外旋又は内旋して変形癒合しているもの
50度以上回旋変形癒合している場合は、次のいずれにも該当することととなるので、確認するものとする。
(a) 外旋変形癒合にあっては、肩関節の内旋が50度を超えて可動できないこと、また、内旋変形癒合にあっては、肩関節の外旋が10度を超えて可動できないこと
(b) エックス線写真等により、上腕骨骨幹部の骨折部に回旋変形癒合が明らかに認められるもの
(2) 手指の障害
ア 欠損障害
(ア) 「手指を失ったもの」とは、母指にあっては指節間関節、その他の手指にあっては近位指節間関節以上を失ったものをいい、次のものが該当する。
a 手指の中手骨又は基節骨で切断したもの
b 近位指節間関節(母指にあっては、指節間関節)において、基節骨と中節骨とを離断したもの
(イ) 「指骨の一部を失ったもの」とは、1指骨の一部を失っている(遊離骨片の状態を含む。)ことがエックス線写真等において認められるものをいう。
ただし、後記イの(ア)に該当するものは除く。
イ 機能障害
(ア) 「手指の用を廃したもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
a 手指の末節骨の長さの2分の1以上を失ったもの
b 中手指節関節又は近位指節間関節(母指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害(運動可能領域が健側の運動可能領域の2分の1以上制限されたものをいう。)を残したもの
c 母指については、橈側外転又は掌側外転のいずれかの運動可能領域が健側の運動可能領域の2分の1以上制限されているものも、「著しい運動障害を残すもの」に準じて取り扱うものとする。
d 手指の末節の指腹部及び側部の深部感覚及び表在感覚が完全に脱失したものも、「手指の用を廃したもの」に準じて取り扱うものとする。
なお、医学的に障害部位を支配する感覚神経が断裂し得ると判断される外傷を負った事実を確認するとともに、筋電計を用いた感覚神経伝導速度検査を行い、感覚神経活動電位(SNAP)が検出されないことを確認して等級を決定するものとする。
(注) 「感覚の完全脱失」とは、表在感覚のみならず、深部感覚をも消失したものをいい、外傷により感覚神経が断裂した場合に限られる。
(イ) 「手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
a 遠位指節間関節が強直したもの
b 屈伸筋の損傷等原因が明らかなものであって、自動的屈伸が不能となったもの又はこれに近い状態にあるもの
3 併合等の取扱い
(1) 併合
次に掲げる場合にあっては、併合して等級を決定するものとする。
ただし、併合して等級が繰り上げられた結果、障害の序列を乱すこととなる場合は、障害の序列に従って等級を決定するものとする。
なお、上腕骨又は前腕骨(橈骨、尺骨)の骨折によって骨折部に偽関節又は変形を残すとともにその部位に疼痛(第12級相当)を残した場合には、いずれか上位の等級によるものとする。
ア 上肢の障害
(ア) 両上肢に器質的障害(両上肢の亡失を除く。)を残した場合
(例1) 「右上肢に偽関節を残し」(第8級第8号)、かつ、「左上肢を手関節以上で失った」(第5級第4号)場合は、併合等級第3級とする。
(例2) 「右上肢をひじ関節以上で失い」(第4級第4号)、かつ、「左上肢を手関節以上で失った」(第5級第4号)場合は、併合すると第1級となるが、当該障害は、「両上肢をひじ関節以上で失ったもの」(第1級第5号)の障害の程度には達しないので、第2級とする。
(イ) 1上肢の器質的障害及び他の上肢の機能障害を残した場合
(例) 「右上肢を手関節以上で失い」(第5級第4号)、かつ、「左上肢に1関節の用を廃した」(第8級第6号)場合は、併合等級第3級とする。
(ウ) 両上肢に機能障害(両上肢の全廃を除く。)を残した場合
(例) 「右上肢を全廃し」(第5級第6号)、かつ、「左上肢に1関節の著しい機能障害を残した」(第10級第10号)場合は、併合等級第4級とする。
(エ) 同一上肢に欠損障害及び変形障害を残した場合
(例) 「1上肢を手関節以上で失い」(第5級第4号)、かつ、「同上肢の上腕骨に偽関節を残した」(第7級第9号)場合は、併合すると第3級となるが、当該障害は、「1上肢をひじ関節以上で失ったもの」(第4級第4号)の障害の程度には達しないので、第5級とする。
(オ) 同一上肢に機能障害及び変形障害を残した場合
(例) 「1上肢の手関節の機能に障害を残し」(第12級第6号)、かつ、「同上肢の上腕骨に変形を残した」(第12級第8号)場合は、併合等級第11級とする。
(カ) 1上肢に変形障害及び機能障害を残すとともに他の上肢等にも障害を残した場合
(例) 右上肢に「前腕骨の変形」(第12級第8号)と「手関節の著しい機能障害を残し」(第10級第10号)、かつ、左上肢を「手関節以上で失った」(第5級第4号)場合は、まず、右上肢の変形障害と機能障害を併合の方法を用いて準用等級第9級とし、これと左上肢の欠損障害とを併合して併合等級第4級とする。
イ 手指の障害
(ア) 1手の手指の欠損障害及び他手の手指の欠損障害(両手の手指の全部を失ったものを除く。)を残した場合
(例) 「右手の示指を失い」(第11級第8号)、かつ、「左手の環指を失った」(第11級第8号)場合は、併合等級第10級とする。
(イ) 1手の手指の機能障害及び他手の手指の機能障害(両手の手指の全廃を除く。)を残した場合
(例) 「右手の母指の用を廃し」(第10級第7号)、かつ、「左手の示指の用を廃した」(第12級第10号)場合は、併合等級第9級とする。
(ウ) 1手の手指の欠損障害及び他手の手指の機能障害を残した場合
(例) 「右手の5の手指を失い」(第6級第8号)、かつ、「左手の5の手指の用を廃した」(第7級第7号)場合は、併合等級第4級とする。
(2) 準用
次に掲げる場合にあっては、併合の方法を用いて準用等級を定めるものとする。
ただし、その結果、等級の序列を乱すこととなる場合は、その等級の直近上位又は直近下位の等級をもって決定するものとする。
ア 上肢の障害
(ア) 同一上肢に2以上の器質的障害を残した場合
(例) 「1上肢の上腕骨に偽関節を残し」(第7級第9号)、かつ、「同上肢の橈骨及び尺骨に変形を残した」(第12級第8号)場合は、準用等級第6級とする。
(イ) 同一上肢に欠損障害及び機能障害を残した場合
(例) 「1上肢を手関節以上で失い」(第5級第4号)、かつ、「同上肢の肩関節及びひじ関節の用を廃した」(第6級第6号)場合は、これらを併合の方法を用いると準用等級第3級となるが、「1上肢をひじ関節以上で失ったもの」(第4級第4号)には達しないので、その直近下位の第5級とする。
なお、手関節以上の亡失又はひじ関節以上の亡失と関節の機能障害を残した場合は、機能障害の程度に関係なく、前者については準用等級第5級、後者については準用等級第4級とする。
(例) 「1上肢をひじ関節以上で失い」(第4級第4号)、かつ、「同上肢の肩関節の用を廃したもの」(第8級第6号)は、準用等級第4級とする。
(ウ) 同一上肢の3大関節に機能障害を残した場合(用廃を除く。)
(例1) 「1上肢の手関節に機能障害を残し」(第12級第6号)、かつ、「同上肢のひじ関節に著しい機能障害を残した」(第10級第10号)場合は、準用等級第9級とする。
(例2) 「1上肢の肩関節及びひじ関節の用を廃し」(第6級第6号)、かつ、「同上肢の手関節に著しい機能障害を残した」(第10級第10号)場合は、これらを併合の方法を用いると、準用等級第5級となるが、「1上肢の用を廃したもの」(第5級第6号)には達しないので、その直近下位の第6級とする。
なお、「1上肢の3大関節のすべての関節の機能に著しい障害を残したもの」は、序列を考慮し、準用等級第8級とし、また、「1上肢の3大関節のすべての関節の機能に障害を残したもの」は、序列を考慮し、準用等級第10級として取り扱うものとする。
(エ) 1上肢の3大関節の機能障害及び同一上肢の手指の欠損障害又は機能障害を残した場合
(例1) 「1上肢の手関節に機能障害を残し」(第12級第6号)、かつ、「同一上肢の母指の用を廃した」(第10級第7号)場合は、準用等級第9級とする。
(例2) 「1上肢の肩関節及びひじ関節の用を廃し」(第6級第6号)、かつ、「同一上肢の母指及び示指を失った」(第8級第3号)場合は、これらを併合の方法を用いると準用等級第4級となるが、「1上肢の全廃」(第5級第6号)には達しないので、その直近下位の第6級とする。
イ 手指の障害
1手の手指に欠損障害を残すとともに同一手の他の手指に機能障害を残した場合
(例) 「1手の小指を失い」(第12級第9号)、かつ、「同一手の母指の用を廃した」(第10級第7号)場合は、準用等級第9級とする。
ウ 他の障害の等級を準用するもの
(ア) 前腕の回内・回外については、運動可能領域が健側の運動可能領域の4分の3以上制限されているものは準用等級第10級、2分の1以上制限されているものは準用等級第12級とする。
なお、回内・回外の可動域制限と同一上肢の関節の機能障害を残す場合は、併合の方法を用いて準用等級を決定する。
ただし、手関節部又はひじ関節部の骨折等により、手関節又はひじ関節の機能障害と回内・回外の可動域制限を残す場合は、いずれか上位の等級によるものとする。
(イ) 上肢の動揺関節については、それが他動的なもの、自動的なものであるとにかかわらず、次のように取り扱うものとする。
a 常時硬性補装具を必要とするものは、関節の機能障害として準用等級第10級とする。
b 時々硬性補装具を必要とするものは、関節の機能障害として準用等級第12級とする。
(ウ) 習慣性脱臼は、関節の機能障害として準用等級第12級とする。
(3) 加重
ア 次に掲げる場合にあっては、加重として取り扱うものとする。
(ア) 1上肢に障害を有していた者が、同一上肢に系列を同じくする障害を加重した場合
(例1) 1上肢を手関節以上で失っていた者が、更に同一上肢をひじ関節以上で失った場合
(例2) 1上肢の手関節に機能障害を残し、又はひじ関節の用を廃していた者が、更に手関節の著しい機能障害を残し、又は手関節及びひじ関節の用を廃した場合
(例3) 1上肢の橈骨及び尺骨に変形を有していた者が、更に同一上肢の上腕骨に偽関節を残した場合
(イ) 1上肢に障害を有していた者が、更に既存の障害の部位以上を失った場合((ア)に該当する場合を除く。)
(例1) 1上肢の橈骨及び尺骨に変形を有していた者が、更に同一上肢をひじ関節以上で失った場合
(例2) 1手の手指に欠損又は機能障害を有していた者が、更に同一上肢を手関節以上で失った場合
(ウ) 1手の手指に障害を有していた者が、更に同一手の同指又は他指に障害を加重した場合
(例1) 1手の小指の用を廃していた者が、更に同一手の中指の用を廃した場合
(例2) 1手の母指の指骨の一部を失っていた者が、更に同指を失った場合
イ 上肢又は手指の障害で、次に掲げる場合に該当するときは、規則16―0第26条の規定にかかわらず、新たな障害のみが生じたものとみなして取り扱うものとする。
(ア) 1上肢に障害を残していた者が、新たに他の上肢に障害を残した結果、組合せ等級に該当する場合(両手指を含む。)において、規則16―0第26条の規定により算定した障害補償の額が、他の上肢のみに新たな障害のみが生じたものとした場合の障害補償の額に満たないとき
(例) 既に「右上肢を手関節以上で失っていた」(第5級第4号、184日分の年金)者が、新たに「左上肢を手関節以上で失った」(第5級第4号)場合、現存する障害は、「両上肢を手関節以上で失ったもの」(第2級第5号、277日分の年金)に該当するが、この場合の障害補償の額は、左上肢の障害のみが生じたものとみなして、第5級の184日分を支給する。
なお、1上肢に障害を残していた者が、同一上肢(手指を含む。)の障害の程度を加重するとともに他の上肢にも障害を残した場合において、組合せ等級に該当しないときは、記の第1の4の(8)の(例4)の例による。
(イ) 1手の手指に障害を残していた者が、同一手の他指に新たな障害を加重した場合において、規則16―0第26条の規定により算定した障害補償の額が、他指に新たな障害のみが生じたものとした場合の障害補償の額に満たないとき
(例) 既に「右手の示指を亡失していた」(第11級第8号、223日分の一時金)者が、新たに「同一手の環指を亡失した」(第11級第8号、223日分の一時金)場合、現存する障害は、「母指以外の2の手指を失ったもの」(第9級第12号、391日分の一時金)に該当するが、この場合の障害補償の額は、「同一手の環指の障害のみが生じたもの」とみなして、第11級の223日分を支給する。
(ウ) 1手の複数の手指に障害を残していた者が、新たにその一部の手指について障害を加重した場合において、規則16―0第26条の規定により算定した障害補償の額が、その一部の手指に新たな障害のみが生じたものとした場合の障害補償の額に満たないとき
(例) 既に「右手の中指、環指、小指を用廃していた」(第9級第13号、391日分の一時金)者が、新たに「同一手の小指を亡失した」(第12級第9号、156日分の一時金)場合、現存する障害も第9級第13号に該当するものであるが、この場合の障害補償の額は、「同一手の小指の欠損の障害のみが生じたもの」とみなして、同指の用廃分(第13級第7号、101日分の一時金)を差引いた55日分を支給する。
(4) その他
母指の造指術を行った場合にあっては、当該母指の機能的障害と造指術により失った指(示指又は環指、母趾等)の器質的障害を同一災害により生じた障害として取り扱い、これらを併合して等級を決定し、又は準用等級を定めるものとする。
Ⅹ 下肢(下肢及び足指)の障害
1 障害の等級及び程度
(1) 下肢及び足指の障害について、規則別表第5に定める障害の等級及び程度は次のとおりである。
ア 下肢の障害
(ア) 欠損障害(系列区分26・30)
第1級第7号 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
第2級第6号 両下肢を足関節以上で失ったもの
第4級第5号 1下肢をひざ関節以上で失ったもの
第4級第7号 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
第5級第5号 1下肢を足関節以上で失ったもの
第7級第8号 1足をリスフラン関節以上で失ったもの
(イ) 機能障害(系列区分26・30)
第1級第8号 両下肢の用を全廃したもの
第5級第7号 1下肢の用を全廃したもの
第6級第7号 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8級第7号 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
第10級第11号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
第12級第7号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
(ウ) 変形障害(系列区分27・31)
第7級第10号 1下肢に偽関節を残し、著しい障害を残すもの
第8級第9号 1下肢に偽関節を残すもの
第12級第8号 長管骨に変形を残すもの
(エ) 短縮障害(系列区分28・32)
第8級第5号 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
第10級第8号 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
第13級第9号 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
イ 足指の障害
(ア) 欠損障害(系列区分34・35)
第5級第8号 両足の足指の全部を失ったもの
第8級第10号 1足の足指の全部を失ったもの
第9級第14号 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
第10級第9号 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
第12級第11号 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
第13級第10号 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの
(イ) 機能障害(系列区分34・35)
第7級第11号 両足の足指の全部の用を廃したもの
第9級第15号 1足の足指の全部の用を廃したもの
第11級第9号 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
第12級第12号 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
第13級第11号 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
第14級第8号 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
(2) 規則別表第5に定められていない下肢及び足指の障害については、規則16―0第25条の4第2項の規定により、その障害の程度に応じて規則別表第5に定める他の障害に準じて等級を決定するものとする。
(3) 下肢及び足指の運動機能の評価及び測定については、以下によるほか、別添「関節の機能障害の評価方法及び関節可動域の測定要領」に準じて取り扱うものとする。
2 障害等級決定の基準
(1) 下肢の障害
ア 欠損障害
(ア) 「下肢をひざ関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
a 股関節において、寛骨と大腿骨とを離断したもの
b 股関節とひざ関節との間(大腿部)において、切断したもの
c ひざ関節において、大腿骨と下腿骨とを離断したもの
(イ) 「下肢を足関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
a ひざ関節と足関節との間(下腿部)において、切断したもの
b 足関節において、下腿骨と距骨とを離断したもの
(注) 足関節は、脛骨・腓骨と距骨とにより構成されている。踵骨は、距骨との間で距骨下関節を構成し、舟状骨・立方骨と距骨・踵骨との間でショパール関節を構成している。
(ウ) 「リスフラン関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
a 足根骨(踵骨、距骨、舟状骨、立方骨及び3個の楔状骨からなる。)において、切断したもの
b 中足骨と足根骨とを離断したもの
イ 機能障害
(ア) 「下肢の用を全廃したもの」とは、3大関節(股関節、ひざ関節及び足関節)の全部が強直したものをいう。
なお、3大関節が強直したことに加え、足指全部が強直したものもこれに含まれる。
(イ) 「関節の用を廃したもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
a 関節が強直したもの
b 関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にあるもの
「これに近い状態にあるもの」については、上肢と同様に取り扱うものとする。
c 人工骨頭又は人工関節を挿入置換し、かつ、当該関節の運動可能領域が健側の運動可能領域の2分の1以上制限されるもの
(ウ) 「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
a 関節の運動可能領域が健側の運動可能領域の2分の1以上制限されるもの
b 人工骨頭又は人工関節を挿入置換した関節のうち、上記(イ)のc以外のもの
(エ) 「関節の機能に障害を残すもの」とは、関節の運動可能領域が健側の運動可能領域の4分の1以上制限されるものをいう。
(オ) 「廃用性の機能障害」に係る治癒認定及び「キュンチャー等の除去」に係る取扱いについては、上肢における場合と同様とする。
ウ 変形障害
(ア) 「1下肢に偽関節を残し、著しい障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいい、常時硬性補装具を必要とするものをいう。
なお、癒合不全に係る取扱いについては、上肢における場合と同様とする。
a 大腿骨の骨幹部等に癒合不全を残すもの
b 脛骨及び腓骨の骨幹部等に癒合不全を残すもの
c 脛骨の骨幹部等に癒合不全を残すもの
(イ) 「1下肢に偽関節を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
a 大腿骨の骨幹部等に癒合不全を残すもので、上記(ア)のa以外のもの
b 脛骨及び腓骨の骨幹部等に癒合不全を残すもので、上記(ア)のb以外のもの
c 脛骨の骨幹部等に癒合不全を残すもので、上記(ア)のc以外のもの
(ウ) 下肢における「長管骨に変形を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいい、変形が同一の長管骨に複数存する場合も含む。
なお、長管骨の骨折部が短縮なく癒着している場合は、たとえ、その部位に肥厚が生じていても長管骨の変形としては取り扱わないものとする。
a 次のいずれかに該当する場合であって、その変形を外部から想見できる程度(15度以上屈曲して不正癒合したもの)以上のもの
(a) 大腿骨に変形を残したもの
(b) 脛骨に変形を残したもの
なお、腓骨のみの変形であっても、その程度が著しい場合にあっては、「長管骨に変形を残すもの」とする。
b 大腿骨若しくは脛骨の骨端部に癒合不全を残すもの又は腓骨の骨幹部等に癒合不全を残すもの
c 大腿骨又は脛骨の骨端部のほとんどを欠損したもの
d 大腿骨又は脛骨(骨端部を除く。)の直径が3分の1以上減少したもの
e 大腿骨において、外旋が45度以上又は内旋が30度以上回旋変形癒合したもので、次のいずれにも該当するもの
(a) 外旋変形癒合の場合は、股関節の内旋が0度を超えて可動できないこと、内旋変形癒合の場合は、股関節の外旋が15度を超えて可動できないこと
(b) エックス線写真等により、明らかに大腿骨の回旋変形癒合が認められること
エ 短縮障害
「下肢の短縮」については、上前腸骨棘と下腿内果下端間の長さを測定し、健側の下肢と比較し、短縮した長さを算出するものとする。
(2) 足指の障害
ア 欠損障害
「足指を失ったもの」とは、その全部を失ったものをいう。したがって、中足指節関節から失ったものがこれに該当する。
イ 機能障害
「足指の用を廃したもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
(ア) 第1の足指にあっては末節骨の2分の1以上を失ったもの
(イ) 第1の足指以外の足指を中節骨若しくは基節骨を切断したもの又は遠位指節間関節若しくは近位指節間関節において離断したもの
(ウ) 第1の足指にあっては指節間関節、その他の足指にあっては中足指節関節又は近位指節間関節に著しい運動障害を残したもの
なお、「著しい運動障害を残すもの」とは、運動可能領域が健側の運動可能領域の2分の1以上制限されるものをいう。
3 併合等の取扱い
(1) 併合
次に掲げる場合にあっては、併合して等級を決定するものとする。
ただし、併合して等級が繰り上げられた結果、障害の序列を乱すこととなる場合は、障害の序列に従って等級を決定するものとする。
ア 下肢の障害
(ア) 両下肢に器質的障害(両下肢の亡失を除く。)を残した場合
(例1) 「両下肢に長管骨の変形を残した」(それぞれ第12級第8号)場合は、併合等級第11級とする。
(例2) 「右下肢を3センチメートル以上短縮し」(第10級第8号)、かつ、「左下肢を5センチメートル以上短縮した」(第8級第5号)場合は、併合等級第7級とする。
(例3) 「右下肢に偽関節を残し」(第8級第9号)、かつ、「左下肢を5センチメートル以上短縮した」(第8級第5号)場合は、併合等級第6級とする。
(イ) 両下肢の3大関節に機能障害(両下肢の全廃を除く。)を残した場合
(例1) 「右下肢の足関節の用を廃し」(第8級第7号)、かつ、「左下肢のひざ関節の用を廃した」(第8級第7号)場合は、併合等級第6級とする。
(例2) 「右下肢の用を全廃し」(第5級第7号)、かつ、「左下肢のひざ関節及び足関節の用を廃した」(第6級第7号)場合は、併合等級第3級とする。
(ウ) 1下肢の3大関節の機能障害及び他の下肢の器質的障害を残した場合
(例1) 「右下肢の足関節の用を廃し」(第8級第7号)、かつ、「左下肢のリスフラン関節以上で失った」(第7級第8号)場合は、併合等級第5級とする。
(例2) 「右下肢のひざ関節に著しい機能障害を残し」(第10級第11号)、かつ、「左下肢に偽関節を残した」(第8級第9号)場合は、併合等級第7級とする。
(例3) 「右下肢の用を全廃し」(第5級第7号)、かつ、「左下肢を3センチメートル以上短縮した」(第10級第8号)場合は、併合等級第4級とする。
(エ) 同一下肢に欠損障害及び変形障害を残した場合
(例1) 「1下肢をリスフラン関節以上で失い」(第7級第8号)、かつ、「同下肢の長管骨に変形を残した」(第12級第8号)場合は、併合等級第6級とする。
(例2) 「1下肢を足関節以上で失い」(第5級第5号)、かつ、「同下肢の大腿骨に偽関節を残した」(第7級第10号)場合は、併合すると第3級となるが、当該障害は、「1下肢をひざ関節以上で失ったもの」(第4級第5号)の障害の程度には達しないので、第5級とする。
(オ) 同一下肢に機能障害及び変形障害又は短縮障害を残した場合
(例1) 「1下肢の足関節の機能に障害を残し」(第12級第7号)、かつ、「同下肢の脛骨に変形を残した」(第12級第8号)場合は、併合等級第11級とする。
(例2) 「1下肢のひざ関節の機能に障害を残し」(第12級第7号)、かつ、「同下肢を3センチメートル以上短縮した」(第10級第8号)場合は、併合等級第9級とする。
(カ) 1下肢に器質的障害及び機能障害を残すとともに他の下肢等に障害を残した場合
(例) 「右下肢の足関節の用を廃し」(第8級第7号)、「同下肢を1センチメートル以上短縮し」(第13級第9号)、かつ、「左下肢を足関節で失った」(第5級第5号)場合は、まず、右下肢の短縮障害と機能障害を併合の方法を用いて準用等級第7級とし、これと左下肢の欠損障害とを併合して第3級とする。
(キ) 同一下肢に「踵骨骨折治癒後の疼痛」(第12級第13号)及び「足関節の機能に障害を残した」(第12級第7号)場合は、併合等級第11級とする。
イ 足指の障害
(ア) 1足の足指の欠損障害及び他足の足指の欠損障害(両足の足指の全部を失ったものを除く。)を残した場合
(例1) 「右足の第1の足指を失い」(第10級第9号)、かつ、「左足の足指の全部を失った」(第8級第10号)場合は、併合等級第7級とする。
(例2) 「右足の第1の足指を失い」(第10級第9号)、かつ、「左足の第1及び第2の足指を失った」(第9級第14号)場合は、併合等級第8級とする。
(イ) 1足の足指の欠損障害及び他足の足指の機能障害を残した場合
(例1) 「右足の足指の全部を失い」(第8級第10号)、かつ、「左足の足指の全部の用を廃した」(第9級第15号)場合は、併合等級第7級とする。
(例2) 「右足の第1の足指を失い」(第10級第9号)、かつ、「左足の第1及び第2の足指の用を廃した」(第11級第9号)場合は、併合等級第9級とする。
(ウ) 1足の足指の機能障害及び他足の足指の機能障害(両足の足指の全廃を除く。)を残した場合
(例1) 「右足の第1の足指の用を廃し」(第12級第12号)、かつ、「左足の足指の全部の用を廃した」(第9級第15号)場合は、併合等級第8級とする。
(例2) 「右足の第1の足指の用を廃し」(第12級第12号)、かつ、「左足の第1及び第2の足指の用を廃した」(第11級第9号)場合は、併合等級第10級とする。
(2) 準用
次に掲げる場合にあっては、併合の方法を用いて準用等級を定めるものとする。
ただし、その結果、等級の序列を乱すこととなる場合は、その等級の直近上位又は直近下位の等級をもって決定するものとする。
ア 下肢の障害
(ア) 同一下肢に2以上の器質的障害を残した場合
(例) 「1下肢の大腿骨に偽関節を残し」(第7級第10号)、かつ、「同下肢の脛骨に変形を残した」(第12級第8号)場合は、準用等級第6級とする。
(イ) 同一下肢に欠損障害及び機能障害を残した場合
(例1) 「1下肢を足関節以上で失い」(第5級第5号)、かつ、「同下肢の股関節及びひざ関節の用を廃した」(第6級第7号)場合は、これらを併合の方法を用いると準用等級第3級となるが、「1下肢をひざ関節以上で失ったもの」(第4級第5号)には達しないので、その直近下位の第5級とする。
(例2) 「1下肢をひざ関節以上で失い」(第4級第5号)、かつ、「同下肢の股関節の用を廃した」(第8級第7号)場合は、これらを併合の方法を用いると準用等級第2級となるが、1下肢の最上位の等級(第4級第5号)を超えることとなり、序列を乱すので、第4級とする。
(例3) 「1下肢の足関節の用を廃し」(第8級第7号)、かつ、「同下肢をリスフラン関節以上で失った」(第7級第8号)場合は、これらを併合の方法を用いると準用等級第5級となるが、「1下肢を足関節以上で失ったもの」(第5級第5号)には達しないので、その直近下位の第6級とする。
(ウ) 同一下肢の3大関節に機能障害を残した場合(用廃を除く。)
(例1) 「1下肢の足関節の機能に障害を残し」(第12級第7号)、かつ、「同下肢のひざ関節に著しい機能障害を残した」(第10級第11号)場合は、準用等級第9級とする。
(例2) 「1下肢の股関節及びひざ関節の用を廃し」(第6級第7号)、かつ、「同下肢の足関節に著しい機能障害を残した」(第10級第11号)場合は、これらを併合の方法を用いると準用等級第5級となるが、「1下肢の用を全廃したもの」(第5級第7号)には達しないので、その直近下位の第6級とする。
なお、1下肢の3大関節のすべての関節の機能に著しい障害を残したものは、序列を考慮し、準用等級第8級とし、また、1下肢の3大関節のすべての関節の機能に障害を残したものは、序列を考慮し、準用等級第10級として取り扱うものとする。
(エ) 1下肢の3大関節の機能障害及び同一下肢の足指の欠損障害又は機能障害を残した場合
(例1) 「1下肢の足関節の機能に障害を残し」(第12級第7号)、かつ、「同下肢の第1の足指の用を廃した」(第12級第12号)場合は、準用等級第11級とする。
(例2) 「1下肢の股関節及びひざ関節の用を廃し」(第6級第7号)、かつ、「同下肢の足指の全部を失つた」(第8級第10号)場合は、これらを併合の方法を用いると準用等級第4級となるが、「1下肢の用を全廃したもの」(第5級第7号)には達しないので、その直近下位の第6級とする。
イ 足指の障害
(ア) 足指を基部(足指の付け根)から失った場合は、「足指を失ったもの」に準じて取り扱うものとする。
(イ) 1足の足指に、規則別表第5上組合せ等級のない欠損障害又は機能障害を残した場合
(例1) 「1足の第2の足指を含み3の足指を失ったもの」は、「1足の第1の足指以外の4の足指を失ったもの」(第10級第9号)と「1足の第2の足指を含み2の足指を失ったもの」(第12級第11号)との中間に位するものであるが、その障害の程度は第10級第9号には達しないので、その直近下位の第11級とする。
(例2) 「1足の第2の足指を含み3の足指の用を廃したもの」は、「1足の第1の足指以外の4の足指の用を廃したもの」(第12級第12号)と「1足の第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの」(第13級第11号)との中間に位するものであるが、その障害の程度は第12級第12号には達しないので、その直近下位の第13級とする。
(ウ) 1足の足指に欠損障害を残すとともに同一足の他の足指に機能障害を残した場合
(例1) 「1足の第1の足指を失い」(第10級第9号)、かつ、「同一足の第2指以下の用を廃した」(第12級第12号)場合は、準用等級第9級とする。
(例2) 「1足の第3の足指を失い」(第13級第10号)、かつ、「同一足の第1の足指の用を廃した」(第12級第12号)場合は、準用等級第11級とする。
ウ 他の障害の等級を準用するもの
(ア) 下肢の動揺関節については、それが他動的なもの、自動的なものであるとにかかわらず、次のように取り扱うものとする。
a 常時硬性補装具を必要とするものは、関節の機能障害として準用等級第8級とする。
b 時々硬性補装具を必要とするものは、関節の機能障害として準用等級第10級とする。
c 重激な労働等の際以外には硬性補装具を必要としないものは、関節の機能障害として準用等級第12級とする。
(イ) 習慣性脱臼及び弾発ひざは、関節の機能障害として準用等級第12級とする。
(3) 加重
ア 次に掲げる場合にあっては、加重として取り扱うものとする。
(ア) 1下肢に障害を有していた者が、同一下肢に系列を同じくする障害を加重した場合
(例1) 1下肢をリスフラン関節又は足関節以上で失っていた者が、更に同一下肢を足関節又はひざ関節以上で失った場合
(例2) 1下肢の足関節に著しい機能障害を残し、又はひざ関節の用を廃していた者が、更に足関節又はひざ関節以上で失った場合
(例3) 1下肢の足関節の機能に障害を残し、又はひざ関節の用を廃していた者が、更に足関節の著しい機能障害又は足関節とひざ関節の用を廃した場合
(例4) 1下肢の脛骨に変形を有していた者が、更に同一下肢の大腿骨に偽関節を残した場合
(例5) 1下肢を1センチメートル以上短縮していた者が、更に同一下肢を5センチメートル以上短縮した場合
(イ) 1下肢に障害を有していた者が、更に既存の障害の部位以上を失った場合((ア)に該当する場合を除く。)
(例1) 1下肢の脛骨に変形を有していた者が、更に同一下肢をひざ関節以上で失った場合
(例2) 1下肢を1センチメートル以上短縮していた者が、更に同一下肢をひざ関節以上で失った場合
(例3) 1足の足指の欠損又は機能障害を有していた者が、更に同一下肢をリスフラン関節以上で失った場合
(ウ) 1足の足指に障害を有していた者が、更に同一足の同指又は他指に障害を加重した場合
(例) 1足の第5の足指の用を廃していた者が、更に同一足の同指又は他指に障害を加重した場合
(エ) 左右両下肢(両足指を含む。)の組合せ等級に該当する場合
1下肢に障害を残す者が、新たに他の下肢にも障害を残し、又は同一下肢(足指を含む。)に新たに障害を残すとともに、他の下肢にも障害を残した結果、次に掲げる組合せ等級に該当するに至ったときの障害補償の額についても、加重として取り扱うものとする。
a 両下肢をひざ関節以上で失ったもの(第1級第7号)
b 両下肢を足関節以上で失ったもの(第2級第6号)
c 両足をリスフラン関節以上で失ったもの(第4級第7号)
d 両下肢の用を廃したもの(第1級第8号)
e 両足指の全部を失ったもの(第5級第8号)
f 両足指の全部の用を廃したもの(第7級第11号)
イ 下肢又は足指の障害で、次に掲げる場合に該当するものは、規則16―0第26条の規定にかかわらず、新たな障害のみが生じたものとみなして取り扱うものとする。
(ア) 1下肢に障害を残していた者が、新たに他の下肢に障害を残した結果、組合せ等級に該当する場合(両足指を含む。)において、規則16―0第26条の規定により算定した障害補償の額が、他の下肢のみに新たな障害のみが生じたものとした場合の障害補償の額に満たないとき
(イ) 1足の足指に障害を残していた者が、同一足の他指に新たな障害を加重した場合において、規則16―0第26条の規定により算定した障害補償の額が、他指に新たな障害のみが生じたものとした場合の障害補償の額に満たないとき
(ウ) 1足の複数の足指に障害を残していた者が、新たにその一部の足指について障害を加重した場合において、規則16―0第26条の規定により算定した障害補償の額が、その一部の足指に新たな障害のみが生じたものとした場合の障害補償の額に満たないとき
(4) その他
次の場合には、いずれか上位の等級によるものとする。
ア 骨切除が関節部において行われたために、下肢に短縮障害及び関節機能障害を残した場合
イ 長管骨の骨折部位が不正癒合した結果、長管骨の変形又は偽関節と下肢の短縮障害を残した場合
ウ 大腿骨又は下腿骨の骨折部に偽関節又は長管骨の変形を残すとともに、その部位に疼痛(第12級程度)を残した場合
別添
関節の機能障害の評価方法及び関節可動域の測定要領
第1 関節の機能障害の評価方法
関節の機能障害は、関節の可動域の制限の程度に応じて評価するものであり、可動域の測定については、日本整形外科学会及び日本リハビリテーション医学会により決定された「関節可動域表示ならびに測定方法」に準拠して定めた「第2 関節可動域の測定要領」(以下「測定要領」という。)に基づき行うこととする。
ただし、労災保険の障害(補償)給付は労働能力の喪失に対する損害てん補を目的としていること等から、関節の機能障害の評価方法として以下のような特徴がある。
1 関節の運動と機能障害
(1) 関節可動域の比較方法
関節の機能障害の認定に際しては、障害を残す関節の可動域を測定し、原則として健側の可動域角度と比較することにより、関節可動域の制限の程度を評価するものであること。
ただし、せき柱や健側となるべき関節にも障害を残す場合等にあっては、測定要領に定める参考可動域角度との比較により関節可動域の制限の程度を評価すること。
(2) 関節運動の障害評価の区別
各関節の運動は単一の場合と複数ある場合があり、複数ある場合には各運動毎の重要性に差違が認められることから、それらの運動を主要運動、参考運動及びその他の運動に区別して障害の評価を行う。
各関節の運動のうち、測定要領に示したものは、主要運動又は参考運動として、その可動域制限が評価の対象となるものである。
各関節の主要運動と参考運動の区別は次のとおりである。
部位 主要運動 参考運動
せき柱(頸部) 屈曲・伸展、回旋 側屈
せき柱(胸腰部) 屈曲・伸展 回旋、側屈
肩関節 屈曲、外転・内転 伸展、外旋・内旋
ひじ関節 屈曲・伸展
手関節 屈曲・伸展 橈屈、尺屈
前腕 回内・回外
股関節 屈曲・伸展、外転・内転 外旋・内旋
ひざ関節 屈曲・伸展
足関節 屈曲・伸展
母指 屈曲・伸展、橈側外転、掌側外転
手指及び足指 屈曲・伸展
これらの運動のうち、原則として、屈曲と伸展のように同一面にある運動については、両者の可動域角度を合計した値をもって関節可動域の制限の程度を評価すること。
ただし、肩関節の屈曲と伸展は、屈曲が主要運動で伸展が参考運動であるので、それぞれの可動域制限を独立して評価すること。
(3) 主要運動と参考運動の意義
主要運動とは、各関節における日常の動作にとって最も重要なものをいう。多くの関節にあっては主要運動は一つであるが、上記のとおりせき柱(頸椎)、肩関節及び股関節にあっては、二つの主要運動を有する。
関節の機能障害は、原則として主要運動の可動域の制限の程度によって評価するものであること。
ただし、後記2の(3)に定めるところにより、一定の場合には、主要運動及び参考運動の可動域制限の程度によって、関節の機能障害を評価するものであること。
なお、測定要領に定めた主要運動及び参考運動以外の運動については、関節の機能障害の評価の対象としないものであること。
2 関節の機能障害の具体的評価方法
関節の機能障害の評価は、具体的には「せき柱及びその他の体幹骨、上肢並びに下肢の障害に関する障害等級認定基準」の各節によるほか、以下にしたがって行うこと。
(1) 関節の強直
関節の強直とは、関節の完全強直又はこれに近い状態にあるものをいう。
この場合、「これに近い状態」とは、関節可動域が、原則として健側の関節可動域角度の10%程度以下に制限されているものをいい、「10%程度」とは、健側の関節可動域角度(せき柱にあっては、参考可動域角度)の10%に相当する角度を 5度単位で切り上げた角度とすること。
なお、関節可動域が10度以下に制限されている場合はすべて「これに近い状態」に該当するものと取り扱うこと。
例 ひざ関節(屈曲)に大きな可動域制限があり、健側の可動域が130度である場合は、可動域制限のある関節の可動域が、130度の10%を5度単位で切り上げた15度以下であれば、ひざ関節の強直となる。
(2) 主要運動が複数ある関節の機能障害
ア 関節の用廃
上肢・下肢の3大関節のうち主要運動が複数ある肩関節及び股関節については、いずれの主要運動も全く可動しない又はこれに近い状態となった場合に、関節の用を廃したものとすること。
イ 関節の著しい機能障害及び機能障害
上肢・下肢の3大関節のうち主要運動が複数ある肩関節及び股関節については、主要運動のいずれか一方の可動域が健側の関節可動域角度の2分の1以下又は4分の3以下に制限されているときは、関節の著しい機能障害又は機能障害と認定すること。
また、せき柱(頸椎)にあっては、屈曲・伸展又は回旋のいずれか一方の可動域が参考可動域角度の2分の1以下に制限されているときは、せき柱に運動障害を残すものと認定すること。
(3) 参考運動を評価の対象とする場合
上肢及び下肢の3大関節については、主要運動の可動域が2分の1(これ以下は著しい機能障害)又は4分の3(これ以下は機能障害)をわずかに上回る場合に、当該関節の参考運動が2分の1以下又は4分の3以下に制限されているときは、関節の著しい機能障害又は機能障害と認定するものであること。
また、せき柱については、頸椎又は胸腰椎の主要運動の可動域制限が参考可動域角度の2分の1をわずかに上回る場合に、頸椎又は胸腰椎の参考運動が2分の1以下に制限されているときは、頸椎又は胸腰椎の運動障害と認定するものであること。
これらの場合において、「わずかに」とは、原則として5度とする。
ただし、次の主要運動についてせき柱の運動障害又は関節の著しい機能障害に当たるか否かを判断する場合は10度とする。
a せき柱(頸部)の屈曲・伸展、回旋
b 肩関節の屈曲、外転
c 手関節の屈曲・伸展
d 股関節の屈曲・伸展
例1 肩関節の屈曲の可動域が90度である場合、健側の可動域角度が170度であるときは、170度の2分の1である85度に10度を加えると95度となり、患側の可動域90度はこれ以下となるので、肩関節の参考運動である外旋・内旋の可動域が2分の1以下に制限されていれば、著しい機能障害(第10級の9)となる。
例2 肩関節の屈曲の可動域が130度である場合、健側の可動域角度が170度であるときは、170度の4分の3である127.5度に5度を加えると132.5度となり、患側の可動域130度はこれ以下となるため、肩関節の参考運動である外旋・内旋の可動域が4分の3以下に制限されているときは、機能障害(第12級の6)となる。
なお、参考運動が複数ある関節にあっては、1つの参考運動の可動域角度が上記のとおり制限されていることをもって足りるものであること。
第2 関節可動域の測定要領
1 労災保険における関節可動域の測定
(1) 関節の機能障害は、関節そのものの器質的損傷によるほか、各種の原因で起こり得るから、その原因を無視して機械的に角度を測定しても、労働能力の低下の程度を判定する資料とすることはできない。
したがって、測定を行う前にその障害の原因を明らかにしておく必要がある。関節角度の制限の原因を大別すれば、器質的変化によるものと機能的変化によるものとに区分することができる。さらに、器質的変化によるもののうちには、関節それ自体の破壊や強直によるもののほかに、関節外の軟部組織の変化によるもの(例えば、阻血性拘縮)があり、また、機能的変化によるものには、神経麻痺、疼痛、緊張によるもの等があるので、特に機能的変化によるものの場合には、その原因を調べ、症状に応じて測定方法等に、後述するとおり、考慮を払わなければならない。
関節可動域の測定値については、日本整形外科学会及び日本リハビリテーション医学会により決定された「関節可動域表示ならびに測定法」に従い、原則として、他動運動による測定値によることとするが、他動運動による測定値を採用することが適切でないものについては、自動運動による測定値を参考として、障害の認定を行う必要がある。
他動運動による測定値を採用することが適切でないものとは、例えば、末梢神経損傷を原因として関節を可動させる筋が弛緩性の麻痺となり、他動では関節が可動するが、自動では可動できない場合、関節を可動させるとがまんできない程度の痛みが生じるために自動では可動できないと医学的に判断される場合等をいう。
また、関節が1方向には自動できるが逆方向には自動できない場合の可動域については、基本肢位から自動できない場合は0度とすること。
例 手関節を基本肢位から自動で90度屈曲することができるが、橈骨神経損傷により自動では伸展が全くできない場合、健側の可動域が屈曲・伸展を合計して160度のときは、患側の可動域は、健側の4分の3以下に制限されていることとなり、「関節の機能障害」に該当する。
(2) 被測定者の姿勢と肢位によって、各関節の運動範囲は著しく変化する。特に関節自体に器質的変化のない場合にはこの傾向が著しい。例えば、前述した阻血性拘縮では手関節を背屈すると各指の屈曲が起こり、掌屈すると各指の伸展が起こる。
また、ひじ関節では、その伸展筋が麻痺していても、下垂位では、自然に伸展する。
そこで、各論において述べる基本的な測定姿勢のほか、それぞれの事情に応じ、体位を変えて測定した値をも考慮して運動制限の範囲を測定しなければならない。
(3) 人の動作は、一関節の単独運動のみで行われることは極めてまれであって、一つの動作には、数多くの関節の運動が加わるのが普通である。したがって、関節の角度を測定する場合にも、例えば、せき柱の運動には股関節の運動が、前腕の内旋又は外旋運動には、肩関節の運動が入りやすいこと等に注意しなければならない。しかし、他面、かかる各関節の共働運動は無意識のうちにも起こるものであるから注意深く監察すれば、心因性の運動制限を診断し、又は詐病を鑑別するに際して役立つことがある。なお、障害補償の対象となる症状には心因性の要素が伴われがちであるが、これが過度にわたる場合は当然排除しなければならない。その方法としては、前述の各関節の共働運動を利用して、被測定者の注意をり患関節から外させて測定する方法のほかに、筋電図等電気生理学的診断、精神・神経科診断等が有効である。
2 関節可動域表示並びに測定法の原則
(1) 基本肢位
概ね自然立位での解剖学的肢位を基本肢位とし、その各関節の角度を0度とする。
ただし、肩関節の外旋・内旋については肩関節外転0度で肘関節90度屈曲位、前腕の回外・回内については手掌面が矢状面にある肢位、股関節外旋・内旋については股関節屈曲90度でひざ関節屈曲90度の肢位をそれぞれ基本肢位とする。
(2) 関節の運動
ア 関節の運動は直交する3平面、すなわち前額面、矢状面、水平面を基本面とする運動である。ただし、肩関節の外旋・内旋、前腕の回外・回内、股関節の外旋・内旋、頸部と胸腰部の回旋は、基本肢位の軸を中心とした回旋運動である。また、母指の対立は、複合した運動である。
イ 関節可動域測定とその表示で使用する関節運動とその名称を以下に示す。
なお、下記の基本的名称以外によく用いられている用語があれば( )内に表記する。
(ア) 屈曲と伸展
多くは矢状面の運動で、基本肢位にある隣接する2つの部位が近づく動きが屈曲、遠ざかる動きが伸展である。ただし、肩関節、頸部・体幹に関しては、前方への動きが屈曲、後方への動きが伸展である。また、手関節、手指、足関節、足指に関しては、手掌または足底への動きは屈曲、手背または足背への動きが伸展である。
(イ) 外転と内転
多くは前額面の運動で、体幹や手指の軸から遠ざかる動きが外転、近づく動きが内転である。
(ウ) 外旋と内旋
肩関節及び股関節に関しては、上腕軸または大腿軸を中心として外方へ回旋する動きが外旋、内方へ回旋する動きが内旋である。
(エ) 回外と回内
前腕に関しては、前腕軸を中心にして外方に回旋する動き(手掌が上を向く動き)が回外、内方に回旋する動き(手掌が下を向く動き)が回内である。
(オ) 右側屈・左側屈
頸部、体幹の前額面の運動で、右方向への動きが右側屈、左方向への動きが左側屈である。
(カ) 右回旋と左回旋
頸部と胸腰部に関しては、右方に回旋する動きが右回旋、左方に回旋する動きが左回旋である。
(キ) 橈屈と尺屈
手関節の手掌面の運動で、橈側への動きが橈屈、尺側への動きが尺屈である。
(ク) 母指の橈側外転と尺側内転
母指の手掌面の運動で、母指の基本軸から遠ざかる動き(橈側への動き)が橈側外転、母指の基本軸に近づく動き(尺側方向への動き)が尺側内転である。
(ケ) 掌側外転と掌側内転
母指の手掌面に垂直な平面の運動で、母指の基本軸から遠ざかる動き(手掌方向への動き)が掌側外転、基本軸に近づく動き(背側方向への動き)が掌側内転である。
(コ) 中指の橈側外転と尺側外転
中指の手掌面の運動で、中指の基本軸から橈側へ遠ざかる動きが橈側外転、尺側へ遠ざかる動きが尺側外転である。
(3) 関節可動域の測定方法
ア 関節可動域は、他動運動でも自動運動でも測定できるが、原則として他動運動による測定値を表記する。自動運動による測定値を用いる場合は、その旨明記する〔(4)のイの(ア)参照〕。
イ 角度計は、十分な長さの柄がついているものを使用し、通常は、5度刻みで測定する。
ウ 基本軸、移動軸は、四肢や体幹において外見上分かりやすい部位を選んで設定されており、運動学上のものとは必ずしも一致しない。また、手指および足指では角度計のあてやすさを考慮して、原則として背側に角度計をあてる。
エ 基本軸と移動軸の交点を角度計の中心に合わせる。また、関節の運動に応じて、角度計の中心を移動させてもよい。必要に応じて移動軸を平行移動させてもよい。
オ 多関節筋が関与する場合、原則としてその影響を除いた肢位で測定する。例えば、股関節屈曲の測定では、ひざ関節を屈曲しひざ屈筋群をゆるめた肢位で行う。
カ 肢位は「測定肢位および注意点」の記載に従うが、記載のないものは肢位を限定しない。変形、拘縮などで所定の肢位が取れない場合は、測定肢位が分かるように明記すれば異なる肢位を用いてもよい〔(4)のイの(イ)参照〕。
キ 筋や腱の短縮を評価する目的で多筋を緊張させた肢位で関節可動域を測定する場合は、測定方法が分かるように明記すれば、多関節筋を緊張させた肢位を用いてもよい〔(4)のイの(ウ)参照〕。
(4) 測定値の表示
ア 関節可動域の測定値は、基本肢位を0度として表示する。例えば、股関節の可動域が屈曲位20度から70度であるならば、この表現は以下の2通りとなる。
(ア) 股関節の関節可動域は屈曲20度から70度(または屈曲20度~70度)
(イ) 股関節の関節可動域は屈曲は70度、伸展は-20度
イ 関節可動域の測定に際し、症例によって異なる測定法を用いる場合や、その他関節可動域に影響を与える特記すべき事項がある場合は、測定値とともにその旨併記する。
(ア) 自動運動を用いて測定する場合は、その測定値を( )で囲んで表示するか、「自動」または「active」などと明記する。
(イ) 異なる肢位を用いて測定する場合は、「背臥位」「座位」などと具体的に肢位を明記する。
(ウ) 多関節筋を緊張させた肢位を用いて測定する場合は、その測定値を〈 〉で囲んで表示するが、「ひざ伸展位」などと具体的に明記する。
(エ) 疼痛などが測定値に影響を与える場合は、「痛み」「pain」などと明記する。
(5) 参考可動域
関節可動域については、参考可動域として記載した。
(6) その他留意すべき事項
ア 測定しようとする関節は十分露出すること。特に女性の場合には、個室、更衣室の用意が必要である。
イ 被測定者に精神的にも落ちつかせる必要があり、測定の趣旨をよく説明するとともに、気楽な姿勢をとらせること。
(7) 各論