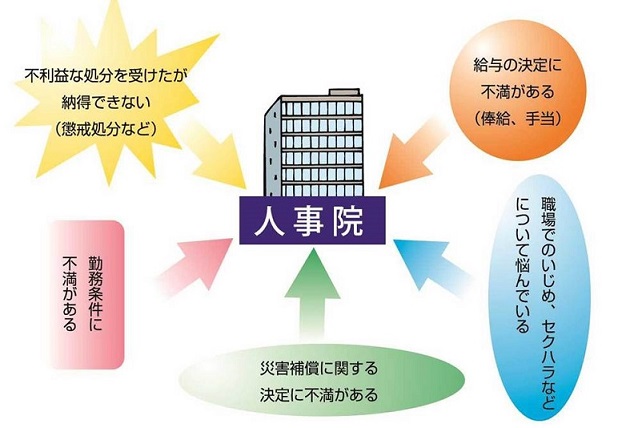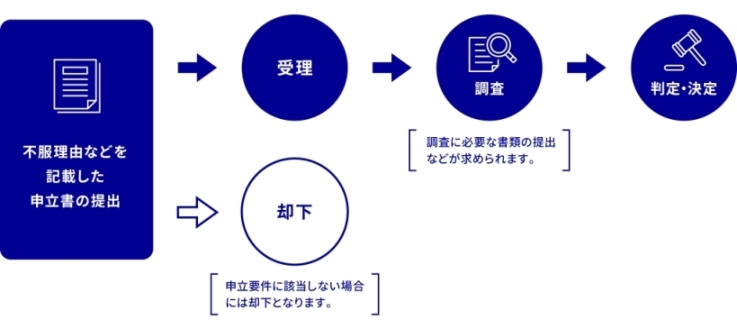公平審査制度に関連する法律・人事院規則
(参考)国家公務員関係法令等一覧
担当窓口
さらに詳しく、人事院が行っている公平審査制度や相談制度について知りたい方は、下記の担当部署にお問い合わせください。
本院
人事院事務総局公平審査局
〒105-0001 東京都港区虎ノ門2-2-3 虎ノ門アルセアタワー
※ 人事院事務総局(本院)の庁舎移転により、令和8年2月9日より所在地が変更になりました。
03-3581-5311(代表)
- 公平審査制度全般 調整課 内線5871
- 勤務条件や勤務環境等に関する相談 職員相談課
直通 03-3581-3486
(開設時間(平日)9:00~17:00)(原則30分以内)
地方事務局(所)
人事院北海道事務局第一課
〒060-0042 札幌市中央区大通西12丁目 札幌第3合同庁舎
011-241-1249
人事院東北事務局第一課
〒980-0014 仙台市青葉区本町3-2-23 仙台第2合同庁舎
022-221-2002
人事院関東事務局第一課
〒330-9712 さいたま市中央区新都心1-1 さいたま新都心合同庁舎1号館
048-740-2005
人事院中部事務局第一課
〒460-0001 名古屋市中区三の丸2-5-1 名古屋合同庁舎第2号館
052-961-6839
人事院近畿事務局第一課
〒553-8513 大阪市福島区福島1-1-60 大阪中之島合同庁舎3階
06-4796-2181
人事院中国事務局第一課
〒730-0012 広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎2号館
082-228-1182
人事院四国事務局第一課
〒760-0019 高松市サンポート3-33 高松サンポート合同庁舎南館
087-880-7441
人事院九州事務局第一課
〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-11-1 福岡合同庁舎
092-431-7732
人事院沖縄事務所調査課
〒900-0022 那覇市樋川1-15-15 那覇第一地方合同庁舎西棟
098-834-8401