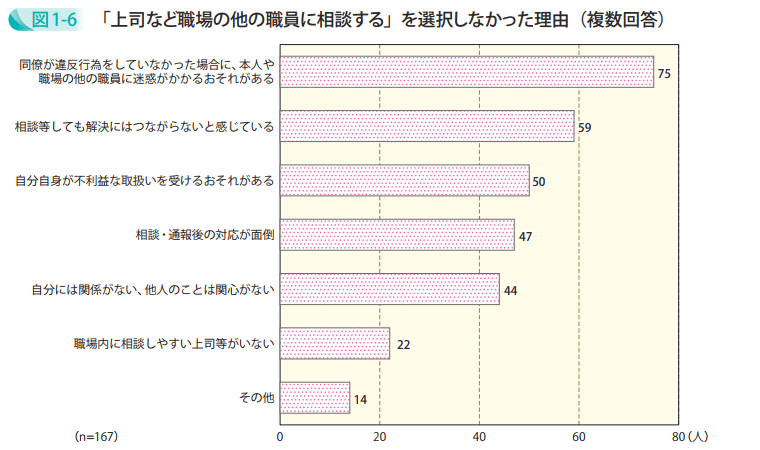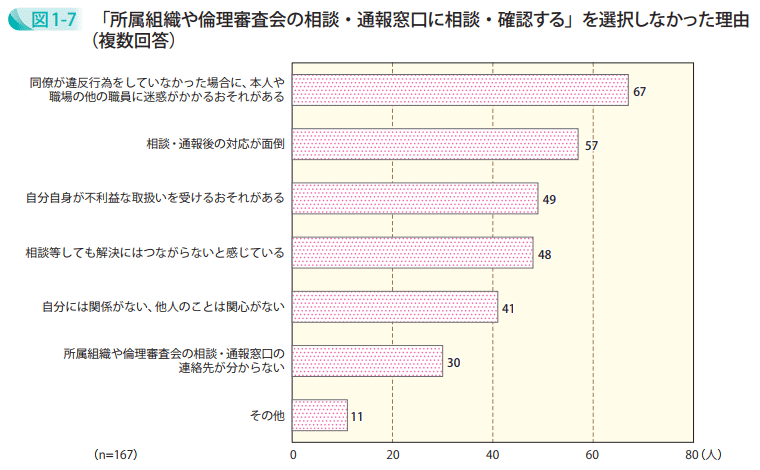公務員倫理に関しては、職員自身が襟を正すべきことは当然のことであるが、国民や職員の仕事の相手方となる事業者等にも周知することは、職員・事業者双方にとって、円滑な業務運営に資するものとなる。そのため、1(3)で述べた各府省からの周知等の取組と併せて、倫理審査会としても国民や事業者等への広報を行っている。また、倫理審査会では、倫理の保持のための施策の参考とするため、倫理制度や公務員倫理をめぐる諸問題について、各界から意見を聴取しており、また、各府省の倫理法・倫理規程の運用実態、倫理法・倫理規程に対する要望等の把握に努めている。令和4年度においては、次の(1)~(3)の活動が行われた。
(1)国民や事業者等への広報活動
国家公務員と接触する機会のある事業者等に対して倫理法・倫理規程の周知及び理解の促進を図るため、全国の経済団体等に対し機関誌やウェブサイトへの公務員倫理に関する記事やパンフレットなどの掲載、会員企業のコンプライアンス担当部署に対する広報依頼など、事業者等に対する広報活動への協力の依頼等を行った。
1(3)で述べたように、職員向けの啓発用ポスターとは別に新たに作成した事業者向けの啓発用ポスターについては、令和4年11月から12月にかけて、倫理審査会の会長及び委員が日本経済団体連合会、経済同友会、日本商工会議所及び全国中小企業団体中央会を訪問し、事業者向けのポスター等の広報依頼を行うとともに、国家公務員倫理に関するルールの説明及び意見交換を行った。訪問した団体からは「官と民の情報交換の機会は大事であり、倫理法があることで過度に萎縮するのはよくない。官と民の情報交換の機会は確保しつつ、お互い一定の節度を持ってやっていくのが大事であり、民間に公務員側のルールを周知するというのは良い取組ではないか。」、「事業者向けポスターの作成は本年度が初めてとのことだが、膨大な数の企業に周知するためには、継続して啓発活動を行うことが重要である。少なくとも数年間は続けた方がよい。」といった意見が聴かれた。これらの団体からは、啓発資料のウェブサイトや機関誌への掲載、会員への送付等、事業者等に対する広報活動に多大な協力を得た。また、地方公共団体に対しても、国家公務員倫理月間の啓発用ポスターの電子媒体を47都道府県、20政令指定都市に配布し、国家公務員倫理に関する周知を要請した。
また、近年の幹部職員による倫理法等違反事案の発生を踏まえ、引き続き各府省における職務の相手方となる事業者等への倫理法・倫理規程の周知に重点を置いた。そこで、各府省に対し、利害関係者となり得る関係団体や契約の相手方等に対して直接、事業者向けの各種広報資材(公務員倫理制度について事業者等に知ってもらいたい内容を簡潔にまとめたカード形式の啓発資料やYouTube動画)等を用いて、公務員倫理保持のための制度の周知や理解・協力を求める取組の実施あるいは検討を要請した。一部の省庁では、倫理審査会作成の事業者向けカードや事業者用ポスターを活用した周知徹底のほか、関係団体等に倫理保持の協力を要請する文書を発出する、会合など直接接する機会に倫理保持への協力を要請するなどの取組が行われた。倫理審査会としては、各府省で実施された啓発活動の具体例の共有等を通じ、各省とも連携しつつなお一層の事業者等への広報活動の展開が重要であると考えている。
さらに、事業者等に対し、公務員倫理に関するより一層の周知を図るため、12月の倫理月間中には、政府広報の機会を利用して、BSテレビ番組中のミニコーナーで、事業者等に対する公務員倫理及び国家公務員倫理月間の広報活動を行った。
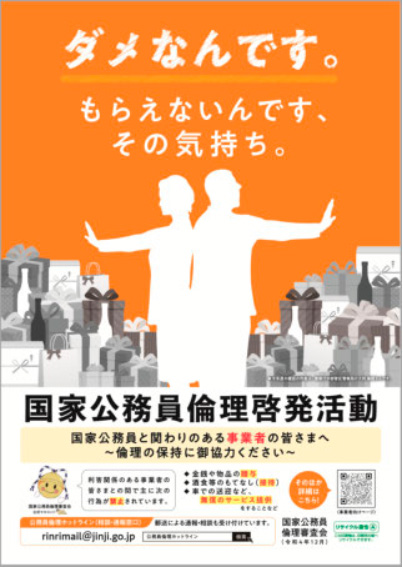
事業者向けの啓発ポスター

左から、伊藤委員、秋吉会長、市川副代表幹事、秋池副代表幹事
(経済同友会訪問時)

政府広報テレビの収録風景

国家公務員倫理月間の政府広報(テレビ)
【コラム】倫理百考 ~倫理月間を振り返って~
昨年度の倫理月間での新たな試みは、「国家公務員と事業者とが協力して倫理保持を」という観点から、倫理ポスターを公務員向けと事業者向けの2種類作成し、経済団体を訪問して公務員倫理への理解と協力をお願いしたことである。お忙しい中ご協力いただいた経済団体の皆様に、心より感謝申し上げる。
ところで、その2種類のポスターを眺めていて、あることに気付かされた。それは、「公務員倫理」をどう捉えるのか、ということである。
事業者向けのポスターに記載された「ダメなんです。もらえないんです、その気持ち。」という標語は、倫理を「~してはいけない」と捉える、プリミティブな考え方といえよう。一方、公務員向けのそれに記載された「倫理観 高いあなたに 信頼感」という標語は、倫理を守っていればこんないいことがあるという、発展的な捉え方ではないか。前者を、個人の行動の是非を教える伝統的な「予防倫理」とし、後者を、「なすべきこと」に着目し行動を促していくポジティブな「志向倫理」と説明する識者もいる(村松邦子・人事院月報第869号24頁参照)。
どちらがいいとか悪いとかいうものではない。倫理法・倫理規程が施行されて20数年経過した現在でも、残念ながら倫理法令違反は一定数発生しており、倫理保持のための予防倫理が基本であって出発点であることに疑いない。ただ、多くの公務員が、倫理法令を当然のように遵守しつつ、日々、職務に励んでいることも、また、疑いのない事実であろう。そんな志の高い公務員にとって、倫理法令は、それに違反すれば処分を受ける、だから守るという、ネガティブな、煩わしいだけのものなのであろうか。倫理観が高ければ職場で信頼を得られる → 周囲や国民の信頼を得て仕事ができることにやりがいを感じる → 公務員生活が充実するというように、それを守ることによって幸せな公務員生活を送ることができるという、より価値の高いものではないか。
考えを巡らせていると、なぜ我々は公務員倫理を守るのかという根源的な問題にもたどり着くように思われる。
(2)有識者からの意見聴取の実施
倫理審査会では、各界の有識者から、国家公務員の倫理保持の状況や倫理保持のための施策、これからの官民連携と倫理保持の在り方などについての意見聴取を行っている。令和4年度においては、報道関係者、弁護士、学識経験者など各界の有識者から個別に意見を聴取した。
〈有識者からの主な意見〉
- ・ 民間企業は「公務員が言うこと、行うことは正しい」という前提で行動する傾向にあるので、国家公務員には倫理に関するルールをしっかり教育する必要がある。倫理面での運用上グレーな部分にも的確に対応できるように、知識を習得させるだけではなく、公務員としての矜持を高めるための取組が必要。
- ・ 国家公務員の「飲食費用は割り勘で」というルールは民間企業にかなり周知されているが、公式な会議だけでなく、飲食を共にして本心で話し合うことで関係を構築するには心理的なハードルが高いと思う。贈与等報告書の提出が必要となる金額の設定等は時代に合わせて若干見直してもよいのではないか。
- ・ 企業のビジョン・パーパス(「自分たちの会社は何のために存在しているのか」、「どのような価値を社会に提供するために会社が作られたのか」等)のように、国家公務員としての存在意義・責務とは何かという原点を改めて一人一人の国家公務員がしっかりと心に刻み、組織全体として共有・浸透することが非常に重要。国民の信頼を裏切る不祥事が起こると将来有望な若い人が国家公務員の仕事を選ばなくなるというリスクがあるということも認識すべきであり、結果として国民にとっても大きな損失に繋がるので、改めて国家公務員には倫理保持の重要性を認識してほしい。
- ・ 一般に内部通報窓口に連絡することはハードルが高いイメージがある。相談内容に幅広に辛抱強く対応していれば、「窓口に相談すれば解決してくれる、完璧ではないにせよ何かしら動いてくれる」と思ってもらえるようになり、窓口として機能していく。また、通報者の秘密保持、通報が不利益を被らないことが担保され、周知徹底されている実績を一つ一つ積み上げていくことも重要。たとえ、通報した内容を実際に調査した結果、事実とは異なっていたとしても、勇気を持って情報を寄せた人を評価する必要。
- ・ 幹部社員の不祥事は企業に与えるインパクトが非常に大きいので、民間企業ではそこに対するガバナンスをどう効かせるかということに注力していると言っても過言ではない。公務員の組織でも、通報制度が幹部職員に対しても忖度なく機能するということをどう見せるかが非常に重要なポイントだろう。
- ・ 組織カルチャーとしての心理的安全性は、不祥事を防ぐという観点でも非常に重要。「これはおかしいのではないか」、「このやり方は問題があるのではないか」と思った時に、上司や仲間に伝えることができるハードルの低さに大きく関わってくる。世代や上下関係を問わず、率直に感じたことが言えるようにするといった方針をリーダーがしっかり示して、自ら実際に行動で示していくことが、心理的安全性を担保するカルチャーをつくる上で重要。
- ・ 公務員倫理は、個人の幸福追求権と対立・矛盾するとか、緊張関係にあるものとして捉えるのではなく、むしろ公務員個人が本来の使命を果たすことによって、より良い職務を遂行し、幸福な職務遂行に寄与する観点からも捉えるべき。倫理に背くとか、問題がある行為は、良心の呵責を感じることにもなりえて、少なくとも清々しい、気持ちの良い仕事にはならないのではないか。精神衛生上も、自己の小さな経済的な利益よりも、より大きな利益のためにより良い仕事をするように務め、よりよい仕事を通して自己実現を図るところに公務員倫理の重要な意義があると思う。
(3)アンケートの実施
倫理審査会では、倫理保持のための施策の企画等に活用するため、毎年、各種アンケートを実施している。令和4年度に実施したアンケート結果の概略は、次のとおりである。
・ 市民アンケート
国民各層から年齢・性別・地域等を考慮して抽出した1,000人を対象に令和4年8月に実施(Web調査)
・ 職員アンケート
一般職の国家公務員のうち、本府省、地方機関の別、役職段階等を考慮して抽出した2,500人を対象に令和4年9月から10月にかけて実施(原則Web調査とし、同調査による回答が困難な者に限り郵送調査。回答数2,252人)
ア 国家公務員の倫理感についての印象(市民アンケート)[図1-1]
市民アンケートで「国家公務員の倫理感の印象」について質問したところ、「倫理感が高い」又は「全体として倫理感が高いが、一部に低い者もいる」と回答した割合は 52.7%であった。一方、厳しい見方をしている回答割合(「全体として倫理感が低いが、一部に高い者もいる」又は「倫理感が低い」と回答した割合)は14.9%であった。
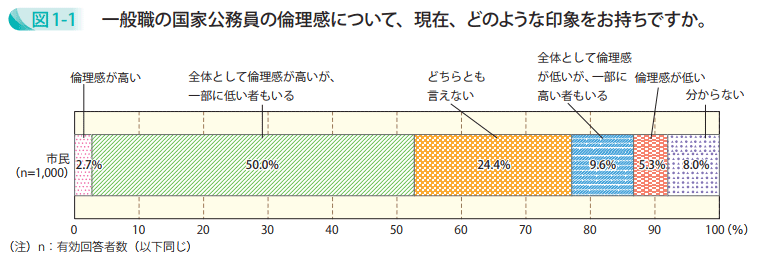
一般職の国家公務員の倫理感について、現在、どのような印象をお持ちですか。のcsvファイルはこちら
イ 所属する組織の倫理感についての印象(職員アンケート)[図1-2]
職員アンケートで「所属する組織の倫理感の印象」について質問したところ、好意的な見方をしている回答割合(「倫理感が高い」又は「どちらかと言えば倫理感が高い」と回答した割合)は81.0%であった。一方、厳しい見方をしている回答割合(「どちらかと言えば倫理感が低い」又は「倫理感が低い」と回答した割合)は2.8%であった。
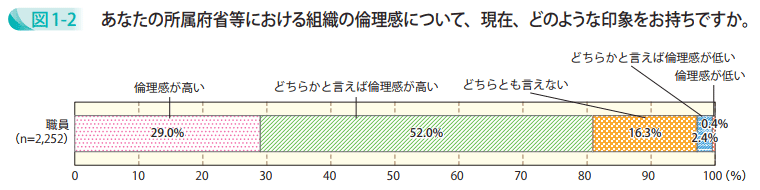
あなたの所属府省等における組織の倫理感について、現在、どのような印象をお持ちですか。のcsvファイルはこちら
ウ 近年の一般職の国家公務員の職務に係る倫理の保持の状況についての印象(市民アンケート)[図1-3]
市民アンケートで「近年の一般職の国家公務員の職務に係る倫理の保持の状況」について質問したところ、好意的な見方をしている回答割合(「良くなっている」と回答した割合)は、一般職員については4.0%、幹部職員については2.4%であった。一方で、厳しい見方をしている回答割合(「悪くなっている」と回答した割合)は、一般職員について32.1%、幹部職員について39.2%であった。
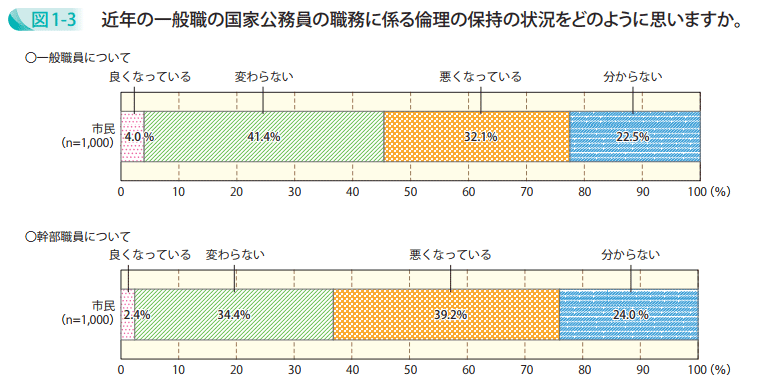
近年の一般職の国家公務員の職務に係る倫理の保持の状況をどのように思いますか。のcsvファイルはこちら
エ 倫理に関する研修の受講状況(職員アンケート)[図1-4]
職員アンケートで、公務員倫理に関する研修等に最後に参加してからどのくらいの期間が経過しているか質問したところ、1年未満と回答した割合が83.3%、1年以上3年未満と回答した割合が11.9%であり、両者を合わせた割合は95.2%であった。
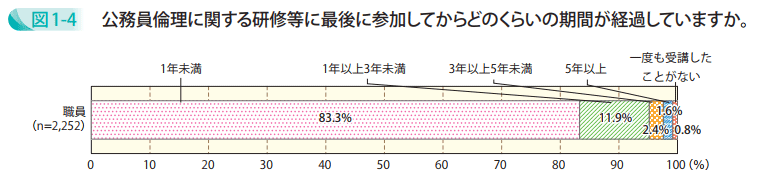
公務員倫理に関する研修等に最後に参加してからどのくらいの期間が経過していますか。のcsvファイルはこちら
オ 違反行為を見聞きした場合の行動(職員アンケート)[図1-5]
職員アンケートで、同僚が倫理法・倫理規程に違反すると疑われる行為を行ったことを、もし、見聞きした場合に、どのように行動するか質問したところ、「本人に問いただす」と回答した割合が7.6%、「上司など職場の他の職員に相談する」と回答した割合が63.8%、「所属組織や倫理審査会の相談・通報窓口に相談・確認する」と回答した割合が20.2%であった。
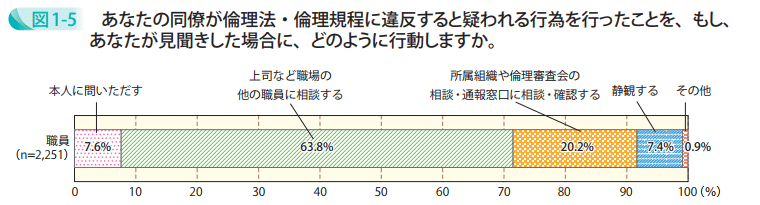
あなたの同僚が倫理法・倫理規程に違反すると疑われる行為を行ったことを、もし、あなたが見聞きした場合に、どのように行動しますか。のcsvファイルはこちら