|
|
| 「女性国家公務員の採用・登用の拡大に関する指針」の4(4)では、「各府省は、女性職員に助言、指導するメンターを導入するなど、女性職員の登用に資する取組を推進するよう努める。人事院は、メンターの導入の手引きを示すなど必要な支援を行うものとする。」と定めている。この手引きは、同指針に基づき、各府省がメンターを導入する場合に考慮、検討すべき事項等を示すものである。 |
| |
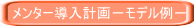 |
| |
| 1.メンター導入の意義等 |
|
|
|
|
民間の職場であると公務の職場であるとを問わず、一般に職場では、上司と部下のような公式の関係のほか、職場の先輩と後輩ともいうべき私的な人間関係の中で、先輩が後輩に対して、目標となる人物像(ロールモデル)となっていたり、仕事の悩みや職員の職業生活形成(キャリア形成)について助言、指導をしている例が見られる。
このような人間関係は、後輩にとっては、職場における自己のキャリア形成に資するものであり、人事管理上の観点からみた場合には、職員の成長が促される好ましいものである。民間企業の中には、先輩後輩の関係が後輩職員の成長を促すという効果に着目して、これに人事制度上の位置づけを与える仕組み(いわゆるメンター)を設けて職員の育成のために活用している企業もある。
公務においても、先輩後輩の関係の中で職員が成長していくことは、好ましいことであり、そのような関係が自然に機能している組織であれば、あえて人事当局が特段の措置を講ずることもなく、職員相互の私的関係に委ねておけばよいと考えられ、必要に応じて管理職員に対する研修の機会等を通じて職場における人間関係の重要性について啓発を図るなどの方策を取ることが考えられる。
しかしながら、職員相互の私的関係の自然な機能発揮が期待できない状況、例えば、女性職員の数が少ないなどの理由により、彼女たちが先輩後輩の関係の中で成長していく環境を形成しにくい状況においては、民間におけるメンター導入の例と同様に、公務においても女性職員の育成、登用の観点から、人事当局が一定の関わりをもつ仕組みとしてメンターを導入することが有効な場合もあると考えられる。
この場合、メンターは、人事当局から委嘱を受けて、広い意味での人事管理の一部を担うものとして、キャリア形成に関する相談に当たる者と位置づけられる。
以下は、人事当局が一定の関わりを持つ仕組みとしてこのような相談者(メンター)を導入する場合の留意事項等を示すものである。
(注)用語について
メンターは上記でいう先輩を意味するが、メンターを設ける仕組み自体を指してメンターということも多い。この手引きでも、「メンター」という用語を仕組み自体を意味する場合も含めて用いることとし、後輩を「メンティー」、先輩がメンターとして後輩の相談を受けて助言・指導を行うこと一般を「メンタリング」、実際に面談して相談を行うことを「メンタリング相談」ということとする |
|
| |
| 2.メンターの目的と関係者の役割等 |
|
|
|
|
メンターを導入することは、職場の先輩であるメンターが後輩であるメンティーに対して目標となる人物像になったり、助言、指導を行うことで、その後輩職員の成長を側面から支援する体制を作るということである。
直属の上司が業務上部下を指導するのとは異なり、基本的にはメンティーからの申出によって行われるメンタリング相談を通じて、メンティーのキャリア開発の意欲や意識改革を促すことによって育成を図り、ひいては登用の促進に資することを目的とするものである。
メンター導入に当たっての基本的事項として、メンター、メンティー、人事当局の役割及びメンタリング相談についての内容を示すと、おおむね次のとおりである。 |
|
|
|
|
|
|
|
(1) |
メンター |
|
|
|
|
メンターは、メンティーからの申出に応じて、メンティーのキャリア形成に関する事項等について先輩職員として自己の経験等を基に助言、指導(メンタリング)を行う。メンターの役割は、メンティーの側面支援であるから、メンティー本人が自ら考え、気づき、判断することを促すように努める必要がある。したがって、メンターは、メンティーのキャリア形成等に関して、メンティーの希望を人事当局に伝えたり、メンティーの上司等第三者に人事上の働きかけをするなどの役割は担っていない。 |
|
|
|
|
|
|
|
(2) |
メンティー |
|
|
|
|
メンティーは、メンターから助言、指導を受ける者であり、自ら主体的、自発的にメンタリング相談を行い、メンターからキャリア形成等について助言、指導を受けながら、組織内において成長することを目指す立場にある。 |
|
|
|
|
|
|
|
(3) |
人事当局 |
|
|
|
|
人事当局は、導入計画を策定し、その計画を職員に周知してメンターについての理解を広め、メンターの選定を適切に行い、メンターに必要な研修を行うなどメンターの導入が円滑に行われるように配慮する。
さらにメンタリング相談の実施状況等を適宜把握し、必要があれば、メンター、メンティーの意見を聴取するとともに、実施結果を分析し、導入計画の改善を図っていく。
なお、メンティーが安心してメンタリング相談に臨むことができるよう、人事当局は基本的にはメンタリング相談の内容には、関知しないことにしなければならない。 |
|
|
|
|
|
|
|
(4) |
メンタリング相談 |
|
|
|
|
メンタリング相談は、メンターがメンティーからの申出に応じて面談し、メンティーからの相談の聞き役となるとともに、必要な助言、指導を行うことである。
相談内容の具体例としては、次のような事項が考えられるが、その内容はキャリア形成に関連するものである必要があり、純粋に私生活上の相談は含まれない。 |
|
|
|
|
- キャリアアップを図るために必要なこと
- 仕事上行き詰まった時の対応
- 仕事と家庭を両立していくための手法
- 部下の指導、育成
- その他キャリア形成上必要な事項
|
|
|
|
|
|
|
| 3.導入計画の策定 |
| |
|
メンターの導入を図る各府省人事当局(女性の採用・登用拡大担当部署)は、導入計画を策定することが望ましい。
導入計画に定める事項は、おおむね次のとおりである。 |
|
|
|
|
|
|
(1) |
メンターの導入の目的 |
|
|
|
メンターの導入は、各府省の女性職員の採用・登用拡大計画に基づく取組であり、意欲と能力のある女性職員を側面から支援することでその育成を図り、女性の登用に資するものであることを明確にする。 |
|
|
|
|
|
(2) |
対象となるメンティー |
|
|
|
各府省の「女性職員の採用・登用拡大計画」における重点方針(係長級職員の育成に力を入れるなど)、職場の実情(メンター候補者の業務の繁閑など)等を考慮して、対象となるメンティーの範囲、募集(選定)方法を明らかにする。 |
|
|
|
|
|
(3) |
メンター |
|
|
|
メンターとなる者を明らかにするとともに、メンターの役割を明記する。 |
|
|
|
|
|
(4) |
研修、説明会の実施 |
|
|
|
人事院で実施するメンター養成研修に参加させるなど必要に応じメンターに対し、研修や説明会を行う旨を明らかにする。 |
|
|
|
|
|
(5) |
その他 |
|
|
|
- メンタリング相談の実施について、相談の対象となる内容、 秘密の保持、実施期間等の実施事項を定める。
- メンターとメンティーを当局で組み合わせる場合にはその方法等を示す。
- メンターは、職員の育成、登用を目的とするものであるから、その対象を女性職員に限定せず、男性職員に拡大することも差し支えない。
- メンター導入の趣旨とする先輩後輩の関係の中でキャリア形成に関する相談が行えるのであれば、既存のカウンセリング制度などを活用することも考えられる。
|
|
|
|
|
| |
| 4.実施上の注意事項(人事当局が注意すべき事項) |
|
| |
|
| (1) |
職員への導入計画の周知 |
|
|
メンターを導入する場合には、一定の周知期間をおいて、省内LANなどを利用して職員に導入計画の周知を図り、その理解を得る。 |
|
| |
|
| (2) |
対象となるメンティー |
|
|
メンター導入の目的を踏まえ、意欲と能力を有する女性職員を対象とする必要があるが、すべての女性職員を対象とするのか、係長級等一定の範囲に限定するのか、各府省の「女性職員の採用・登用拡大計画」における重点方針、職場の実情等を考慮して検討する。 |
|
| |
|
| (3) |
メンターの選定 |
|
|
- メンターの選定は、メンターの導入にとって重要な点であるので、慎重に行うことが必要である。
- メンターは、メンティーを育成するにふさわしく、かつ、女性職員の登用に理解のある者を選定するべきである。
- 具体的人選に当たっては、できるだけ経験豊富な職員に相談を行ってもらうという観点からは、ある程度上位の管理職層から選定することが考えられるが、一方、メンタリング 相談を円滑に行うということを考慮すると、対象となるメンティーとメンターの年齢や役職があまり離れていない方が良いとも考えられるなど、様々な考え方があるので、各府省の実情等を考慮して適切な人選を検討することが適当である。
|
|
|
|
|
|
| |
|
| (4) |
メンタリング相談 |
|
|
- メンタリング相談は、通常メンティーからの申出により、メンターとメンティーが話し合って実施時間、実施場所等を決定する。人事当局としてメンティーの育成、登用の観点から必要があると認める場合には、目安としてメンタリングの相談時間、回数等について例示することも考えられる。
- メンタリング相談は、職務との関連性を考慮の上、双方が勤務時間外に行うことを希望する場合のほかは、メンター及びメンティー双方の上司の了解の下に、通常、勤務時間内に行う。
※導入当初においては、メンターとメンティーの組合せ、相談のセッティング等を円滑に進めるためには、人事当局が、事実上の紹介、あっせん、誘導等の計らいをすることも考えられる。
|
|
|
|
|
|
| |
|
| (5) |
メンタリングの実施期間 |
|
|
多くの職員にメンタリング相談の機会を与えるという観点から一定の期間(例えば、1年間)を定めて実施することが望ましい。いずれはメンティーがメンターになるということになれば、取組が円滑に進むことも期待できる。 |
|
|
|