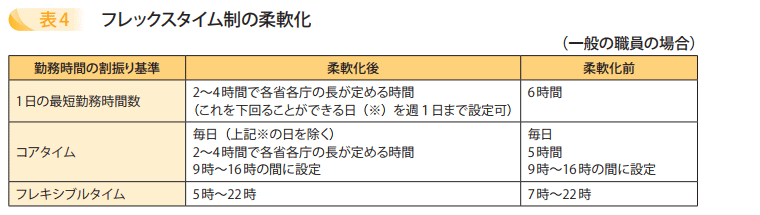官民を問わずテレワークによる働き方が広がってきていることを踏まえ、令和4年1月から令和5年3月にかけて、学識経験者により構成する「テレワーク等の柔軟な働き方に対応した勤務時間制度等の在り方に関する研究会」(座長:荒木尚志東京大学大学院法学政治学研究科教授)を計15回開催した。研究会においては、関係者からのヒアリング等を交えながら、テレワーク、フレックスタイム制、勤務間インターバルといった検討事項について議論が行われた。令和4年7月12日には、フレックスタイム制及び休憩時間制度の柔軟化を早期に実施すべきとの中間報告が取りまとめられた。これを踏まえた措置を実施するため、令和5年1月20日、必要な規則等の改正を行った(同年4月1日施行)。さらに、同年3月27日には、より柔軟なフレックスタイム制等による働き方、テレワーク、勤務間インターバルの在り方について最終報告が取りまとめられた。
(1)中間報告の概要
テレワークやフレックスタイム制の活用による柔軟な働き方の推進は、職員一人一人の能力発揮やワーク・ライフ・バランスの実現、健康確保に資するものであり、ひいては職員のエンゲージメントを高め、公務能率向上や多様な有為の人材誘致・活用にもつながるものである。研究会においては、このような観点から検討事項について議論が行われ、このうち早期に実施すべき事項として、フレックスタイム制及び休憩時間制度の柔軟化について提言が行われた。
ア フレックスタイム制の柔軟化
① 勤務時間の割振りの基準(1日の最短勤務時間数、コアタイム及びフレキシブルタイム)について、一定の幅を持った形で柔軟化し(基本的枠組み)、各府省がその範囲内で業務の実情等に応じて府省・部署ごとに最適な割振り基準のパターンを設定できるようにする。
② 勤務時間の割振り基準について、各府省が人事院と協議して、基本的枠組みよりも更に柔軟なパターンを設定できるようにする。
③ 単位期間に係る当初の割振りを行う期限を「できる限り単位期間が始まる日の前日の1週間前の日まで」から「単位期間の開始以前」に見直す。
イ 休憩時間制度の柔軟化
① 官執勤務制及びフレックスタイム制の場合、休憩時間を置く時間帯にかかわらず、連続する正規の勤務時間が6時間30分を超えることとなる前に休憩時間を置くことができるようにする。
② フレックスタイム制の場合、職員の申告を考慮して休憩時間を置くことができるようにする。
(2)規則等の改正
研究会の中間報告を受けて、令和4年8月8日の人事院勧告時の報告においては、フレックスタイム制及び休憩時間制度の柔軟化について、中間報告の提言の内容を基本として、規則等の改正などの必要な措置を速やかに講ずることを表明した。
その後、関係各方面と調整を進め、令和5年1月20日、規則15-14(職員の勤務時間、休日及び休暇)を改正する規則等を公布・発出し、同年4月1日から施行した。
また、規則等の施行に向けて、部内規定や表計算アプリによる申告様式の例、職員向け周知用資料を作成して提供し、各府省における円滑な実施を支援した。
(3)最終報告の概要
最終報告では、公務において最も重要な目的・理念は質の高い公務の提供とその持続であることが指摘され、その実現に向けて、第一に、ディーセント・ワークを推進するため、職員の業務負荷を軽減し、勤務環境を向上させる施策を実施すること、第二に、個人の尊重の観点から、公務においてより柔軟な働き方を推進することが求められるとされた。これらを踏まえて、今後、公務における働き方に関して推進すべき施策として、より柔軟な働き方、テレワーク、勤務間インターバルについて、主に次のとおり見解が示された。
ア より柔軟な働き方
① フレックスタイム制の拡充
- ・ 選択的週休3日の対象職員の拡大
- ・ 勤務開始後の勤務時間の変更
- ・ 非常勤職員の1日の勤務時間の上限見直し
② 夏季休暇の使用可能期間及び年次休暇の使用単位の見直し
イ テレワーク
① 業務上支障がない限り、基本的に職員が希望する場合には、テレワーク勤務をすることができるよう基準を明確化
② テレワーク時の勤務管理、長時間労働対策、健康管理等について考え方を整理。テレワークの円滑な運用のためマネジメント支援やシステム整備が必要
ウ 勤務間インターバル
① 勤務間インターバル確保について各省各庁の長の責務を早期に法令上明記
② 最終的には、全職員を対象に、原則11時間のインターバル確保を目指す。
③ 当面は現行制度の運用改善等を推進し、現状・課題を把握。課題解消に向けた取組を試行として段階的に実施した上で、本格的実施のための制度的措置を検討
また、勤務間インターバルや柔軟な働き方に関する施策を実効的なものとするためには、超過勤務の縮減が必要不可欠であることから、政府全体の取組として、一層の業務改革や適正な人員体制の確保に取り組むことを求めている。さらに、特に国会対応業務に従事する職員については、行政側の自助努力による業務合理化だけでは、勤務間インターバルの確保は困難であることから、研究会として、勤務間インターバルの趣旨や国会対応業務の改善について、国会の理解・協力を強く求めている。